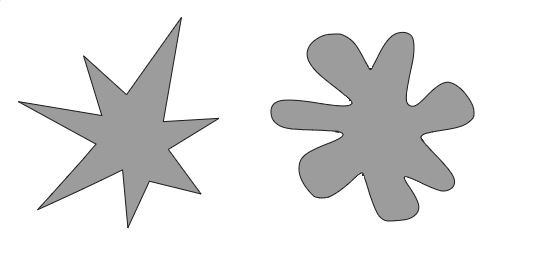カ行
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
抜粋したテキスト |
| 414 |
管理システム |
かんりしすてむ |
第三章
国家と社会の寓話 |
論文 |
|
中学生のための社会科 |
市井文学 |
2005.3.1 |
|
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| ユートピア |
集団の成員としての個人と自由な個人 |
たった一つの希望 |
項目
1 |
① 大なり小なり政治的(つまり社会集団的)理念と論理に関わりをもつ思想ははじめから開かれていなければ「ユートピア」社会を作り得ない。別の言い方をすれば、一般社会のもつ雑種性の自由度と管理システムより優れた管理社会を作り得なければ何の意味もない。つまりは開かれても引き入れる利点をもたないならばどんな口先の当たりがよくても意味をもたない。 (P173)
② これを歴史の理想的な理念でいえば、人間は過去を徹底的に追究することによってしか「未来の歴史」を語ることはできない。追究の不徹底や誤謬に惑わされている限り「未来の歴史」は虚偽以外のものしかもたらさない。「無知が栄えたためしはない」これがマルクスのつぶやきの意味かとおもう。「知る」ことは「怖い」ことでもあるのだ。
(P175)
|
項目
2 |
③ もし伝統の山岸会型の閉じられかつ管理される者と管理首脳とその下僚とを混同したり同一化したりしない管理制度があり得るとすれば一つしかない。
管理される者の利益、自由度、志向性、意志をいつも最優先に置くこと。言い換えれば管理制度がそのために必要である当のことを第一義とすることだ。そうでなければ当の管理社会は廃棄されるか改善される以外に意味を持たない。管理社会が開かれて一般社会のなかにあるためには、会員の等価労働が必要となる。この場合の交換価値は一般社会の価値よりも、同種の業目、品目より低くなることは確実である。そこで管理首脳は有利に別途の利潤を管理必要者にまわすことができることになる。たぶん管理組織のなかで被管理者の利益、自由度を最優先するという原則は破られないはずだ。
(P178-P179)
④ 管理社会の首脳の側面から考えると現在の高度管理に異論をもち、自己の発想、現役割、もしかすると収入と支出の自由と規模から考えて自己修正した管理システムを実現しようとする首脳など存在しないといえるかもしれない。わたしもはじめそう考えてもはやどんな修正意見も先細りになってゆくし、反対や改善にまわることはあり得ないとおもえた。絶望するほかないとおもえた。
(P179-P180)
けれど実例を挙げてみる。有能な経済専門家だとわたしは思っている『経済発展の理論』のジョゼフ・シュンペーターのいちばん説得性のあるマルクスに対する異論を例にとってみる。だが人間の力が当面する通例のようなもので、難しい通り路は塞(ルビ
ふさ)がりやすいものだ。私はこの絶望的にみえる通路こそ塞ぎやすいことを考えるに至った。既成の解決法は何も要らない。爆破も崖崩れも要らない。細い路に水を引き入れるか、軽く塞げばいい。科学や技術は便利なものだが、人間を超えることはできない。
わたしは管理社会が高度になればなるほど壊れやすいということに気づいた。この場合についていえば、理想を願望し、だが等価以上の何も自己利益に結び付けない、どこにも徴候がないところに踏みとどまっている管理成員を想定できれば半分は成就したとおなじだ。自らその管理システムを実行する成員と、それを説得できる人員とそれだけで十分なのだ。
(P181-P182)
⑤ シュンペーターが指摘しているのは資本主義と社会主義の集団的な社交で、おそらく社会的な社交としては最後のものだ。しかしマルクスはあらかじめ予期していた論議で、べつに貧乏臭さに固執するのが思想だといっているのではない。集団の成員としての個人と自由な個人とのあいだには明確な違いがあり、この違いの認知こそが究極の問題なのだといっている。 (P183-P184)
⑥ 一般社会に囲まれたユートピアの特徴は簡単に要約される。
① 欲望を叶えられる者とその欲望を求めて手に入れてくる者とは別人で分離されていることだ。
② どんな仕事にたずさわるのも自由だが、ユートピアの経営に直接関わることに無関係だということだ。
別の言い方をすれば欲求は遂げられるが欲求を遂げに動く主体ではないこと。自由な仕事でユートピアに寄与できるが、そのユートピアを経営する経済力や指導力をもつことはないことだといえる。
そして大切なことはユートピアを志向するあらゆる管理方式はこのやり方を大なり小なり真似ていることだといえる。例えば、ファシズム(ナチス)やスターリニズム(ロシア=マルクス主義)は、権力者とその下僚が同一の理念をもち、それが一般社会人民の上に独占君臨する方式である。またすべての資本主義社会システムは、何とかして管理システムの上層に位置したいために、激しい能力、学力、経済力の競争に打ち勝とうとする「自由」競争の生涯を送ることになる。これらの違いは管理メカニズムの最上位の権力者が、その下僚を自分の理念に似せた「鉛の兵隊」もしくはそのシンパに仕立てるか否かにかかっており、その変質はたやすいものと考えるべきだ。
これらの高度な管理システムをどこかに含む国家や社会、また部分社会を擬似ユートピアと呼ぶとすれば、わたしの乏しい知見からは、この擬似性を免れている高度社会は現在まで存在していない。
どうすればこの擬似性を免れるか、わたしなりにぎりぎりのところまで考えてみた。なぜなら管理システムの高度化は今後電子装置、交通装置の発達と情報科学者たちの無自覚な寄与や関与によって加速加重をかけられることは疑いないからだ。
科学のもつ中立性は押しとどめることはできないし、またこの科学の中立性は人間の倫理性とは無関係に、どんな資本主義の競争にも社会主義の独裁にも利用され得るからである。率直にいって現在の擬似ユートピアを超える方法は皆無ではないかという絶望感に襲われる。しかしこの絶望感、言い換えれば科学のもつ中立性こそは、また大きな利点であることが見出される。それは絶望の希望というべきものだ。たった一つの希望とは、繰り返しになるがつぎのような原則だ。
「すべての管理システムをもっている国家、社会、部分社会は管理される者の利害、健康、自由を最優先すること。これに反する管理システムは破棄されるか、または修正されること。」
(P185-P188)
|
| 備考 |
註 ④について 文章の流れ |
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
抜粋したテキスト |
| 431 |
個人の判断力 |
こじんのはんだんりょく |
どう生きる? これからの十年 |
インタヴュー |
『ブッククラブ回』2006.10 |
吉本隆明資料集165 |
猫々堂 |
2017.5.25 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人生最大の辛さ |
わからないのは |
|
|
項目
1 |
①
吉本 戦後になったその転換が、僕にはもう人生最大の辛さというか、わからなさだったんです。その時の転換の上のおっかなさという体験が、どうしようもないショックだった。ひとつひとつ自分で考えて解いていかないと生きちゃおれん、というか。その時に、何が俺はいけなかったのか、何が駄目だったのかという事を考えないと、ちょっと生きた心地もしない感じだった。その悔しさが、結局は考えることの根本的なエネルギーなんじゃないかな。少なくともそういう事に関する限りだったら、俺は考えることを止めないぞっていう、誰がなんといったって、俺は自分で考えるよっていう。もちろん怠け者ですから絶えずそんな事ばっかり考えてという事はないのですけれどもね。でも持続的に考えてきたというのはありますね。
吉本 すべてのことを自分なりに考える、追及すべきことは追及する、とやってきたつもりです。「それ」という感じだけでしかわからないぐらい、おおいにわからない事もあるんですけど、たまたますぐにわからないのは「わからない」にしておこう、そのうちわかる事になるかもしれないっていうそういうやり方だから。
吉本 そうしてだんだん自分で少しずつ「わかってきたぞ」という場所ができてきたから、そういう他者(引用者註.少し前のインタビューアーの言葉「古今東西の哲学者とか思想家」を指す)に対する向かい方がうまれてきたんだと思います。できるだけ率直に思っていることは本当に言うというのが、原則というか、心掛けなんです。ただ、そういうやり方をやっていると、つい逸脱して何となく同格じゃねえかって妄想を抱くことがあり得るわけです。いい気になると「お前知りもしないこと言うな」とか言われることも多くやっています。そのつど自分自身に対しては反省はある。自分の生き様を逸脱したことを時々言ったり、やってもいないこと、たとえば政治的なことを発言する時に、「オレちっとも政治ってことをやったことねえな」ってことがある。そりゃ実際やっている人から見たら、僕らの政治批判みたいなのは全然見当外れだよということになるのかもしれません。これは僕の性格的なところからくる弱点なんだろうなと思います。それをやっている人からみると実際に体験していることはいろいろあるでしょうから、なかなか思っている通りにはいかないんだよ、ときっと反発されちゃうということはたくさんやっていると思いますね。だからできるだけ注意しているんですけど。「おまえそんなに偉いのか?」っ(註.ママ)言われるようなことは自分の原則としては言いたくないだけど、つい、うかうかと・・・・・・(笑い)。 (P38-P39)
②
吉本 変わっていくということ自体について肯定的ですね。文明も歴史も科学も刻々考えられて、また感じられて、そのつど時代によって変わっていくものだと思っています。社会の変化に見合うだけの勉強をして、考え方を深めていれば、個人の判断力で対応できるんじゃないかと思っています。ただ、ものすごい変わり方の時はどうしようもないこともあるような気がしますね。僕にとって、敗戦の時の変わり方というのは、もっと大きいものというか、もっと根底的なものだった。あの変わり方は、僕がいくら個人として見識を高めたって、それに対応するだけの力は無かっただろうなと思います。それ以後は一生懸命考えているから、時代の変わり方については自分なりの判断はあります。自分の考え方が正確であるかとか、妥当であるかということについては何も保証がないわけだけど、ただ、自分ではわからなくなったなという事は今までのところは無いような気がしているんで、まだ当分は大丈夫でしょう、と思っていますけれど。(笑い)。 (P40)
|
| 備考 |
こういう対談の貴重さは、それらが吉本さんの著作の概念や論理に対する内省に当たっているということである。つまり、ここにはためらいや揺らぎを含めた吉本さんの言葉や思想の現場があり、言葉の肉体性がある。
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
抜粋したテキスト |
| 436 |
感性の秩序の変革 |
かんせいのちつじょのへんかく |
「現代詩における感性と現実の秩序」 |
|
『大岡山文学』1950年11月25日 |
吉本隆明全集2 |
晶文社 |
2016.9.30 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 現代詩 |
現実 |
感性の秩序 |
批判 |
項目
1 |
①
現代詩が現代に生存する詩人の、感性による統応操作として在る限り、詩の表現形態と韻律に対応する感性の秩序を、現代の現実社会における人間精神の秩序と関連させることによって、また現実そのものの諸条件と照応させることによって論ずることが出来るように思われます。
僕がここで触れたいのは現代詩の発展方向としての詩の形態内容と韻律の問題だけであり、それを現代の諸条件から帰納することが出来ればこのお便りの目的は達せられるわけです。人間の感性の秩序が現実社会の秩序の写像として形成されていった歴史的な過程を想起して見るならば、現代の現実社会に於る秩序の認識の喪失は、われわれの感性の秩序をの喪失に対応しているように思われます。
われわれの感性の秩序が混沌として方途を喪っているとき、しかもそれが現代における現実社会の秩序の認識の喪失に原因すると考えざるを得ないとき、われわれの生存の意識を永続的に支えてくれるものは感性による批判という形態で現実に対決することの外にはなかった筈です。・・・中略・・・僕は唯現代における現実の構造が、現代詩それ自体に感性による批判(これは詩の上では韻律の問題として現れる筈です)の機能を要請せざる得ない点を指摘致したいと思います。そしていきおいわれわれは詩概念自体に変革を加えざるを得ないでありましょう。
僕はここいらで詩の韻律の問題に転じようと思います。詩における韻律は決して言語の持つ音韻の連象を意味するものではありますまい。言語が人間の意識作用の表象として存在するものであり、詩が何らか意識の持続状態の表現に対応するものであることを考えるならば、詩の韻律は実は意識状態のアクセントの表象であると考える外ありません。詩の音韻というのはこの意識状態のアクセントが最もプリミティブに語音に托されて表象された場合に外ならないと思います。そしてわれわれの詩的操作を検討して見ますと、この意識状態のアクセントは詩人のその時における感性の判断の表象である筈です。僕が詩の中で感性が演ずる批判的な機能を韻律に結びつけて考えているのは正しくこの点においてです。いま定型詩の定型韻というものによって詩の典型を代表させて見ますと、それは肯定韻または従属韻とも言うべきもので、感性はこの定型韻によっては断じて批判の形をとることが出来ません。更に詩の韻律が〈音楽〉と類推して考えられるあらゆる状態において、感性の判断は批判の形をとることが出来ません。詩人の感性が意識の深部において批判の形をとる場合、(まったく!詩人は主題によってではなく、意識の深部において批判せねばならない!)それは否定韻または否定の否定韻として表象されねばならず、このことは詩の韻律を換言すれば意識状態のアクセントの表象を、まるで音韻を構成しない錯綜した構造にせねばならない筈です。
即ち詩が感性による批判の機能によって現実の秩序に対決する限り、詩の韻律は〈音楽〉から決定的に訣別せねばなりません。現代詩の重要な問題のひとつがここにあります。われわれはどうやら一切のリズムの快感から別れねばならないらしいのです。丁度人間精神が現代において最早神性を憧憬するあの従属感覚から別れねばならないように!斯のように現代詩はその形態内容においても、且て批評が果してきた機能と内容とを自らの内部に包摂するに至るでしょう。(註.1)
以上の論点は現実社会における人間精神の感性の秩序の変革という思想上の課題からも裏付けることは可能でしょう。
(「現代詩における感性と現実の秩序」『吉本隆明全集2』P346-P347 初出 1950年11月)
|
| 備考 |
(註.1)
この部分は、この批評とほぼ同時期に書かれた詩集『固有時との対話』(1952年8月1日)の「批評詩」とも呼ぶべき詩作品に実践されていると思われる。
この「現代詩における感性と現実の秩序」という批評は、しばらく後の『高村光太郎』や戦争詩の批判へのベクトルを内包している。この後、戦争-敗戦の過程で自分自身を含めて何が根本的にまずかったのかが、「詩意識の論理化」や「内部世界の論理化」などをキーワードとして批評活動が展開されていく。
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
抜粋したテキスト |
| 442 |
現代詩と大衆のつながり |
げんだいしとたいしゅう |
「現代詩の発展のために」 |
論文 |
1957年1月 |
吉本隆明全集4 |
晶文社 |
2014.9.30 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 詩人と大衆の内部には多くの共通点がある |
共感の基礎 |
|
|
項目
1 |
①
現代詩と大衆とのつながりは、詩人の内部と大衆の内部とのつながりあいによってしか、実現しえない。詩人と大衆の内部には多くの共通点がある。そのかぎりでは、詩人の詩は表面的にどんなに難解であり、専門的であるとしても、かならず共感の基礎があるといわなければならない。
②
現代詩が、いまの規模と構成をもっているかぎり、大衆とのつながりやコミュニケーションを求める方法は一つしかありえない。それは、現代詩人が、自己の内部世界と、大衆の内部世界との相違点と、共通点を意識的につかみ出して、それを手がかりにして大衆とつながることである。現代詩が、やさしいコトバでわかりやすくというような、大衆の内部をも、詩人の内部をも小馬鹿にしたような通路をたどるかぎり、ますます大衆との真のつながりも、芸術性をも喪う外ない。それは、俗流民主主義詩人の詩作品と、その指導の下でのサークル詩運動が、どんな作品を生んだかをあわせて考えるとことによって自明である。
(「現代詩の発展のために」『吉本隆明全集4』P375-P376 初出 1957年1月)
|
| 備考 |
この現代詩と大衆との関係ということは、一般化すれば専門家と素人との関係と言い換えることができる。そういうふうに一般性を持つと同時に難しい問題を含んでいる。しかし、芸術の領域の違いにも寄るかもしれないが、工夫次第では、専門家と素人との橋渡しも可能かもしれない。次のような体験をした。
今日(2017.7.20)、NHKの「ららら♪クラシック『とことん音楽!わたしのショパン』」(2017.7.20 この番組、3~4回くらい観たことがある)を偶然ぼんやりと観ていた。ここでの音楽作品の解説(NHKの番組案内によると、ピアニストの仲道郁代)は、わたしのようなクラシックに関心もなくあまり聴いたことがない素人にも親切でわかりやすい。ショパンの曲の具体的な表現とその音楽的な表現の意味するものにわかりやすく触れていた。また、青年期に故郷ポーランドを後にしてパリに出たショパンの曲に、故郷の民衆の音楽のリズムの影響があることも具体的に指摘していた。
もちろん、専門家と素人とがある共通の地平に立てたとしても、人間が生み出した言葉という自由(制約)の恣意的な解釈可能性や作者(個)との相互理解ということのむずかしさという問題が横たわっている。
(ところで、現代詩に関する吉本さんの晩年の捉え方については、)
吉本 一番先細りになりそうなのは、現代詩というふうに言われていますが、そのとおりになりそうな気がします。
短歌は千数百年、俳句も数百年の伝統をもっていて、万世一系かどうかはわかりませんけれども、短歌と俳句はちょっと日本語が存在する限り、滅びないんじゃないかなというふうに思っています。
道浦(母都子) 常に、短歌は滅びる、滅びると言われながら、滅びないできていますね。
吉本 ええ、逆にそう思いますね。だから、たとえばあなたの世代ともっと若い世代というので、詩を書いている人はいるでしょうけれども、その書いているものが、これでどうかなるのかね、疑わしいねって今は、思いますね、逆に。だからそれは反対に、短歌とか俳句のほうが残る。まだ寿命はあるというか、そういう感じがします。
そこがやっぱり一番、めんどうっていえば、めんどうな、日本の詩歌の、詩のめんどうなところだと思いますけれども、それでもちゃんと歌の場合は、伝統的に千数百年の歴史をもっています。はじめに問答の歌謡があって、問答の歌謡からだんだん七五調の短歌になんとなく、こう、ひとりでに水が集まるみたいに集まっていった。それがだんだん、表現として間延びをしてくると、今度は次の形式、俳句と詩が出てくる。その形はなくならないような気がするんです。つまりは、必ずそっちは残るでしょうけれども、ただ、現代詩と言われているものは、これはどこにももう取り柄がない。とらえどころがないっていいましょうかね。これは本当にわからないよっていう感じがしますね。
現代詩を書いている人たちは、もう今から、どうしていいのかわからない、どうしてどう抜け道を作っていいのか、今からこの一、二年間だと思いますけれども、もうすでにわからなくなっているんじゃないかな。だからといって、こうすればいいというのは、誰か模範を示してくれれば、だいたいそこへずっと集中していくわけで、その作者なら作者を主体にして、だんだん集約されていくということがあり得るんだけれども、今のところ、そうはいえないっていう段階ですね。
だからたとえば、あなたや『サラダ記念日』の俵さんのように脇の力といいますか、脇を締める力っていいますか、そういう力をもって詩を書く人っていうのは、今いないですね。どう考えたって、現代詩が先になくなっちゃうと思います。
・・・中略・・・
それが本当に少数でも、二人でも三人でも、おっ、っていう人が出てくれば、ちゃんとそこに、なんとなく集約していく。ひとりでに形がちゃんとついてくるっていうことがありうるんだろうけれども、そういうのはないし、また、僕らの年齢の人でも、それより少し若い人もだいたい似たようなものですね。詩の衰退に対して、関心をもって考えなから詩を書いているという人は、あまりいないんですよね。
それこそ、立原道造みたいな人はそれをやりました。詩を書きながら、具体的な形象に関する限りは、最盛期の短歌と詩をつなげようという、つまり、連結しようということをやっていますよね。
道浦 『新古今集』から学んで書いていらっしゃる。
吉本 ええ。短歌の人でも、岡井隆さんは詩なんかもちゃんと書いてるじゃないかと。昔からよく試みて、研究している人だけれども、まっとうな詩をちゃんと書いていて、呼吸は短歌の呼吸が残っている。本当に呼吸というしかしょうがないんですけれども。でも、ちゃんとした現代詩を書いているじゃないかっていうふうに思います。
(『吉本隆明 最後の贈りもの』 P109-P112 2015年4月)
※本書のこの「吉本隆明に聞く 短歌のゆくえ」は、2009年1月のインタビューとのこと。
この吉本さんの現代詩に関する認識は、吉本さんがたどってきた和歌(短歌)の変貌や俳句などの興隆の歴史と言葉というものの歴史、そして自らの詩作体験を踏まえた視線からの晩年の言葉である。もちろん、現代詩が死んでも別の文学的な表現は残るだろう。しかし、意志的・意識的に詩を書き続けている者にとっては、現代詩の生命感あふれる表現ということは切実な課題であるはずだ。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
抜粋したテキスト |
| 457 |
9条は先進的な世界認識 |
「9条は先進的な世界認識」 |
|
『東京新聞』2007年8月8日 |
『吉本隆明資料集169』) |
猫々堂 |
2017.10.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 超先進的な世界認識 |
憲法の非戦の考え方 |
考えどころだっていう課題 |
|
項目
1 |
①
つまり憲法九条はどの資本主義国にもどの社会主義国にもない、超先進的な世界認識なんだと思うんです。これは右か左かで論じたら全然狂っちゃうわけですよ。
戦争では、弱い方の土地が戦場になって荒らされる。米国なんかすり傷を負った(引用者註.)だけで大騒ぎでしょ。本当の戦争なんか知らないんですよ。だから僕の理解の仕方では、うまい物は食ってないけど平和な暮らし方をしているうんと後進的な国家や社会、地域、アマゾン川流域の共同体みたいなところは多分、憲法九条に賛成してくれるはずですね。
日本人はそういう人たちと連携して「おれたちは米国とも中国やロシアとも違うよ」って国際的な広場で積極的に主張したらいい。そしたら憲法の非戦の考え方にとっては大きな力になると思います。今のように非戦条項を放り出したまま米国一辺倒っていうのが一番だめなやり方です。
近代化の過程にある東洋諸国の中で、日本は文化的にも文明的にもあるいは産業的にも科学技術的にも、近代化はほぼ終わってます。だから僕に言わせれば「日本は考えどころだぜ、ここでまた西欧のまねをしてちゃだめだぜ」って。金もうけに頭がよく働くヤツが得するような、ばかな社会をつくるまねをするなって思いますね。
自分らの土地と天候と風俗習慣あるいは遺伝子的なものに一番適合したやり方を考えてみろよって思います。世界中のどこにも同志となる国がない特殊な国でしょ、日本は。
憲法九条に同意してくれる国と一緒にやろうじゃないか、平和について世界を変えようじゃないかってことができたら一番いいね。そういうところが考えどころだっていう課題だと思います。
(「9条は先進的な世界認識」P105-P106『東京新聞』2007年8月8日、『吉本隆明資料集169』)
(引用者註.)この「かすり傷」は、2001年9月11日「アメリカ同時多発テロ事件」のことを指しているものと思われる。
|
| 備考 |
現在の日本の社会は、相変わらず先の大戦の戦犯の生き残りやその子孫、あるいはわたしたち普通の生活者から大きく乖離したアメリカ帰りの政治家や官僚によって牛耳られている。まだまだわたしたち普通の生活者(あるいは、市民、国民
)がほんものの主人公となっていない。さらに、敗戦後70年が戦争の体験や教訓を風化させ、わたしたち普通の生活者の意識の中にもその風化が及んでいるように感じられる。「ネトウヨ」にかぎらず、世界政治における軍事バランスという虚構の軍事や防衛に足下をすくいとられている者も多いような気がする。
人類は、集落を形成し、そして隣の集落との摩擦や争い、国(お国はどちらの「国」で、戦国時代など)同士の侵略、戦争、江戸期以降の統一社会・国家の形成、近代民族国家の成立、というように幾多の血を流しながらではあるが戦争という矛盾を解消してきた。世界には、まだ国内で対立し合う地域もある。また、現在少し立ち止まっているがEUのような民族国家を超えた試みも存在する。これは国家間の対立や戦争という矛盾の解消の方法とも見ることができる。人類は、戦争に関しては、主要には国家間レベルの解消の舞台にまで上り詰めてきている。この一方で、核兵器を脅しの手段とした力の政治が世界には居座り続けている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 460 |
還りがけの視線―書くことの世界から |
「川上春雄さんを悼む」 |
論文 |
「ちくま」2001.12 |
『ドキュメント吉本隆明①―〈アジア的〉ということ』 |
弓立社 |
2002.2.25 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 文筆をもてあそぶこと |
|
|
|
項目
1 |
①
文筆をもてあそぶことは、おそろしいことだ。これはさまざまな出来ごとに書く人間として出遇ってきたわたしの実感のひとつだ。著作家は著作によって死ぬこともあるし、殺傷することもあるにちがいない。
(川上春雄さんを悼む」「ちくま」2001.12 、『ドキュメント吉本隆明①―〈アジア的〉ということ』所収 弓立社)
|
備
考 |
この言葉は、長年書くという世界で、本質的な批評に奮闘してきた吉本さんの内省の言葉のように見える。言葉が時に人を深く傷つけることがあるのは、この人間の互いに関わり合う社会に生きているわたしたちの誰もが持つ実感である。吉本さんは他者の作品や思想やイデオロギーもたくさん批判したり、論争したりもしてきている。自らが言葉として生き延びていく過程では、言葉が他者を「殺傷」しているなと感じられることも多々あったのだろう。
現下のSNSに駆動されて引き出されるわたしたちの存在も、その言葉も、「つぶやく」ことのおそろしさをも秘めているはずである。
この「さまざまな出来ごとに書く人間として出遇ってきたわたしの実感」には、吉本さんがどこかに書いていたが、吉本さんの本を読んで悩み考え詰めて自殺してしまった青年があり、その葬式の場でだったか父親から(お前のせいでこうなったんだ)みたいな責められ方をしたことがあるということも含まれているだろう。また、ガンにかかった吉本さんの姪の女性からの(死んでいく自分というものをどう考えたらいいの?)という深い問いかけに答えることができなかったということも含まれているだろう。
ところで、この言葉は、書くという世界の内部での「内省の言葉」のように見えるとわたしは書いた。この言葉には、説明的にはっきりとは分離しがたいけれども、行きがけの内省の言葉そのものではなく「還りがけの言葉」の視線が含まれているのではないかと思う。その佇んでいる吉本さんの表情のようなものからわたしはそう感じるのである。ここで、「還りがけ」ということは、現在は行きがけ中心が知や書くことの主流のように、他人の言説と言い争ったりの俺が俺がの血気盛んな社会でわかりにくいと思われるが、個の死ということではなく普遍としての書くことの死滅のイメージであり、知の世界からの帰還のイメージということである。しかし、まだまだそのことを明瞭なイメージで語ることは難しいような気がする。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 465 |
個にとって世界とはなにか |
「歴史と宗教」 |
インタビュー |
『現代思想』1975年4月号 |
『吉本隆明資料集169』 |
猫々堂 |
2017.10.15 |
インタビュアー 三浦雅士
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 歴史意識として個にはいってくる時間 |
いまの段階 |
矛盾のいろいろな解決法 |
|
項目
1 |
①
― 歴史的時間と個人的時間はどのようにかかわるのでしょうか。
吉本
個体が生まれてから死ぬまでの時間というのは、これも歴史的社会的な変遷がありますが、三十年から七十年くらいの範囲ですね。それで、歴史時代にはいってからの時間というのは、世界史的には五千年なら五千年、日本でいえば千数百年ということになります。神話時代をぬけて歴史時代にはいってからということでいうとそうなります。いまでも神話時代のような意識の地域もあるでしょうし、それも現在的に同時に並んでいるということです。歴史時代を数千年経てきているという地域もありますし、千数百年という国家もありますし、まだ神話時代さながらに生き死にしているという地域もある。そのなかで個の意識にはいってくる時間、歴史意識として個にはいってくる時間について、はっきり云えることは、歴史的にいっても地域的にいってもいいわけですが、未開においては、個の中では歴史時間が無限にとられているとおもうんですよ。したがって個の意識の時間もまた無限にとられているわけです。そこで、もっとはるかに進展した段階での歴史意識を考えてみると、それは、個の時間の範囲内でしか歴史の時間を把えないというふうになるんじゃないでしょうか。
未開人の場合には、肉体が終ったところが個人の終りではない。肉体が終ると魂の時間が続いていますし、それがまた別個の肉体に宿るということもある。再生するわけです。生命を悠久にかんがえているわけです。現在がずっと続いている。その場合には歴史性がない。神話性だけがある。神話性というのは宇宙の空間的なイメージがあればいいわけです。歴史時代にはいってはじめて、歴史時間と個の時間のギャップ、矛盾がはっきり自覚されてくる。自覚されてきて歴史時代にはいる。それが極度に進んだ場面を想定すると、個の時間意識と歴史の時間とは同じなんだというところにいくんじゃないかと。逆にいえば、個の生成が歴史の生成そのものであって、現在いまここに自分が存在するということが個であるとともに歴史性そのものでもある、と、究極にはそういうかたちで一致してしまうんじゃないかな。
②
吉本
それではいまの段階ではどうかといえば、せいぜい百年足らずが個の生まれてから死ぬまでの時間ですが、まずその時間の範囲内で歴史に関与する。そして、自分が死んで関与することができなくなっても、複数の自分というか、それは関与しつづけるだろうということ、それが歴史意識にとって重要な仮説、というかイメージになっているわけですね。だから、まだ未開のイメージが残っていて、自分の生存の時間よりも歴史の時間の方が長いだろうと考えている。しかし、これがもっと極限まで展開していけば、やはりそんな馬鹿なことはないのであって、自分の生成消滅、個の生成消滅は、歴史の時間と同じである、というようになっていくでしょう。どうしてそうなり得るかというと、個が死んでも歴史的な時間は続くだろうということは依然としてまちがいないんですけどね、そこに価値観がはいってくる。つまり、個の生成消滅以外の歴史性を考えるのはまったく無意味である、無価値である、そういう価値観が、個の意識の中で大きくなっていくとおもいますね。疑問の余地なくそうなってゆくとおもいます。いまの人間はそうではない。じぶんが死んでも、じぶんにとっては終りだろうけれども、まだ社会はあるし、歴史は続くだろう、いまの段階では個々の人間は平均的にいってそうかんがえているとおもいます。しかし、そこにはちょっと曖昧性が介入していて、ほんとうにつっこんでいけば、個が死んだときに歴史も社会もなお生きつづけるだろう、そういうことを立証することはできるのか、といった場合には、ほとんどそれは不可能なんですよ。過去にそうだったからというだけで、それは実証が難しいんですね。難しい部分だけ、それは、信仰、宗教とはいわないまでも、観念を観念的にかんがえているということに属するとおもいます。それは、価値観が徹底していない段階だからだろうとおもいます。ほんとうに価値観が徹底してきたら、個人の生成死滅以後に歴史があるとかんがえること、あるいは個人の意識の外に歴史があるとかんがえるのはまったく無意味だ、とかんがえていくでしょう。そうなったときはすっきりするとおもいます。いまの段階では、自分が死んでもまだみんなやっていくんだろうな、とこうなるわけです。しかし、そんなことはわからないですよ、誰も証明はできないです。自己証明ができないのにあるイメージをもっているというのは、それは信仰の問題ですよ。観念を観念的にかんがえる問題、宗教性の問題です。過去もそうだからこれからもそうであるだろうというのが唯一の類推の基盤であるわけですが、自己立証できない問題です。その矛盾がなぜあるかというとやはりそうだからじゃないか。個人の生成死滅ということと歴史の生成展開発展とは対応することであって、それ以上の意味づけはまったく無意味だということです。
(「歴史と宗教」 1975年4月 P158-P160『吉本隆明資料集169』猫々堂)
聞き手 三浦雅士 『現代思想』1975年4月号
③
吉本
この矛盾にはいろいろな解決法があったわけで、宗教でいえば来世が、他界があるとかね、霊魂は滅びないとかね。マルクスは、その矛盾は個と類の問題なんだと云っている。類としての自己は続く、人類としての類を引き受けていく自分は続く、続いていくと考えている。じぶんの子供とか、そういう具体的なものを介在させてもそうだし、あるいは、じぶんが生み出した道具とか物とか観念とかそういうものを通して、類としてのじぶんは続いていく、こうかんがえていますね。個は死滅するけれど類としては生きると、そういうものとしてマルクスはその矛盾を云っています。未開社会の場合は、肉体の死滅は個の死滅ではないといまでもおもっているでしょう。それは、過渡期というか、いまはそういう段階だからそうなのではないでしょうか。この矛盾を解決する方法としてさまざまな考え方がだされているわけですよね。
(「同上」 1975年4月 P160-P161)
④
― 補足して伺いたいと思います。『共同幻想論』の「対幻想」の章において、時間の原因としての女性、あるいは性ということが示唆されているように思われます。それは一個の人間的時間の提示のように思われます。性と時間、あるいは性と歴史についてどのようにお考えでしょうか。
吉本
性の問題でいえば、歴史時間に該当するのが世代の時間だと思います。世代の時間を止揚するということは現在に全部凝縮させてしまうというか、個の男か女であるとともに世代時間をもそこに包括してしまうものになるということです。個と、男女あるいは性の問題は、そのようにして、世代時間と個の時間を一致させられる。世代の時間と個の時間がそのようにして性の問題として一致してゆくとおもいます。それが根本的、本質的なところになります。
ところで、その時間は歴史的な時間とどのようにつながってゆくか、ということが次の問題になってゆくわけです。そうすると、地域によって違いがあるけれど、もっともはじめに母系制があって、そこから歴史が展開してゆくうちに父系制に変っていった、という考え方がある。日本なんかそうですね。あるいははじめに男があって、父系的社会ができて、歴史時代にはいったというのもある。しかし、当初に何があって、それがどのような契機で変っていったかということについては、はっきりとした法則性はどうもないんじゃないかという気がする。おそらく、現在考えられている種族とか人種とかの概念がありますが、そのために、たとえば種族の母親のようなものがあった、はじめに女性があったというようにかんがえやすくなっているんじゃないか。それは、いまの種族とか人種とかの概念でいっているからそうなんであって、人間というのはどのように発展してきたのか、それは依然として固定的ではないようにおもわれます。いまかんがえられている種とか人種とかは、どうもぼくには、壊れていってもっとちがう概念がそれに替るんじゃないか、という気がします。ちがう概念に替らないと、遡れもしないし今後のこともわからないんじゃないか、という気がするんです。いまかんがえられている種という概念は、人間というのはある単一の地域で猿らしきものから進展してそれがさまざまなところに移動して、そして各人種を移動したり混血したりして形成した、とかんがえられているわけですが、だけどそれが疑わしいんじゃないか。単一の地域から発生したのでも、猿から進化してにんげんになったのでもない、とぼくにはおもえます。それで、種という概念を替えなければいけないんじゃないか、とおもうわけです。いまかんがえられている種だったら、黒人を人類とすると、白人というのは人類じゃないとか、そういうようにいわなくてはならなくなっちゃうじゃないでしょうか。あまり包括的な概念ではない、とおもえるんですよ。猿は猿なんで、猿は進化するわけはない、猿はそれ自体で究極的な種である。人類というのは全然ちがう。しかも、ある段階における人類というのは、たとえばある地域から発生した人類だった。道具なんかをもっとよく使えるような人類は、それとはちがう地域から来た人類なんだ。どうもそういうような気がするんですよ。だからいまの種の概念は狭い概念なんであって、それは過去も包括できないし、未来も包括できない概念だとおもうんです。そういう根底的なところから変わっていったら、おそらく、母系的であるとか父系的であるとかいう云い方も変わってくるんじゃないか。ある種族、ある人種、あるいはある地域は、はじめに母系制があったとか、あるいは父系制があったとか、そういう云われ方自体をもっと包括する、そういう概念になっていくのではないかとおもえるんです。
(「同上」 1975年4月 P161-P162)
※①、②、③、④は、続いた文章です。
|
| 備考 |
(備考)
④について
ささいなことの備忘としてであるが、吉本さんが人間は猿から進化したということを受け入れた言葉も吉本さんの文章のどこかでわたしは出会った印象がある。
一連の問題で、わたしにはとても重要だと思われたので、長い文章を引用した。これはとても難しい問題であるが、その背景にはふとした瞬間に誰もが思い浮かべたことがある、不明であるとしか言えないようなこの世界の有り様やそんな世界に自分が生きていることへのイメージや疑問が控えている。そして、わたしたちが抱くそういうイメージにも歴史的な段階のような水準があるということ。
このインタビューで触れられた問題は、1975年4月とある。これは三十余年後の、2006年7月~10月の吉本-茂木健一郎の対談(『「すべてを引き受ける」という思想』吉本隆明/茂木健一郎
2012年6月刊)における晩年の吉本さんの言葉や考えにつながっている。次の部分には、割とすっきりとした見通しとして二つの人類史が語られている。
吉本―人間の身体も一個の人類史である。(引用者註.小見出し)
まだ熟した考えではありませんが、最近ぼくはこんなことを考えています。
人類史というのは、人間がおサルさんと分かれたときから現代までずっと続いていて、ふつうはわれわれの身体の外にある環境(外界)、つまり政治現象や社会現象などの歴史も一応、「人類史」と考えられています。ところが、このあたりのことをもう少し細かくいうと、これまで考えられてきた古代史以降の環境の歴史というのは、いわば文明史あるいは文化史にすぎない。人類史全体ではないということになります。したがって人類史を探るにはやっぱり人間がおサルさんと分かれたところまでさかのぼる必要があるのではないか。
それからもうひとつ、「人類史」にはそうした人類史のほかに、もう一種類あるのではないかということを考えています。別種の人類史とは何かといえば、個々の人間がそれぞれの身体性のなかにふくんでいる人類史です。個々の人間の身体性の範囲のなかで行われる精神活動や身体の運動性は人類史を内包していて、文明の移り変わりとか社会の変遷といった一般的な人類史とは別個のものとして考えられるように思います。
そうしたふたつの人類史を媒介するものが、身体性の順序からいえば、種としての遺伝子の変化、風俗習慣の変遷、地域的差異に基づく言語の発展の仕方の違い、文明・文化の進展具合と、その根底にある自然へのはたらきかけ方・・・・・・これをつづめていえば、種、住んでいる地域的環境、言語、この三つがふたつの人類史を媒介している。いまはそんなふうに考えています。
(『「すべてを引き受ける」という思想』p70-p71 吉本隆明/茂木健一郎)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 467 |
芸術の価値は自己表現 |
「超人間、超言語」 |
対談 |
「群像」2006年9月号 |
『吉本隆明資料集168』 |
猫々堂 |
2017.9.10 |
※ 対談 中沢新一・吉本隆明 2006年6月7日
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 使用価値と交換価値 |
自己表出と指示表出 |
|
|
項目
1 |
①
吉本 つまらないといえばつまらないことなんですけど、『資本論』の中でマルクスは、ギリシャを未開的な社会で、ギリシャ芸術がすばらしいのはどういうわけだみたいなことを盛んに問題にしているんですが、ほんのちょっと、うかうかとすれば読み過ごしだという本当に一行か二行ぐらい、芸術の価値も労働価値じゃないかということをいっているんですよ。翻訳の人の文章だと、「価値じゃないだろうか」と疑問符的にいって、自分でも少し疑っていする。・・・中略・・・
芸術というのは即興的にうまくできちゃうことがありますし、いくら考えて手をかけたって、この詩はあまりいい詩になりそうもないなということもあります。それは、マルクスもそういうことを一、二行、それも疑問符をつけていっている。長谷部(文雄)さんの翻訳ではそうなると思います。つまり、これが経済的価値論と芸術の価値の分かれ目だなと僕は理解したんですね。
言語の価値というのは、(註.1)★『資本論』の「使用価値と交換価値」という概念と同じつもりで、「自己表出と指示表出」と、これが言葉の本性だみたいなことをいっている★わけですけれども、経済論から来る価値論に、これ以上かかわっちゃいけないなというので、僕は、芸術の価値は自己表現に必ず帰着するといっている。その自己表現というのは作者の自己表現であって、芸術、文学なんていうのは読者が勝手に読んで、勝手にこれはいい作品だといって、百人いれば百人違っちゃう。けれども、もしほかのことが同等であるとすれば、百回読んでくれれば、必ず一致するところへ行く。その収斂する点はどこかといったら、作者の芸術力ですね。そこまでやれば芸術の価値の、例えばだれの何という作品とこの作品とどっちがいいかというのは決められるはずだ。僕は、究極的にはそうだと考えて、最近そういうことを書きました。『言語にとって美とはなにか』のときには、だいたいそういうことは考えていたけれども、そこまで言い切れなかった。
②
中沢 このあいだの「SIGHT」(引用者註.これは、2006年7月刊の「SIGHT」28号に掲載された「言語論要綱」〔吉本隆明資料集166」所収〕を指していると思われる)ではそう言い切っていますね。
吉本 言い切れると思って、そういうふうに書いたのです。芸術作品を鑑賞する領域はそんなのではなくて、各人各様に違うというところに特色があるんだから、それでいいんだけれども、もしも本気になって、いや、それはおかしい、あいつはいいというけれども、おれはいいとは思わないとかいう違いをどこかに同一化しようとすれば、一回あるいは二、三回読んだとかいうのじゃなくて、とにかく百回ぐらい読んでくれ。百回ぐらい読んだら必ず同じようなところに行くに違いないと考えています。
(「超人間、超言語」P50-P51『吉本隆明資料集168』)
※ ①と②とは連続した文章です。
|
| 備考 |
(備 考)
・吉本さんの発想の型。
とにかく、日常的な印象把握に終わらず、そこからその実感を携えて、ものごとの根源的な有り様にまで追求していく。この背景には、吉本さんの苦難の「大洋期」以後の固有の自己形成と文学の経験と実験化学の習練、そして科学や数学的な発想を身につけてきたことなどがある。
・この吉本さんの「芸術の価値は自己表現」ということは、特に文学においては古代国家の成立あたりから現在につながっている、独立してきた個が芸術の表現を担う人類史の段階でのことに属している。なぜこのような但し書きをするかといえば、人類の歴史で言えば、それ以前の個が共同性の中に埋もれてまどろんでいた段階の、人類としての芸術的な表現というものもあり得るからである。
・この「百回読む」ということを意識して、わたしは作品を読んだことがある。この百回はとてもていねいに読むという比喩でもあると思うのだが、私が読んだのは、上橋菜穂子の『ラフラ』という45ページの短編で、しかも十一回だった。
(作品を読むということ ⑩ ―作品の入り口で ⑩ (2014.5))
http://blog.goo.ne.jp/okdream01/e/4d21b0ab56abc4fed7ae7783e7b76ced
・(註.1)★ ★に関して
吉本さんは初めマルクスの『資本論』の使用価値を自己表出と見なし、交換価値を指示表出と見なしていたが、後には逆に、使用価値を指示表出と見なし、交換価値を自己表出と見なすようになった。わたしは、「自己表出」などをネットで検索していてこのことに偶然出会った。今はそのことがよくわからないし、また追究する余裕はないから、ここに備忘として長いけれど資料としてあげておく。以下の文章は、初めてネットで出会った中村友三氏という人のものである。もうリンク切れていることもあり、長いけれど全文を挙げておく。
http://yuzonakamura.asablo.jp/blog/2015/02/16/7573979
YUZO'S NOTE PAGE 中村友三
自己表出 ―
2015年02月16日 22:14
2012年10月15日(月)08時55分41秒
吉本隆明は『言語にとって美とはなにか』での指示表出と自己表出という概念を、マルクスの『資本論』から考え出してきたと述べており、手元にある資料では以下のものがあります。
『言葉という思想』(弓立社 1981年の「幻想論の根柢」。1978年に京都教育文化センターで行われた講演のテープ起こし。音声は『吉本隆明 五十度の講演』ほぼ日刊イトイ新聞 2008年の「共同幻想論のゆくえ」に収録。)
『超西欧的まで』(弓立社 1984年の「経済の記述と立場」。1984年に日本大学で行われた講演のテープ起こし。音声は『吉本隆隆明 五十度の講演』(ほぼ日刊イトイ新聞 2008年の「経済の記述と立場」に収録。)
『ハイ・イメージ論 Ⅱ』(福武書店 1990年の「拡張論」)
『吉本隆明 自著を語る』(ロッキング・オン 2007年の「言語にとって美とはなにか」)
『日本語のゆくえ』(光文社 2008年の「第2章 芸術的価値の問題」)
一番最初に読んだのは光文社の『日本語のゆくえ』で、ここでは指示表出は交換価値から、自己表出は使用価値から取ってきたと述べています。しかし最近ネット上で検索すると<指示表出は使用価値、自己表出は交換価値から>という関係で考えている人がたくさんいるのを知りました。『日本語のゆくえ』では次のように述べています。
「この使用価値という概念は、僕の芸術言語論でいうと、自分なりに自分が納得できる言葉である「自己表出」と、コミュニケーションのための言葉である「指示表出」に対応します。初めはそう考えて、使用価値に当たるのが「自己表出」で、交換価値に相当するのが「指示表出」であるとしておけばいいのではないかと思っていましたから、『言語にとって美とはなにか』でもそう書いたわけです。」このことから最初は「指示表出→交換価値、自己表出→使用価値」と考えていたことがわかります。
「交換価値」から「共同意思によって決められた等価性」という概念を抽出し、たとえば「社会的規範で決められた意味を示す等価物」という概念につなげて指示表出に対応させ、また「使用価値」から「人間が関与してくるときに生まれる普遍的特性」という概念を抽出し、「人間の本来的価値である自己疎外」という概念につなげて自己表出に対応させれば、言語表出の二重構造ができあがります。「自己表出=表現」は<からだが資本>というように本来的には資本として、交換とは関係ないところにある価値そのものとしての「沈黙」や、自己疎外による累積性としての自己増殖ともつながります。
それに対して<指示表出は使用価値、自己表出は交換価値から>という考えを詳しく述べているのは『ハイ・イメージ論』(福武書店 1990年)の「拡張論」での論述です。ここでは使用価値と交換価値ではなく、1段階進んで、商品が実際に交換過程に入ったときにそれぞれ変容した相対的価値形態と等価形態から拡張概念を抽出します。相対的価値形態からは「使用価値のちがいが実体のちがいという系列」を、等価形態からは「(交換)価値がじぶんじしんにたいする差異によって任意の実体におきかえできる系列」という概念を抽出し、商品体の二重構造と対応させます。
ここではマルクスの『資本論』での相対的価値形態を説明する「相対的価値形態=等価形態」という<式>を使って対応させます。
この式の意味は、「自分の物を他人の物と交換するときに、自分の物を基準に相手の物と比較して価値が同じかどうかを判断すること。」を言っており、「比較しなければ(主部)、つぎの段階(述部)で等価(合意価値)に達しない。」という<判断の順序>に従わせた左項→右項という格付けと意味付けをしています。この<式>に先ほど抽出した概念を表象する言語を代入して対応させます。
たとえば、左項の相対的価値形態の場所に他人が持ってきた「1個のりんご」を、右項の等価形態の場所に自分の「2個の梨」を置くと「1個のりんご=2個の梨」になり、それは「1個のりんごは2個の梨と同じ価値だ。」という文章になり、さらに「1個のりんごは2個の梨と同じようだ。」という文章も成立します。左項の相対的価値形態の場所には名詞などの指示表出的な言葉を、右項には名詞のほかに、助詞、助動詞や形容詞などの自己表出的な言葉を置けるが、左項には助詞や助動詞を置くことができないということがこの式でわかります。そうすると先ほど相対的価値形態から抽出した「使用価値のちがいが実体のちがいという系列」は指示表出に、等価形態から抽出した「(交換)価値がじぶんじしんにたいする差異によって任意の実体におきかえできる系列」は自己表出に対応することになり、ここで初期の対応と逆転します。
ここで疑問なのは、そもそもこの式は文法の語順と同じではないか、これでは「思考順序→文法→等価式→文章」というように、もとに戻っただけで、そこに言葉を入れてもただの文章になっただけで、対応を説明したことにはならないのではないかということです。ただ逆に、人間にはそういう語順以外のものがあるのか?という考えも成り立つわけです。
この先はこの逆転から導いた対応で説明が進んで行きますが、むずかしくてわかりません。本人も「ここまででもほんとはたくさんの疑問につきあたる。」と述べています。たとえば、「リンゴの使用価値としては紅くきれいで甘酸っぱい果肉の像をすぐ想いおこさせるが、言語の指示表出としてのリンゴはリンゴという概念を指示するだけだ。」という疑問を述べていますが、これを指示表出を自己表出に置き換えれば「リンゴの使用価値としては紅くきれいで甘酸っぱい果肉の像をすぐ想いおこさせるし、言語の自己表出としてのリンゴも紅くきれいで甘酸っぱい果肉の像を想いおこさせる。」と言えるわけで、これは相対的価値形態(使用価値)→指示表出という対応づけによるものだと思います。
自分の対応での商品価値(意識表出)の変容プロセスはつぎのようになります。
1 物には人間が関与してくるときに生まれる普遍的特性としての使用価値があり、これを資本と考える。(自己疎外)
2 社会的存在としての商品の価値は、使用または消費されることによってのみ実現される使用価値と、使用価値からまったく独立してあるものとして現れた交換価値の二重構造になる。(内部表出)
3 実際の交換過程に入った商品の使用価値は、他の商品の使用価値との比較で相対的なもの(相対的価値形態)に変容し、一方が他方の価値の基準になるという関係ができ、この関係から生まれた合意価格(等価形態)で交換が成立する。この場合の合意価格を交換価値という。(外部表出=表現、会話、表記)
4 交換後の使用価値は社会的な価値と個人的な価値に二重化し、社会的な価値は交換価値として等価化する。(反作用、対象化)
つまり、2の段階で抽出すれば<式>に拘束されずに概念抽出ができます。
「使用価値、交換価値」の段階で類似概念を抽出するのと、「相対的価値形態、等価形態」という段階で類似概念を抽出するのとは意味が違ってきますし、抽出する概念によっても違ってきます。<式>を使う使わないに関係なく、「相対的価値形態、等価形態」という段階での対応を考えるのであれば、ここでは「同じ価値だと判断する方法と論理」を言っているので、あるかたち(形態)に変容(客観化と基準化)したものというところまで上昇し、相対的価値形態からは、たとえば「価値が普遍化できる状態」という概念を、等価形態からは「社会的に共有された状態」という概念を抽出し、相対的価値形態→自己表出、等価形態→指示表出として対応させるとすれば、「究極の自己表出は等価的な指示表出になる。」という意味に考えることができます。これと意味として近似的な表現が「拡張論」にあります。
「等価価値形態の表出が(自己表出が)、どんな使用価値との対応をもとめずに、等価の等価(等価内部における等価)を目指すような領域にはいる。」
この文章で「等価価値形態」を「相対的価値形態」に換え、この引用文の前に述べられている文脈から「使用価値」は「指示表出」に換えることができ、「等価の等価(等価内部における等価)」は自己表出の連鎖による指示表出化と考えれば、「相対的価値形態の表出が(自己表出が)、どんな指示表出との対応をもとめずに、等価的な指示表出を目指す領域に入る。」となり、「究極の自己表出は等価的な指示表出になる。」という文章と意味が通じます。これはまた「文学作品の抽象的で緊張度が高い言葉を<法>に入れてもいいのではないか」という考え(『吉本隆明 五十度の講演』ヘーゲルについて「法の言語と文学の言語」1995年 西武百貨店での講演 ほぼ日刊イトイ新聞 2008年)にも通じるものだと思います。
by 中村友三
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 471 |
〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉 ① |
「親鸞から見た未来」 |
講演 |
|
『吉本隆明が語る親鸞』 |
東京糸井重里事務所 |
2012.1.16 |
※「親鸞から見た未来」は、1988年10月の講演。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 現在の特徴 |
何が永遠の課題で、何が緊急の課題なのか |
|
|
項目
1 |
①
現在ということの特徴(引用者註、これは小見出し。以下同じ。)
現在、さまざまな社会現象や世界現象が我々の目の前で起こっています。そうした社会現象や事件に、ひとつの特徴があるとすれば、一見すると、〈緊急の課題〉に見えるもののなかに、本当は〈永遠の課題〉が混ざって、一緒に出てきていることではないかと思われます。もうひとつ申しあげれば、小さな問題と考えられていることのなかに、永遠の問題と緊急な問題とが一緒に混ざって入ってきているということが、とても大きな特徴ではないかと思うのです。
大きな事件や大きな問題として出てくることのなかに、大きな問題が真にあると考えたり、また、小さな問題を小さな問題とだけ考えると、誤解を生ずるかもしれない気がして、それが、現在の特徴のような気がしています。
(「親鸞から見た未来」P178『吉本隆明が語る親鸞』2012年1月)
※「親鸞から見た未来」は、1988年10月の講演。
②
〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉は、二者択一ではない
この問題に対する親鸞の考え方は、ぼくにとってはたいへん示唆の大きい考え方です。 ぼくなりの解釈を申しあげますと、眼前に切実な問題や事件、あるいは社会現象が次々に起こっている場合に、それを〈緊急の課題〉と考える、あるいはこれは〈永遠の課題〉なのだと考える、どちらの考え方をとっても、たぶん、駄目なのではないかと思います。 もっと投げやりな言葉を使えば、それはどちらでもよくて、大した問題ではなく、手をつける場面に自分が当面していたら手をつけたらいいし、していなかったら、それでもよろしいではないですかと、ぼくなら考えます。
つまり、これは二者択一の問題として存在しないと思います。
先ほどぼくは、あらゆる社会的な事件、身近に迫ってくる問題や現象は、緊急の課題と永遠の課題が混ざって出てきていると申しあげました。
混ざって出てきている問題に対して、二者択一で、たとえば緊急な課題にだけ対処する、あるいは緊急な課題はどうでもいいと考えて、永遠の問題としてだけ考えるというふうに、どちらかを選択すると、必ずその事柄に対する理解を間違えると思います。
社会では、これをどちらかの課題として解けとか、おまえはどちらかの課題に着けとしばしば言われますが、その言われ方はたぶん間違いです。
これはよく見なければいけません。つまり、ひとつの課題として見えるもののなかに、何が永遠の課題で、何が緊急の課題なのかを、よく見なければいけないと思います。
この問題に対して、「聖道の慈悲と浄土の慈悲は違うのだ」という親鸞の言い方は、ぼくにはたいへん示唆が多くて、勇気を与えられるのです。
(「同上」P181-P183)
③
親鸞の浄土についての考えを、現在に応用する
現在、身近に迫ってくる社会的な事件は、〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉が両方混ざって出てきていると理解した方がいいと申しあげました。そういう考え方にたいへん示唆を与えてくれたのが親鸞の「浄土から再び還ってきて、自在なる慈悲を発揮すべきだ」という考え方なのです。
緊急の課題っていうのは、こちらからあちらへいく課題です。それでは永遠の課題とは何かといったら、ある社会的な事件があったら、その事件を、時間的にいえば未来、もっと親鸞的な言い方をすれば浄土、あるいは死からの光線で照らし出してみなければわからない問題です。その永遠の課題が、あらゆる社会現象のなかに見ようとすれば見られるようになったことが、とても重要なことです。
たぶん、親鸞の浄土とは似ても似つかないものですが、生死に対する考え方や命に対する考え方が、仏教が発生当時からもっているものと、現在の文明社会におけるものとでは違ってきたことのあらわれとして、考えるほかないでしょう。
「ひとたび浄土へ往って還ってきて、自在に慈悲心を発揮すべきだ」ということは、あるひとつの課題のなかに必ず緊急な問題と永続的な問題の両方が入っているんだ、ということです。一見つまらないように見えても、そこには永遠の課題が入ってきていると言えることが非常に重要なことではないかと思われるのです。(※以下略するが、具体的な喫煙の問題に触れる。)
(「同上」P185-P186)
※ 細かなことであるが、まず「吉本隆明の183講演」のA112「親鸞から見た未来」、その「講演テキスト」をコピーしてそこからわたしが引用する部分を取り出し、『吉本隆明が語る親鸞』所収の「親鸞から見た未来」と照らし合わせ、そちらの文章に手直ししている。吉本さん自身が手直ししたのだろうか、講演そのものの語りに対して、本になった方は、語りの文体ではあるがずいぶんと切り整えられてすっきりしている。つまり、吉本さんの語りの具体性が整序されている。
|
| 備考 |
(備 考)
①について、永続的な問題と緊急な問題が二重の色合いで立ち現れるようになってきた現在の特徴は、現在というものがある大きな歴史の段階の終盤にさしかかっているからではないだろうか。
〈緊急の課題〉も〈永遠の課題〉もごちゃ混ぜで、二者択一に迫ったり考えたりしてきた状況の中、誰もが薄々とは感じてきたようなこと―その問題は本質的な解決は現状では難しく対処療法的に振る舞わざるを得ないとか自分たちの生涯の内ではその問題が根本的に解決されることはないだろうとか―を現在の状況的な課題として〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉を抽出したのは、絶えず考えを深く詰めてきた吉本さんならではである。
③は、言葉や論理が親鸞の時代と現在とでは時代的に大きく変貌してしまっていて少し苦しげにも見えるが、つまり、「親鸞の浄土とは似ても似つかないもの」に見えたとしても、〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉という中に、親鸞の思想をすくい取り現在に生かしたことは、絶えず考え続けてきた吉本さんの優れた思想の達成と言うことができると思う。
この〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉(または、永続的な課題)という捉え方は、わたしたちが日常の中で曖昧にしてきたことをすっきりさせ、そしてより正しい判断を下すよう助けてくれると思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 476 |
逆立ということ |
第二章 吉本隆明『共同幻想論』を語る |
インタビュー |
|
『ミシェル・フーコーと「共同幻想論」』 |
光芒社 |
平成11年 |
※ 読みは、「ぎゃくりつ」あるいは「さかだち」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 実感(具体例) |
抽出された概念(三つの幻想) |
自己幻想と共同幻想との相互関係の通常状態と励起状態 |
|
項目
1 |
①
吉本 ぼくは、共同幻想の最小単位っていうのは、三人だ、三人集まったときっていうのは二人とは全然違うんだっていうんですね。たとえば、三人集まって、同人雑誌を作って、会費はいくらずつ払おうってなったときに、会費は、千円ずつ毎月払おうとかって三人で決めて、三人で同意したとします。そのうちに、たとえばそのなかの一人が失業しちゃって千円が出せなくなっちゃった。そうした場合に三人で取り決めた、毎月千円払うこと、という取り決めで、その人はもうグループからはずれてもらうんだ、なぜなら、三人で同意して取り決めた規則からはずれちゃったんだから、それはやっぱり、やめてもらうよりしかたがない、っていうふうになりますね。その個人は最初の取り決めのときは同意したそういうグループからはずれざるをえなくなった。そうなったとたんにもうその個人にとっては、じぶんも参加して取り決めた三人の規則っていうのは重荷になってきますし、また、否定的になっていく。また逆に守っている人の方からみれば、その人はいかなる事情があってもとにかく払えなくなったんだから、あいつは、やっぱりグループではない。取り決めだけに照らしていえば、つまり、国家でいえば、法に照らしてだけいえば、もう、法にはずれたんだ、というふうになってくる。そういうふうにして個人と、三人のグループで決めたこととはだんだん反対して相互否定的になっていくことはあるわけで、そういうふうにかんがえてみると、どうしても、共同の取り決め、国家のなかでの個人っていうのは、本当は、自分も暗黙のうちに同意して国家の法律っていうのはできているんだけど、じぶんがそれを守れなくなったら途端に、共同で取り決めたそれと、個人の精神性とは違和感をもつようになって、もっと極端になれば、反対に否定的になっちゃう。だから、ぼくは、共同幻想というものと個人の幻想というのは元来が逆立するものなんだというふうにかんがえたんですね。
そういうところが特色で、あとは、その三つに分けたなかで何が特色かっていえば、対幻想、つまり家族とか社会というのは、家族の精神性っていいますか共同性っていうのは、共同幻想つまり国家みたいなものからも閉じられていくっていうふうになる。また、男女が恋愛でもいいんですけど、男女が関係をもち濃密になってくればくるほど周囲から閉じられていくってことがあります。つまり、家族という概念は、結局は二人の共同なんだけど、社会的な共同性とも、また個人とも違うレベルのところでかんがえて、取り扱わないといけないんじゃないかなっていうことはやっぱり、特徴といえば特徴だとおもうんですね。個人の精神性と共同社会における精神性っていうのは逆立、逆さまなんだっていうのが、多分、共同幻想をかんがえていくときの特色っていいますかね、ポイントであったようにおもうんですけどね。
萩野 個人幻想と共同幻想が逆である、逆立している、逆立ちしている、そういう形なんだといわれたところが、私は本を読んでいて、深い意味があるような気がしていたんですが、ただ、今お話しを聞くとそれは初めから反対ではなくて、つながっているんだけれども、ある問題を介すると全然違う方向に作用する、逆立するという考え方ですね。
吉本 そうですね。極端までといいますか本質までいっちゃえば逆に行くだろうけれど、普通一般的にはどうなっているかというと、一種の違和感としてある。・・・中略・・・だけど、きわどくしていけば、どちらも、やっぱり、逆立して矛盾して、相互否定的になってるとおもうんです。普通、一般的に正常なときには一種の違和感としてある、あるいは同和感としてあるっていうだけでいいんじゃないでしょうか。逆までいかないんじゃないでしょうかね。でも、とことんまで推し進める事態がやってきてしまえば逆立してしまうっていうふうになります。
(『ミシェル・フーコーと「共同幻想論」』P64-P66 吉本隆明・中田平 光芒社 平成11年)
|
備
考 |
(備 考)
ささいなことだが「逆立」の読みについて。
上の吉本さんの語りの終わり部分「個人の精神性と共同社会における精神性っていうのは逆立、逆さまなんだっていうのが」と、その吉本さんの言葉を受けた萩野氏の「個人幻想と共同幻想が逆である、逆立している、逆立ちしている」という言い方によって、「逆立」は「ぎゃくりつ」と読まれていると推定できる。
三つの幻想として抽出された概念は、本質として位相が違うということになる。個と共同性が、普通は個の中で軽い異和感や同和感と感じられて相互の異質さはあんまり意識されないとしても、突き詰められた状況では相互の異質さが際立ってくる、つまり位相の違いが気づかれることになる。
三つの幻想という概念の抽象性は、恣意的な思いつきといったようなものではなく、きちんとわたしたちの生活実感と対応させられている。その実感が踏まえられている。同人雑誌の例や恋愛関係にある男女の例などは、その実感の例に当たっている。
「逆立」ということがわからないとかいうことを昔ときどき見かけたが、それは論者が頭の概念世界でばかり考えているからだろうと思われる。理論物理が実験科学参照するように、概念や論理というものが日々の大多数の人々の実感をきちんと参照すべきなのだ。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 484 |
加速する現在 |
「鶴見俊輔―何をどう言っても安心な人」 |
インタビュー |
『道の手帖 鶴見俊輔』2008年12月30日発行 |
吉本隆明資料集173 |
猫々堂 |
2018.3.10 |
※ 聞き手 大日方 公男
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 僕なんかが十年二十年前に考えた予想や想像を超えて |
スピード |
急きたてられている |
収縮や抽象化を進める |
項目
1 |
①
―・・・・・社会の変化にどう対応したらいいのか、何かメッセージはございますか。
吉本 科学技術に依存する産業で、僕なんかが十年二十年前に考えた予想や想像を超えて遙かに先にいっていると感じます。人間はそれにひたすら付いて行くしかないという今の事態は驚きですね。コミュニケーションの手段が飛躍的に進展するのは便利でもあるし、利益にもなるでしょうから、社会的にも抵抗しがたい。僕らは多少は自己体験に引き寄せて息を継ごうとしているけれど、若い人たちがそのスピードが当たり前だと感ずれば、ひたすら後を追いかける以外のゆとりはなくなっている。そのスピードは産業や科学技術だけでなく、文化や学問や文芸までも被っている。僕は文芸という狭い領域から眺めているだけですが、政治や社会、学問や科学、芸術や文芸の差がなくなるまで抽象化して考える以外にないと、思っています。社会や科学のことを考えることが同時に文芸の問題にも応用できるところまで収縮や抽象化を進める以外に方法はないというのが僕の実感です。若い人は細分化されたそれぞれの分野を追いかけてそこから派生する問題を考えるのが役にもたつし楽しいかもしれません。でも、僕は相当な分野にまで共通の問題としてそれが理解できるところまで、もう少し考えを詰めて、現在起こっている問題を捉えようと思っています。多分科学技術のようなものが先頭きった主役になるかもしれませんが、そうすれば少しゆとりが生じるだろうと思います。一瞬にして地球の裏側の人と顔を見ながら対話できるということが、あらゆる文化や文明の問題に繋がっているルートを見つけることが、自分なりの切実な課題だと思っています。逆に言えば詩も小説も他の分野に当てはめても応用が利き、そこでの考え方が分かるというところまで行けばいいと思います。でもそれが分かっているのでなく、むしろ困っている、急きたてられているというのが今の実感です。
(「鶴見俊輔―何をどう言っても安心な人」P48-P49『道の手帖 鶴見俊輔』2008年12月30日発行 『吉本隆明資料集173』猫々堂)
|
| 備考 |
(備 考)
晩年の吉本さんから見た〈現在〉というものの有り様とそれを捉えようとする時の困難さと考えられる方法について語られている。そうして、このことはわたしたちにとっても継続する課題である。今のわたしがあれこれ言うことはできないけれど、例えば文学的表現のひとつの場所にすぎない現代詩を、全文学的な表現において、さらには人間的な全芸術表現において、きちんと位置づけ納得したいなという欲求は持っている。そうして、わたしたちにこうしたある普遍への欲求を促すのは、人間的なあらゆる分野で人類史的な内省を促すという〈現在〉の歴史的な段階の持つ性格によるものであり、その促しではないかという気がしている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 493 |
けんかの作法から |
「佃ことばの喧嘩は職業になりうるか」 |
論文 |
「小説新潮」臨時増刊 1985.7 |
重層的な非決定へ |
大和書房 |
1985.9.20 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 超越的 |
いやいやながら受け身で |
|
|
項目
1 |
①
私はやがて喧嘩から音声を喪うようになった。つぎにしゃべり言葉を喪いはじめた。大人に近づいていったのだ。
やがていつの間にかとうとう、書き言葉で喧嘩する商売にすべり込んでいたのである。幾たびか言葉の白刃の下をくぐった経験からいえば、書き言葉の喧嘩にはひとつの公理系が見つけられる。
(1)論理によって反駁できない論理はありえない。どんな完璧にみえても論理には、きっと欠陥が見つけられるものだ。これはゲーデルの不完全定理とは関わりなく見つけられたものである。
(2)相手の弱味をにぎったとおもったときが、じつはいちばん隙ができる機会で、危ないときである。
(3)書き言葉では、喧嘩に勝つという意味は超越的になる。相手の言葉にたいするこだわり(つまりそれがあるから喧嘩をしているその当のこと)をできるだけていねいにかい潜り、そのこだわりの外へ、できるだけ遠くまで出てゆくこと。それが勝つことだ。
(4)書き言葉は文字でのこってしまうし、また声を抑圧しているために、腕力沙汰や、しゃべり言葉の喧嘩にくらべて、いっそう深く傷を与え、また傷を負う。私みたいなものがいうと、噴きだして笑う者がいるかもしれないが、できるなら書き言葉の喧嘩はしない方がいい。するときはいつもいやいやながら受け身で、だが本気になってやれ。
(「佃ことばの喧嘩は職業になりうるか」『重層的な非決定へ』吉本隆明 大和書房 1985年9月)
|
| 備考 |
(備 考)
この喧嘩について述べた文章も長らく探していたものの一つである。最近出会った。上の引用部分の(3)の「書き言葉では、喧嘩に勝つという意味は超越的になる。」というような言葉がずっとおぼろげに印象に残っていた。そして、最近のこの項目との関連で言えば、ここの「超越的」ということは項目492の「普遍文学」、普遍の言葉ということと関係がありそうに思う。
書き言葉の喧嘩として挙げた「公理系」の(4)は、吉本さんの体験的なものと資質とが加味されたものとして出ていると思う。
(4)にあるように書き言葉のけんかに限らずあらゆるけんかはしないに越したことはない。が、個の資質的な必然と状況との促しによってけんかに及ぶことは誰にもあり得る。
「ひとつの公理系」の(1)にある「ゲーデルの不完全定理とは関わりなく」ということは、おそらく論理そのもの根幹、存立の基礎を疑ったゲーデルの不完全性定理とは関係なく、論理の内の世界においてということだと思う。
現在の内から現在の空間に生み出されるあらゆる論理は、現在においては完全に見えるようであっても、人間の歴史の流れにおいては部分的であることを免れない。このことは太古からの人類の歴史をたどってくれば確からしく思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 504 |
学童期 |
「学童期というのは人間の持っているものが全部出てきてしまう」 |
インタビュー |
『子供はぜーんぶわかってる』―超「教師論」・超「子供論」 |
批評社 |
2005.8.1 |
聞き手 尾崎 光弘 向井 吉人
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人間の動物性(獣性) |
生意気なやつ |
ある特定の育てられ方をした子供 |
|
項目
1 |
①
吉本 いただいた資料にも書かれていましたけれども、学童期というのは人間の持っているものが全部出てきてしまう、フロイト流に言えば人間の動物性(獣性)というものが出てきますし、いろいろなものが極端に出てきます。だから何ていいましょうかね。僕は今もそうですが、もしかしたら中学生以降なら先生をやれるかもしれないな、と思いますけれども学童だけはダメだと思っています。生意気なやつ(註.1)というのは、何て言いますか何不自由なく育ち親もよく扱ってくれた子供だと思うのですが、僕は大人になってもそういう子には何となく反感を持っていて、言うことが生意気だとちょっと本気になって喧嘩したくなっちゃう時があるのです。子供と本気になって喧嘩するなんてみっともないな、と思いますからやらないだけで、本当は癪にさわってしょうがない、そういう子供がいるのですね。ある特定の育てられ方をした子供には特に極端に出てくるのです。僕の子供時代はいじめっ子ですから生意気なやつは、仲間と一緒にいじめてしまいそれで済んだのですが、大人になってからは本気にならないとやれないや、と思いますね。
尾崎 やっちゃいますか?(笑)
吉本 抑えてやらないけれども本気になっちゃうのです。
尾崎 よくわかりますね。
(『吉本隆明 子供はぜーんぶわかってる』―超「教師論」・超「子供論」 P27 批評社 )
吉本 隆明 尾崎 光弘 向井 吉人
|
| 備考 |
(備 考)
「生意気なやつ」というのは、確かにいるような感じがするし、わたしも出会ったことがあるように思う。そういう子どもとの応対は、「癪にさわってしょうがない」し、まともな応対は不可能のように感じられる。つまり、その場から立ち去るほかない。これは、「生意気なやつ」本人以外では誰にも思い当たるところがあるような気がする。素人考えで言えば、そんな「生意気なやつ」というのは、よく気がつく母を守護神として自分が全能のように振る舞う性格のようなものを形作ってきた者であろうか。
しかし、同じような育てられ方をしても、その後の家族や地域や友達などの環境因も加わり、ふしぎなことに人は様々であり得る。
この「人間の動物性(獣性)」というのは、わたしも子ども時代を体験してきたことから言えば、動物そのものとは違った、人間的な残虐性を持った人間的動物性という気がする。つまり、動物性の残虐さと人間性の暗黒部分とが結びついたもののように思う。
(追 記) 2020.3.19
(註.1) 関連として。
近所の悪ガキの遊び仲間がわたしの家の猫を捕まえて、近くの掘割の橋の上から投げ込んだと聞いて、待ち伏せして仕返しをしたことがある。わたしにたいする反感をわたしの好きな猫を溺れ死にさせることで晴らした根深さが許せなかった。無邪気な魂も通俗的な正義感もみえないとおもった。
そんな少年の芯のつまった悪さの日常の繰返しが何によって成り立っているのか、理解の外にあったからだ。
いまでもこういう少年初期の子どもは苦手だ。本気で怒りたくなってしまうからだ。芯の通った悪ガキで、その芯がどこからくるのかわからないのだ。そして大方は親たちのごうまん、そのごうまんを許している富裕(お金持ち)のせいにしていた。
(『少年』P143-P144 徳間書店 1999年5月 )
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
| 514 |
北と南の同一性 |
『吉本隆明 戦後五〇年を語る』170 |
インタビュー |
週刊 読書人1999年7月16日号 |
読書人 |
※聞き手 山本哲士・内田隆三・高橋順一
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 時代的にとことん遡っていけば同一だというところに行く |
三種類ぐらいの説 |
後はもう、もっと奥地の問題 |
天皇制の問題 |
項目
1 |
①
吉本 僕は、柳田国男は大部分見えていたと思うのです。山本さんが言われたように、空間的に言いますと、僕らが気をつけてきたのは、日本列島の中での南の方、つまり琉球、沖縄といったところです。その辺りでいろいろなことを考えてきたのですが、北の方と言いましょうか、関東以北、北海道、樺太、沿海州といった辺りでもう一回見ていって、それがどこで南の方の問題と合致し同一だと言えるのかをやらなければいけないと思っています。
それからもう一つ、空間的に言えることは、日本列島とアジアの大陸、とくに沿岸地区との関係なのですが、大雑把にいうと、日本列島の内部では、北の方と南の方はほぼ同じではないか。人種的にも同じだし、気候が違うから風俗はちがったりしますが、文化的には同じではないかと柳田国男は考えていたと思います。では、大陸と日本列島の内部、あるいは大陸の沿岸部はどうなのか。そこまで同じだとは柳田は考えていなかったと思います。しかし、そこが問題になるわけで、日本列島の古い時代、要するに近畿地方を主体ではなく、南の方と北の方を主体に考え、同一だというところまで時間的に遡ったところでいえば、日本列島と大陸沿岸部とは違うと言えない、同じではないかという問題意識があると思うのです。
なぜかと言いますと、中間の発祥点を東南アジアと考えて、そこからどこを経由してもいい、インドやマレー半島を経由してもいいのですが、それがオセアニアの島の方まで回り回って入って来たという経路と、東南アジアから沿岸部を通ってずっと北の方まで延びて行ったという経路と、二つの経路が考えられます。僕は時代的にとことん遡っていけば同一だというところに行くと思うのですが、そこは柳田国男が考えていないところです。僕らはそれを考えに入れないといけない。日本列島と大陸沿岸部は同じで、そこまで行けるのではないかという問題意識は、柳田国男の時代では出しにくかったと思いますが、今はもう出せるのではないでしょうか。
②
吉本 どういう解釈があるかというと、一つは、日本の天皇は騎馬民族の末裔で、大陸からやって来たという江上波夫さんのような説があります。それから、南の島伝いに来たという説と、もう一つ、これは柳田国男の考えですが、東南アジアから琉球・沖縄に渡り、琉球・沖縄から九州に北上してきて、そこである期間滞留し、航海術に長けてきてから、瀬戸内海をたどって近畿地方に来たという説があります。三種類ぐらいの説がありますが、この三つは同じだというところまで行けるのじゃないか。もとは南中国のどこか、たとえば雲南省のようなところかも知れないし、あるいは東南アジアかも知れないけれど、そこがもとで、日本に今ある三つの説は本当は違わないというところまで時間・空間的に遡れるのではないか、そこまでだいたい行けるのではないかと僕は思っています。
③
吉本 後はもう、もっと奥地の問題になってきて、古アジア的な人種と言われているところまで行ってしまう。民族に分かれる以前の段階に行ってしまうわけです。そこまでは別に何も言う必要はないと思います。日本列島の文化や、あるいはそこの支配者や制度がどうだということを言う場合には、だいたい騎馬民族説と、島伝いに来たという説、それから柳田国男みたいな説に分かれます。
吉本 大嘗祭における儀式で、悠紀殿・主基殿というのがありますが、その小屋は、北方の朝鮮系と同じではないかという説の人もいます。いや、そうじゃない、これは南太平洋の島にある、酋長さんが儀式するときの小屋と同じだと書いている人もいます。実際に見た人で、そう書いている人もいるわけです。
僕が思うには、三つとも違うように見えて、本当は同じではないのか。その時間・空間の同一性が問題として残っているだけで、それが解明されれば、同一だと言えるところまで行けるのではないか。そこまで行けば、天皇制の問題はだいたい終わりになるのではないかという気がしています。
今あるような対立線は、馬鹿らしいといえば馬鹿らしいのです。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』170 週刊 読書人 1999年7月16日号)
※聞き手 山本哲士・内田隆三・高橋順一
※①と②と③の初めまでは、連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
解体すること、遡行すること、そうすれば、ある時間軸上で対立的に見える問題も「同一」という所まで行けるのじゃないかという吉本さんの解体と遡行という方法は、依然として方法的優位を持っているように見える。
この世界の現状は、一般大衆の生活や意識は別として、政治や知識層では相変わらず民族国家とその固有の伝統なるものの秩序感覚で武装されているように見える。そういう現状に対して、ここでの問題は、時間軸を遡行すると当然のこととして、それらの固定化した現状を吹き飛ばし、この列島も日本人も、世界に向かって開かれて在る、現在的に開かれて在るということをわたしたちに指し示している。
|
講演日:1995年7月9日 吉本隆明の183講演の「講演テキスト」より引用
関連項目516,517
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 国家の前には法 |
法っていうのの前には宗教があった |
発展の経路の分岐点になる概念 |
国家の条件 |
項目
1 |
①
5 国家ができる前、何があったか(引用者註.「講演テキスト」の小見出し)
フーコーのあれに入っていきますけど、つまり、国家なら国家っていうのは、たとえば、それ自体の歴史を持っているって考えればいいと申しましたけど、その考え方は、ヘーゲルとか、マルクスとかっていう人たちの観点から、どうしても出てくるのです。
そうすると、国家っていうものの以前に、何があったのかっていうと、いろんな言い方ができるんですけど、国家の前には法、法律の法ですけど、法っていうのがあったんだ、で、法っていうのの前に何があったんだ、法っていうのの前には宗教があったんだっていう、そういう歴史的な経路をたどっていきますと、そういう一種の発展の経路の分岐点になる概念っていいますか、考え方が成り立ちます。
つまり、国家が国家として成立しない以前には、何があったんだろうか、つまり、国家の歴史をたどるとして、その以前には、何があったんだろうかっていえば、それは、法があって、それが国家の代わりをしてたっていうふうに言うことができると思います。
その場合の法っていうのは、たとえば、むかしの、古代の、村なら村の集団性っていいますか、地域性っていいますか、それは何が規制して、何がそれに対して、関係づけて、枠組みをつくっていたのかっていえば、やっぱり、村の掟が、その代わりをしてたって言うことができます。
つまり、国家が成り立つ以前には、何が国家の代役をしていたかっていうと、それは、やっぱり、掟っていいましょうか、法が代役をしていたんだって考えることができます。人間の集団性っていうののなかで、部族っていう概念がありますけど、部族っていう概念のところまでは、部族っていうのは、いくらたくさん連合して集まっても、部族の集まりっていうことだけでは、掟とか、法とかっていうのは、それを、枠組みをつくったり、生活を規制したりする掟っていうのはあるわけだけれど、それは、国家と違うわけです。国家の代役はしているわけだけど、国家とは違うわけです。
何が違うかっていうと、いちばん違うのは、つまり、国家の条件っていうのがあるわけだけれど、国家の条件っていうのは、ヘーゲル・マルクス流に言えば、それ自体が独立したひとつの枠組みの世界をつくっているかどうかってことが、いちばん大きな、国家になっているか、あるいは、国家以前の、つまり、法律、あるいは、法にしか過ぎないかってことの、いちばんの分かれ道です。
②
それで、国家が国家として閉じてて、人々が生活している社会とは、別問題なんだっていうことを、いちばんはっきりそれを象徴させるのは何かっていったら、それは、武力です、武装力です。つまり、市民社会とか、村の社会でも、村の共同体でも、ほかの村とケンカしなきゃならないとか、ほかの村から、この村の物を持ってかれるのはやだって言ったら、こん棒でも、弓矢でも持って、武装して、そういうふうにさせないように、ほかの村との争いになったときには、武装して争うみたいなことっていうので、武装っていうのはあるわけですけど、国家っていうのと何が違うかっていうと、国家っていうのは、そういうような、村なら村が生活を守るためとか、自分たちの社会の共同体を守るために、武装力をもって、ほかの村と争うみたいな、そういうやりかたと、国家とは、ぜんぜん別の次元で、閉じられた国家っていうものの、いまの政府って言えば、いちばんいいんですけど、政府が政府として動かせる、政府だけとして動かせる武装力っていうのを、いわゆる村々が、共同体が、ほかの共同体とケンカしたり、争ったときのために持っている武装力とまったく違うように、国家が、自分の武装力を持って、あるいは、支配する長老たちが、そういう武装力を、自分たちで持って、それが、村を守る、自然にできあがった武装力とは違う次元で、そういう権力を、長老たちが持ったっていうふうになったときには、だいたい、国家っていうのが、できる糸口っていうのが、いちばんつくわけなんです。
ようするに、国家は国家として閉じられた、あるいは、村々を治めていた長老会議みたいのがあるとすると、長老会議は、村の人たちがどうであるかってことじゃなくて、自分たちが、こう言えば動かせるような、そういう武装力をつくろうじゃないかっていう話し合いになって、そういうのをつくっちゃって、それは、村の人たちが、隣の村とケンカしたときに、やむをえずつくった、そういう武装勢力とは、まるで次元が違うっていうようなかたちで、そういうのを持ったときには、そういうのが、国家というものの糸口になるわけです。
ですから、それはどういうことかっていうと、ようするに、国家が、法律、あるいは、掟っていうのがあった段階から、それが、ちょっと発達していっちゃうと、それが国家形態になる。国家形態になったいちばんの象徴を、どこで見ればいいかっていったら、村を治めている、首脳とか、長老とかが、自分たちの命令で動くような武装力を持とうじゃないかって、村の人たちがどうしたっていう、そういう武装力とは違うところを持とうじゃないかっていうふうに考えて、そういうのを持ったときが、いちばん閉じられた、村の共同体とは違った、閉じられた首脳部の共同体っていいますか、首脳部の共同体のまとまりができたっていうことを意味します。これがやっぱり、国家の徴候だっていうことになります。
そうすると、村々の掟っていうのは、たちまちのうちに、国家の長老会議っていいますか、長老会議なら長老会議の掟とか、武装力で、ものを言わせるぞみたいな、そういう関係付けとか、命令とか、そういうのに、たちまちのうちに包括されていくっていうことになります。それが、国家のはじめで、ですから、逆にいうと、国家以前の国家と同じ役割は、法律、あるいは、掟っていうものが、それをやっていた役割をしていた。すると、掟っていうもの以前に、掟の代わりをしていたのは何だろうか、それは、宗教であるっていうふうに言うことができます。
それは宗教的に、村のなかに、かならず、神がかりができる人がいまして、神がかりができる人が、神がかりで、神さまの御託宣で、こうせい、ああせいっていうなのを、神がかりになったときに、村の人たちに、それを命令するっていいますか、これは、神の命令であるっていうことで命令する。それは、法律ではないんですけど、やっぱり、法律の代わりに、宗教的な神がかりの御託宣なんですけど、つまり、神さまはこう言ったぞっていうふうな言い方なんですけど、それは、それ自体が、法律の代わりになるっていうふうになります。
そうすると、国家の以前には、やっぱり、法律があり、法律の以前には、それの代わりをしていたのは、やっぱり宗教だっていうことになります。つまり、神がかりの人の御託宣っていうのが、神の言葉として、村々を規制していくとか、村々を支配していくとか、村々に命令していくっていうようなことの代用をします。
③
そうすると、国家っていうのの、いちばんはじめのかたちっていうのは、法律っていうのから、宗教っていうかたちに、さかのぼっていって、こういうかたちが、国家のかたちの、いちばん古いかたちだろうと、そうすると、国家の歴史っていうのは、そういうふうにして、たどっていけば、国家っていうのは、そういう歴史をたどって、いまの国家になったんだっていうふうに言うことができます。
いまの近代国家以降、あんまり変わり映えがしていないんですけど、近代国家以降にできた、いわば民族国家っていうふうに言われているものなので、現代でも、それは壊れていない、つまり、市民社会の要求のほうから、壊れそうになって、産業経済の要求から、国家の枠組みが壊れそうになってはいますけど、依然として壊れてなくて、日本国は日本国として政府を持ち、アメリカ国はアメリカ国の政府を持ちっていって、国家のかたちを保っております。
それで、それに対して、市民社会っていうのは、その規制をひとりでに破らなきゃ、貿易もできないし、産業も発達しないってなりますから、だから、それを破ろうという勢いっていうのは、産業のほうにはいっぱいあるわけですけど、国家、あるいは、政府でもいいですけど、それはやっぱり、国家の枠組みを守ろう、守ろうっていうふうに、保とう、保とうっていうふうにしてるっていうふうに考えることができます。
(『 A172フーコーについて』吉本隆明の183講演 講演日:1995年7月9日)
※①、②、③は、連続する文章です。
|
備
考
|
(備 考)
邪馬台国論争というものがあった。わたしは推理小説を読むようにおもしろく古田武彦の本をずいぶん読んだことがある。その古田武彦は、邪馬台国論争で、「邪馬台国」(「邪馬台国」という名称も正式には違うと述べている)は博多近辺の九州にあったと、九州王朝説を主張していた。一方、吉本さんは中年期のまだ若い頃だったと思うが、邪馬台国論争に触れてそれがどこにあったかはあんまりたいしたことないと述べていたと記憶する。たぶん、現在の政権下でわが国で開催された、何々サミットはいつどこで開かれたとか、こういうことが、歴史にとってはほとんど意味をなさないのと同じものだと思われる。もちろんどんなささいなことでも、わからないよりわかった方がよいとは言える。一方、「邪馬台国」のような小国家がこの列島にどれほどどのように存在し分布していたかということは意味のあることである。これは、ある抽象度で歴史を捉えることに近い。
ここでの吉本さんの話は、「国家ができる前、何があったか」という問いに対して、具体像で答えているわけではない。具体像では、この列島に限らず世界の各地域でも様々なバリエーションがあっただろう。ここでは、世界普遍性とも言うべきある抽象度でイメージし捉えられている。「それ自体が独立したひとつの枠組みの世界をつくって」いく国家の成立への過程と構造として語られている。そして、この言葉のイメージや概念や論理の中には、これまでの吉本さんのすべての思想的な経験が含まれ、それらが駆動している。その思想的な経験とは、分けて具体的に言えば、人間の歴史に関わる他者の数々の書物を批評的に読むという体験や『共同幻想論』や『南島論』などの自らの書くいう体験、そして自分が戦争-敗戦と歩んできた体験である。
付け加えれば、このある抽象度ということに関しては、吉本さん自身がかつて『共同幻想論』(1968年)の「序」で述べていたことである。
柳田国男は、この列島をずいぶん歩き回った。そしてその記述された言葉には、柳田が見聞きし触れた対象の具体像が溶け込んでいる。一方、吉本さんによるとへ-ゲルはアフリカを旅することもなくアフリカについて記述を成したという。ヘーゲルの世界史は、アフリカを未開で野蛮な世界と捉えている。とても深い洞察力を持っていたから、もしヘーゲルがアフリカを旅していたらまた違ったアフリカのイメージを持ったのかもしれない。このことは、遠く離れた世界のことや他者理解に際して、わたしたちにとってもとても現在的な問題であり続けている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
| 520 |
考古学的な面 |
フーコーについて |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日 |
講演日:1995年7月9日 吉本隆明の183講演の「講演テキスト」より引用
関連項目521,522
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 結節点、境界面 |
フーコーとヘーゲル・マルクスの出会う場所 |
境界面を見る |
日本の宗教を具体的な例として |
項目
1 |
①
7 知の考古学という方法 (引用者註.「講演テキスト」の小見出し)
それで、なぜこんな話になったかっていうと、宗教がどこで法になるかっていう、その結節点っていうか、境界面っていうのがあるわけです。この境界面の考察の仕方によっては、フーコーがそういう言い方をする「知の考古学」っていうふうに、つまり、知恵に関して出てきたものごとっていうのは、考古学的に蓄積されるものであるっていう、極端にいいますと、考古学的に蓄積されて、現在に至るものである。
ですから、考古学的な面っていうのはどこにあるかってことを見つけさえすれば、ヘーゲル・マルクス流の法から国家へ移るんだって、ようするに、原則的に段階を考えて、それから、法の以前には宗教があったんだっていう、そういう段階的な考え方と、接触点を用いるわけです。
段階的な考え方っていうのは、たいへん抽象的であり、また、普遍的であるって、そのふたつの条件を持たないと、段階的な考え方っていうのは成り立たないで、ヘーゲルっていうのは、一生懸命それを見つけ出したってことなんですけど、それとおんなじように、フーコーは、そうじゃないと、知恵にかかわることは全部、段階じゃなくて考古学だ、つまり、考古学的な知恵のある面をはっきりさせると、知恵っていうのは、考古学的な遺物と同じように、層になって次々次々重なってきて、現在に至るんだっていうふうに考えることができるっていうのが、たぶん、やさしく言い直した、フーコーの基本的な考え方です。
そうすると、ヘーゲル・マルクス流の考え方、つまり、段階的な考え方っていうのと、そうじゃない、知恵の広がりっていうのが、層を成していて、それがどんどんどんどん積み重なりをやってきて、現在に至るんだっていう場合に、それじゃあ、知恵の考古学の層っていうのは、どうやったら見つかるんだっていうことを接触させるためには、境界面を見るのが、いちばんいいだろうっていうことになると思います。
それだから、いま、お坊さんのっていうか、僧侶の話をしましたから、あれしますと、宗教が法になるっていう契機をいちばんはっきり、日本の宗教を具体的な例としてとりますと、どういう境界面を切ればわかるんだっていうことで、切ってみますと、それを切ったはじめっていうのは、ようするに、いま申し上げてきました、日本の宗教でいえば、浄土系の宗教、つまり、具体的な人でいえば、法然とか、親鸞とかっていう、そういう人たちがはじめた、これは中世、つまり、鎌倉時代にはじまったわけです。新宗教のひとつなんですけど、法然・親鸞っていう人たちが、はじめて、宗教と法との切り口っていうのを、はじめて明確にしたわけです。
そうすると、その明確にしたところを取り出せれば、それは、段階じゃなくて、考古学的な層なんだっていう、層の移り変わりなんだっていうことがいえるっていうふうに、ぼくは思います。
②
(引用者註.仏教の修行について)
つまり、文明なんかつくらないで、乞食みたいな恰好をして座って、体のどこに精神を集中すれば、どういうイメージができるかって、何千年もかかって、そんなことばっかり考えてきたんです。だから、それは馬鹿馬鹿しいっていったら馬鹿馬鹿しいんだけど、まあ馬鹿馬鹿しいわけです(会場笑)。文明的にいえば、馬鹿馬鹿しいわけですけど、しかし、何千年もかかって考えだしたことですから、やっぱり根拠はあるわけです。つまり、やっと考えたんだよってことでいえば、精神の集中点っていうのは、いくつかありまして、仏教で決まっているわけで、それをどんどんどんどん進めていきますと、終いには、額にやってきて、それから、頭のてっぺんになって、頭のてっぺんまで精神の集中点があれすると、そこで出てくるイメージが出てくれば、修行は終わりっていうことになるわけです。
そうすると、死がただつくれるだけじゃなくて、イメージとしてただつくれるだけじゃなくて、死のなかに自分がいる、あるいは、死の世界のなかに自分がいるっていう、あたかも如実にっていいますか、如実にそのなかにいるってかたちで、死の世界のなかで、手触りとか、物が見えるし、まわりも見えるしっていうようなかたちで、自分もそのなかにいるのとおんなじようにして、死の世界のイメージがつくれるっていうわけです。そうすると、こんなにはっきりと、具体的に、ちゃんとあるんだから、だから死後の世界はあるぜってなるわけです。
そして、死後の世界は、こういうふうにして、修練することでもって、見たり、体験したりすることができるとすれば、現実の世界を体験することとおんなじじゃないかってことになるわけです。
そうすると、そこまで修行すれば、ようするに、生も無常であると思えば、死も無常である、つまり、はかないものであると、生もはかないものである、あるいは、生きているこの社会は苦悩であると思えば、死後の世界も苦悩であるとか、とにかく、いま、この世界も、あの世の世界も、みんなおんなじだよっていう境地に到達したときは、仏教における悟りってことになると思います。
③
でも、かれらは、何をそこでしたかっていうと、宗教、この場合は仏教なんですけど、仏教がやる宗教的修練っていうのには、意味はないんじゃないかな、つまり、自分が、たしかに修行して、そういうイメージをつくって、生死を克服するイメージをつくったってことは、自分でできたっていうふうに言うけれど、それは、別に言い換えれば、一般の人にはそれはむずかしすぎるし、できないからって言い方をしますけど、ほんとうをいえば、そういうことには、意味がないんじゃないかっていう、そういうイメージをつくるって、そういうことには、意味がないんじゃないか、あっても、その人にとって意味があるだけなんじゃないかっていうことに気がつくわけです。
そしたら、どうすればいいんだ、宗教っていうのは、どうあればいいんだってことを考えたと思います。その場合に、法然、親鸞は、言葉で南無阿弥陀仏って言えばいいんだっていうふうに言うけども、それは、どういうことを意味するかっていうと、そういう修練はしなくてもいいと、だけど、そうじゃなくて、ようするに、信仰の問題、つまり、宗教的な問題は、倫理の問題、つまり、善悪の問題に移し変えれなきゃだめだっていうことを、はじめて、自分たちが見つけ出して、自分たちが言いだしたわけです。
だから、法然、親鸞の、そういう言い方を、いちばん極端にいいますと、極端な言い方ではっきり言っているのは、「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」っていう言葉が、親鸞にもありますし、法然やその弟子たちにもありますけど、それに類した言葉がありますけど、つまり、善人だって往生できるんだと、だから、悪人なら、なおさら往生できるんだっていうふうに言ったわけです。
そう言うことによって、何を意味するかっていうと、信仰の問題は倫理の問題だと、しかし、その倫理の問題とは何かっていったら、ようするに、世間一般社会、たとえば、いまだったら、いまの日本の市民社会に通用している善悪の基準っていうのとは違う、かれらは、浄土っていうものの規模における善悪っていうのは、人間の社会があみだしている善悪の規模より、はるかに大きいもので、そんなものは包み込んでしまうような大きな善悪っていうのはあるわけで、それを仮に、ぼくはそういう言葉を使うわけですけど、普遍的な善悪だって考えれば、言い方をすれば、それは、普遍的善悪とは何なのかとか、普遍的善悪に帰依すべきだ、それを信ずべきだ、あるいは、それを信じられる方向にいくべきだっていうふうに、宗教の問題を移し変えてしまうわけです。信仰の問題とか、信仰を高度にするために、修練するっていう、それまでの仏教における修練の仕方っていうのを全否定するわけです。全否定して、それは倫理の問題だ、しかも、人間社会における、常識的に、他人をぶん殴ったら悪だとか、あるいは、他人を殺したら悪だとかいうふうな意味合いの、人間の社会がつくりあげている善悪の問題っていうのとは、はるかに規模の大きな善悪っていうのに、どういうふうに向かえるかってことが、それが信仰の問題なんだっていうふうに、置き換えたわけです。
じゃあ、人を殺したら悪であるっていうけど、それは人間社会の小さな規模の善悪の問題に過ぎないんだっていうと、誤解を生ずるので、ぼくは、日常茶飯事で、サリン事件のああいうふうな話題のとき、無差別に関係のないやつを殺しちゃうから悪いですねみたいなことを言ったら、それなら、関係ある人を殺したらいいっていうのか、言えるんですかってまともに言われて、ものすごく困ったわけで、それはそういう意味じゃないので、それは、たとえば、親鸞なら親鸞の言葉でいいますと、悪人のほうが善人より往生しやすいんだっていう言い方をして、善悪の規模がはるかに浄土っていいますか、信仰が到達すべき地点にあるところの倫理的な善悪は、つまり、普遍的な善悪は、もっと大きな善悪なんだってことからいいますと、親鸞の云い方は、人間っていうのは、なにかの契機、機縁です。だから、モメントってことです。つまり、機縁がなければ、人間っていうのは、ひとりの人間だって殺すことはできないよっていう言い方をしています。
だけども、個々の人にとっては、だれも殺したくて殺して、おもしろがって殺しているわけではなくて、殺したくないなって思いながらでも、戦争だからとか、自分も鉄砲を撃たなきゃ殺されちゃうからとか、そういう機縁があってあれすれば、殺したくなくたって、人間っていうのは、千人、百人、殺すっていうことだってありうるんだよっていうふうな言い方で、人間の社会が、あるいは、人間がつくりだす善悪の基準の問題っていうことの成り立ちかたっていうのと、怪しさっていうものと、もっと大規模な、宗教的、本来なら、信仰が到達すべき境地っていいますか、そういうのを考えると、それに該当するところの普遍的倫理、普遍的善悪っていうものに到達しようとすることが、宗教の問題であって、その善悪っていうのは、人間の社会がつくりあげた、あるいは、人間関係がつくりあげたそういうものより、もっと大きいものなんですよっていう言い方をしています。そして、それに到達することが、宗教の問題です。
それに到達するためにどうすればいいんだ。それは、言葉で、真心からの信心でもって、言葉で南無阿弥陀仏っていうふうに言えば、それで浄土にいけるんだっていう言い方をしたわけなんです。
(『 A172フーコーについて』吉本隆明の183講演 講演日:1995年7月9日)
|
備
考
|
(備 考)
例えば、もうずいぶん昔であるがヘーゲルやマルクス関連で〈疎外〉や〈弁証法〉ということが流行った時期があった。吉本さんが文章のどこかで、そのマルクスの〈疎外〉という概念も本当にわかっている者はわが国ではごく数人しかいないと思うと語られていた。この列島に新しいものが押し寄せ一時期流行し忘れられていく、こうしたことはなじみの風景ではある。若い頃の吉本さんは、マルクスの〈疎外〉という概念を自分のものとして理解して、それを自分の思考の表現によく駆使しされていたように見える。
ところで、〈疎外〉という概念や〈弁証法〉という考え方を絶対視する者もいただろう。ちょうどそれを新たに生み出し駆使したヘーゲルやマルクスがそうしたように。しかし、ここで吉本さんがやっているのは、フーコーの知の考古学という方法とヘーゲルやマルクスの段階的な考え方の一方を否定するのではなく、二つの方法が出会う場所を探っていることになる。自然科学で、光は、光子性と波動性の二重性を持つと観測的な事実を踏まえて言われているが、大雑把な例えのイメージで言えば、ヘーゲルやマルクスの段階的な考え方とフーコーの知の考古学という方法とは〈光〉という対象を捉えようとする場合の光子性と波動性になぞらえることができると思う。いずれの方法もそれで十全かどうかは保留するとしても、〈光〉という対象の真に迫れることは確かだと思われる。
吉本さんは、日本の宗教を具体的な例として、ある境界面を切ってみせて、解析している。それはフーコーの方法が本当に有効なのかという検証を伴う実験的なものである。こういうのが、他人(ここではフーコー)の優れた概念や思想を本当に生かすことなんだと思う。当たり前すぎることだが、そういう思想的な前提がわが国の思想状況においては希少だという気がするからここに書き留める。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
| 522 |
考古学的な層と段階 |
フーコーについて |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日 |
講演日:1995年7月9日 吉本隆明の183講演の「講演テキスト」より引用
関連項目520,521
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 聖徳太子の十七条の憲法 |
倫理と法との混合したもの |
法から国家へいくっていう経路 |
ひとつの考古学的な切り口のための法の抽出 |
項目
1 |
①
10 考古学的な層と段階 ( 引用者註.「講演テキスト」の小見出し)
そうすると、源信から親鸞まで、浄土系統がたどった、歴史的な経緯はどういうふうになっているかってたどることはできます。しかし、そういうたどり方をしても、考古学的な面っていいますか、そういうものは出てこないわけなんです、ちっとも。それだったら、そういうたどり方をするならば、そのたどり方をいつまでやってたって、はじまらないって、そんなこといくらやったってダメだってことで、段階っていう考え方をヘーゲルはあみだしていると思います。
その段階っていう考え方はどういう考え方かっていうと、歴史的経緯であるとともに、不連続なので、つまり、不連続な結節点っていうのが、歴史の中にあるんだと、それが段階なんだ。だから、段階っていう考え方は、抽象的であると同時に、歴史的であるっていう、そういう要素を兼ね備えた段階っていう考え方をすれば、歴史っていうものをひとつの生態として把握していくことができるんだよっていうのが、ヘーゲル・マルクス流の考え方だとすれば、浄土系統の歴史的経緯はあるんですけど、日本仏教のありかたにとって、何が考古学的な切り口っていうのになるかっていったら、それは、やっぱり、普遍的な倫理っていう面で、信仰の問題を切るっていいますか、その面で切るっていうような切り方をすれば、それは、考古学的な層となりうると、その上に何が積み重なるかっていうと、法的な経緯が積み重なってっていうことになっていって、それで、国家の問題に至りつくだろうっていうふうになるわけです。
重要なことは、そういう考古学的な層っていう考え方が、かならずしも、歴史的な段階とも、それから、歴史的な発展っていいましょうか、発展とも、けっして一致しないってことなんです。つまり、フーコーの考え方は、必然的に間抜けする問題は、歴史主義っていうことを断ち切るっていうことは、ひとつ必然的に出てきちゃうんです。
②
どうしてかっていうと、それじゃあ今度は、法っていうものと、国家の間の、つまり、法から国家へ転移する場合の切り口っていうものを考えたら、どういうことになってくるだろうかってことになってきます。
そうすると、これも具体例がありますから、日本のあれでいいますと、日本国でいちばん古いっていいましょうか、古い一等初めに憲法って名前がつけられているのは、聖徳太子の十七条の憲法です。十七条の憲法っていうのの中に、第一条は、「和を以て貴しとなす」っていう、あるいは、やわらぎって読むのかもしれませんけど、「和を以て貴しとなす」っていうのが第一条です。つまり、和解的であること、人と仲良くするっていうことでしょう。つまり、仲良くすることをもって、いちばん尊重すべきこととするんだっていうのが、第一条です。
しかし、これは、どうでしょうか、法であるだろうか、それとも、倫理であろうかっていうふうになるわけです。そうすると、これは、倫理と、これを法って、憲法って言ってるけど、ほんとは倫理と法との混合したもの、あるいは、中間物っていいましょうか、入り混じったものでもいいですけど、そういうものに過ぎないんじゃないかってことになります。
そうすると、「和を以て貴しとなす」っていうのは、市民社会を規制する倫理というよりも、これが、憲法だったらそうなんだけど、ほんとはそうじゃなくて、一種の普遍的な倫理であるとともに、つまり、法となり得る要素も持っているとともに、また、憲法と名付けているように、そのころは市民社会じゃなくて、農民が主ですけど、農民社会を規制する言葉でもあるという意味合いで、聖徳太子は、それをつくったとされているものであるわけです。
そうすると、これは、普遍的倫理であるとともに、法としての性格をもってそれを効用とする、普遍的倫理を効用とする要素も持っているっていうことになって、そのふたつを持っているんじゃないかってなります。
③
そうすると、十七条の憲法のなかに、ただ一か所だけ、何条か忘れましたけど、農繁期における農民の賦役、税金の代わりにおまえ労働しろって、つまり、賦役ですけど。人頭税みたいなものなんですけど、国家が農繁期に農民を使っちゃいけないっていうような項目が一か所あるわけです。それは、いわば、法律に近いんです。普遍的倫理の根元にある宗教であるというよりも、やや法律に近いんだっていうふうに、完全な法律に近いんだって言える部分だと思います。それは、たぶん、十七条の憲法のなかに一か所です。あとは、農民社会を律する倫理であるか、あるいは、それから出ていって、普遍化しようとする宗教的要素を持っている、普遍的倫理を目指している条項であるか、それとも、ほんとの法律であるかっていうが、全部はあんまり区別がつかないのが、日本国憲法のはじまりにあるわけです。
そうすると、今度は、法から国家へいくっていう経路は、どうしたらいけるんだっていうふうになるわけです。そうしたらば、ぼくの理解の仕方では、たとえば、具体的に言って、十七条の憲法のなかで、いま言いました、農繁期に国家は使っちゃいかんぞっていうような、そういう条項だけにしていけば、国家っていうものが形成されるってなるわけです。それが形成されれば、農民社会っていうもののありかたと、国家のありかたとは、ヘーゲル・マルクスじゃないけど、分離できるわけなんです。
④
しかし、ぼくの理解している限りでは、それじゃあ、武家時代になって、鎌倉幕府では貞永式目とか、建武式目とかっていうのがあるんです。そうすると、それは、みなさんもご覧になれば、岩波書店の日本古典思想大系みたいなのを読んでみれば、すぐに書いてありますから、武家が政府になるわけです。鎌倉時代になって、朝廷が政府じゃなくて、武家が政府になるわけですけど。武家を規定する式目をみても、ちっとも法律にならないんです。依然として、武家社会を規制する道徳であるか、あるいは、武家社会を規制する道徳であるとともに、それを超えて、普遍的な道徳原理であるのか、それとも、国家的な、そういう道徳的要素を追っ払っちゃった、つまり、ぜんぶ削り取って、ちゃんと法律になっているかっていう考えと、依然として、十七条憲法とそんなに変わり映えがしないってことになります。これが徳川時代になって、鎌倉幕府法っていうのが、武家諸法度みたいなのがありますけど、そういうのをみたらどうなんだっていったら、原理が儒教的な原理になっただけで、やっぱり、倫理っていう問題が払底できていないんです。純粋に法律的っていうところになっていかないんです。なっていかないってことは、ようするに、国家っていうことになっていかないじゃないかってことは、厳密な意味で、つまり、西洋的な意味での国家って言えないじゃないかって、そのとおりなわけです。そこがネックなわけです。いまでもそうですけど、ネックです。
⑤
11「法的な規定」という切り口 ( 引用者註.「講演テキスト」の小見出し)
そういうところで、幕府時代を経て、幕府時代になって、鎌倉幕府法が、倫理じゃなくて、これはやっぱり法律だよってなったとすれば、幕府は、日本国の国家、つまり、政府を形成している中心であって、そうしておいて、人間社会っていうのは、それから分離して、人間社会っていうのはあって、中間に武家層とか、領主層みたいなのがあって、小さな国の、アメリカでいえば、ワシントン州とか、ニューヨーク州とか言ってるのとおんなじ、州とおんなじ枠組みが下にあるわけです。鎌倉(徳川)幕府は国家の中心になってってなってるわけです。
徳川幕府の兵隊っていいますか、旗本でもなんでもいいんですけど、そういうなのが、国軍っていうことになって、農民社会っていうのは、それから分離して、上にあるかもしれないけど、規定はやかましいかもしれないけど、それとは別のものなんだよっていうふうになるはずなのに、それがならないものですから、依然として、日本国における国家っていうのは何なのかっていったら、この土地は領主さまから授かったものだとか、ようするに、徳川家のあれから授かったものであるぐらいの観念を、どうしても農民が払底しないわけです。それで、心の中までいえば、国家っていったら、みんなそういうふうにぜんぶ包んだものだっていう観念を、日本人っていうのは、それを吹き払うことができないわけです。いまだって、ほんとはできないわけです。
そういうふうになってるのは、なぜかっていったら、道徳、それから、法っていうもの、それから、宗教っていうものと、それから、国家っていうものと、その切れ目、切れ目の考古学的な層っていいましょうか、それを見つけようとすると、段階的にそれは見つかるかもしれないけど、考古学的な層を見つけようとすると、非常に困難なわけなんです。
ですから、今度は、どこでもって、式目とか、武家諸法度っていうようなものが、どこで国家の国法になっていくんだってことを考えていくと、どうしても、国法といえるものをつくりあげることができないことになります。
それじゃあ、国軍っていうのはあったかっていうことになりますけど、幕府自体は国軍だと思って、諸藩の兵はみんな国軍だと思って、幕府がいざなんとかって言えば、みんな幕府の兵隊として機能すると思っていたかもしれないけれども、どっかに藩の兵隊であって、武力であって、もしかすると、遠いところの、九州とか、東北とかの藩は、幕府に反抗するかもしれないっていうあれをいつでも持っているような、つまり、国軍としての統一性じゃなくて、国軍なんていえるのは、旗本だけだっていうことになって、これは、幕府を取り巻いている親衛隊みたいな機能しかなくて、国軍とは到底言えないよみたいになって、すこぶる曖昧で、藩の武力であるのか、幕府の武力であるのかっていうのが、どちらでも移行できるみたいなので、非常に曖昧なことになっているわけです。
そうすると、その切り口っていうのが、どうしても、法的な規定が国家になるっていうことの境界面が、ひとつの考古学的な切り口だと考えるとすれば、武家諸法度とか、式目とか、そういうものの中から、法に近いものっていいますか、法に近いものだけをピックアップしてとってきて、そのほかのものはぜんぶ捨ててしまうっていうようなことをやりますと、かろうじて、それが考古学的な層をつくることになります。それをやらなければ、どうしても、日本における国家の、法から国家へ移っていく場合の、考古学的な層として保存できる層っていうのを、設定することができないことになります。
そうすると、それは、追及したうえで、何が、これは法として成り立ちうるけど、これは法としては成り立たないとかっていうことになるかっていったら、なかなか規定するのがむずかしいと思います。それをきっとやることが、法の歴史みたいのをやる研究者の眼目っていいますか、題目になるんだろうと思います。
(『 A172フーコーについて』吉本隆明の183講演 講演日:1995年7月9日)
※①、②、③、④、⑤は、連続する文章です。
|
備
考
|
(備 考)
ヨーロッパを無意識にでも引きずったヘーゲル・マルクスの〈段階〉という考え方やフーコーの〈考古学的な層〉という考え方を、この列島の精神史に適用しようとするとなかなかすっきりとはいかない問題が出てくるということが吉本さんによって実験的に言われている。このことは、ヨーロッパは〈アジア的な段階〉をすばやく通り過ぎたのに対して、アジア地域は〈アジア的な段階〉をとても長く継続してきたという、ヨーロッパ地域とアジア地域との異なる事情によっているだろう。
ヨーロッパ的な優れた概念や考え方をわが列島の歴史に当てはめてみようという吉本さんの実験的なことから、わたしが引き出せることは、今のところ次のようなことだ。アジア地域のこの列島社会が、あまりにも長く〈アジア的な段階〉に割と自足して浸かっていた、あるいは停滞して浸からざるを得なかったという状況が、吉本さんの指摘したような〈考古学的な層〉として切り出せないようなあいまいさをもたらしたのだろうということ。こうした状況は、ヨーロッパ的な宗教から法へという段階の視線からすれば、停滞的あるいは法や倫理の混合したあいまいさを持つ歪んだものに映るのかもしれないが、わたしたちには良し悪しは別にしてああわかるというなじみの状況である。
この問題をさらに、一般論として抽出すれば、人類史というものは歴史の中でどのような挙動をするものなのかという問題になると思われる。
上の引用に関連して、
13 近代日本の原罪
ですから、フーコーの切り口っていうのと、それから、ヘーゲル・マルクス主義の段階的な考え方とを、合致させるためには、幕末から明治に至る革命の過程で、武家諸法度みたいなものの中から、それから、各藩の持っている藩法っていうのは、多少ずつ違いますけど、その藩法の中から、法律らしい法律っていう項目をピックアップしていって、それを普遍化したら、どういう規定になるかっていうことを、内在的に考えていってつくれば、ちゃんと、国民の憲法らしい憲法ができたに違いないんですけど、それをしなかったし、できなかったっていうのが、日本国の一種の原罪みたいなものだと思います。
これを原罪と考えない考え方もあります。つまり、原罪と考えるためには、西洋化=近代化って考えるならば、たしかに原罪だと、しかし、西洋化=近代化と考えないとしたらどうなんだとか、東洋的専制、あり方っていうのを基準にしたらどうなんだとか、ようするに、日本国っていう特殊性っていうのは、せいぜい段階的に分解して、これは、アジア的要素と、アフリカ的要素の大きな混合物だと思いますけど、日本っていうのは。それを伝統とする、つまり、古代とすると思いますけど。そういうものを、特有なものって考えたら、これは、各地域がそれぞれ、特有であるって考えたものなんだっていえば、さまざまな論議がありますから、それは、一概に、一定的に、これはいいんだって規定することはできないと思います。
さまざまな考え方がありうると思いますけど、さまざまな問題がそこにあるっていうことは、確実なわけで、やっぱり、非常に簡単に、西洋化=近代化って考える人は、「天皇は神聖にして侵すべからず」とか、「天皇は国民統合の象徴だ」とか、そういう項目を信仰して、信じていて、天皇が死ぬと、死んだときには、皇居の前行って、拝んだりする人もいるので、西洋化=近代化って思ってるやつは、これは土人だっていうふうに言うわけです。土人だって日本人なわけで、そういうやつは、土人っていうのは、そのうちになんとかなるさって思う以外にないって、それは、いまの日本の知的な風景のなかに、みなさんがかなりな程度、信じている風景のなかに、それが依然としてあるっていうふうに、ぼくは思います。
これは、なかなかむずかしい問題で、これは、さまざまな複雑な問題で、そんな簡単に片づけてもらっても困るし、それなら、いっそ神聖天皇にしようじゃないかっていうのも困りますし、平和憲法を擁護しようとか言いながら、天皇は国民統合の象徴だっていうのを残してしまうっていう考え方も困ります。困るとぼくは思います。それは、ぜんぶ困ります。どういうものにしたって、ぜんぶ、どっかが凋落しちゃうよなってことになってしまいます。
ぼくらが、九条はとっておいたほうがいいって、これは、世界でいちばん進んだ憲法の条項だからとっておいたほうがいい、それから、天皇は国民統合の象徴だっていうのは、これは、とっちゃったほうがいいって、ぼくがそういうふうに言うと、あの野郎って、誰も賛成してくれない、ようするに、とんでもないやつだって思われてるか、あいつは偏屈でしょうがないんだって言われるかどっちかだと思います。
それくらい、みなさんも、ご自分の考えはこうだって持たれたほうがいいと思います。いいんですよ、どういうのを持たれても、おれは神聖天皇がいいっていう人がいたっていいけど、ただ、いずれにせよ、自分の考えを持たれたほうがいいし、これは、なかなか統一しようとすると、なかなかできない。多数決をやると、国民とすれば、どっかに決まると思いますけど、そのくらい、むずかしい問題として、しかし、このむずかしさ、あいまいさっていうのは、われわれが引きずっているむずかしさっていいますか、あるいは、けっして、自分とは無関係ではないのであって、ぼくらは、国民統合の象徴はとっちゃったほうがいいと思いますけど、とっちゃったほうがいいと思ったおまえは、戦後50年における、自分の考え方の首尾一貫性っていうのを信ずるか、自分で信じられるかってなってくると、ぼくは、戦争のときは、神聖天皇に賛成だって思ったんです。
さらに、天皇機関説とか、天皇は立憲君主だという考え方が、そのときもありましたけど、ぼくは、いちばんやりやすいって言ったらおかしいんですけど、これならば、兵隊いって命を捨てるっていう名目っていうのは立つなっていうふうに、つまり、同胞のためとか、肉親のためとか、それから、国家のためとか、それから、天皇のためとか、いろいろ考えるわけです。
なんか考えて、つっかえ棒をあれしないと、なかなか簡単に、人間っていうのは死ねるものじゃないのであって、そういうのを考えて、ぼくは、やっぱり、非常に宗教的な天皇、つまり、神聖天皇です。そういうふうに考えると、自分ら、つまり、人間以上のところに位するなにかみたいに思えて、それがつっかえ棒にいちばんなりやすいなっていうのが、ぼくらの考え方です。
戦争は敗けて、敗けたって急に考え方の転換はできないので、当初は、ぼくらは、なんらかの意味で、天皇規定っていうのは、残っていた方がいいって、自分は思っていて、当初をいうと、国民統合の象徴だっていう項目に対して、ぼくは肯定的でありました。ぼくが決めたわけでもなんでもないんですけど、ぼくは、肯定的でありました。
だけど、いろいろ勉強していくうちに、自分なりに、これはやっぱりダメなんだなっていうふうに思ってきましたけれど、そういうふうに考えると、自分はずいぶん、自分の考え方を、自分なりに、50年かかって、いろいろ変わってきたなって、その都度、自分なりに、いろいろ考えてきて、その考え方に頼るじゃなくて、進歩したっていうふうに、主観的には思えるんだけど、しかし、おまえ首尾一貫しているかって言われると、首尾はちっとも一貫していないってことになります。
(『 A172フーコーについて』吉本隆明の183講演 講演日:1995年7月9日)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
| 528 |
現在の政治の最大の課題 |
「フリーター、パラサイト・シングル、家族」 |
インタビュー |
吉本隆明資料集176 |
猫々堂 |
( 「フリーター、パラサイト・シングル、家族」、『吉本隆明が語る戦後55年』第1巻 2000年2月5日発行、
『吉本隆明資料集176』所収)
※インタビュー日は、2000年10月13日
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 超資本主義への移行 |
民族国家の現状 |
国家はただ社会に奉仕するために存在 |
|
項目
1 |
①
―超資本主義への移行に対して、政治はどういう舵取りをすればいいのでしょうか。
吉本 社会の変化に対して、政治的国家がやるべきことは決まっています。金融機関や産業機構を変え、資本主義の状態から超資本主義の状態に移行することです。この点は、自民党であろうと共産党であろうと違いはありません。
ですから、いまは各政党の間の距離はほとんどなくなりましたね。政治的国家に対するイデオロギーの違い、理念の違いなんかは大きな問題になりません。消費が過剰となった超資本主義に社会機構を合わせることが最大の課題です。
保守的であるとか進歩的であるとかは、何の意味もありません。誰が政策を担当しても、どの政党が政権を握っても、同じことしかできないという気がします。仮に共産党が政権をとっても、超資本主義への移行は必然であるし、自民党と同じ政策しかできない。ならば、自民党のほうがずっと場馴れしているし、金融政策や産業政策のツボを心得ているから相応しいことになります。これが、現在の国民大衆がどうしようもない保守党に票を入れている理由でしょう。
(『吉本隆明資料集176』P36 「フリーター、パラサイト・シングル、家族」、『吉本隆明が語る戦後55年』第1巻 2000年2月5日発行)
②
吉本 社会をよりよく運営するために政治的国家があるわけです。(逆ではありませんよ。)欧州共同体が示すように、もう民族国家はたいして大きな意味をもっていません。国家は社会より重要でもなく大きくもない。ただ社会に奉仕するために存在しています。また今度は、次第になくなっていくものだと考えていいわけです。突き詰めれば、国家は問題ではなく、社会における個人、個人の社会生活、経済的な豊かさ、自由度がもっと向上すればいいということです。
(「同上」P39)
|
備
考
|
(備 考)
②の吉本さんの視線や考え方は、近代以降に欧米の大波をかぶったあとのこの列島の考えや思想に属している。アジア段階の思想や考えからは、たとえそんな考えの萌芽が深く潜在しているとしても、表面には決して出て来ないような考えや思想である。このことはどう考えるべきだろうか。人類史として考えれば、文明や文化や思想はいろんな地域で互いに影響し合ってきた。それが征服によってそうなったという場合もあったろう。こうしたことから言えることは、わたしたちは、人類の理想のあり方を追求する人類史の叡智の上に現在があるということである。
「超資本主義への移行」については、わたしの遠くからの生活者目線では、復古・改憲中心政権はともかく、官僚層も古い石垣の石換えや石補給程度で、本格的な石垣の作り直しのような構想は持っていないように見える。外交にしろ、経済システムにしろ、なんら新しい徴候が出ているようには見えない。
EUも揺れてはいるが、「民族国家はたいして大きな意味をもっていません」とすれば、現在の偽主流にいる民族国家の現状は、経済のグローバル化で静かに深く雪崩打っていく国家の最後の徒花であろうか。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
| 529 |
書くことの根本 |
「やっぱり詩が一番」 |
談 |
吉本隆明資料集177 |
猫々堂 |
『読売新聞』2010年7月25日掲載
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 生涯の理想 |
詩が一番自分がこもっている |
自分に自分を伝えたい |
|
項目
1 |
①
戦争中はいつ死んでもいいような気持ちで自分を追いつめていって、終戦でそれをはぐらかされた。だから就職しても、まじめになれないんですよ。戦後はもう、会社に行って熱心に勤める気にはならなかった。化学関係の仕事をしながら趣味として詩を書いて、安閑と暮らそうというのが生涯の理想だったんですけど、とんでもない話で。
でも言いたいことはいっぱいあって、書きたいこともいっぱいあった。当人は「好きだから書いてるだけだよ」と思うし、そう思いたい。詩なんて一番金にならないことですからね。
だんだん世間を見ているうちに、面白くないことが周囲でも遠くでもたくさん起こる。それを黙ってやり過ごせないから、評論も書くことになりました。
(作家の)埴谷雄高さんには「人の悪口は慎んだ方がいいぞ」と会うたびに言われました。そうしているうちにまた癪に障るタネが出てきて、繰り返し論争してました。本当は無駄なんだけど、ここで黙っているのは人間として我慢ならないよ、という思いになるんです。
『共同幻想論』はある時期の記念碑的な作品として残っていますが、本当を言えば、詩が一番自分がこもっていると思います。力こぶの入れ方が違う。僕はうまい詩人じゃないけれど、やっぱり詩が一番、自分の持ち物を入れたような気がします。
②
書くことの根本にあるのは、自分に自分を伝えたいということ。書いた人と読んだ人とは偶然出会っただけです。偶然手にして、「俺が考えていることと同じだ」と思ってくれたら、それ以上何も望むことはない。
(「やっぱり詩が一番」P77-P78、『吉本隆明資料集177』猫々堂 『読売新聞』2010年7月25日掲載)
※ ①と②は、文章は続いています。
|
備
考
|
(備 考)
この文章はこれで全文。「談」とあるから、記者が少し手を入れて切り整えているのかもしれない。また、それが吉本さんのチェックを受けているのかどうかはわからない。
この吉本さんの敗戦体験は、この列島の住民の誰にも訪れた全社会的なものであったわけだが、死の体験と見なすことができるだろう。しかも、その死の体験は自分の身近な人や知り合いなどの他人の死の体験ではなくて、形容矛盾ではあるがまさしく自分自身の死の体験とも言うべき重さや深さや広がりを持ったものだったろうと思われる。この列島社会ではこれに類する規模の全社会的な体験はあんまりないのではなかろうか。吉本さんの「生涯の理想」は打ち砕かれ、生きざるを得ない敗戦後の社会では「就職しても、まじめになれないんですよ。戦後はもう、会社に行って熱心に勤める気にはならなかった。」というのは現在から眺めれば自然の成り行きだったのだろうと想像される。
吉本さんの戦後の表現者としての真摯な格闘は、そんな焼け跡の世界で死の体験をなんとか潜り抜けようとする悪戦苦闘であり、そうした中から吉本さんの無類の思想が形作られてきたのである。このことはある痛ましさとともに無類のおくりものとしてわたしは受けとめている。
わたしは近年、吉本さんの晩年の言葉は特に大事だなという思いがしている。言葉やイメージや思想を長年くり返し積み上げてきた上の、いわば含みや深さのある還りがけの言葉のように見えるからである。別の言い方をすれば、普遍の言葉のイメージが以前より強く感じられるからである。
たぶん若い吉本さんなら、「書くことの根本」についてこのような表現はしなかったろうと思う。それはともかく、人間が文字というものを獲得し、書かれる世界を長らく踏み固めてきたことが、「自分に自分を伝えたい」というまどろっこしいが、より緻密に感じ考える内省的な世界を生み出してしまった。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 530 |
簡単には言えねぇ |
「吉本隆明さん、今、死をどう考えていますか?」 |
インタビュー |
『よい「お葬式」入門』2009年8月25日刊 |
吉本隆明資料集175 |
猫々堂 |
2018.5.25 |
聞き手 木村俊介
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 死に含まれる複雑な心情 |
同じようなやりきれなさ |
生きて帰った偶然を「良し」とする |
あの万歳の内実 |
項目
1 |
①
―今、死をどう考えていますか?
吉本 現時点の僕の死生観を、とポンと訊かれても、一言で伝えることはできないんですよ。死についての考え方は、各人によって、しかも各人の中でも、「どんな死をどのように捉えているのか」によって、随分、変化してゆくものでしょう?ですから簡潔に「死に関する持論」を喋るなんてことはできません。たった一つの死に焦点を当てても、余りに沢山の要素が引っ絡まっているので、死に含まれる複雑な心情までは理解して貰えないだろうなぁ、と、言いにくい話になっちゃうんですよね。
太平洋戦争末期、素人目でも「負けるかも知れない」という時期、僕は数え歳で二十歳で、もう徴兵検査を終えていて、死は非常に近いものでした。徴兵されたら、生きて帰れるなんて想定できなかった。死ぬかもしれない。いや、かならず死ぬ。そのための覚悟を持たなければ。では、どのように考えたら、中途半端な年齢の死に対して納得できるのだろうか。それで当時は、親兄弟や知人に生きて貰うために自分は死ぬのだ、と肯定することにしたんです。今ふりかえれば幼稚で自分勝手な発想だなぁと思いますけど。
②
―直面した、やりきれない死は?
吉本 僕らの詩の仲間に村上一郎さんという人がいました。戦中は海軍将校に進むコースに乗り、軍事訓練を受けないで海軍の少尉に任官して、生きて帰ったことに非常に負担を感じていましたね。戦後は共産党に入って、アメリカを生涯の仇敵にすることを自分の存在意義にしていたけど、後年、自殺してしまいました。村上さんは仲間の集まりで「この自殺かあの自殺か」と自殺の方法の話ばかりするので、僕らは同じようなやりきれなさを感じながらも「そこまで負担に感じることはないでしょう」と説得するんです。生きて帰った偶然を「良し」とするという結論でいいのではないか、と。でも何回言ったって村上さんは聞いてくれなかった。それで最後は頸動脈を切って死んでしまった。こういう死について話すことは本当に難しいなと思います。まずは村上さんの心情自体が非常に複雑で難しい。それに「生きていけばいいじゃないですか」というのも幾許かの共感や独特の屈折を含みながらの説得で、その説得側の心情を説明することも難しい。沢山の要素が引っ絡まった自殺だから簡単に意見を言いたくないんですね。
村上さんの通夜が終わったら僕らの仲間は飲み屋に寄りました。酒を一口飲んだところで、僕らの中でも大変にいい詩人だった谷川雁が音頭取って・・・・・・「村上一郎、万歳!」。皆で万歳三唱をしたんですよ。この情景はありありと覚えています。この万歳は何の意味か。その説明はまた難しいんですよね。そうそう簡単な万歳ではなかった。村上さんは自分の目的を達成したのだという意味の万歳かと言えば、そうでもない。悲しい。何で死んじゃったんだ。そういう残念な心情も含まれて、しかし村上さんを棺桶に入れて通夜が終わった夜なのだから弔ってやりたいという心情も含まれて、時代と戦争、同時期に運命を共にした青年のそれぞれの心情の籠められた万歳・・・・・・。と言うしかないのかなぁ。つまりやはりこれも「なかなか簡単には言えねぇ」ってことになりますね。あの万歳の内実は、今話したような断片から、その隙間を推察してくださいとしか説明できないんじゃないか。
(「吉本隆明さん、今、死をどう考えていますか?」P28-P30、『吉本隆明資料集175』猫々堂 『よい「お葬式」入門』2009年8月25日刊)
|
備
考
|
(備 考)
吉本さんには、死ということを対象として探索した『死の位相学』という本がある。これは死というものをある抽象の水準で捉えたものだという印象がある。しかし、ここで語られる〈死〉は、なんか今までと違った印象を与える。
「なかなか簡単には言えねぇ」ということは、日常的な生活世界ではわたしたちがよく経験することである。なんとか句点を打たなくてはならないから、とりあえずという感じで表現することも多い。ただ、そのような中で、何か降り積もっていくものがあるのも確かである。
ここでは主要に抽象の水準で捉えるのではなく、死というものを自分に引き寄せた個別性として、具体性として、追究し、語られているように見える。
②の「村上一郎、万歳!」については、この一年後くらいの以下のような語りもある。ちなみに村上一郎は、1975年(昭和50年)3月29日、54歳で亡くなっている。
「それでぼくらはお通夜の日に行きまして、それで帰りに飲み屋さんに寄って、そこで、その人は村上一郎さんという人なんですけれども、谷川(雁)さんの音頭取りで、村上一郎万歳というのを三唱しようではないかというので、よかろうというので、その通夜の晩に、その席にいた四、五人ですけれども、村上一郎万歳三唱というのをやりました。それでやっと少し気持ちが晴れたといいましょうか、気持ちが和んだといいますか、そういうこともありました。」
(「柳田国男から日本、普天間問題まで―戦後第四期の現在をめぐって―」『神奈川大学評論』2010年7月30日刊、『吉本隆明資料集177』P92
猫々堂 )
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
| 538 |
繰り返し読める戦後の文学者 |
「八十五歳の現在」 |
インタビュー |
吉本隆明資料集177 |
猫々堂 |
『週刊 金曜日』2010年6月18日号掲載
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 武田泰淳 |
小林秀雄 |
太宰治 |
|
項目
1 |
①
―・・・中略・・・下町っ子は、ある種の「自立の思想」を持っているんです。からめとられるとか、上から言われるなんてふざけんなと言う。吉本さんの本を読んでそういう感覚をすごく感じていました。
吉本 そう言っていただけると、とてもうれしいですね。僕の書いたものなんて廃れる一方ですが、戦後の文学者で言えば、繰り返し読める文学者は、作家なら武田泰淳、批評家なら小林秀雄、短編なら太宰治というこの三人だと思うんです。小林秀雄さんなんかは、しゃべっても書き言葉と同じくらい残るなと思うし、武田泰淳や太宰治の書いたものもなくならないよと思います。
(「八十五歳の現在」P75『吉本隆明資料集177』P92 猫々堂、『週刊 金曜日』2010年6月18日号)
|
備
考
|
(備 考)
武田泰淳の作品はほとんど読んでいないからか、武田泰淳は意外だった。武田泰淳の『富士』を読んでみようかと思う。吉本さんは、今までになく深く鋭い読み手でもあるから、評価は参考になるとわたしは思っている。その深く鋭い読みは、例えば、『言語にとって美とはなにか』に引用されたり触れられている作品の数を見れば分かるだろう。膨大な数の作品を読んできて読みの修練も重ねてきたのだと思う。もちろんそこには、科学者がやる、必要なところだけの部分読みもあるかもしれないけれど。
吉本さんは、評価すべきすぐれた本格的な詩人として、詩人についても何人か挙げていたと思う。吉増剛造、田村隆一、谷川俊太郎だったか・・・。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 576 |
公ということ |
「第一章 老いのからだ」 |
インタビュー |
|
『生涯現役』 |
洋泉社 |
2006.11.20 |
聞き手 今野哲男
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 働くってことはいつでも賃労働です |
公の機関というのは、大きくなると見返りがつくからです。 |
公共の大きな施設でもなく、せいぜい町会でやるていどのものがいいと思う |
|
項目
1 |
①
働くってことはいつでも賃労働です。だからそれを守るために、ボランティアなんてとんでもないという原則がぼくにはあるわけで、その原則を認めた上で例外的にやってくれる人がいるのなら、無理にこちらから拒絶することもないから、ボランティアと呼ぶか無賃労働と呼ぶかどうかは別として、そういうことがあってもいいんだけども、でも原則としては賃労働、働くということはからだの何かを消費することで何かの価値を生むということですから、その消耗に対しては対価を支払うのが当然だと思うし、これだけははずしてはいけないと思うんです。
(『生涯現役』P76-P77 洋泉社 2006年11月 )
②
たとえば世間には東京都主催の老人ホームもありますし、それから各区のものもあるわけで、そういうところって、だいたい安いか無料なわけですが、でも、ぼくにはそういうところにいけともいえない。
なぜかというと、公の機関というのは、大きくなると見返りがつくからです。つまり、何時から何時までの間に申し込みにこいとか、きたらどうしなきゃならないとか、そういう制約がはじめから決まっているわけです。少し公の度合いが大きくなると、事務にまつわる時間的な手間はもちろん、これは保険でもそうですけど、支給するまでにああしろとかこうしろとか、かなわねえというくらいに威張られちゃってね。若い奴がそんなに威張るなといいたくなるで、話を聞いてると、もう老人をいじめてるとしか思えない威張り方をするようになるんです。
(『同上』P77-P78 )
③
ぼくがホスピス的な施設でもなく、公共の大きな施設でもなく、せいぜい町会でやるていどのものがいいと思うのは、そういうところから出てくる話です。そういうお役所ではなく、いいことを目指す運動でもない、小さな町会の事務所にいって、誰か近所の人で、地域のこともわかっていて、話し相手も出来て、金は自分で払って、それで洗濯なら洗濯だけを何時から何時までやってくれないか、副食を買ってきてくれないかと、ご本人が承知してくれる範囲で仕事を頼んで、公を頼るのはそのくらいが限度だ、せいぜいが町会くらいということになれば、いくらかでも払うのは大変だけど、それで煩わしさから逃れられるならまあ安いもんだと思うわけです。
それから、時間を決めておいて、終わったら帰ってもらえばいいわけで、そうすると余計な気詰まりといいますかね、ぼくは入院しているといつもそれを感じちゃうんだけど、要するにそれがなくなって、自由空間と自由時間が保てるんですよ。
(『同上』P79 )
※①と②は、連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
東京都の「自立支援センター」(寮)という公的機関の規則を挙げて、公というものの有り様を見てみる。
●自立支援センターとは
・住居と仕事を失った方に対して、生活保護を受けず
に就労による自立を支援する施設。
・職員が24時間常駐し、運営管理を実施。
●自立支援センターの主な事業内容②
自立支援事業
・就労意欲があり、就労に支障がないと認められる方 に対し、就労自立を支援する。
・就職後は、借上げたアパート等を自立生活訓練の場として提供し、住宅を確保するための 転宅費用のための貯蓄を支援する。
・アパート等への入居後は、再び住居を失ったり、失職しないよう、就労状況の把握や、必要に応じた相談支援等のアフターケアを行う。
●自立支援センターの日課
●自立支援センターでの遵守事項
「自立支援センター 設置にともなう事業説明会」(足立区福祉部 東京都福祉保健局) より
file:///C:/Users/nishi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/IS77OOBZ/zigyosetumei.pdf
ここには、自立支援センター 訪れる人々はある落ち込んだ状態にあるという認識(それはいいだろう)に基づいて、正常な状態にはい上がれるように、啓蒙・強制・管理するという思想が表れている。個の「自由空間と自由時間」を尊重し確保するという意識や思想はうかがわれない。しかし、公的施設は、こういう発想が「普通」であるような一般性を持っていると思える。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 580 |
格差社会 |
「第三章 老いと「いま」」 |
インタビュー |
|
『生涯現役』 |
洋泉社 |
2006.11.20 |
聞き手 今野哲男
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 今までの日本の社会構造 |
そういうところから得た自分なりの感じ |
社会のあり方が、旧来の日本型から西欧型に移りつつあるということ |
|
項目
1 |
①
最近、格差社会ということばが使われているようですけど、このことばのとらえ方について、少し確認しといたほうがいいと思うことがあります。・・・中略・・・
ぼくは、格差というのを、そうやって貧困の固定化がからんだ単純な問題としてとらえるならば、そんなことはいままでだっていくらもありましたし、階層といおうが、階級といおうがそれでお終いじゃないか、話はもうすんでるよって思います。ことさらに格差社会なんていう必要はないと思うんですね。だから、格差社会ということで何をいおうとしているのか、そこをまずはっきりさせとかなくちゃいけない。
日本という国は、これは柳田国男が農業経済学者だったときにはっきりいっていることなんですが、農業でも昔から同じような小さな地主さんたちがたくさんいて、その下に小作人がいて、豪農と呼ばれるような人がときたまいてという構造になっていて、一番数の多い小さな地主さんたちはほぼ同じ大きさだっていう、それが日本の農業の特徴だってはっきり論じています。これは、ほかの国に比べるとわりあい特殊なことなんで、それ以降のことでいえば、ぼくもそのモデルを念頭にものをいったときがありますが、たとえばボードリヤールがきたときに、日本の社会構造というのは全体を一つの長方形として考えると、上のほうにほんの少しの金持ち、つまり大財閥や大企業とかというのがあって、下のほうに同じようにほんの少しの貧困層があって、残りを仮に中産階級と呼ぶとすれば、ほとんどの人がそこに入ってしまう。これが昔から変わらない日本の姿なんだといったことがあります。要するに、いまはそこが崩れつつあるんです。現象的にそうなっていきている。格差社会という新しいことばを使うのであれば、そこまで遡って考えないといけないと思います。
(『生涯現役』P130-P132 洋泉社 2006年11月 )
②
すると格差社会というときにね、上・中・下はあるけどたいした差はない、アンケートをとると、あるときは自分が中流だと思う人が、八〇から九〇パーセントもいたというけれど、そんなのは日本の社会の大雑把なモデルからいえばもともとそうなんですよ。本質的に農業時代から同じなんです。それを押さえていわないと意味がわからない。
日本で唯一革命が起こったといえるのは戦後革命です。占領軍が一定規模以上の地主から土地を接収して小作農を自作農にしたというね。あれ以外は何もなかったし、そういうふうにしていままできたんだけど、それがここ数年の間にとうとう変わってきました。本当にあっという間の変化で、素人でもわかるように激しく変わっている。
ぼくらは経済問題についてはただの素人ですから、いる場所としては庶民といいますかあるいは市民といいますか、ともかくそれ以上の情報が入ってこないわけです。というより、テレビや新聞なんかが伝える以上の情報、たとえば政府なんかがいう情報ははなから信用していないわけですが、そういうところから得た自分なりの感じを信用する限りでも、確実にそういうふうになってきましたね。ここ一、二年くらいで、がくっと変わってきたと思ってるわけです。仮にぼくを進歩派というふうにいうならば、進歩派には大変不利なように変わりつつある。
で、ぼくがその変化が何かってことを考えるときに、たぶん格差というものが拡大したということの本当の意味が見えるんだろうと思います。単純な格差自体なら、いまいったような事情が昔からあったわけですけど、それといまとの違いの中心がどこにあるかというと、ぼくは社会のあり方が、旧来の日本型から西欧型に移りつつあるということなんじゃないかなと思います。
③
そうすると、全体を形作る長方形のなかで、自分を中産層だと思う人が八〇、九〇パーセントもいるという数字を維持してきたこの構造が、西欧資本主義国と同じように、にっちもさっちもいかないものになってしまうのかどうか。そして、それがどういうことなのか。それが大事な問題になってきます。
(『同上』P133-P134 )
※②と③は、連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
経済社会の構造が、このように急激に変貌してきたということは、少なくともわたしたち生活者のせいではない。それは当然ながら、政治担当する政権や官僚層や経済団体のグローバル化の名の下の諸政策の推進によるはずである。しかし、それの流れを受けいれている(ように見える)のは、わたしたち一般大衆である。その西欧化の浸透を受けてきたわたしたちの生活感性であろうと思われる。もちろん、それらの流れに対する異論や反対があっても、職場などの個々人の具体的な場で、一人一人の生活者が突っ張るのは難しい。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 582 |
個人幻想と共同幻想は本質的に逆立する ① |
(「資本主義の新たな段階と政権交代以後の日本の選択」他 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集 177』 |
猫々堂 |
2018.7.25 |
聞き手 津森和治 (2009年12月4日) 『別冊ニッチ』第2号 2010年6月10日発行
※関連項目476「逆立ということ」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 「全き自由」 |
あらゆる共同幻想を排除しないとそれは成り立たない |
共同幻想を排除してしか個人幻想は自立できない |
特殊の場合に個人幻想と共同幻想が一致した場合、それは本質的にもともと違うのだということには変わりない |
項目
1 |
①
津森 ・・・略・・・ですから「全き自由」という意味では、個人幻想はそのまま一〇〇にすればいいのではないか。共同幻想がある限りいつか必ず共同幻想というものが覆い被さっていって、あるいは浸食していって、個人幻想をゼロにしてしまう。極端に言えば、死ということになる。そこまで浸食してしまうことがあり得るので、それは「全き自由」のためには、どうしても自己矛盾を起こすのだから、これを排除するしか自由の完成というのはあり得ない、とおっしゃっているのでしょうか。これが国家ということでもあり得ましょうし、国家だけではなくて共同幻想ということで言えば、仲間内の意識も共同幻想になり得ます。ですからあらゆる共同幻想を排除する、なくす、という形でしか「全き自由」は実現できない、という文脈で自由を完成するためには国家を廃絶するしかないし、国家だけではなくてあらゆる共同幻想を排除しないとそれは成り立たない、宿命的にそういう関係にあるのだ、というふうにおっしゃっているのかどうかということなのですが。
吉本 どう言おうとそうなっているのではないかと思います。僕の言葉を使ってしまいますけれども、個人幻想と共同幻想は本質的に逆立するものであるということを含まなければ、あるいは含むものと考えなければ、個人幻想と共同幻想とは必ず制約しあっている、現実的にそうではないかと思います。それ以外のものを考えようがないくらいどこにもないじゃないですか。・・・中略・・・
たとえば、後進国というかイラクが戦争をはじめた場合に、極端に言えば、一個人と一イラク共同体とは同一である。だから自分が爆弾を抱えて死ねば、自分に倍する敵に対する被害を与えることはできるということで盛んに自爆するわけですし、日本の特攻隊もそうですね。
それは特殊の場合に個人幻想と共同幻想が一致した場合に限れば、おっしゃるように言えるけれども、それは本質的にもともと違うのだということには変わりない訳です。多分、変わりないということはどこかに現れるわけですけれども、個人の考え方のなかにあるか、共同幻想の、共同体の観念の中に現れるか、どちらかに飲みこまれるわけですね。それだから個人幻想と共同幻想が同値してしまうことはありうるわけです。これがもし、個人幻想と共同幻想が同値することはあり得ないというのでしたら、その場合には、すでに個人幻想か共同幻想か、どちらかが無化されたときです。そんなことがない限り、一番の極点に位するのは、おっしゃるような矛盾ですけれども、この矛盾は矛盾として同一なのだ、個人幻想と共同幻想は同一だという意味合いであって、矛盾という意味はそこで解消されるか、あるいはどちらかが内部に押し込めてしまうか、どちらかであって、そういう場合は一致することはあり得る、と言える。これは本質的に個人幻想と共同幻想は別の本質をもっているのだ、ということに対する無視にはならないのではないでしょうか。僕はそのように考えます。
②
吉本 そういう考え方をしますが、もう一つあります。たとえば家族とか親族の共同性というのは、何となく赤の他人の共同性に対して個人性とも違うというのは、まったく根拠が違うからなのです。根拠というのは、本質が違うからなのです。そうしますと家族、親族というのはどんなに少なかろうと多かろうと、それにかかわりなく、共同の仕事をしようとしていまいと、それとかかわりなく、家族の幻想の本質は性なのです。これはまったく異質のものであって、これはまたいわゆる共同幻想が政治幻想と仮定した場合を考えても、政治幻想と個人の家族、親族の幻想とは次元が違うので矛盾は起こらない。ですけれども次元を違わせないように共同幻想を創り出したら必ず矛盾する、ということも確かなことです。それは本質の理解としては、その考え方は避けられるのではないかと、僕の考えではそうなりますね。ですから、それは一個人がたくさん集まったのが、共同性だというところだけ考えないで、もう一つ共同性と個人性というのは、矛盾することはあるかと言えばある、ということも考えなければいけないし、しかしその矛盾は同一化は成り立つし、同一化によってその矛盾は解消されて存在し得るのだ、ということです。
津森 吉本さんとしては、同一化して矛盾を解消するというのはおかしいのではないか、むしろ共同幻想を排除してはじめて個人幻想というのが自由を完成するという形でないと同一化するということでは個人幻想をある意味では否定するということになりますね。
吉本 そうですね。
津森 そういうふうにしか成り立たないと言いますか、そういうことはおかしいではないか、つまり共同幻想を排除してしか個人幻想は自立できないのだ、ということになるのでしょうか。
吉本 そのとおりだと思いますが、おっしゃることは、僕流の言葉でいえば、現実性ということと、本質が同一だと考えるとおっしゃるとおりになりますけれども、現実性というのは、極端にいうとマルクス主義者はよく唯物的な関係だけを考えると、確かにそのとおりそういうことになる訳です。片方は解消する以外にどうしようもないけれども、幻想性として考えれば、幻想性としてというのは本質を含めて考えれば、その矛盾は具体的に現実的にどちらかが呑み込んでいるという要素はあってもそれは矛盾しない、ということがあり得るというふうに理解すべきではないでしょうか。
津森 日常はそうだと思います。
吉本 ですけど、現実はみんなそうで、都合の悪いところは打ち消してしまって無いものと仮定してしまってやっているのではないかと言えば、確かにそのとおりだけれども、それは本質ではないやり方であって本質を含まない考え方だと思います。そこのところは、唯物論とか観念主義とかでなければ、今流に言えば、唯脳主義とすいうものに不完全さがあるとすれば、そこではないでしょうか。つまり反対物が同一化するということはあり得るのだということです。現実的にそれがあり得るのかどうかという問題は、現実的な問題としてどちらかが、どちらかを飲み込んでしまう以外にそういうふうにはならない、ということになりますけれども、本質を含む現実性ということを考えるとすれば、あるいは現実性というなかの中核には本質性が必ずあるのだ、というそういう考え方を取れればそれは矛盾ではなくて逆立でもなくて、逆立していても現実的に同一化できるということはあり得るのではないか、というふうに僕が考えるとそうなってしまうのです。共同幻想と個人幻想を同一化したら矛盾ではないかというのは、現実的にはごもっともですが、それ以外の個人と多数の集団性のあるものとの同一関係というのは、現実には存在していないものだというのは、そのとおりだと思いますが、存在していないから、共同幻想と個人幻想は同一化している状態というのは成り立たないのだとはなかなか言い切れない。
(「資本主義新たな段階と政権交代以後の日本の選択」P44-P48 『吉本隆明資料集 177』猫々堂 )
※①と②は、連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
今回と次回は、「(本質的には)自己幻想と共同幻想は逆立する」ということと、「共同幻想の死滅」という、さまざきな人々にさまざまに波紋を巻き起こしたと思われる事柄を取り上げる。わたし以外の人々にも考えるきっかけになればと思う。
ここで語られている吉本さんの「全き自由」とそれへの道筋ということは、歴史をたどってきて現在からの理想のイメージの視線で語られているものである。その未来に向けたイメージの現実性を支えるのは、人類がたどってきた歴史の段階としてまだ国家という強力な共同幻想が生み出されていなかった段階の存在であり、さらにそこから、なぜ国家という強力な共同幻想が生み出されてしまったかというモチーフの存在である。それを明らかにすることは、同時に理想のイメージの現実性を明らかにすることでもあると思われる。
ここでは、自己幻想、対幻想、共同幻想の三つの幻想の軸と、その相互の関係について、しばしば提出される疑義に関してインタビューアーに吉本さんがもう少し具体的に語るという形になっている。わたしには少しわかりにくいところもあるが、要は、各幻想の本質性と現実的な姿の関わりの問題のように見える。
関連として、『共同幻想論』のすぐれた捉え返しと思える著作に、宇田亮一の『吉本隆明『共同幻想論』の読み方』がある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 583 |
個人幻想と共同幻想は本質的に逆立する ② |
(「資本主義の新たな段階と政権交代以後の日本の選択」他 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集 177』 |
猫々堂 |
2018.7.25 |
聞き手 津森和治 (2009年12月4日) 『別冊ニッチ』第2号 2010年6月10日発行
| 検索キー2 |
検索キー3 |
| 僕は共同幻想と個人幻想ということを定義づけていたというときにすでにその同一化はあり得るのだということが、僕の場合には入っていると思います。そして同一化してしまうというのは、一つの極限であって反対の場合も全然関係がない、ということだってあり得る、そういうことも含めてそうなのですが、僕はそういう考え方をしています。 |
本当はどちらかが先にあってその矛盾を飲み込むから関係ない、飲み込むから矛盾はない、という意味ではなくて、はじめから矛盾はないということを前提にしないと共同幻想と個人幻想の相違と同一性というのは考えられない、というのが僕の考え方です。 |
項目
1 |
①
津森 究極的には、共同幻想は排除されるべきであるということを『共同幻想論』のなかでお書きになられていたと思いますが、究極的には、という意味ではどうでしょうか。
吉本 それは僕が言い方を訂正しなければいけないと思いますけれども、こういうことなのです。僕は、これで理解してもらえるはずではないかと高をくくっていたと思います。そのようなことに本質ということが入るわけはないだろうと高をくくっていたと思います。矛盾があるのだけれども、あまり小さい矛盾だから矛盾はないと仮定しようじゃないかと高をくくった言い方をしていたのだと思います。そこはしばしばいろんな人から文句を言われたり、抗議されたりしているところですけれども、でも、それは本質はこうだということを理解した上で、矛盾はこのようにいっぱいあるじゃないかという言い方なら成り立つけれども、はじめから共同幻想と個人幻想が矛盾しているから同一化することなどあり得ない、というのを前提とするというのは、少なくとも僕の場合には、おつしゃるところまで突っ込まれれば、それはどちらかが飲み込んで、外に現れないということもあるかも知れないけれども、同一化ということを本質的に言えば、そういう矛盾なしに共同幻想と個人幻想は極限において同一化するという場合は、極限においてまったく同一化も関係ない、起こらないという言い方と同じようにあり得るというふうな言い方をしなければならないと思います。
津森 解消するという意味なのでしょうか。
吉本 解消とは違いますね。解消することがあり得るということ、それはただの理想としてあり得るということになりますから、僕は共同幻想と個人幻想ということを定義づけていたというときにすでにその同一化はあり得るのだということが、僕の場合には入っていると思います。そして同一化してしまうというのは、一つの極限であって反対の場合も全然関係がない、ということだってあり得る、そういうことも含めてそうなのですが、僕はそういう考え方をしています。自分ではしていないつもりでもラフな言い方で言えば、そんなことは現実的にはいくらでもある、みんなそうではないかと言えば、そうだということになります。それで本質はどうかということと、現実的な現れがどうかということとの区別がつかないことになってしまいますから、僕はそうではなくて、すでに極限において矛盾する、しかしその矛盾は同一化できるということは、はじめから含まれているように思います。
津森 逆立はしているけれども、そんなに矛盾ということを言わなくてもいいということでしょうか。
吉本 そうではないのです。そうじゃないというのを納得されるように説明するのはなかなか難しいと思っていますけれども、僕はそうじゃないのです。共同幻想と個人幻想は極限において同値する。つまり一致する。逆に、極限においてまったく関係ない、一人の人間の共同幻想と個人幻想とはまったく関係ない。そういう場合ももちろんあり得る、というふうに考えます。あり得るというのは、ラフな言い方をするとそうなのですが、本当はどちらかが先にあってその矛盾を飲み込むから関係ない、飲み込むから矛盾はない、という意味ではなくて、はじめから矛盾はないということを前提にしないと共同幻想と個人幻想の相違と同一性というのは考えられない、というのが僕の考え方です。
僕の考えは厳密な人からいつもやられていますから、そのためにこれを厳密化して考えなおすというのは大変だなあ、と思いながら、でも共同幻想と個人幻想の矛盾をどちらかが飲み込んでいるか否か、あるいは、言葉や行動に現さないからこうなっているのだ、というふうに考えて、矛盾はなくなるのだ、とは思っていないのです。
そこは大変重要なところなのですが、僕が文句をいわれるのは大抵そこの問題です。
(「資本主義新たな段階と政権交代以後の日本の選択」P48-P50 『吉本隆明資料集 177』猫々堂 )
|
備
考
|
(備 考)
まず第一に強調したいのは、吉本さんの『共同幻想論』のモチーフということである。自身も言われているように、戦争ー敗戦の中で体験した、国家やイデオロギー ―それらは人を媒介として私たちの前に立ち現れる ―が個を圧殺することがあるという体験、簡単に知識層までもそれらに取り込まれてしまったということ、そうした個に迫って来る無用な倫理の強迫をどうしたら解除できるかが、敗戦の深い痛手から立ち上がってきた吉本さんの『共同幻想論』の主要なモチーフであった。ちなみに、『改訂新版 共同幻想論』の巻末の「解題」(川上春雄)には、吉本さんの「幻想論の根柢」(『言葉という思想』所収)から本書のモチーフが以下のように語られている。人間の生み出す三つの幻想が層(位相)として取り出され、互いに関わり合うという概念の構造は、未だその緻密化の課題が残されているとしても、以下に尽くされている。
ヘーゲルのかんがえた意志論のすべての領域は、うまく層に分けて関連性がつけられるならば、奇妙な形で理念に倫理的にしかかかわってゆけないとか、逆に無理に、倫理、道徳、人格の問題を捨象するとかいうことをしなくてすむのではないか、そうすることでヘーゲルの意志論は生かせるのではないかとみなしていきました。つまり、個人の意識(ぼくは「幻想」という言葉を使っていますか)個人の幻想に属する層と、対なる幻想、つまり個人が他の一人の個人と関係づけられるときにでてくる意識の領域、これはいってみれば、家族とか男女の性の世界ですけれど、そういう観念の層と、それから、国家とか法律とか社会とかに属する共同の観念の世界、共同の意志の世界というように、層に分離してその関連性をつけられれば、たぶんわれわれは共同の目的、意志と、個人の意志とのはざまに引き裂かれて苦悶するという、阿呆らしいことはしなくてもすむのではないか、そういう意味での倫理的なことは、解除されるのではないかとかんがえていったのです。
上の津森氏の最初の発言の後に、註として以下の言葉が『共同幻想論』から引用されている。
* 真に〈他界〉が消滅するためには、共同幻想の呪力が、自己幻想と対幻想のなかで心的に追放されなければならない。
そして共同幻想が自己幻想と対幻想のなかで追放されることは、共同幻想の〈彼岸〉に描かれる共同幻想が死滅することを意味している。共同幻想が原始宗教的な仮象であらわれても、現在のように制度的あるいはイデオロギー的な仮象であらわれても、共同幻想の〈彼岸〉に描かれる共同幻想が、すべて消滅せねばならぬという課題は、共同幻想自体が消滅しなければならぬという課題いっしょに、現在でもなお、人間の存在にとってラジカルな本質的課題である。
(吉本隆明『共同幻想論』「他界論」)
この「他界論」の末尾の言葉をわかりやすくするために、「他界論」の出だしの文章を補足として書いておく。
社会的な共同利害とまったくつながっていない共同幻想はかんがえられるものだろうか?共同幻想の〈彼岸〉にまたひとつの共同幻想をおもい描くことができるだろうか?
こう問うことは、自己幻想や対幻想のなかに〈侵入〉してくる共同幻想はどういう構造かと問うことと同義である。
いうまでもなく、共同幻想の〈彼岸〉に想定される共同幻想は、たとえひとびとがそういう呼びかたを好まなくても〈他界〉の問題である。そして〈他界〉の問題は、個々の人間にとっては、自己幻想か、あるいは〈性〉としての対幻想のなかに繰込まれる共同幻想の問題となってあらわれるほかはない。しかしここに前提がはいる。〈他界〉の問題が想定されるには、かならず幻想的にか生理的にか、あるいは思想的にか<死>の関門をとおらなければならないことである。だから現代的な〈他界〉にふみこむばあいでさえ、まず〈死〉の関門をくぐりぬけるほかないのである。
(吉本隆明『改訂新版 共同幻想論』「他界論」P118 角川文庫)
※『共同幻想論』も、版の違いによって少しずつ文章が手直しされている。
上の吉本さんの語り出しの言葉、「解消とは違いますね」や「そうではないのです」を見ると、真意が相手に伝わっていないという場のふんいきが感じられる。
最初の吉本さんの発言、「でも、それは本質はこうだということを理解した上で、矛盾はこのようにいっぱいあるじゃないかという言い方なら成り立つけれども、・・・・・・」から以下がわたしにはちょっとわかりにくい。話し言葉であるが、文としてみると、長い一文になっている。おそらくこの頃は、吉本さんの目が不自由なせいもあり、書き起こした後の吉本さんのチェックも入っていないだろう。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 584 |
共同幻想の死滅 |
「個人・家族・社会」 |
論文 |
『吉本隆明全著作集4』 |
勁草書房 |
1969.4.25 |
※『看護技術』昭和43年7月号初出(1968年)
関連項目562 「吉本さんのこと ③」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人間は〈個人〉であったり〈家族〉であったり〈社会〉であったりしながら存在している |
〈個人〉はどのようなものとして〈社会〉の共同性の一員であるのかという問題である。 |
〈個人〉は自分が存在しているしかたを逆立させることによってしか、〈社会〉の心的な共同性に参加することができない。 |
人間はもともと社会的人間なのではない。孤立した、自由に食べそして考えて生活している〈個人〉でありたかったにもかかわらず、不可避的に〈社会〉の共同性をつくりだしてしまったのである。 |
項目
1 |
①
ところで、人間が人間らしい条件とはどういうことかなのか。この問いに直接答えるのはむつかしい。・・・中略・・・わたしたちにはっきりしているのは、人間は〈個人〉であったり〈家族〉であったり〈社会〉であったりしながら存在しているということだけである。しすし、これとても人間が〈個人〉であるとはどういうことか、〈社会〉であるとはどういうことか、そしてそれが人間らしい条件とどうつながっているのかと問いつめてゆくと、それに答えることは意外にむつかしいことがわかる。
(「個人・家族・社会」P454『吉本隆明全著作集4』勁草書房)
※『看護技術』昭和43年7月号初出(1968年)
つぎに問題となりうるのは、〈個人〉はどのようなものとして〈社会〉の共同性の一員であるのかという問題である。もっと厳密にいえば、〈個人〉の心的な世界は、〈社会〉の心的な共同性(共同幻想)とどのように関係づけられるかという問題である。
〈社会〉の心的な共同性は、現在では〈国家〉とか〈法律〉とかいう形であらわれている。古代では、共同の宗教という形であらわれたことがあった。もっと部分的な社会を考えれば、共同の風俗とか共同の習慣とか、共同の約束とか、共同の信仰とかがその小さな社会の共同の心として存在している。ある〈個人〉の心的な世界にとって、この〈社会〉の心的な共同性は、まったく快適なものと思われるかもしれない。また、別の〈個人〉の心的な世界にとって、この〈社会〉の心的な共同性は偽りのおおいものとして映っていることもありうる。またある別の〈個人〉の心的な世界にとって、この〈社会〉の心的な共同性はまったく桎梏以外の何ものでもないと考えるほかないかもしれない。この関係は考えるかぎりさまざまでありうる。こう考えてゆくと、この〈社会〉の心的な共同性は、個人〉の心的な世界がそれぞれちがっているのと同じように、ちがったものとして受けとられるほかはないようにみえる。そして、〈個人〉の環境がその生涯の線に沿ってさまざまでありうるように、社会〉の心的な共同性に対してさまざまな評価がありうるのである。そして境界が類似しているところでは、その評価に共通の部分が生まれてくると考えることができる。
しかし、この場合、本質的なことはただひとつである。〈個人〉の心的な世界がこの〈社会〉の心的な共同性に向かう時は、あたかも心的な世界が現実的なもので、具体的に日常生活している自分は架空のものだという逆立によってしか、〈社会〉の心的な共同性に向かうことができないということである。いいかえれば、〈個人〉は自分が存在しているしかたを逆立させることによってしか、〈社会〉の心的な共同性に参加することができない。この関係は、人間にとって本質的なものである。
(「同上」P464-P465)
②
人間はもともと社会的人間なのではない。孤立した、自由に食べそして考えて生活している〈個人〉でありたかったにもかかわらず、不可避的に〈社会〉の共同性をつくりだしてしまったのである。そして、いったんつくりだされてしまった〈社会〉の共同性は、それをつくりだしたそれぞの〈個人〉にとって、大なり小なり桎梏や矛盾や虚偽として作用するものだということができる。
それゆえ〈社会〉の共同性のなかでは、〈個人〉の心的な世界は〈逆立〉した人間というカテゴリーだけ存在するということができる。そして、この〈逆立〉という意味は、単に心的な世界を実在するかのように行使し、身体はただ抽象的な身体一般であるかのように行使するというばかりではなく、人間存在としても桎梏や矛盾や虚偽としてしか〈社会〉の共同性に参加することはできないということを意味している。〈社会〉の共同性のなかでは、〈個人〉は自分の労力を、心情を、あるいは知識を、財貨を、権威を、その他さまざまなものを行使することができる。しかし、彼(彼女)が人間としての人間性の根源的な総体を発現することはできないのだということは先験的である。この先験性が消滅するためには、社会の共同性(現在ではさまざまな形態をとった国家とか法とかに最もラジカルにあらわれている)そのものが消滅するほかないということもまた先験的である。
(「同上」P465-P466)
|
備
考
|
(備 考)
この項目は、『改訂新版 共同幻想論』(吉本隆明 角川文庫)の巻末の「解説」者、中上健次がその解説中に引用している文章に触発されて選択したものである。中上の引用部分は、上記の②の部分である。この「個人・家族・社会」の文章も『共同幻想論』が刊行されたのも同じ1968年である。
吉本さんの、人間の生存の基本イメージについては前に取り上げたことがある。(562 「吉本さんのこと ③」)そのことと関わる形で共同幻想の死滅のイメージが述べられている。ここには、問題点が二つある。
吉本さんの提出した、「人間の生存の基本イメージ」が、吉本さん固有のものに限らず、人間に普遍的に言えるかということ。もうひとつは、「共同幻想」が死滅するものだとしても、死滅するのは、遙かな未来においてである。つまり、それは人類の「永続的な課題」ということになる。この死滅の意味は、項目582 「個人幻想と共同幻想は本質的に逆立する ①」においても、本項目においても、「〈社会〉の共同性のなかでは、〈個人〉は自分の労力を、心情を、あるいは知識を、財貨を、権威を、その他さまざまなものを行使することができる。しかし、彼(彼女)が人間としての人間性の根源的な総体を発現することはできないのだということは先験的である。この先験性が消滅するためには、社会の共同性(現在ではさまざまな形態をとった国家とか法とかに最もラジカルにあらわれている)そのものが消滅するほかないということもまた先験的である。」と「共同幻想の死滅」のイメージが明確に述べられている。しかし、人間的本質からそのことは可能か、どう可能かという問題である。
この「共同幻想の死滅」に関しては、わたしはまだよくわかっていない。吉本さんの〈共同幻想の死滅〉の過程を永続的な過程として突き進んでいっても、人間が三人以上集まれば何らかの形で〈共同性〉は残るのではないかと思う。ということは、そこから「共同幻想」も生まれるということだろう。しかしまた、〈共同幻想の死滅〉の過程を永続的な過程として歩むことは、その反照としてあらゆる共同幻想の有り様に影響を波及させていくだろう。
宇田亮一 は、『吉本隆明『共同幻想論』の読み方』で〈共同幻想〉には二つあり、お祭りや組織内の取り決めなどほったらかしておいてもよい低強度の共同幻想と国家などのほったらかしておくわけにはいかない高強度の共同幻想があると述べていた。低強度の共同幻想であれ問題性はあるものの、このことは現在的なイメージとしてよくわかる。
吉本さんの〈共同幻想の死滅〉のイメージと宇田亮一の共同幻想の捉え方からするイメージが同一なのかどうか、今のわたしは確定的に言えない。つまり、よくわかっていない。現在性ということと、そこから理想の過程を遙かに歩んでいく歴史の過程ということ、そのような理想のイメージの現実性を支えるのは、お猿さんから別れた人間の本質の有り様であろうとは思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 616 |
現在の状況認識について
―「僕の判断」2005 |
第三章 『高村光太郎』 |
|
|
『吉本隆明が最後に遺した三十万字 上巻 「吉本隆明、自著を語る」』 |
ロッキング・オン |
2012.12.24 |
第三章 『高村光太郎』は、「SIGHT」第二十三号 2005年3月号に掲載。
インタビュアー 渋谷陽一
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 最近の僕の相当切実な課題 |
一種の平和の最後っていう感じで僕の中に渦巻いています。 |
このまま普遍的な国際性に滑り込んでいけるって思ってる気がする |
|
項目
1 |
①
吉本 だから、その頃(引用者註.戦時中)どういうふうにだんだん追い詰められてきたのか、そういうことが最近の僕の相当切実な課題にもなってますね。で、やっぱり平和な戦後60年って言いますけど、ほとんどそのどん詰まりみたいなところに今はあると思いますから、もしかすると自衛隊は正規の軍隊で、それでもし戦争状態になればそれは出掛けていくんだとか、国内で戦争するのだって公然と合法的にそうなるかもしれないなっていう状態がまた、一種の平和の最後っていう感じで僕の中に渦巻いています。つまり今の政府(註.1)の人たちは国民の主権っていうことは全然もう捨てちゃってるか考えていなくって、このまま普遍的な国際性に滑り込んでいけるって思ってる気がするんですよ。で、そこにくると僕らは逆にそういうふうに持っていっちゃダメなんだよって思うけど、もはや共産党は抵抗しないし進歩的な文化人は抵抗しないし黙ってるだけで、ちょうど戦争に入った時とか、それと同じになってるじゃないのっていうのが僕の今の感じ方ですね。これは若い人に訊いてみると、このまま国際性の中に滑り込めるっていうふうに思ってる気がするんですよ。それはやっぱり戦後っていうか戦無派の現在の若い人たちにも、そんなことばかり言ってたって、その理屈が通らなくなったらどうすんだっていう課題が突き付けられてくるっていうことだと思いますね。で、僕もやっぱり自分なりに追い詰められた時に俺はどういうふうにできるんだっていうことはやっぱりやらないと、それを考えざるを得なくなっていくだろうなっていう感じがするんです。
(『吉本隆明が最後に遺した三十万字 上巻 「吉本隆明、自著を語る」』P61-P62 ロツキング・オン 2012年12月)
※この発言は、SIGHT第25号 2005年3月号に掲載されたもの。
②
そこは今ものすごく問われてることのような気がしますね。そんな時に高村光太郎でもないし小林秀雄でもないし横光利一でもないし保田與重郎でもないしっていうふうに、自分なりの考えに即しながらそういう道を自分で開いていけるかっていうことはもう僕自身の重要な課題で、そんなことはもう戦後すぐにわかってたわけだけど、だんだんだんだん客観的な意味合いでもこれはちょっと追い詰まってきたなった感じがする。多分今の若い人たちはそんなに切実にそうなってるとは思ってないかもしれないけど、僕の判断が正しいっていうか正確だとすれば、本当は戦前と同じで相当追い詰められているんですよ。(註.2)だからそういう見方をすると、テレビを見ててもね、この頃は食いもんとお笑いしかないんですよ、極端に言うとそれが一番多い番組なんです。それもはっきり言ってロクな内容ではない。それは戦争中と同じでね、でももう笑うより仕方がないっていうかね(笑)
― だけどやっぱりそうやって本当に戦前を知っている吉本さんから言われると、なんだかほんとにいや~な感じになるんですが。
吉本 なるでしょ(笑)、そうなんですよ。
(『同上』P62 )
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
今の政府というのは、小泉純一郎政権を指す。
(註.2)
吉本さんの「僕の判断」には、わたしは気づいていなかった。わたしは若者ではなかったけど、「多分今の若い人たちはそんなに切実にそうなってるとは思ってないかもしれない」という部類に入っていたと思う。長らく自己や世界との対話をくり返してきたからこそ、吉本さんには情況が見通すことができていたのだろう。残念なことに、現在の安倍ネトウヨ政権の登場によって吉本さんの「僕の判断」が正しかったことが示されている。
政治やマスコミ、SNSなど社会の表層は、生活者(市民、国民)の生活はそっちのけで、未来の構想もなくおそまつな外交や経済動向や改憲に入れあげているという不毛な状況が続いている。また、政権のゾンビとなった復古イデオロギーで社会を塗り変えていこうというくさび打ちも続いている。わたしたち生活者が、現在の政権をその座から蹴ったくり落とせば少しはましなのだが、どこもそうたいしたことはできないというあきらめや絶望からか選挙などでその力を行使すれば追い落とせるのに、大衆(の総意)はそうしない。ほんとはわたしたち生活者大衆こそがこの社会の主人公だということを行使して示すべきだとわたしは思っている。
まだ若かった吉本さんは、敗戦後に自分の戦中の皇国少年としての有り様や社会や人々の有り様を徹底して対象化していった。敗戦後そういう道を自覚的・自立的に歩んできた吉本さんが、また戦争中と同様の情況の到来に必死になるのは当然であった。自らの思想生命がかかっていると言ってもよかった。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 648 |
子供が秘密の場所をもつこと |
第2部 学童期の子供をめぐって |
インタビュー |
『子供はぜーんぶわかってる』―超「教師論」・超「子供論」 |
批評社 |
2005.8.1 |
聞き手 尾崎 光弘 向井 吉人
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| アフリカ的な段階では個々の大人でも秘密の場所を持っています |
中上健次の小説「一番はじめの出来事」 |
『リトル・トリー』 |
|
項目
1 |
①
―子供が秘密の場所をもつことは人類史的にも深い根底がある(引用者註.本文の小見出し)
吉本 学童期の晩期は別ですが、幼年期の終わりから学童期の初期は何かしらそれぞれが秘密の場所を持っています。広く社会的な人類史の上から未開・原始の時代を僕はアフリカ的な段階と言っていますが、そういう段階では個々の大人でも秘密の場所を持っています。大人だったら自分の奥さんや子供も知らない秘密の場所を持っている、奥さんもまた秘密の場所を持っている。ここへ来ると気分が落ち着くような、家族にも教えないような憩う場所それぞれが必ず持っていると言えますね。
僕らでも幼年期の終わりから学童期に掛けて、よくお茶筒の中に自分で手を加えた格好良いベーゴマを入れて土の中に埋めましたね。ベーゴマに限らず、大事なものを隠して、「誰も知らない場所に俺の好きなものが埋めてあるんだぞ」と何となく良い気持ちになっていました。今の子供はそれほど顕著にそういう場所を持っていると言えないかもしれないけど、僕らの時は家からちょっと遠く離れた場所で遊ぶようになって、外遊びが身についた頃にそういう場所や入れ物を持っていたように思いますね。
もう少しすると今度は家族の視線が届かない場所で一日遊んで帰ってくるという時期ですね。帰るときになり、だんだん近くへ来るとなんとなく親の匂いといいましょうか、視線がちゃんと感じられるところに入って行き、家へ帰ってくる。そういう遠くの場所を持っていたように思います。
②
吉本 それは割合に必然的というか、非常に根底の深いもので、そういう場所はある時期の人類にとって非常に重要だったし、またある時期の子供にとっては非常に重要な場所であったと思いますね。宝物を土に埋めてはときどき掘り出すことは必然的だったように思いますけど、現在の都会では薄れてきています。でもたぶん今でもこもりきりで、テレビゲームで遊んでいる子供だって親や兄弟にわからないように何かをどこかにしまっておくことはあるんじゃないかという気がします。
尾崎 今は学童期前期の話ですよね。
吉本 前期ですね。幼児期の終わりから学童期に掛けて外遊びを自覚的にやるようになってから、秘密の場所を持つとか、あるというのは重要なことだと思いますね。
文学でその時期を描いているのは亡くなった中上健次だけですね。現在その分類に入る作家は彼だけで、それを見事に描いています。中上健次の小説(引用者註.「一番はじめの出来事」)ではそういう秘密の場所に集まってきた子供たちが材木を集めてきて、村の外れに小屋らしきものを造るわけです。そこで遊んだりだべったりして、ひとりでに家族には知らせないようになっていく・・・・・・「どこで遊んできたんだ?」と聞かれても「いやぁ、ちょっと遠めでな」みたいなことを言うだけで教えない。
③
(引用者註.フォレスト・カーターの小説『リトル・トリー』にも「秘密の場所」のことが出てくると語った後)
吉本 歴史的に無意識のうちに秘密の場所をもつ時期があった、成長期の場合にもあった。成長期でいえば幼年期から学童期にかけて遊びが生活だと身について考えられるようになった時期といいましょうか、それに該当する時期に秘密の場所を持ちます。その小説の場合は原住民の人たちが死ぬとそこへ埋めてもらうのが習いになっていると書いてあるんです。非常に日常生活にとって重要な場所であって、そういう場所をそれぞれが持っているという描写があります。僕らが子供だった時の体験でも、ある時期に秘密を持つことを好むのは普遍的で、その根底では生活が即遊びと同じで区別を付けていないことと合致するのは必然性があるのでしょう。それはおっしゃるところの熱中に関連すると思いますが、たぶん熱中というのはやはり生活と遊びを区別する必要がなかった歴史時代を根底として、個人の一生涯のある時期に――現在は壊れてしまっているのか、なごりがあるのかわかりませんが――、秘密の場所を持つことの重要さや遊びすなわち生活それ自体という深い根拠のある考えを自覚した時に生ずるのではないかと思います。
(『子供はぜーんぶわかってる―超「教師論」・超「子供論」』P76-P81 批評社 2005年8月)
吉本隆明 聞き手 向井吉人・尾崎光弘
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
吉本さんは、「文学でその時期を描いているのは亡くなった中上健次だけですね。現在その分類に入る作家は彼だけで、それを見事に描いています。」と断定的に語っている。この発言に関しては、吉本さんは『言語にとって美とはなにか』でもたくさんの小説作品を取り上げている。また、それ以前やそれ以後も文芸批評としても多くの作品を読んでいる。つまり、吉本さんとしては、断言できるほど作品を渉猟してきたという自信が背景にあるものと思われる。
ここでも、現在のわたしたちの人の生涯における事象が、人類の歴史の段階と対応させた考え方がなされている。ある留保を含みつつそのような考え方を吉本さんが取り始めたのは、『母型論』(1995.11)辺りだろうと思われる。本書は、2005年8月刊であり、ここでも同じくそういう捉え方がなされている。『母型論』の「序」によると、
もうひとつの欲求につなげるためにいうと、言葉と、原宗教的な観念の働きと、その総体的な環境ともいえる共同の幻想とを、別々にわけて考察した以前のじぶんの系列を、どこかでひとつに結びつけて考察したいとかんがえていた。どんな方法を具体的に展開したらいいのか皆目わからなかったが、いちばん安易な方法は、人間の個体の心身が成長してゆく過程と、人間の歴史的な幻想の共同性が展開していく過程のあいだに、ある種の対応を仮定することだ。わたしは何度も頭のなかで(だけだが)この遣り方を使って、じぶんなりに暗示をつくりだした。
この対応はフロイトが初めに取った方法であるとどこかで吉本さんが述べていたように記憶するが、この対応が正しいとすれば、遙かな太古の不明の靄は、現在のわたしたちの生涯における振る舞いをより微細に見ていくことによってその不明の靄が打ち払われていくことになる。
現在の子どもたちの「秘密の場所」の有り様は具体的にはどうなっているのだろうか。疑問点としてメモしておく。
|
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人類の未開時代の精神の有り様 |
新しい精神の異常な動きやイメージが出てくることはなく、すべて過去の時代にあった精神の動きです |
正常と異常 |
|
項目
1 |
①
妄想や幻覚も同じで、現在の社会では異常とみなされますが、妄想や幻覚のある人が多数を占めれば正常となります。そういう状況はありうるのです。人類の未開時代では、幻覚や妄想のある人のほうが正常で、ない人は異常だったということがありえたわけです。現在の社会では精神異常でも、未開社会にもっていけば、正常と異常が逆転することもありうるわけです。精神の異常はけっして固定的なものではありません。
また、かつて人類が体験したことがないような、新しい異常もありえません。未開時代に体験したか、いま体験しているかの違いだけで、過去に一度も体験したことのない精神の動きを人類はもちえないのです。新しい精神の異常な動きやイメージが出てくることはなく、すべて過去の時代にあった精神の動きです。そのほうが多数を占めていたなら正常といわれたとおもいます。
正常とか異常とかは、いまの社会段階で判断しているだけですから、確たる根拠はありません。ただ現在では不自由なだけです。日常生活に差し支えるし、他人とのコミュニケーションに差し支えるから、治さなければいけないというだけのことです。ほんとうは異常ではないのですから、本来的には治しようがありません。少数だから異常とされていますが、ほんとうはそういえないわけです。
(『詩人・評論家・作家のための言語論』 P100-P101 吉本隆明 メタローグ 1999年3月)
|
備
考
|
(備 考)
「かつて人類が体験したことがないような、新しい異常もありえません。未開時代に体験したか、いま体験しているかの違いだけで、過去に一度も体験したことのない精神の動きを人類はもちえないのです。新しい精神の異常な動きやイメージが出てくることはなく、すべて過去の時代にあった精神の動きです。」
この断定的な口調に、わたしはドキリとした。つまり、本当にそうなんだろうかという疑念が走った。しかし、この言葉の背景には、『心的現象論』(『心的現象論序説』)を書き上げた吉本さんの膨大な考察の足跡があり、そこから見渡した言葉がある。また、フロイトにならって人類の歴史を個の生誕からの生涯と対応させて考えた吉本さんによれば、母の物語を携えて生きていくわたしたちは、その物語になんとか修正を加えていくことができるとしても、新たな母の物語を作ることはできないということになる。上の言葉は、このことと対応しているように見える。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 663 |
〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉 ② |
吉本隆明 「ほんとうの考え」007 自分 |
対話 |
|
『ほぼ日刊イトイ新聞』 |
|
2009.9.9 |
※ 吉本隆明・糸井重里 対話
関連項目471〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉 ①
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| いまの問題と持続的な問題がまとまる頂点、集合点がある |
「自分という視点 |
実感 |
自分が外側にいたらダメなんです |
項目
1 |
①
糸井 だけど、きっとお若いときから、
思考の形は同じところがありますよね。
「ひらめく」というよりは、
「つながる」ということ。
吉本 ええ。
自分では「持続性」と言ってます。
時代のいろいろなことは、
状況によって変えなきゃいけない、
あるいは、変わんないとウソだよ、という
部分があります。
それとは別に、もうひとつ、
永遠の課題というものがあります。
自由で平等で
苦しがったり失業したりする人が
いなくなることはいいことで、
これは永遠の課題です。
だけど、そう簡単に、
ひとつの国ががんばって
政府をぶっ倒したとしても、
それがはじまるわけではない。
変わるものと永遠のもの、
このふたつを綿密にとらえないと、
実相というものは
なかなか浮かんでこないです。
いまの問題と持続的な問題がまとまる
頂点というか、集合点があるんです。
そこだけ捕まえていれば、
どういうことに適応させても、
たいていそんなに大きな間違いはしないよ、と
ぼくは思います。
②
糸井 誰の中にもきっと、薄いけど、
その考え方はあるんだと思います。
その考え方の助けになることのひとつは、
もしかしたら
「自分という視点」ではないでしょうか。
一般論で語っていると、
いまも永遠も、どこかへ行っちゃいますし。
吉本 そのとおりですね。
いろんなことにくわしく、
要点をまとめることができたとしても、
自分が入っていない場合があります。
そういう人の意見を聞いていると
実感がないから、どうしても不満が残ります。
糸井 どんなに勉強してもダメなんですよね。
「自分が入らないこと」は、もしかしたら
現代の病かもしれません。
しかし、最近、お笑いの世界では、
自分が入っている実話や楽屋話を
芸にする人たちが増えてきました。
太宰治や織田作之助が
私小説を書いていた時代のあの確かさを、
芸人さんが、お笑いの中に自分で入れて
「私お笑い」をはじめたんでしょうね。
吉本 ああ、なるほど。
それは、そういうことが欲しいからでしょう。
糸井 自分を入れなくては
お笑いが成立しないということを
敏感にわかったんだと思います。
吉本 自分が外側にいたらダメなんです。
お笑いだけじゃなくて、文学もそうですし、
きっと政治もそうだと思います。
自分が入ってこないし、
そして、入ってきたと思ったら、それは
よくよく聞いていると他人のものだったりする。
(前の)総理大臣だって(註.1)
そういうところがあったんじゃないかな。
あれだけ度胸がいいやつは
自民党にはほかにいねぇから、というのは
わかるんだけど、
要するに、自分のことを入れてないから
ああいうことが言えるんだな、とぼくは思います。
アメリカは入れてるかもしれないけど、
自分を入れてないから、
すべらかにああいうことが言えるんだぞ、と
思います。
だけど、ひと昔前の、
根拠地型の政治家は、(註.2)
自分が入ってることしか言わない。
それはやっぱり、自分をいれない人に
いまは押しまくられちゃうんですよ。
糸井 自分の「痛い」だの「痒い」だのが
入った考えが、ほんとうは必要なんだけど、
いまは「痛い」「痒い」を
言っちゃいけない時代なんでしょう。
吉本 そういう時代なんでしょうね。
(吉本隆明 「ほんとうの考え」、007 自分 2009-09-09) 『ほぼ日刊イトイ新聞』所収
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
この対話の日、9月9日から見て、直前の総理大臣は福田赳夫を指すが、(前の)とあり、また表現内容から見てこれは小泉純一郎(2001年-2006年)のことではないだろうか。
(註.2)
これは田中角栄を指しているだろう。
糸井重里が「 誰の中にもきっと、薄いけど、その考え方はあるんだと思います。」と語っているように、確かに、これはなんとかすぐに解決できそうだけど、それはすぐには解決できない問題だよなとか、誰もが感じることがあると思う。吉本さんは、そこから〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉(持続的な課題)として、ひとつの概念や論理として取りだして見せたのである。
さらに、 「いまの問題と持続的な問題がまとまる頂点というか、集合点があるんです。そこだけ捕まえていれば、どういうことに適応させても、たいていそんなに大きな間違いはしないよ、とぼくは思います。」と語られているが、残念ながら具体的なイメージとして説明的に語られているわけではない。しかし、少なくとも、〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉(持続的な課題)を同列に置き、二つを対立的なものとみなさないということは言えそうである。(関連項目471では、「永遠の問題と緊急な問題とが一緒に混ざって入ってきているということ」が特色。「これは二者択一の問題として存在しないと思います」と述べてある)後はこの吉本さんのおくりものをわたしたちが受けとめていけばいいのだと思う。この集合点のイメージが解明されることは、さまざまな無用な対立に終止符を打つことにもなるだろう。
糸井重里が周到に繰り出した「自分という視点」は、対象の内側に入ることでもあり、自分の実感にもつながるものである。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 664 |
学校というもの |
「06文化はいいことだ、の落とし穴」 |
対話 |
|
『ほぼ日刊イトイ新聞』 |
|
2008.12.30 |
「テレビと落とし穴と未来と。」 吉本隆明 ・糸井重里 対話、「06文化はいいことだ、の落とし穴」2008-12-30
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 学校のいいところ |
学校というのは、公園なんです |
一般社会で、支配的な経済力を
持っているということ |
|
項目
1 |
①
吉本
いいことはダメですね。
ですから、文化が高級だとか、
いい学校と言われる学校を出れば優秀だとか、
そういう馬鹿なことを言っているやつは
ダメだということになります。
そういうことは関係ありません。
学校は学校です。
学校は、同じ金を出せば、
同じように誰も一律に扱って、
大学だったら、教授先生の意向で
生徒がちゃんと守られている、
これが学校のいいところですよ。
学校のいいところって、それしかないですよ。
だから、学校というのは、公園なんです。
赤ちゃんを乳母車に乗せて、公園に遊びに来て、
おかみさんがたがそこでけっこうおもしろく
ときを過ごしていく。
学校というのはそれですよ。
真理の追求の場所だなんて、
そういうものじゃないんですよ。
はじめからそうじゃないはずなんです。
公園ですから、暴力だって、
ときどきそういう悪童がいてやるわけだけど、
謝れば謝って、頭をちょっと下げれば、
教授先生もそこがいいところで、
ちゃんと「いいよ、いいよ」って、
「学校をつづけなさい」と言ってくれるわけです。
だけど、一般社会にスッと出たら、
そんなの通用せんです。
たちまちダメです。
それで反抗するんだといったら、
もう生涯、そいつが生活していく場所を
全部奪って取ってしまうということを
社会は実際にやりますからね。
糸井
ええ、できちゃいますよね。
吉本
やっぱり、支配的な経済力を
持っているというのは、
すごいものだなと思います。
それに異を唱えることができないというところまで
ちゃんと徹底的にやりますからね。
それで、徹底的に
バツにされちゃうというふうになっちゃいます。
ぼくも同じで(笑)、
ここまで考えるようになったのは、
自分が体験したからなんです。
文化の事業は、
いいことをしているつもりでやっているんですよ。
あいつに悪い待遇をした覚えはないというふうに、
いつでも言えるようなやり方です。
そこはすごいところだと思います。
糸井
公共の、公益のために。
吉本
決して悪いことをしたって、
どこにも欠陥があることをした覚えはないと、
いつでも言えるようにちゃんとできてます。
(つづきます)
(テレビと落とし穴と未来と。 吉本隆明 、「06文化はいいことだ、の落とし穴」2008-12-30)
『ほぼ日刊イトイ新聞』所収
|
備
考
|
(備 考)
学校も社会も表向きの姿、言葉というのがある。学校は、「真理の追求の場所」であるとか、文化は、「高級」であるとか、誰もが一度は耳にしたことがある言葉というものがある。しかし、それはその渦中の具体性を生きる者にとっては白々しさを伴う言葉だと思われる。つまり、それって自分たちの現実とはだいぶん違うよなあという思いを抱くのではないだろうか。ちょうど、長々と続く空疎な校長の話のように感じられるのではないかと思う。学校という小社会の渦中での生徒や先生としての内側での体験や実感を忘れないならば、校長さんの言葉や世の教育論の真偽がわかる。
ここに語られているような渦中の具体性の実感から出発しないかぎり、表層は模様替えされたとしても問題はいつまで経っても先へ先へと形を変えて繰り延べられるだけである。例えば、教育政策としての「ゆとり教育」からその廃止へ、こうしたことは教育の現場の抱える問題性に対してかすりもせずに、推移していくばかりである。すなわち、たいして意味もないことが真面目な顔をして論議され、推進されている。
|
※ 創作学校での講演が本書の元になっている。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| ふたつの大きな層がある |
旧日本語と新日本語 |
どれにも似ていない理由 |
|
項目
1 |
①
日本の言葉は、まだわかっていない部分が多くあるので確定的なことはいえませんが、少なくともふたつの大きな層があるとかんがえられます。大ざっぱにいうとひとつは旧日本語の層、もうひとつは新日本語の層です。
旧日本語は、奈良朝以前に日本列島に住んでいた人たちの言葉です。新日本語は、奈良朝以降に新しい文明と一緒に入ってきた言葉です。つまり現在の日本人は、奈良朝以前からいた旧日本人と、奈良朝以降にやってきた新日本人との混血だということです。現在の日本語は、旧日本語と新日本語が混ざり合って、どちらとも違う言葉になったものだとかんがえられます。
(『詩人・評論家・作家のための言語論』 P114 吉本隆明 メタローグ 1999年3月)
②
日本語の起源については、朝鮮語に似ていると主張する人、スリランカのタミール語に似ているという人、またはパプア・ニューギニアの言葉に似ているという言語学者などがいます。またインド北部のレプチャ族のレプチャ語に似ているという人もいます。多くの学者がさまざまな地域の言葉に似ていると主張していますが、どれひとつとして確定的な説はありません。別な言い方をすれば、どれにも似ていないことになります。本来的にいえば、ある言語は近隣の言葉に似ているはずですが、いまの段階では、どれにも似ていないといったほうがよいわけです。
どれにも似ていない理由はふたつあります。
ひとつは現在の日本語が、旧日本語と新日本語が融合しているので、もとの形がわからないためです。もとのふたつに戻せるなら、近隣の言葉と似ているか似ていないかを判断できますが、もとに戻すこと自体が困難ですから、どれに似ているともいえないのです。
もうひとつの理由は、旧日本語がどこと似ている言葉で、いつごろのどんな言葉か、不確定な部分があることです。
たとえば、アイヌ語は北方の人の言葉であるか、南方の人の言葉であるか確定できていません。アイヌ人はいまの北海道や樺太に住んでいますが、だんだん中央から追い払われてシベリア大陸のほうに引っ込んでしまったとかんがえれば、アイヌ語は北方の言葉だとなるかもしれません。しかし、比較的妥当とおもわれる言語学者によれば、アイヌ語は南方の言葉です。では、どうやって南から来たのか。大陸の沿岸を南から北へ移動して日本列島にたどり着いたとかんがえればよいのか。あるいは、東南アジアの沖にあるインドネシアの島から、オーストラリア近くにあるニューギニアの島々に移り、その人たちが黒潮によって日本列島にきて北のほうに住んだとかんがえたらいいのか。実はまだ、ほんとうのところはよくわかっていません。
日本語については、もっと不確定なことがたくさんあります。しかし大ざっぱにいえば、旧日本語と新日本語がミックスして、やや両者と違う言葉になっているのが奈良朝以降の日本語だとかんがえるのが妥当だとおもわれます。
(『同上』 P115-P117 吉本隆明)
※ ①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
旧日本語と新日本語の織り成したドラマについては、まだ文字もなく記録もない時代のことであるからまだ大まかなところしかわかっていないということ。しかし、そのドラマはわたしたちの現在の言葉や精神の有り様にまで残留し影響しているはずだから、例えば人類の足跡に関する遺伝子解析の登場のように、今後もいろんな所から少しずつ明らかになっていくに違いない。そしてそのことは、わたしたちの心や文化の有り様への内省に当たると言えそうである。
それと、わたしがいつも思うことではあるが、わたしたちはそのことを内省的に論理としてわかっていなくても、そのこと自体を自然性として実践している。ちょうど、心臓などの不随意活動のように、わたしたちはいつでも知らない間にあることを実行しているということ。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 667 |
言葉の起源を考える ② ― 旧日本語 |
「言葉の起源を考える」 |
|
『詩人・評論家・作家のための言語論』 |
メタローグ |
1999.3.21 |
※ 創作学校での講演が本書の元になっている。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 逆語序 |
オーストロネシア語(「南の島の言葉」) |
一般的に具体性のある言葉で話し、あまり抽象語が得意でないのは、旧日本語を含めてオーストロネシア語の特徴だとかんがえられます。 |
オーストロネシア語とインド-ヨーロッパ語、なぜそういう性格になったか |
項目
1 |
①
ぼくらが調べてわかったこと、わかっていないことについて、すこし立ち入って話したいとおもいます。
たとえば、琉球沖縄語は南の言葉だとおもわれますが、これもすこしあやしいところがあります。存外、北の言葉かもしれませんから確定的にはいえませんが、日本列島の南端に住んでいるのだから、琉球沖縄語を南の言葉だとかんがえますと、琉球沖縄語と本土の言葉はまず類縁関係にあります。つまり、どちらも似ている言葉で、時代をさかのぼれば同じ言葉だといってよいでしょう。
たとえば、奈良朝以降のわれわれの表現では、じぶんの住所を「東京都中央区京橋何丁目何番地」といいます。広い地域をまず先にいって、次にそのなかに含まれている狭い地域を、そのまたなかに含まれている地域をあらわすのが特徴です。琉球沖縄語に残っている言いまわしには逆の言い方があります。まず狭い地域を先にいって、そのあとに広い地域をいうわけです。
折口信夫が、「日琉語族論」というすぐれた論文のなかではじめてそれを指摘しました。「東京都中央区京橋」という言い方が正語序とかんがえれば、琉球沖縄語は逆語序であり、逆語序は正語序よりも古い時代のものだと折口信夫はかんがえたわけです。このばあいの古いとは、奈良朝以前を意味します。たとえば本土語で「小橋」は小さな橋のことです。琉球沖縄語では「橋小」【ルビ はしぐわ】といいます。
琉球の『おもろさうし』という歌謡集は、十二~十三世紀ころにつくられたとおもいます。日本の奈良朝時代は、琉球の発達度では十二~十三世紀に該当し、そのころに編まれた歌謡集ですから、古い時代の言葉や言いまわしがたくさん残っています。奈良朝以降の日本の古典『古事記』『万葉集』などには残っていない言いまわしがいくつもみられるのですが、そのひとつが逆語序です。
たとえば「辺留笠利(ひるかさり)かち」という言い方があります。「かち」は「どこどこへ」の「へ」です。ここでは辺留のほうが狭い地域です。つまり、笠利という村落の辺留という場所という言い方で、これは中央区東京都という言い方と同じです。
(『詩人・評論家・作家のための言語論』 P117-P120 吉本隆明 メタローグ 1999年3月)
②
一般的に南島語、ネシア語といわれる言葉を話す地域、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア、インドネシアと東南アジアとの中間にある島(ネシア)全体を合わせるとオーストロネシア語群になります。オーストロは「南の」ですから、「南の島の言葉」という意味になります。琉球沖縄も含まれ、もしかすると旧日本列島も含まれるかもしれません。
オーストロネシア語群の特徴は、われわれが使っている言葉にもみられます。たとえば「あいつの腹はわからない」とか「あいつは腹黒いやつだ」という言い方があります。これは内臓語といっていいでしょう。これと同じような言いまわしがポリネシア語のなかにあります。「腹がわからない」といいますし、「はらわたが偏っている」のは偏屈だという意味です。
一般的に具体性のある言葉で話し、あまり抽象語が得意でないのは、旧日本語を含めてオーストロネシア語の特徴だとかんがえられます。同じような言いまわしは現在の日本語にもたくさんあります。極端な例としては「へそが曲がっている」とか「つむじ曲がり」とか、身体に関する言葉で精神の状態をあらわします。日本語もそういう言い方のほうがわりあいに特異です。
われわれは近代のインド-ヨーロッパ語を輸入していますから、たとえば「腹黒い」という表現は一種のメタファー(暗喩)で、「根性がわるいやつだ」という意味の比喩を使っているとかんがえがちです。しかしそれは逆で、古い日本語の時代をかんがえますと、「あいつは根性がわるい」という意味を伝えるには、「腹が黒い」という具象的な言い方しかなかったのです。
もともと抽象語がなかったのですから、抽象的なことをかんがえられないのが、日本語を含めた古いオーストロネシア語の大きな特徴です。いまの日本語で抽象的なことをいうためには、明治以降につくった抽象語を使わなければなりません。もとをただせば、オーストロネシア語の特徴を残しているということです。
(P122-P124)
③
インド-ヨーロッパ語は抽象的な言いまわしが得意で、論理的なことをかんがえるにはインド-ヨーロッパ語がよく使われてきました。日本語を含むオーストロネシア語は、抽象的なことをいうには不便で、具象的なことをいうには便利です。なぜそうなったのでしょうか。
ぼくらの唯一の解釈は、言葉の発達には具象的なことでしかあらわせない段階があり、何かしらの契機によって、オーストロネシア語全般はそこで長期間にわたって停滞して、民族語の特色になってあらわれたということです。では、インド-ヨーロッパ語ではどうしてそれがなかったのか。ぼくの理解では、具体的なことであらわす段階はあったけれども、何かしらの契機で速やかにその段階を通過していったということです。
これは誤解の起こりやすい問題です。たとえば、類人猿の頭蓋骨は横からみると長く、南アフリカ人の頭蓋骨は鼻の部分があまり出ていなくて、ヨーロッパ人は鼻の骨が出っ張っている。それは発達の過程で徐々に鼻の部分が出っ張ってきたのだと、かなり優秀な考古学者でも信じています。そう誤解しやすいけれども、鼻の低い高いは発達の段階とあまり関係はなく、知恵のあるなしとも関係はないのです。人種的特色は、発達のどの段階で停滞し、それが特色となったかというだけです。
類人猿の頭蓋骨が横長で、発達するにつれて縦長になり、徐々に鼻が出っ張ってきたといえば、ヨーロッパ人がいちばん発達していることになってしまいます。アフリカ人がやがてヨーロッパ人のような顔になるわけではありません。
オーストロネシア語が具体性のある言葉を得意とし、インド-ヨーロッパ語が抽象的なことが得意になったという問題は、それと同じです。
ただ、オーストロネシア人は論理的な抽象語が苦手だったから、抽象的な学問があまり発達しなかったとはいえるだろうとおもいます。
(P124-P126)
※②と③は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
上の文章の後に、次のようにある。
しかし、どちらが発達しているかという問題は別の話です。美的なものをつくることが人類の文化がめざす最後の目的だとすれば、日本人は決しておくれているわけではありません。しかし「二たす二はどうして四になるのか」をかんがえることが文明発達の果てだかんがえれば、いまでも相当おくれをとっているとはいえそうです。 (P127)
吉本さんは、高村光太郎を論じた若い頃は特に、西欧のファーブルのように昆虫の研究で一生をつぶしたというようなことをずいぶん評価していて、日本的な工芸などの美にうつつを抜かすようなことには否定的であった、あるいは厳密に言えば消極的な評価だったような気がする。もちろん、このことは表現者としての存立に関わる大衆の原像を見据える思想の根幹の場面においてではなく、その上の思想の地平の場面の問題としてである。
ここに引用した言葉では、並列的に並べて語られているように見えるが、ある留保のもと、遙かお猿さんから別れたところから始まる人間や人類というというものの姿(根源的本質性)に照らされている晩年の吉本さんの立ち位置があるように思われる。
③の「ぼくらの唯一の解釈」に関して思い出すことは、このことと対応していると思われるが、〈アジア的段階〉はヨーロッパにもあったが、アジア地域では長らく停滞し、ヨーロッパ地域ではそれをすばやく通過し〈ヨーロッパ的段階〉に突き進んだ、と吉本さんは捉えていたと記憶する。そしてそれに関しては、その背景の地勢的な固有性の違いにも触れられていたと思う。
|
※ 創作学校での講演が本書の元になっている。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 旧日本語には抽象的なことをあらわす言葉がなかった |
いまの感覚ではメタファーになりますが、メタファーとは違います。 |
日本の詩歌の起こりでは、何かを伝えるためには自然物を描写する以外になかったのです。 |
日本語をいまよりもっとはっきりさせよう |
項目
1 |
①
旧日本語には抽象的なことをあらわす言葉がなくて、「あいつはわるいやつだ」というには「腹黒い」という言い方をするよりほかにありませんでした。いまの感覚ではメタファーになりますが、メタファーとは違います。そうとしかいえなかった。その段階 (註.1) からきた特色だとかんがえるのがよいとおもいます。
萩原朔太郎(一八八六~一九四二) (註.2) 以降、近代詩に大才をもつ詩人はあまりいませんが、その偉大でない詩人たちが苦心に苦心をかさねて、現在の日本語表現で効果的なメタファーをつくりました。一生懸命にいろいろな方面からつついてみて、イメージがよくわくようなメタファーをつくってきたわけです。
けれども、国文学の最初はメタフォリカルな言い方しかなかったのです。これも、折口信夫がある程度洞察しています。日本の詩歌の起こりでは、何かを伝えるためには自然物を描写する以外になかったのです。
たとえば『古事記』には、神武天皇の九州時代に生まれた子供が、神武天皇が死んでから神武天皇のお妃、つまり継母と結婚したとあります。そうして大和に来てから、継母が以前に産んだ子供が邪魔になってきて殺そうとする。お妃の伊須気余理比売(いすけよりひめ)は、じぶんの子供たちに「うちの新しい旦那が陰謀でおまえたちを殺そうとしているぞ」と教えるために歌を詠みます。
狭井川よ 雲立ちわたり 畝火山 木の葉さやぎぬ 風吹かんとす (『古事記』 歌謡二一)
「狭井川」は三輪山のそばにある川です。この歌はすべてが自然描写で、山に雲があって、風が吹いているといっているだけです。しかし当時の人にはそうは聞こえない。「あの辺りで陰謀をやっているぞ」という意味に受け取ったわけです。
②
ほくらが神話を読むばあいは、自然を描写した比喩で何かを物語っているように読んでいますが、おそらく当時の人は逆です。自然を描写する以外に、「あいつは陰謀でおまえを殺そうとしているぞ」という言い方はなかったとかんがえるのが正しいとおもいます。
ですから、ぼくもその端くれですが、萩原朔太郎以降の新しい詩人たちが一生懸命に方々からつついてきたので、「こういうメタファーの使い方が現在の日本ではいいんだぜ」というのをだいたい確定しています。しかし、まったく新しい言語表現というわけではありません。日本語の詩の言いまわしは、はじめはすべてメタファーでした。意味をじかにいう抒情詩はあとから出てきたのです。
③
メタファーは最も新しい日本語の言語表現であると同時に、最も古い日本語の言語表現であったということになります。抽象的なことを伝えるために具象物をもってくるという日本語の特色は、広くいえばオーストロネシア的な言葉、つまり古い日本語の大きな特色だということができます。
このようなことを次々と探究していくことによって、日本語をいまよりもっとはっきりさせようというのが、ぼくらが一生懸命になってかんがえていることです。
(『詩人・評論家・作家のための言語論』 P128-P131 吉本隆明 メタローグ 1999年3月)
※①②③は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
前回の項目で語られた「一般的に具体性のある言葉で話し、あまり抽象語が得意でないのは、旧日本語を含めてオーストロネシア語」が停滞的に長く続いた段階。
(註.2)
萩原朔太郎には、ヨーロッパの文化、文明の大波をかぶった影響下に、自ら考えつめた詩論、『詩の原理』がある。ヨーロッパの思想や概念を駆使しながら日本の古来からの詩も包み込みつつ優れた詩論を展開している。もちろんその背後には、自身も翻訳できたのかどうかは知らないが、西欧の書物が急速に取り入れられ翻訳されていった状況がある。
年譜によると、1917年(大正6、32歳)2月に詩集『月に吠える』を出版している。その後、1920年(大正9、35歳)に『詩の原理』素稿を書き上げ、改稿にとりかかる、とあるから、ヨーロッパの思想や文化や詩を潜り抜けてその影響下に詩集『月に吠える』にまとめ上げられた詩を書き続けたのだろう。そうして、両者の体験をもとに実感を伴うものとして『詩の原理』をまとめ上げたのだと思う。
①より
「いまの感覚ではメタファーになりますが、メタファーとは違います。」という言葉は大事である。今読んでいる『月と蛇と縄文人』(大島直行 角川文庫)は興味深い考察に満ちているが、これも、当時の縄文人の精神性の表れを現在からの視線や感覚を交えて「メタファー」という語を使っているようで、少し気にしながら読んでいる。難しいことだけど、現在からの視線・感覚の「メタファー」と「メタファーのようなもの」の先まで突き抜けて出かけてみなくてはならない。わたしには、目下その道筋はうまく見えないけど、なんとか道だけは通じているような気がする。この太古への遙かな時間性を現在の世界に変換すると、わたしたちひとりひとりと他者への距離ということになる。すなわち、難しい他者理解の問題になる。これもたぶん道は通じていると思う。
③より
「このようなことを次々と探究していくことによって、日本語をいまよりもっとはっきりさせようというのが、ぼくらが一生懸命になってかんがえていることです。」、このことは人間活動の全てについて言えることで、例えば、言葉の現状で別に日常の生活にあんまり不便がないとしても、言葉の困難を抱えている人もいるかもしれない。あるもの、あることを明らかにしようというのは人間の根源的な欲求のひとつかもしれない。そのことが、世界を日々呼吸するわたしたちの呼吸をいくらか和らげたり、少しずつこの世界を明るく照らし出していくのだろうと思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 672 |
家族とは何か |
第一日・胎児期一 「ほんとうのこと」の起源 |
インタビュー |
『ハイ・エディプス論』 |
言叢社 |
1990.10.25 |
P19本文の小見出し 飢餓感の根源は〈母との物語〉のなかにある
P26本文の小見出し 人間はなぜ家族をつくるのか
「本書は、一九八九年六月十五日から十月十八日までの期間に、五日間にわたって吉本邸でおこなったインタビューを
整理し、これにていねいな削除と若干の加筆を施していただき成ったものです。」(島亨「あとがき」より)
※インタビュアー 島亨(言叢社同人)
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 理想的な母親、理想的な環境、理想的な乳胎児の一年半ということ。 |
欠如 |
|
|
項目
1 |
①
吉本 ・・・略・・・。いまいった理解のしかたからは、単純なことでしょう。その場合の女の人も乳児のとき大なり小なり飢餓感、飢渇感、欠如感を受けとっていると理解できます。胎児としてのじぶんが受けた飢餓感、欠如感が、授乳する側にまわったときやはり出てくる。そう解釈をすればとても簡単です。
もうひとつ敷衍できることは、例えば、ここに理想的な聖母みたいな母親がいて、理想的な環境で、子供が生まれた。そして理想的な胎児の十ヵ月と、乳児の一年、合計一年半を理想的な家庭環境(亭主との関係は理想的)にあった。母親も理想的な聖母だし、母親の子供にたいする物語でも理想的だという乳児がありえたとしたら、家族というか、男女の永続的な同棲はなくなるんじゃないでしょうか。つまり、性行為というのはありますし、恋愛もありますし、全部ありますけれど、一生一緒に住むことを人間は考えないんじゃないでしょうか。
島亨(編集部) どうなります?
②
吉本 逆なことをいいます。家族とは何か、人間はなぜ家族をつくるのか、男女が恋愛して同棲して家をつくって、それが一生続くか十年続くかわからない。でもなぜそうするのかといえば僕は欠如だとおもいます。乳胎児期の欠如がなかったとしたら、そんなことしないとおもいます。充たされた乳胎児期を理想的に一〇〇パーセント過ごして、しかも母親の環境、母親の母親の環境、三代くらいみんな理想的だったと仮定して、その乳児がおおきくなって男女ともにそうだったとしたら、永続的に同棲することは無くなるんじゃないでしょうか。なぜ同棲するかといえば欠如が人間にあって、どこかで男女両性とも充たそうとする。もしかして性行為でも、ほかの愛情行為でもいいんですが、その行為の時間だけ充たされれば充分なんだというんじゃなくて、たがいに相手に求めている愛情にはもっと永続的に、抱いてきた欠如というか飢餓感というか、それが満足じゃないということがある。だから婚姻して家族をつくるみたいなことがあるという気がします。そして欠如が深刻なため、すぐにそして繰り返し離婚することになります。
島亨(編集部) そのばあいに、女の児が生まれたとして、子供を産むという衝動というのはわりあい純粋なものとして存続するというふうにおもわれますか?
吉本 そうだとおもいます。つまり、なんらそこにいやだと思うこともないし、必然的に産むことになりそうにおもいます。
島亨 まず産みたくなないなどとはおもわない?
吉本 たぶん、反対だとおもいます。すると「欠如」とか「飢え」とは何なのか、少なくともいまある社会の進展の方向は物質的な飢えとか食糧的な飢えだけはだんだん解決する方向にいきます。精神的な飢えは並行してなくなっていかないのが、ヨーロッパやアメリカの現状で、日本もだんだんそうなる気がするんです。
島亨 そうしますと、理想的なばあいには「性」と「食」とか、「食」と「養」とかいうものも、わりあいバランスが取れているということ、自然的な形で出てくる感じになる・・・・・・。
吉本 そうおもいます。つまり、他の生物のように「性」は「性」、「食」は「食」で、季節だとか周期ではなくて、全部が恒常化されたところの「食」と「性」という感じです。理想的ならば、そうなるような気がします。
島亨 乳胎児期という問題が基本で、その人の生きる状態というものを規定しているというのですね。
吉本 僕はそう理解しています。でもあてになりませんね。それに決定論にまでいかなくても宿命論になってきますね。そうすると宿命が物質的条件によってつくられるのでなくて、産む者と産まれるものとの関係で作られることに帰着します。
(『ハイ・エディプス論』P26-P28吉本隆明 1990年10月)
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
ここでの吉本さんの判断・考えはどこから来ているのだろうか。ひとつはもちろん、「心的現象論」などの人間的な考察を積み重ねてきた地平・場所からである。もう一つは、自分も家族の中の子どもとしての体験と新たな家族の中の父親としての体験との実感から来ているように思われる。それは一般の家族論とは違っていて、ある唐突感をわたしたちに与える。しかし、その言葉は人や家族の深みから浚(さら)ってきているなあという感触がする。
ずっと前に、吉本さんがインタビューのどこかで、母親によって充たされた育ち方をした人は結婚しないのではないか、という言葉に出会ったことがある。その時は、ふうーん、よくわからないなと思ったが、その言葉も上と同様の地平・場所からやって来ているように思われる。
②の「充たされた乳胎児期を理想的に一〇〇パーセント過ごして、しかも母親の環境、母親の母親の環境、三代くらいみんな理想的だったと仮定して、その乳児がおおきくなって男女ともにそうだったとしたら」ということは、人が閉ざされた家族や小社会にのみ生きることができるならわずかな可能性は考えられるが、人は現在では特に社会との関わりの中で生きるほかないから、そのことは不可能なことのように思われる。ということは、理想の社会の有り様が十分に開花するのはまだまだ遠い果てのように思われることと対応している。
一般の社会学的な家族論を表層論とすれば、吉本さんのこの家族に対する考え方は、わたしたちが今までほとんど出会ったことがない、家族の深層論に当たっている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 679 |
心とは何か |
「心について」 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
1994.9.11 |
講演 A164 「心について}
講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号、これは以下の『吉本隆明資料集130』に収められている。
※今回の講演の対応部分は、『吉本隆明資料集130』 P100~102
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| ぼくは長い間、自分で心という言葉を使っていながら、ほんとうは自分でもよくわからないで漠然と使っていました。 |
三木成夫との出会い |
感覚作用も心の作用も相互に関わり合っている |
主なる働きとしては心というのは、内臓の動きに関連して出てくる精神の働きを言う |
項目
1 |
①
1 心の働きは内臓の働き(引用者註.これは「講演のテキスト」の小見出しです。『吉本隆明資料集130』に掲載されている文章の方にはありません。)
今日は心についてという演題であるわけです。心というのは何かということから、申し上げたいわけです。言葉使いの問題であって、内容の問題ではないじゃないかというふうにも思えるわけですけれど、類似のことをたとえば、心という言葉と精神という言葉と意識という言葉と、指している内容が何が違うんだということになってくると曖昧になってくるから、心と言わなくても精神と言っても同じじゃないか、意識と言っても同じじゃないかというふうに思える箇所もあるわけです。
いくらかそこいらへんが危なっかしいところです。それは言葉使いの問題だけだよと言えちゃうところがほんの少しだけあるように思います。ですから心とはどういうことなんだということを無条件にそこからはじめちゃうことができるかどうかと言ったら、ちょっとだけ疑問が残るんですけれども、ぼくは長い間、自分で心という言葉を使っていながら、ほんとうは自分でもよくわからないで漠然と使っていました。漠然と、ということはそれでいいんじゃないか、あまり厳密でなくていいんじゃないか、厳密にすることは無理じゃないか――意識、精神と心とどこが違うんだと言われると、それは言葉使いだけの問題だということがあるから、曖昧でいいんじゃないかということで心という言葉を使っていました。
②
しかし、実は一昨年くらいに、三木成夫さんの著書を読んで、はじめて心というのは何かということを、いくらか定義することができると思えてきたわけです。それで少し自分でもわかってきたな、というところがあるわけです。
ひとくちに言っちゃいますと、人間の肉体とそこから出てくるさまざまな情念とか感情という問題の間には、大別しましてふたつの区別ができると思います。ひとつは感覚です。感覚というのは目で見てこう感じたということとか、耳で聞いて快かったというような、感覚の働きというのがひとつ明瞭に区別できるものがあるわけです。
ところが感覚の働きというのは、誰でもわかるように目とか耳とか鼻とか触るとか、明らかに感覚器官というものを元にして、いろんなことや快・不快を感じるということが、感覚作用だということははっきりと言えちゃうことになります。するとその感覚作用のなかに心というのはあるか、ということになるわけです。もちろん心というのはそのなかに介入してくるわけです。つまり、感覚的に気持ちのいいものを目にしたために、気持ちがいいなと思ったり、情念がすっきりしてきたりということがあるから、心が介入してくるわけです。
そうするとそこでまた曖昧になってきそうに思うんですけれども、それは感覚的な作用のなかに心の作用が紛れ込んでいくと言いましょうか、混合、融合していくという意味あいで心が介入するわけで、心本来の作用ということとは違うわけで、感覚作用ははっきりと人間の五感ということから受けた反応というもので感じるさまざまな心の動きと言いますか、情念の動き、感情の動きというのが感覚作用であるわけです。
心とは何かということを同じような言い方をしますと、いちばんいい言い方は、内臓の動き、内臓の働きとの関係を主な働きとして起こってくるものが、心の働きだと考えればいいことになります。
そのことはぼくには長い間わからなくて、感覚作用も心の作用というものが入ってくるし、心の作用と言ったってそのなかに感覚の作用が紛れ込んできてということがあるから、どういうふうに区別したらいいのかということを曖昧なまま使っていましたけれど、三木さんという人の本を読みますと、これは明瞭に言えちゃうんだと思いました。
心の作用というのはそういう意味あいで言えば五感とかいうことではなく、内臓の働きに関連するさまざまな情念、情緒の揺れ動きとか、感覚作用のなかでも、感覚作用が入ってきてもいいんですけれども、要するに内臓の働き方によって起こってくる心の作用――そういうとまたあれになっちゃいますけど、そういう人間の情念の動きというものを、心、あるいは心の作用と言えば、明瞭に区別できることになります。
実際問題としてはどちらかが主体になって、感覚作用からの働きが入ってきたりとか、感覚作用のなかに心の働きが入ってきたりというのが、実際われわれが日常体験していることは大なり小なりそうなんですけれど、厳密に言えば、内臓の働きあるいは動きというものに関連して起こってくる人間の情念みたいなものの動きみたいなものが、心というふうに言えばいいということは明瞭に言い切れちゃうように思います。
そういうことをぼくは数年前にはじめてわかって自分なりに納得して、その前は曖昧に使っていました。感覚作用と心の作用というのは、ごったまぜになって出てきますから、どこが違うんだ。だったら言葉としては曖昧に使っていいんじゃないかということで曖昧に使ってきましたけれど、だいたいそこいらへんで、主なる働きとしては心というのは内臓の働きに関連する動きを心と言っている。あるいは内臓の動きに関連して出てくる精神の働きを心と言うとすれば、非常に明瞭なんじゃないかと思えてきました。
(講演 A164 「心について」 「講演のテキスト」より)
|
備
考
|
(備 考)
この講演を文章化し、たぶん吉本さんの手が入っている『吉本隆明資料集130』所収の文章「心について(上)」の出だしは、
心とはなにかについて、近年かんがえてきたことから入っていきたいとおもいます。
とある。心についての吉本さんの考えが、近年に三木成夫の著作の影響下に変化したことが語られている。
②の、五感による感覚作用も心の作用も分離しがたく相互に関わり合っているということは、言葉の自己表出と指示表出の問題と対応している。吉本さんは、三木成夫の著作との出会いから自己表出と指示表出をそれぞれ内臓感覚と五感による感覚とに対応させ、感覚作用も心の作用も分離しがたく相互に関わり合っているのと同様に、言葉も自己表出と指示表出の織物だと捉えるようになる。
ところで、、『心的現象論序説』(1971年)では心はどう捉えられているか。
『心的現象論序説』(北洋社 1971年9月)の「Ⅰ 心的世界の叙述」では心について次のように述べられている。
わたしはここで〈心的〉という言葉がなにを意味するかをはっきりさせておきたい。
ここでいう〈心的〉という概念が〈意識〉にたいしてもっている位相は、あたかも〈思想〉という概念が〈理念〉にたいしてもっている位相のようなものである。〈思想〉という言葉が包括するものは、確定した抽象的な層まで抽出すると〈理念〉にまで結晶しうるが、また日常の生活の水準では、たとえば魚屋が魚をよりおおい儲けで販るにはどうすればよいかというようなことをかんがえたすえ、体験的に蓄積した判断のひろがりのようなものをもふくんでいる。それは、いわば魚屋の内部で〈思想〉を形成する。おなじように、わたしが〈心的〉というとき上層では〈意識〉そのものを意味するが、下層では情動やまつわりつく心的雰囲気をもふくんでいる。
もちろん、ここで心的な現象のもんだいを解こうとしているわたしにとって、〈心的〉とはなにかを定義することは、そのまま心的な現象を解明するという目的ときり離すことができない。定義することは、終りまでたどることである。心的現象を解明する過程において〈心的〉とはなにを意味するかが、どこまでも明晰にとらえられなければならないはずである。さしあたって、〈心的〉という概念は、けっして〈意識〉そのものを意味するものではないことを、はっきりさせておけばいいとかんがえる。
(同書 P10-P11)
この部分から抽出すると、「〈心的〉という概念は、けっして〈意識〉そのものを意味するものではないこと」「わたしが〈心的〉というとき上層では〈意識〉そのものを意味するが、下層では情動やまつわりつく心的雰囲気をもふくんでいる。」ということになる。三木成夫の著作との出会いの後のように、心がまだ構造としてはっきりした姿を現しているわけではないが、実感的なものを踏まえた把握になっていて、誤謬は避けられている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 680 |
心の病とはどういうことか |
「心について」 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
1994.9.11 |
講演 A164 「心について}
講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号、これは以下の『吉本隆明資料集130』に収められている。
※今回の講演の対応部分は、『吉本隆明資料集130』 P110~113
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人間の心の働きと感覚の働きの範囲というのはかなり広い範囲に渡っている |
人間が精神の病、心の病と言っているのは何を指して言っているのか |
人間の精神、意識の働き方の世界の可能性 |
病気だと言われている状態というのは、現在の日常生活にとっては非常に不自由な状態 |
項目
1 |
①
8 心の病とはどういうことか(引用者註.これは「講演のテキスト」の小見出しです。)
それからもちろん、人間の意識と無意識、夢と現実というものの中間にある人間の精神の状態を主体に考えれば、これは一種の白日夢の夢――起きながら夢を見ているみたいに意識がぼんやりしている状態なんだという言い方ももちろんできるわけです。
これはいろんなあれがあります。柳田国男という民俗学者がいますけれど、子どものときボンヤリしちゃって、隣の家の庭にある祠を開けてみたら石があった。そして空を見上げたら真っ昼間だけど星が見えた。自分でもこんな意識の状態でいると自分は頭がおかしくなっちゃうに違いないと思ってそれを逃れるわけです。そういう体験を柳田国男は書いています。
こういう体験というのは誰にでも大なり小なりあるんじゃないかという気がします。ぼくも子どものとき昼間の星というのを見たことがあるように思っています。子どもの時はしばしば、ぼんやりしたそういう状態になることがありうると思うわけです。その場合には夢と現実とのちょうど中間のところにいるわけです。それからまた逆に夜寝てから見る夢で、非常にリアルで現実的な夢を見ることがあるわけですけれど、それはやっぱり白日夢の状態が夢のなかで再現されてくるというのがいちばん典型的な夢になってきます。
そうするとヒステリー症における多重人格というのは、言ってみればさまざまな人格に自分が転換しちゃうと考えると、病気には違いないんですけれど、人間というのは意識と無意識のあいだで、あるいは昼間の現実感覚と夜眠ってからあとの夢の感覚とのあいだで、両方がまじりあったさまざまな状態を人間はとりうるんだよという理解の仕方をすればちっとも病気じゃないよということになると思います。
つまり人間の心の働きと感覚の働きの範囲というのはかなり広い範囲に渡っているので、人間はもしそういう状態になる契機があれば、どのような精神の状態――現実感覚と夢の感覚のあいだのどんな感覚もとりうるし、醒めているときの感覚と眠っているときの感覚のあいだのどんな感覚もとれると理解することもできるわけです。
そういうふうに人間の意識あるいは心の世界というものの大きさを最大限大きく見積もって考えれば、ヒステリー症というものもちっとも病気だとか異常だとかいうことにならなくて、ごく当たり前のことだということになりますし、さまざまな人格に転換しちゃうということがありうるということも別段病気じゃないと言えば言えてしまうところがあります。
②
そうすると、そうなってくると非常に難しくなってきて、人間が精神の病、心の病と言っているのは何を指して言っているのかということになるわけです。そうすると少なくとも現在のところで言えば、これこれの理由だからこれは病なんだということは、現在のところはできないわけです。さまざまな人間の心のとりうる世界のひとつの状態なんだと言うより仕方がないと思います。いちばん広く人間の精神の働きをとると、そうとれてしまいます。そういうようにとりますと、人間の種と言いますか類と言いますか、そういうものとしては、大昔から現在までちっとも変わっていなくて、変わっていない意識の世界、心の世界をある場面のある場所を時代時代でもってとっている、その違いだけが時代の違いだということになってしまうと思います。
もっと変なことを言えば、科学というのは、バーチャルリアリズムと言って、科学的な装置を身につけると、自分がまったく違う世界のなかに入れて、そのなかで自分が触ったり見たりしているのと同じ感覚を体験できる装置というのができるようになっています。そういうことは、最新の科学的な装置だという言い方もできますけれど、逆な言い方をすると、大昔から人間が体験していることの体験のある部分を科学的装置でもってつくることができるようになったという言い方もできるんです。そうすると、人間の科学ができることというのは、人間の可能性の範囲を出、可能性以上のことをできるわけではないということになります。もともと出来ることを、ある装置を使ってできるというのが科学技術なんだという言い方ももちろんできるわけです。
つまりそういう人間の意識の世界というのは一点に凝縮してしまって、この状態で精神を集中しますとそのときは大昔から植物神経で動いている内臓器官が不規則な動き方になってしまう。そこで精神だけは集中できるということになっていいくわけですけれども、それは意識の世界の取り方だということになります。
最大限広くとるのと、最小限、一点に集中してそれが人間の意識だととるのと、取り方によって違ってきちゃうわけです。一点にとるという取り方を非常に鋭くやると、植物神経で動いている内臓器官の働きと矛盾してきまして、ある意味でそれを制限しないと意識の集中ができないということが起こりうるわけです。そういうふうに考えると、人間の意識の世界は極少から極大まで、世界としては広くも一点にもとりうるということになっていくと思います。
そういうふうになっていきますと、人間の世界というのも、これは異常だとか病気だとか言っているのは何なのかと言ったら、要するに病気だと思っているか病気なんだという言い方も出来ちゃうことになります。病気なんてもともとない、人間の精神、意識の働き方の世界の可能性のなかのあるところに偏った意識の偏り方の場所を占めているのが病気だと言ってみたり、異常だと言ってみたに過ぎないんだよということになっちゃうと思います。それだけのことになっちゃうことのように思います。精神の働きの世界に新しいことは何もないですよと言っちゃうと言えちゃうところがあります。だから一点に集中するか、非常に大きな世界としてそれを設定するかということによって、病気であるかないかという言い方も決まって来ちゃうから、なかなか決められないなということになります。
ただ、要するに病気だと言われている状態というのは、現在の日常生活にとっては非常に不自由な状態に違いないということになります。現在ではなく大昔の日常生活にはちっとも不自由ではなかったかもしれないのです。けれども現在の生活にとって不自由な精神の働きをすると、やはりしばしばお医者さんみたいな人あるいは傍の人から見るとあれは異常だとかあれは病気……
【テープ反転】
……そういう気持ちの働き方で、そういう行動をすると、不自由で、日常生活が不自由になっちゃうだろうなということだと思います。そうすると、不自由でないところまでもっていけば、それで治った治ったということになっちゃうと思います。そういう問題だと理解できるわけです。
※①と②は、ひとつながりの文章です。
(講演 A164 「心について」 「講演のテキスト」より)
|
備
考
|
(備 考)
日常的な実感から言えば、病とは人と人が関係する世界の方からやって来るように見える。
大体話は分かると思われるが、②の、末尾の【テープ反転】部分の前後二三行を、『吉本隆明資料集130』に収められている「心について(上)」から引用する。
現在ではなくておおむかしの日常生活にはちっとも不自由ではなかったかもしれないんですが、現在の生活にとって不自由な精神の働きかたをすると、しばしばお医者さんが、あれは異常だとかあれは病気だと指定します。それじゃ、不自由じゃないところまでもっていけば、それでもうなおったということになるとおもいます。
〈母の物語〉によって深く刻まれた個の性格みたいなものは、運命的な決定論ではなく、人が理想の状態を追い求めるようにいくらかの可変性を持つものだ、それが人が生きていくということだ、というように吉本さんは捉えていたと記憶する。しかし、以下の人間の種とか類としてその本性を捉えたばあいには決定論のように感じられる。よって、下の二項は自分の中で保留としておきたい。つまり、考え続ける課題としたい。
そういうようにとりますと、人間の種と言いますか類と言いますか、そういうものとしては、大昔から現在までちっとも変わっていなくて、変わっていない意識の世界、心の世界をある場面のある場所を時代時代でもってとっている、その違いだけが時代の違いだということになってしまうと思います。
逆な言い方をすると、大昔から人間が体験していることの体験のある部分を科学的装置でもってつくることができるようになったという言い方もできるんです。そうすると、人間の科学ができることというのは、人間の可能性の範囲を出、可能性以上のことをできるわけではないということになります。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 681 |
心の病が治るとはどういうことか |
「心について」 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
1994.9.11 |
講演 A164 「心について」
講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号、これは以下の『吉本隆明資料集130』に収められている。
※今回の講演の対応部分は、『吉本隆明資料集130』 P115~116
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 現在の段階で、自覚的になるということは治ったことと同じ |
|
|
|
項目
1 |
10 心の病が治るとはどういうことか(引用者註.これは「講演のテキスト」の小見出しです。)
そうすると治ったということはどういうことかと言ったら、その人の自閉症的な素質が治ったということではなく、素質はあるんだけどふつうの人との連絡がとれるようになった。どうしてかというと、ふつうの人はこういうときにはこういう振る舞いをするもんだということがわかってきた。自分でもどこが自分と違うかということがわかってきた、そういうことに自覚的になってきたら治ったということになるんだ。
それはその通りで、自覚的になるということは治ったことと同じです。きついことが残っているとすれば、その人だけに残っているわけです。自分が少し我慢して、抵抗感があるけれども、こういうときはこう言えばいい、こうすればいい、ということができるようになったというと、治ったということと同じことになります。現在の段階で、心の病ということが治るということはどういうことかというと、いまの段階だったら、自覚的にその病だという状態がわかってきたということになって、ああ人はこう思うんだ、自分も少し抵抗があるけれどそういうふうに振る舞おうとなったときに、治ったと言えると思います。治ってないかもしれないけれど、治ってないのは自分で抵抗感があるのを我慢すればいいということになります。
つまり現在のところ、心の病とか異常というのが、そのことに対して自分が自覚的になって通路ができたといいましょうか、一般に正常だと言われている人に対して、通ずるようになったというときに、治ったと言えると思います。ですから自閉症も同じで、器質の病であるかどうかを決定するのは大変なんです。そんなことを決定するほど現代の医学は発達していないですからいまのところわかりません。
もしかすると一個の細胞が違うだけだとかいうことになるのかもしれません。それは医学がもっと発達すればわかるようになるかもしれませんし、存外器質の病だということが確定できるようになるかもしれませんけれど、いまの段階でそういうことは無理、嘘だと思います。そういうふうに言っている人もいるかもしれませんけれど、定説ではありません。
それからもちろん、育て方がマザコンだからというけれど、そんなことはないですよ。
(講演 A164 「心について」 「講演のテキスト」より)
|
備
考
|
(備 考)
前回の項目680の引用の末尾にも「心の病が治るとはどういうことか」について触れてあった。
(日常生活が)不自由でないところまでもっていけば、それで治った治ったということになっちゃうと思います。
項目678「自閉症をどう捉えるか」でもこの引用部分とかぶる文章を取り上げている。しかし、それは「心について」(上) (『吉本隆明資料集 130』猫々堂
)からのものであり、こちらはそのもとになっている講演「心について」の講演のテキストからの引用である。心シリーズの一連としてこの項目を取り上げている。
この「心の病が治ること」は、身体的な病の治るについても同様のこととして言えるかもしれない。つまり、未来はわからないけれど現在の段階では、身体の臓器や身体部分の病は、完全回復とまでいわなくてもそれが今までのような普通の生活をしていく上でさほど支障が無い程度に回復できれば病気は治ったと言えるのではないかと思う。
|
講演 A164 「心について」
講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号、これは以下の『吉本隆明資料集130』に収められている。
※今回の講演の対応部分は、『吉本隆明資料集130』 P116~117
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 一才未満の育て方と、胎内にいたときの環境は、決定的なものです |
そこは決定論に近い片道決定論 |
人間の精神は宿命を超えていこうとします |
|
項目
1 |
①
11 何が心のあり方を決定するか――生きることの片道決定論(引用者註.これは「講演のテキスト」の小見出しです。)
人間の心のあり方というものを決定する要因というのはふたつあって、ひとつはいま言いましたように体内にいるときと、一才未満のときです。このときの母親との関係、授乳する人との関係、世話してもらえなきゃ生きていけない段階のときの他者との関係がうまくいっているかどうかということと、思春期の入り口にフロイト流に言えば広い意味でのリビドーの異常体験があったかどうかということが少し決定します。しかし大部分は一才未満のときに決定します。あるいは体内のときに決定します。それは人間の心の世界というものを決定的に運命づけます。
それ以外の育て方で変わるというのは、京都精華大学の教授だったのが東京大学の教授になったくらいの変わり方しか作用はありません(笑)。生まれる前の一年と生まれてからの一年、これはどうしようもないです。つまりもちろん親の責任だと言えば親の責任だけど、親に言わせりゃそんな責任も何もない。亭主と盛んに喧嘩していてそれどころじゃないと思っていたり、経済的に苦しくて子ども育てるどころじゃないのに育てているとか、そうだったんだからしょうがないじゃないか、おれの責任じゃないと言われればその通りで、母親の責任でもなんでもありません。けれども一才未満のときと胎児のとき、うまくいっていれば文句なしということになると思います。それじゃそういう人はかならず心の働きがおかしくなるかといったら、そうは言えないんです。おかしくならない人、わかっちゃう人もいるわけです。ここはおれと違ってたんだ、と我慢しちゃえば治ったと同じです。我慢しちゃえなければ病気になります。
ぼくがそんなことを言うと、自分が知らないうちに自分の心の運命が決まっちゃうのか、すると一種の宿命論、決定論じゃないか、おかしいじゃないかということになりますが、ぼくはそう思います。片道決定論といいます。それくらい決定的なものです。そんなものは、フェミニストが子どもを育てるのが嫌だから自由にしてくれというくらいの論理で破れるものではありません。もっと根源的なものです。ですからそこは決定論に近い片道決定論です。
ですから逆に言いますと、精神が異常だとか病気だと言われる、病院に入っている人の一歳までとか体内にいたときどうだったかということを聞けば、かならずそれは育てた人あるいは母親との関係が必ず異常です。百パーセントそうです。けれどもそういう人は必ずおかしくなっちゃうかとういとそんなことはないんです。どうしてかというと、人間の心の世界というのは可塑性があるというか、それを超えていくという自発性があります。人間の精神は宿命を超えていこうとしますし、自分の能力を超えていこうとしますし、性格を超えていこうとします。そういうのが人間ということです。人間が生きるということはそういうことですから、そういう育て方をしたら必ずおかしくなるかと言ったらそうはならないです。しかし逆に言って、おかしくなったと言われている人は、百パーセントそこが間違っています。
育て方はよかったって悪かったって大したことはないんです。貧乏かとか金持ちかとか、そんなことは大したことないんです。だけれども一才未満の育て方と、胎内にいたときの環境は、決定的なものです。それを人間は超えていかなくちゃ行けないということが、それぞれの人が持っている宿命であるわけです。自分の性格に自己嫌悪を持たない人というのもいるわけで、それがいちばん幸せな人です。しかしある部分だけは誰でも多少は自己嫌悪を持っているわけです。嫌な性格だなおれは、と思っているわけです。それを自分なりに直そうということはいつでもあるわけです。それがその人の含み、陰影をつくるんです
(講演 A164 「心について」 「講演のテキスト」より)
|
備
考
|
(備 考)
この講演は、1994年9月11日。大洋期の〈母の物語〉の考察・解明が『母型論』として刊行されたのが1995年1月である。しかし、その巻末の初出一覧によると、「母型論」から「語母論」までは雑誌『マリ・クレール』(中央公論社)1991年5号~11月号に掲載されている。つまり、この講演は、『母型論』での考察・解明を成した後に行われたものである。
わたしはこの分野のことに詳しくはないが、大洋期の〈母の物語〉が生まれ出る人の「片道決定論」となるという『母型論』での考察・解明は、たぶん吉本さんがいろんな人々の考察の上に築き上げた独創的なものであると思われる。そうして、この「母型論」の考察に限っても、それが開けた風穴は人の持ってしまった生存のもやもやを少しでも吹き払うものとなれるはずである。それはまた、吉本さん自身にとってもそうであったろうと思う。
項目679~項目682は、今回で一連の項目としておしまい。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 684 |
顔とは何か |
「心について」 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
1994.9.11 |
講演 A164 「心について」
講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号、これは以下の『吉本隆明資料集130』に収められている。
※今回の講演の対応部分は、『吉本隆明資料集130』 P104-P105
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 発生史的に言いますと、腸管が外側に捲れたものが顔ということになる。 |
人間がエラ呼吸をする魚だったときの、エラというのが首からうえになっているということが生物発生史的には言えます。 |
|
|
項目
1 |
もう少し三木さんの指摘していることで、ぼくなんかびっくりしたことがあるんですけれど、人間の顔は何かというと、いちばんわかりやすいのは、腸から食道、喉仏まで来ている植物神経系で動いている管があるんですけれど、その管を捲り返して開いたものが人間の顔なんだということが、三木さんの考え方です。発生史的に言いますと、腸管が外側に捲れたものが顔ということになる。この人、今日は身体の調子が悪いらしくて顔の調子が曇っているとか、顔色が悪いというのは、胃か腸のあたりで欠陥があるということを意味するのです。胃や腸のところで欠陥があると顔色が悪くなったり曇ったりするのはなぜかと言えば、顔自身が腸管を捲り返したものだということが、顔の表情に該当すると考えれば非常に考えやすいということから来るという言い方をしています。
概して顔みたいなものは全般的に何が発達してきたものかというと、人間がエラ呼吸をする魚だったときの、エラというのが首からうえになっているということが生物発生史的には言えます。エラの発達したものなんだけど、そのなかでいちばん敏感に発達しているのは三木さんの言い方で言えば舌と唇だと言っています。舌と唇というのが、エラから発達した顔面においていちばん発達しているもので、感覚が良く通っているという言い方をしてします。
ぼくらはそういうことを数年前にはじめて知って、急に世界が広がった感じがして、なんとなくいろんなことがわかったんです。たとえば人間がキスをする――舌と唇を使うわけですけれど、そういうのはなぜなんだろうなということが、三木さんの説明を聞いているとなんとなくわかるような気がしました。つまりたいへんいろんなことを教えられてびっくりしたというのがぼくの感じ方です。解剖学的に言えば顔というのはエラで、形態学的に言えば腸管が捲り返ったものが顔の表情なんだ、という言い方が、生物学的な発達史から言えば正しい言い方だということになってきます。
(講演 A164 「心について」 「講演のテキスト」より)
|
備
考
|
(備 考)
「人間がエラ呼吸をする魚だったときの、エラというのが首からうえになっているということが生物発生史的には言えます。」について。100年ほどの生涯の時間を生きる現在のわたしたちには、「人間がエラ呼吸をする魚だったとき」という言葉はピンとこない。生命の発生から進化を遂げて、魚だったものが陸上に上がり小動物になり、人間へと進化してきたと言われても、それらのことは荒唐無稽なものと感じざるを得ない。その数十億年かに及ぶ時間とは異質な時間をわたしたちが生きているからだ。しかし、いろんな論拠からそれらのことが正しいとして、それらの視線を現在に通過させれば、例えばこの小さな規模の時間の中で、人の美醜を論じたり人に価値序列を設けて区別したりしていることがバカバカしく見えるとということがある。わたしたちの生きている世界やその時間の秩序は、国家というものの介入や社会の組織化があり、現実的な具体性として強固ではあるが、それらの異次元の時間スケールからの視線(超高度からの視線とも言えるか)はわたしたちの現在にひとつの風通しを与えるように思われる。
吉本さんが、別の講演で三木成夫の顔ということを取り上げているのがある。上の講演の2ヶ月後講演である。
A165「顔の文学」 講演日時:1994年11月24日 「吉本隆明183講演」ほぼ日刊イトイ新聞
「講演のテキスト」より
2 脱肛と魚のエラ――三木成夫の考え方
専門的に言うと解剖学者というのか、脳生理学者というのかわかりませんけれど、養老さんの先輩筋に当たる三木成夫さんという人がいまして、僕はものすごく偉い人だと思っています。もう数年前に亡くなりましたけれども、この人は顔というのをどういうふうに規定しているかというと、人間の体の発達史に即して人間の顔とは何なのかということを言おうとしているわけです。つまり、機能の面からではなくて、動物から人間に発達してきたものとしての人間の顔とは何かということを三木さんは言っているわけです。
三木さんの言い方をしますと、人間の顔というのは形から考える考え方をすれば、人間の食道まで通っている腸管がちょうど内側から外側へめくれ返ったものだ。肛門で言えば脱こうというのがあるでしょう。つまり、痔の病気に脱こうというのがある。この脱こうと同じで、要するに脱こうの上のほうに付いているのが人間の顔だというのが三木さんという人の考え方です。腸管の延長線が頭のところに来て、それが開いてしまっているというのが人間の顔だと考えれば大変考えやすいし、発達史的に言いますとそのとおりで、そういうふうに考えると人間の顔の位置付けができると、三木成夫さんという人はそういう説き方をしています。この説き方はとてもおもしろいので僕なんかの好きな説き方です。つまりこれを発生史的な説き方といいます。人間が発達してきて、それで人間にまでなったという言い方が、あるいはもっと、人間の定めだったのだ。定めだったんだけど、だんだん陸に上がってきて哺乳類になって、それで人間になったのだという発達した過程というのがあるわけです。その過程から言いますと、つまり過程からいう考え方というのをこの人はよく非常に綿密に、非常にわかりやすく、しかも非常に一貫した考え方をとっていて、結構腸管が上のほうでめくれているというのが人間の顔だと考えれば妥当だし、一番よいと言っています。
もう一つ解剖学的に言うと、魚にえらというのがあるでしょう、人間の顔というのはえらと同じ、えらが発達したものだと考えると大変考えやすいと三木さんは説明しています。顔ということを、あるいは表情をしている顔全般ということを、筋肉も含めて全般ということを、魚のえらが発達したものだと考えると考えやすいということを言っています。
今言いましたように、腸管の延長線が人間の顔の表情、顔ですから、顔の表情の内臓感覚というのがここにきているということになるわけです。三木さんの説明の仕方をすると、口にとっての舌というのだけは内臓感覚だけではなくて、いわゆる感覚器官的なと言いますか、内臓ではなくて、外臓、外臓というのはおかしいですけれど、外とつながった、つまり感覚器官と同じような感覚が舌と唇には入っていて、そこが一番顔の中で敏感な箇所であるという説明をしています。ですから、人間の舌というのは要するに喉の奥から出ている手だと考えるとものすごく考えやすいのだ、そういうふうに考えると非常にわかりやすいのだということを説いています。僕が知っている範囲では、人間の顔についての二つの説き方というのは、人間の顔の機能と役割と解剖学的な性質について説かれている説き方というので、大別してその二つがあると思います。その二つで大体において、顔についての考え方は全部尽きていると言ってもいいのではないかなと思います。
三木成夫が顔について述べているところを引用しておく。『』()は見つからなかった。そこにも記述があるかもしれない。
1.
【註および文献】
(19)
顔とは、いうなれば腸の筋肉が目鼻をつけて、あたかも脱肛のように、外界に露出したものであり、したがってその表情運動は内臓の反応が白日の下に晒け出されたもの、と見ることが出来る。いまこの表情筋が鰓の筋肉に属する。いいかえれば脊椎動物における、もっとも歴史の古い筋肉であることを思い合わせると、たとえば臨終の際に見られる「鼻翼呼吸」が、まさに古生代の昔の鰓呼吸の、束の間の再現であることを思い知らされるであろう。
(『生命形態の自然誌 Ⅰ 解剖学論集』P174 三木成夫 うぶすな書院)
2.
下等動物にくらべ、高等動物特に脊椎動物では、近くのものから、しだいに遠くのものまで感ずるようになる(遠隔受容)。すなわち、遠方から波及した化学的な変化(におい)や物理的な変化(音や光)にも反応するようになり、遠隔受容器としての嗅覚器・聴覚器、そして視覚器がそなわるようになる。
これらの遠隔受容は、脊椎動物が水中から陸上にその居を移すとともにしだいに発達し、ついに人類では何万光年の宇宙のかなたまで見ることができるようになる。すなわち、動物の分化とともに、かれらのすむ世界はしだいに拡大されるのであるが、これらの受容器(鼻・耳・目)は、すべてからだの前端に集まり、しかも左右対称に配列する。これは、近接受容器特に触覚器が、からだ全体にひろがっていることと対照的である。
このようにしてからだの先端には、動物性器官の入り口ともいうべきこれらの受容器が、植物性器官の文字どおりの入口である〈口〉とともに開口することになる。人々はこの部分を"顔"とよぶのであるが、以上のことから〈顔〉とは、その動物の動物性および植物性両器官の全体を象徴するひとつの形態であることがわかる。
(『ヒトのからだ ― 生物史的考察』P106-P107 三木成夫 うぶすな書院)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 690 |
これからの社会と心 ① |
「心について」 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
1994.9.11 |
講演 A164 「心について」
講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号、これは以下の『吉本隆明資料集130』に収められている。
※今回の講演の対応部分は、『吉本隆明資料集130』 P123-P124
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 一才未満のそれと、胎内における子どもの育て方というのが、その子どもの生涯を決定しますよという理論は動かしようがないと思います。 |
なるようになるというだけでけっこうなことじゃないですか。 |
今後の心の問題として重要な二つのこと |
精神の世界における現在の要求 |
項目
1 |
①
16 これからの社会と心 (引用者註.これは「講演のテキスト」の小見出しです。)
ぼくは必ずしも女性は子どもをちゃんと育てたほうがいいよみたいなことは言わないわけです。代理ができるようになったんだから代理の人がやったらいいじゃないですかというふうに言います。一才未満までだよ、と言うと、女の人は一年間子育てにへばりついていろということなのかと怒られるわけですけれども、そんなことは勝手で、一才未満のそれと、胎内における子どもの育て方というのが、その子どもの生涯を決定しますよという理論は動かしようがないと思います。これは社会的に有利であるか不利であるかということとは関係ないので、動かしようがないと思います。
けれどもそれができなくなっちゃうだろうということは文明の進み方からやむをえないんじゃないかということだと思います。経済的には解放されたけど、男女同性の明晰な区別、曖昧ではあったけれども八十パーセント二十パーセント、九十パーセント十パーセントであったけれども、それがだんだん五十パーセント五十パーセントに近づいていくよということは避け難いんじゃないかとぼくは思っています。
避け難いと困っちゃうという人がいるかもしれませんし、生涯特殊出生率が下がる一方で日本国は衰退するんじゃないかと心配する人もいますけれど、ぼくは政治家でも政局担当者でもありませんから、そんなことはちっとも心配しないので、なるようになるというだけでけっこうなことじゃないですか。解放される人がいっぽうでいて、経済的に食べ物がなくなっちゃうならなくなっちゃっていいじゃないですかとぼくは思っていますけれど、いろんな考え方があると思います。
けれども考え方いかんに関わらず、心の問題としてこれは動かしようがないよという問題もあると思います。これがヒステリー症、人格転換ということと、同性愛というこのふたつのことは、心の問題としてはとても重要なことです(ママ ここで「。」か)多重の人格転換になるというのは、異常だとか病気だという範囲ではなく、器質だという範囲でいえば、社会が複雑になるほど、個々の人間は多重な人間に自分を振り分けないと生活していかれないと段々なるわけです。ですからこの問題はあまり病気にしない、異常ということにしないで、それができるほうがいいに決まっていると思います。職場にいるときと、職場が終わってどこかにふけるやつとはぜんぜん違う人格で済んでれば二重人格くらいで済んでいるわけだけど、そうではなくさまざまな職場での局面で、多重な場所に対応しなきゃいけないということはこれからますます増えていくと思うんです。それに対して病気や異常にならないで適応するというやり方をできるようになったほうがいいに決まっているとぼくは思うんです。それは現代においてとても重要なことのように思いますし、同性愛ということも、自分がそうであるかないかということとは別として、自分の子どもがそうであるかないかという問題はいまよりももっと切実になって、もっと度合いが増えていくだろうと思うわけです。これに対応することがどうできるのか、対応して驚かないしそれでいいんだという考え方と、これはまずいから、私はそういう育て方をしないとか、それも人によって違うけれども、現在とても大きな問題としてそれは存在していきているんじゃないかとぼくは思います。
このふたつは心の世界の問題をとりあげる場合に欠くことができない問題になっていくわけです。それ以外の問題は、古典的な問題でいうと躁病とか鬱病とか、分裂病というのがあります。それはやはり、数としては増えつつあると思います。これからも社会の局面がいろんな意味できつくなると増えていくと思います。しかしそれと同時に、非常に深い鬱病だとか、躁病、分裂病という人は減っていきつつあるんじゃないか。だいたいぜんぶ境界が曖昧になりつつありますし、異常と成城(ママ 「正常」か)との境界も曖昧になっていくかたちで、これからも増えていくだろうということがいえると思います。そういう意味あいでは、古典的な精神の働き方の特徴の区別というのは、だんだん曖昧になっていきつつあるということがいえそうな気がします。
ただ、この境界を超すと正常だしこの境界を超すと異常だということになるから、その境界線に対しては、さまざまな局面で、非常に自覚的で意識的になったというやり方がいいんじゃないかと思います。そういうことを会得することができたらいいんじゃないかと思います。そういうことで昔からの古典的な区別は非常に少なくなると思います。それにかわるものとして、いま言いましたような、大きくいえばヒステリー症に入っちゃう問題――新興宗教における人格変換の問題が増えていくとか、同性愛とかエイズとかの問題が増えていくというかたちで、それに代わるように現在出てきているということになります。その対応性とか柔軟性ということが精神の世界の柔軟性ということになりそうな気がいたします。
(講演 A164 「心について」 「講演のテキスト」より)
|
備
考
|
(備 考)
今後のわたしたちが社会の内でどういう精神的な事態に遭遇するか、その可能態として二つの精神のベクトルとして語られている。
①の第2段落と第3段落の、「けれどもそれができなくなっちゃうだろう・・・・・・いろんな考え方があると思います。」の部分は、『吉本隆明資料集 130』の「心について(下)」(P122-P123)では次のように簡潔に加筆訂正されている。
でも、それができなくなってしまうだろうという運命のすすみかたも、またやむをえないのではないかとおもいます。男女両性の区別というのはひじょうにあいまいになっていくということは、避けがたいんではないかとぼくはおもっています。
また、上記の引用文の末尾「その対応性とか柔軟性ということが精神の世界の柔軟性ということになりそうな気がいたします。」は、次のようになっている。
それに対応する方法、多様性とか柔軟性というのが精神の世界における現在の要求ということになりそうな気がいたします。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 691 |
これからの社会と心 ② |
「心について」 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
1994.9.11 |
講演 A164 「心について」
講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号、これは以下の『吉本隆明資料集130』に収められている。
※今回の講演の対応部分は、『吉本隆明資料集130』 P124-P125
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人間には可塑性がありますから |
人間はそれに適応する以上にそれを積極的に乗り越えていく。 |
乗り越えられないところは、誰がなんと言おうと休みをつくっちゃって、憩いながら元気を出してまた行く以外にないんです。 |
|
項目
1 |
①
17 いかに休むかという課題 (註.これは、「講演のテキスト」の小見出しです)
そのためには、今の段階では休みというか憩いというのは、自分でつくるより仕方がないように出来ているんですよ。職場の言う通りにしていると、有給休暇はなかなかとれないということになるんですね。そこは自分なりの工夫で憩いというのをとっちゃうこと以外に、憩いでもって防ぐことはなかなかできないと思います。それは自分で憩いをつくって防いじゃうという防ぎ方はとてもいいことのように思います。あまり言うこときかないほうがいいと思います。
とにかくきついことばかりが出てくるわけです。そしてぼくの理解の仕方では、そういうことが楽になるということはありえないと思っています。つまり都会はなくて田舎ばっかりになっちゃえばいいし、燃料は牛の糞を使うのが理想的だと言われると、理想的かもしれないけどそうはなりません、逆にしかならないですよということだと思います。人間というのはその逆にしかならないものにどうやって対応できるかという課題はどこかで強いられる。するとどこかで休んでよしやろうじゃないのといく以外にぼくはないと思っています。それはまた人間には可塑性がありますから、環境は乗り越えることができるさ、環境が複雑になったら人間がへばったということはありえないのよ。環境というのは、いま言いました心の病に対してもいい面と悪い面とあって、昔だったら食うものに困って、一才未満の乳児にしょっちゅう怒っているけれど、子育ては一生懸命やる母親が全世界ですから、そういうふうに育った子どもというのは全世界がいつだって面白くないことで満ち満ちているという育てられ方になっちゃうから、それを変えるというのはものすごく難しくなっちゃうんです。いい面も悪い面もあるというのは、いい母親に育てられたら、あとはなんの心配もいらないという育ち方になりますけど、悪ければそれが全世界になっちゃいます。食うに困ることはないし、自分で育てなくても職業の人に育てられるとなると、いい面も悪い面もあるわけです。すると、みな同じになっちゃうよ、性の意識としても同じに近くなっちゃうよ、そしてそれを弱点と見るなら弱点もたくさん出てくるわけです。
しかしそれは仕方がなくて、それを乗り越えていかなきゃ人間は仕方がなくて、ここで止りということにはぼくはないと思います。人間はそれに適応する以上にそれを積極的に乗り越えていく。乗り越えられないところは、誰がなんと言おうと休みをつくっちゃって、憩いながら元気を出してまた行く以外にないんです。それ以外のエコロジストが言うような解決法があるというのはぼくは絶対信じていないんです。やはりそれを乗り越えていくとい(ママ これは「いう」か)解決法しかないとぼくは思います。
その心の世界のいちばん大きい問題は、ふたつの問題にだいたい帰着するんじゃないかと思います。そこの問題がうまく出来ていけば、たぶん現在、あるいはこれから以降起こってくる問題についてはかなりな程度の適応性というのが可能になるんじゃないか、あるいは自分の時代は別としても、自分の次の世代には適応というのを考えることができるんじゃないのかとぼくには思われるわけです。
精神の世界を、精神の世界それ自体として取り出すということを厳密にしてとりだすというのもいいんですけれども、意識のありようというのは動物的な性(ママ これは「生」か)からどういうふうに代わっていくかということを言ってみればいいわけですけれども、それよりもそれが現在において何に当面しているかということのほうが、喋るのにいくぶんかでも参考になるのではないかと思ってそういう話にしてみました。これでいちおう終わらせていただきます。
(講演 A164 「心について」 「講演のテキスト」より)
|
備
考
|
(備 考)
テーマとしては、人間の現在的な困難な課題のとともに、人間の本質である可塑性―困難な状況への適応や乗り越えていくこと―がもうひとつのテーマになっているように思える。
引用の一段落目の「憩いでもって防ぐことはなかなかできないと思います。」という部分が、前後のつながりとして疑問に思われたので、その部分の講演を二三度聴いてみた。スロー再生できればわかるかもしれないが、吉本さんの早口もありよく聴き取れなかった。しかし、当然のことかもしれないが、「つまり」などの吉本さんの語る言葉がこの「講演のテキスト」の制作者によって少し切り整えられていることがわかった。ちなみに、この講演を文章化し、たぶん吉本さんの手が入っている『吉本隆明資料集130』所収の文章「心について(下)」では、この引用の一段落目は次のような簡潔な表現になっている。最初の一文のみであるが、まとまりとして取り出すと、
このためにいまの段階では、休みとか、憩いは自分でつくるよりしかたがないようにできています。(ひじょうにきついことばかりが出てきますが、ぼくの理解のしかたでは、そういうことがらくになることはこれからもないとおもっています。人間には可塑性がありますから、処理はできます。環境が複雑になったら人間がへばったっていうことはありえないので、あくまでものり越えていきます。そうすると、環境というのは、いまいいましたように、心の病にたいしてもいい面と悪い面をもっています。)
また、上の講演のテキストの最後の段落「精神の世界を、・・・・・・これでいちおう終わらせていただきます。」は、『吉本隆明資料集130』所収の文章「心について(下)」では、次のように手直しされている。
明日食べるものに追われるような貧困は、心の問題を集約される主題として、ある意味ではいい作用を人間の心に果たしてきたという言い方も成り立ちます。その意味の貧困が払底してしまった現在の先進社会では、心は集約される主題を喪失して、いたるところで過多な多様な反応にさらされて、方位と比重を測れなくなっていると言うことができましょう。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 699 |
近代日本の後進性の表れ ① |
第2章 男と女の足下にある泥沼
第3章 三角関係という恋愛のかたち |
語り |
『超恋愛論』 |
大和書房 |
2004.9.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 男の本音は、今でも明治時代とそんなに変わっていないんです。 |
だから、男女がお互い自分を殺さなくてすむ生活というのがまだまだ実現しないというのは、男女両方の問題なんですね。 |
社会に後進性の名残があるために、個人の力ではどうしようもないという部分が男女関係においても確実にある |
この「言えない」というところに、日本の後進性の一つがあらわれているとぼくは思います。 |
項目
1 |
①
智恵子と光太郎が目指したような生活は、現代の日本でもまず挫折に終わるでしょう。
理想の結婚生活、つまり、自由な意思で選び合った男女が、ともに自己実現をあきらめずに愛情を持って添い遂げるということは、今でもなかなかできない。その背後には、社会の後進性の名残というものがあるとぼくは思います。
後進性というのは、ひとつには日が暮れたら女の人がご飯を作らなければならないとか、そういうことです。
今では男のほうもそれほどとんでもないことを言う奴は少ないし、後進性といってもあくまでも"名残"なんだからたいしたことはない、と思ってしまいがちですが、それは違います。伝統の深みというのは怖いです。泥沼にはまったようになってしまう。
自己実現をしたいとか、多少なりとも自由に生きたいとか、そう考えている女の人にとって、一人の男と生活を共にするというのは、いまだにかなり大変なことです。
男の本音は、今でも明治時代とそんなに変わっていないんです。
たとえば夏目漱石は、自分の小説の中で、おとなしくて、男に対して献身的で、ひとつも逆らわずにどこまでもついてきてくれるような女性を理想の女性像として描いています。
②
ほとんどの男の本音は、漱石と同じでしょう。毎日が楽だという観点から言うと、そうなります。
知識とか教養があって、対等に何でも語り合えるというのは二番手でいいから、自分がこうやろうと思ったら、それをよくわかってついてきてくれる人と暮らすほうが、生活の中における幸福感は多いと、ほとんどの男が考えているのではないでしょうか。
ぼく自身にしても、わりに本音で何でも言ってしまうので、どこへ行っても喧嘩ばかりになってしまって、楽しいのは寝ているときと、それから家で平穏無事なおしゃべりをしているときだということになる。
奥さんというのは、自分を批判せずに受け入れてくれて、家の中にいつも何となくほんわかした雰囲気があればそれでいいや、という気持ちが正直言ってあります。
でも女性から見たら、そんなのは男の勝手な考えで、女が男の言うことをハイハイと聞いて、自分の意見はひとつも言わずにニコニコしている、なんていうのは、男女関係のあり方の中でもっともくだらない形に思えるでしょう。そう言われてしまえば、それを認めざるを得ません。
古い男女関係というか夫婦関係というか、そういうものが一〇〇パーセント駄目かと言うとそうでもなくて、いいところも少しはあるぜ、というのも確かなんですが、男のほうがそればかりを求めるのは、やはり間違っていると言わざるを得ません。
透谷も独歩も光太郎も、モダンなことを言ってる奴はみんな挫折したじゃないか、と言いたい男たちもいるわけですが、だからといって漱石のような女性観がいいのかというと、もちろんそうではないはずです。
(『超恋愛論』P60-P63 吉本隆明 大和書房 2004.9.15)
※①と②は、ひとつながりの文章です。
③
でも女の人のほうも、封建時代の家父長制みたいなことを言う男は論外でしょうけれども、なんだかんだ言って男にリーダーシップを求めている部分はあると思います。
どんなに独立心に富んでいて、能力もあって、何から何まで自分でできる人でも、いざというときとか、相当きつい局面になったときなどは、男のほうがちょっとだけ先に筋道を通してくれないかな、と思っている面があるのではないでしょうか。自分のほうには責任がちょっと少ないというくらいがちょうどいい、というような感覚です。
だから、男女がお互い自分を殺さなくてすむ生活というのがまだまだ実現しないというのは、男女両方の問題なんですね。
そういう文化の中で育ってきてしまっているわけですから、少しずつ修正していくよりほかないわけです。
男も女も、理想の男女関係が築けないのはその人個人のせいだというなら、「あなたのここがいけない」「きみのここがおかしい」ということで、心がけや努力で何とかなるんでしょうが、なかなかそうはいきません。
やはり、社会に後進性の名残があるために、個人の力ではどうしようもないという部分が男女関係においても確実にあると思います。
これが西洋ならば、恋愛というのは個人と個人の精神の問題で、日が暮れたらどっちが飯の支度をするとかいうようなことは、何ら本質的ではない、ばかばかしいことだということになるんでしょう。
しかし、ぼくはこうした問題を抜きにしては恋愛について語れないと、はっきりそう思っているんです。
(『同上』P65-P67 )
④
ここで三角関係について述べてみようと思うのは、それが、日本の社会が後進性を残したままで、先進国を目指して発展していくときに、必然的にあらわれてくる恋愛の形態の一つではないかと思うからです。
日本の社会の後進性の名残のようなものが、現在の男女の恋愛に影を落としているということを、ここで述べてみたいのです。
いちおう、今の日本は先進国ということになっているわけですが、後進国だった日本が先進国の後を追いかけて、近代化を急速に推し進めていった時代がありました。
透谷や独歩、光太郎といった人たちの挫折の後にくる、日本的な恋愛の典型的な形態は三角関係である、というのがぼくの考えです。
(『同上』P102-P103 )
(引用者註.西欧の小説と比べて)漱石が書くとそうはならない。三者三様にぎりぎりのところに追い詰められて、みんなが自滅するか、一人があとの二人の目の前から消え去るよりほかない、ということになりましょう。
それはなぜなのか。
ぼくは、日本の後進性、つまり、社会が近代化されていないことと、個人の近代的自我が形成されていないことのあらわれであると見ます。
西欧の個人主義を目指してはいたけれども、日本における個人主義は、実は西欧とはまるで違うものだった、ということです。
このことを小説の中で描いた漱石は、近代日本の恋愛関係のあり方を鋭く洞察して、それを文学の問題として引き受けていたといえます。
(『同上』P110 )
⑤
もし、宗助がお米に「安井が帰ってきているよ、大家のところに来るらしいよ」とさらりと言えるような闊達な性格だったなら、去っていった親友と二度と顔を合わせられなくなるような重たい三角関係になど、はじめからならなかったでしょう。
『こころ』の先生にしてもそうです。
Kという親友に、下宿の娘さんを好きだということを打ち明けられたときに、「じつはおれも好きなんだ」
と言ってしまえば、のちのちに禍根を残す葛藤だの煩悶だのは起こらない。
しかし、そこで自分の気持ちを言えないわけです。・・・中略・・・
この「言えない」というところに、日本の後進性の一つがあらわれているとぼくは思います。
なぜ言えないのか。それは、簡単に言ってしまえば、へんに古臭いところがあるからだ、ということになります。
ひとこと言えばすむことを、それができなくて、『門』の宗助は禅寺に修行に行って動揺をおさめようとするし、『こころ』の先生は、長年悩み続けた挙句、最後には自殺してしまいます。
そんなことがありえるのかといえば、ぼくはありえると思います。
ただ反面、何でそのひとことが言えないんだ、馬鹿じゃねぇのか、という気持ちもあります。
ぼくだけではなく、誰でもその両方の気持ちをもっていると思います。「そういうこともあるよな」と「そんな馬鹿なことがあるか」の中間のどこかに自分の心があるというのが本当のところではないでしょうか。
だから、現代から見れば「へんに古臭い」と言えなくもない主人公の煩悶を描いた漱石の作品が、今でもよく読まれているのだと思います。
(『同上』P116-P118 )
|
備
考
|
(備 考)
確かに、日本の社会に「後進性」が残っているならば、その社会を呼吸し、そこに生きている人々の心や精神、行動に何らかの形で表れるはずである。しかし、ここで吉本さんが漱石や芥川の作品にその姿を読み取っているところはすごいなと思う。手で考えながら書くことを重ねてきた吉本さんの言葉の経験知から流れ出た言葉と言うほかない。漱石の作品における三角関係が文明史的なものとしてあるという吉本さんの言及にはずいぶん昔に出会ったという覚えがある。このことについても長らく考えを重ねてきたのだろうと思われる。
また、この三角関係という恋愛の形態はわが国の後進性の表れであるという捉え方には、吉本さんの三角関係の渦中でのにっちもさっちもいかない体験とそこから抜け出てきた体験とが吉本さんの実感としてあると思う。
この恋愛ということは、特に結婚にまで至ったであろう大多数の者にとっては、現在まで日本の社会に残る風習や因習などとのたたかいや妥協などを潜り抜けてきていることになる。例えば、わたしの場合は、結婚式はべつにしなくてもいいやという思いはあったけれども、波風立てずに型どおりに踏んできたということがある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 700 |
近代日本の後進性の表れ ② |
第3章 三角関係という恋愛のかたち |
語り |
『超恋愛論』 |
大和書房 |
2004.9.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 日本の知識人における内向する倫理観 |
この後進性というのはそう簡単には治らないよ、あっさり西欧並みにはなるはずないぜ、という気がする |
簡単には変わらない強固なものを日本が引きずり続けているとしたら、それが西欧とは違う独自の道筋につながっていくのではないか |
|
項目
1 |
①
漱石が「言えない性格」を、そうとう極端なかたちで自分の作品の主人公に与え続けたことは、漱石がもっていた、ある資質のためだと思います。
漱石は、誰もが認める知識人で、世間的に立派な人物とされていました。けれども、漱石自身の中では、他人に対してちいさな虚偽を犯し続けている卑小な人間であるという思いがあったのではないでしょうか。
漱石が描く主人公のかかえる極端な「ためらい」は、漱石のもっていた倫理の過剰さと、自分の内面にどんどん入っていってしまう内向性をあらわしています。
他人から見た自分と、自分自身が見た自分との間に大きなギャップがある。それを見過ごせないのが漱石の倫理観だったといえます。
それで、自分の内面にさらにどんどん入り込んでいき、ますます世間とのギャップが大きくなっていく。
これは日本の知識人の典型とでもいうべき姿で、現代でもまだ脱出できていないのではないかと思います。
西欧ならば、この種のことで悩むことは、まずありえないでしょう。漱石がもっていたような倫理観、つまり日本の知識人における内向する倫理観とでも言うべきものは、西欧における倫理観とはぜんぜん違うものです。
さっき「『言えない』というところに、日本の後進性があらわれている」とぼくが述べたのは、そういうことです。
日本の知識人は、西欧に追いつけ、追い越せということで、近代的自我を実現しようとがんばったわけですが、その自我とは西欧のそれとは似て非なるものだった。倫理そのものの拠って立つところからして、西欧とはまるっきり違うわけです。
いまの日本がそんな後進性なんかまったく引きずっていないとしたら、漱石の小説など古臭くて話にならないと考えることもできるわけですが、そうでもありません。
かれが描いた精神内容というのは現在でも読むに耐えるものですし、同じ問題は、いまもいろんなところに転がっているといいますか、依然として消えずにあると思います。
ぼくなんかは、漱石が描いたような三角関係が、透谷、独歩の挫折の後にくる、近代の恋愛における「挫折の終わり」であって、現在までこの問題は解決されていないように思えてしかたがありません。
この後進性というのはそう簡単には治らないよ、あっさり西欧並みにはなるはずないぜ、という気がするんです。
(『超恋愛論』P119-P122 吉本隆明 大和書房 2004.9.15)
※①は、ひとつながりの文章です。
②
ところでぼくが、芥川と同様、日本独特の自我や倫理のあり方を「後進性」と呼んでいるからといって、日本も西欧のあとについて、西欧と同じように進んでいくべきだと思っているかというと、そうではありません。
日本が近代から現代へ、そしてこれから先の社会に移っていくにあたって、その道筋が、必ずしも西欧の軌道の模倣のようになっていくかというと、そうはいかないのではないかと思っています。 日本独特のものが入って、西欧とは違う進み方をするのではないか。簡単には変わらない強固なものを日本が引きずり続けているとしたら、それが西欧とは違う独自の道筋につながっていくのではないか、という気がします。
じゃあそれはどんな道筋なのかと聞かれたら、ぼくにもわからない。これからの課題だと言うしかありません。
三角関係は近代における恋愛の「挫折の終わり」であるという言い方をしましたが、ではその次に何がくるのか。
西欧だと、男性も女性も独立独歩で、一緒に住んでみてはまた別れて、というのを繰り返すということがあります。
また、特定の異性と一緒になった後も、相互に別の恋人を持って多角関係みたいに自由に恋愛をしていく、ということもあります。
そういうかたちを取ることで、三角関係のきつさみたいなものは緩和されることでしょう。
西欧の基準でいえば、それは先進的というか、独立した個人と個人のかかわり方が行き着くひとつのかたちであるかもしれません。
しかし、日本もまた同じ道筋を辿るかというと、そうではないんじゃないのかな、という気がするのです。
(『同上』P126-P127 )
|
備
考
|
(備 考)
現在、世界の各地域がグローバル化の大波を被っている渦中にあるが、「日本独特のものが入って、西欧とは違う進み方をするのではないか。」ということは、日本に限らず中国や西アジアのイスラム世界でも同様ではないかと思われる。
そうして、このことは、どのように具体的に進むかはわからないとしても、今後の世界の各地域のベクトルの振る舞いを暗示している。
歴史の段階概念は、ヘーゲル辺りから生みだされたものと思われるが、未開野蛮の段階、アジア的な段階、ヨーロッパ的な段階などと呼ばれるものがあった。現在までのところの歴史を振り返れば、それらが広い地域性と、現在にまで残存していることから考えれば深い時間性とを持った、アフリカ的な段階、アジア的な段階、ヨーロッパ的な段階などと呼ばれる歴史段階は、それぞれのひとつが人類の有り様の絶対性ということではなく、それら全てが今のところの人類の可能性を示していると言うことができるように思われる。また大ざっぱに単純化して言えば、太古の共同性に埋もれていた個の存在が、抽出され、先鋭化してきた現在から眺めると、歴史の段階の中心の推移は、個の存在の有り様の推移と対応しているのではないかと感じられる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 702 |
子どもの時間を分断しない |
第2章 男と女の足下にある泥沼 |
語り |
『超恋愛論』 |
大和書房 |
2004.9.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 因習の泥沼みたいなものを抜け出すには、自分たち以降の世代の意識を少しずつ変えていくしかない |
二五時間目の問題 |
|
|
項目
1 |
①
役割の固定を解消していこうと思ったら、一代や二代では難しいという話をしました。
だからぼくは、子育てのときに、自分なりに気をつけようと思ったんです。因習の泥沼みたいなものを抜け出すには、自分たち以降の世代の意識を少しずつ変えていくしかないわけですから。
ぼくとうちの奥方だって、自分たちはいい形の男女関係でいけるだろうという目論見のもとに所帯を持ちました。
けれども、生活しているうちに、やっぱりこれは本当の意味で近代的には、自分たちは育ってきていないなあ、ということに気がつくわけです。そうすると、一代では駄目なんだと考えるようになりました。子育ての生活は旦那の協力がいるほど大変なものだということはおたがいに理解していたのですが、なかなか身体と心が動きません。でもモットーだけは作りました。二四時間全部を使えないことに出合ったら、さしずめ二五時間を作り出して使えばいいということです。
これは自分のできないことを含んでいる感じで後ろめたいのです。本音を吐けば漱石の理想の女性は、僕も最高の女性だと思っています。申し訳ないです。
②
うちは二人子どもがいますが、両方とも女の子です。それで、子育てのときに、考えたんです。
将来、仕事をしたり、恋愛や結婚をしたりというときに、女だということで何らかの束縛を受けたり、役割を固定されてしまうようなことがなるべくないようにするにはどうしたらいいか、と。
ぼくが出した結論は、「親にできることは、子どもの時間を分断しないように気をつけることではないか」ということでした。
なぜかというと、将来、女の人の人生を一番束縛するもとになるのは、「まとまった時間が作れないこと」ではないかと思ったんですね。
ぼくは、時間を忘れてなにかに熱中する、あるいはただぼーっとしているだけでもいいのですが、とにかく誰にも邪魔されないまとまった時間というのが、人間には必要だと思っています。けれども女の人にはそれが作りにくい。親として気を配ったのはそれだけです。あとは自由に好きなことをやれたら女の人は万歳でしょう。
勉強するとか、何か創造的な趣味をやるとか、そういうことでなくてもいい。家にこもって、一人だけで長い時間を過ごすことが、その女性を作るとぼくは思っています。
はたから見ると無駄に思えるかもしれない、または今の世の中では、"ひきこもり"として問題視されかねないそんな時間こそが、本質的なところで女性の魂をはぐくみ、その人の人生の"価値"を生むのです。
(『超恋愛論』P87-P91 吉本隆明 大和書房 2004.9.15)
※①と②は、ひとつながりの文章です。
③
これは、男でも女でも変わらないことなのですが、やはり女の子のほうが、時間を分断されやすいという現実があります。
ぼくは子どもの頃、親に用事を頼まれても、なんだかんだ理由をつけて逃げていました。そうすると親は、かわりにぼくの姉にその用事を言いつける。姉は、けっこう素直にそれをやるわけです。
子ども心にぼくは、これはよくないな、とわかっていました。わかっていたけれども、自分の時間がとられるのはいやだったから、結局いつも逃げていた。
大人になっても、そのことが頭のどこかにありました。あれはよくなかったと今でも思うのです。
つまり雑用は女の子がやるもの、女の子の時間はこま切れにしてしまってもかまわない、と大人たちは思っていて、ぼくはそれを利用していたわけです。
世の中がそう考えている限り、女の人の人生におけるさまざまな束縛とか、固定された役割を押し付けられがちなことなどは、解消されていかないのではないかと思います。
(『同上』P92-P93 )
だから、子どもが集中して何かやっているな、と思ったときは、お使いを頼んだりせずに、自分でおかずを買いに出かけたりしていました。
ぼくが行ったらぼくの時間が分断されるのだけれども、ぼくならもう、ある程度、仕事のやりかたや時間の配分が自分なりにできているから、それほど差し支えはない。
でも、これから何かをやろうとしている人はそうはいかんだろう、まとまった時間が必要だろう、と思ったのです。
ぼくは、ほかのことに関しては、まったく駄目な親でしたけれども、このことに関してだけは、ある程度はやったんじゃないか、できたんじゃないかと思っています。
ばかに恰好いいことを言っていますが、本当はひでえもので、とくに老いて足腰が不自由になったら、子どもの時間を分断してばかりで懺悔しています。
(『同上』P95 )
|
備
考
|
(備 考)
この子どもの時間をできるだけ分断しないということは、以前に吉本さんの文章で読んだことがあった。しかし、どこで語られていたか覚えてないので、確認しようがないが、ここでのように、子どもが生き方として十全に自分を表現できるように見守る視点や(男女)平等問題の関わりとして語られていたという印象がない。
このことからも、吉本さんはわたし(たち)が無自覚あるいは無意識的に対処していることが多い日常生活の場面で、自分の思想とつながる生活の判断・思想を意識的に考えていたことがわかる。「二十五時間目の問題」もそうした場所から生まれ出ている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 703 |
婚姻届の意外な重さ |
第4章 結婚制度のゆくえ |
語り |
『超恋愛論』 |
大和書房 |
2004.9.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 三角関係の渦中での実感 |
なぜ法律が人の心にここまで深く食い込んでくるのか |
まず宗教があって、それが法律になって、それから国家(近代国家)が生まれたということです。 |
国家というのはやはり強いもんだな、というのがぼくの実感です。 |
項目
1 |
①
婚姻届というものがあります。これは、私たちは結婚しましたよ、ということを国家に届け出るものです。
ぼくは、独身のときは、婚姻届を出す、つまり法律婚をするということに、ほとんど意味を感じていませんでした。
そんなもの別に出しても出さなくてもどっちでもいいじゃないか、国に届けるなんていうことよりも、結婚生活の内実というか、一緒に暮らしているということそのもののほうが大事だよ、という感じだったのです。
けれども、あるときを境に、これは意外に重たいものだぞ、馬鹿にできないぞ、と思い始めました。
前の章で三角関係について述べましたが、ぼくにも同じような経験があります。男と女がいて、そこに割り込んだわけです。やはり三者三様にぎりぎりのところまで追い込まれて、これはもしかすると三人全員が滅びるよりほかないぞ、というところまで行った時期があります。
三人とも真面目になればなるほど行き詰まってしまって、もう元には戻れないし、先にも進めない。にっちもさっちもいかない状態で三人とも自滅するのかと考えたことがあります。
その経験のなかで、ほくは婚姻届を出す、出さないということが人の心にいかに大きな影響を与えるのかを実感しました。法律というものが、意外な重さで個人にのしかかってくるものなんだということを発見したわけです。
同時に、なぜ法律が人の心にここまで深く食い込んでくるのかということを、考えずにはいられませんでした。
それで、自分なりに出した結論というか、考え方の筋道は、法律というものの根っこのところには、広い意味での宗教があるのではないかということです。
いちばん最初に宗教が生まれ、その宗教のうちのもっとも強固な部分が法律となった。宗教の枝葉の部分を除き去って、いちばん固いものだけを取り出したのが、法律だというわけです。
(『超恋愛論』P144-P146 吉本隆明 大和書房 2004.9.15)
②
前の項でいう法律とは、こまかい決まりごとではなくて、のちに国法とか憲法とかになる、すべての法の骨格のようなものです。
つまり、法律はもともと、はるか昔の宗教に由来しているわけで、だからこんなにも人の心に対して力を振るうことができるのです。
紙切れ一枚にすぎない婚姻届を提出することが、意外なほど重たい意味をもってくるのも、それが宗教をもっと固くしたものである法律にもとづく行為であるからなのでしょう。
宗教から生まれた法律が、さらに煮詰まっていって誕生したものが国家であるとぼくは考えます。
国家が法律を作ったのではなく、まず宗教があって、それが法律になって、それから国家(近代国家)が生まれたということです。
余談ですが、国家信仰というのは根強くて、いまの若い人たちの中にも国家、国家と言っている人もいます。
ああいうのを見ていると、この間の戦争で、国家のためだと言われてあれだけたくさんの生命を失って、生き残った人たちも食うや食わずの目にあっているのに、いまだに国家を信じ奉っていることを不思議に思ったりします。
「まるで昔のオレみたいじゃねえか。日本人はあれほどひどい目にあったのに、何も変わってないじゃないか」
とあきれてしまうのですが、考えてみれば、国民国家というものは、宗教のもっとも新しいかたちなわけですから、強固な信仰の対象であり続けているのは仕方がないことなのかもしれません。
(『同上』P147-P149 )
※①と②は、ひとつながりの文章です。
③
企業はすでに国家を超えていますし、グローバル化ということがさかんに言われていて、国家なんていうものはすぐに壊れそうなものですが、そうはならない。国家というのはやはり強いもんだな、というのがぼくの実感です。
それでも欧州では、国家イコール政府、というくらいにしか思っていません。けれども日本人はまだまだ、国家とは国民全部をつつみこむもの、と思っている。人間も土地も、まるごとその中に含む概念として国家を考えているのです。
戦争中と同じような国家主義から抜けきれない理由がここにあります。
(『同上』P149-P150 )
|
備
考
|
(備 考)
わたし(たち)は、あんまり「婚姻届」というものに気にもかけなかったと思う。ただし、吉本さんのように苦しい三角関係などで「婚姻届」というものの重さを実感した人はまた別だろう。現在では、わたし(たち)は、ほとんど〈法〉を意識することなく日々生活している。しかし、この関係的な社会では、いつ何時〈法〉を意識させられるか分からないという引き寄せの可能性を感じている。
「法律はもともと、はるか昔の宗教に由来しているわけで、だからこんなにも人の心に対して力を振るうことができるのです。紙切れ一枚にすぎない婚姻届を提出することが、意外なほど重たい意味をもってくるのも、それが宗教をもっと固くしたものである法律にもとづく行為であるからなのでしょう。」 ということは、何が何でも法(婚姻届)を無視することも可能性としてはあり得るが、法の核には遙か昔の宗教性がたぶん今なおこもっているから、なんだただの印籠ではないかと受け取られることなく、水戸黄門の印籠のように人々をたじろがせるのだろうと思う。だから、婚姻届を抹消するとか、婚姻届を新たに出すとかの結着が、関係する人々にそれなりの説得力として作用し収束点を与えるのだろう。
このことの意味は、この社会の中に生きるわたしたちの〈法〉意識の問題として、様々な場面でもう少し微細に考えてみるに値する問題だと思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
| 707 |
危惧すること |
戦後文学の発生 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日 |
講演日:1980年11月29日 「吉本隆明の183講演」の「講演テキスト」より引用
関連項目
言葉の吉本隆明① 項目131 言葉という地平
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 僕が持っている課題 |
課題は一種の二重性を持っています |
歴史、文学史として作品の時代を一種、完結しなければいけませんが、もう一つは完結しながら、しかしそれを現在の問題のように感じさせる一つの見方がなければならないはずだと思います。 |
|
項目
1 |
①
12 戦後文学の現在性をどうとらえるか ( 引用者註.「講演のテキスト」の小見出し)
僕は危惧することがあります。たとえば僕などが戦後文学の発生(註.1)を問題にした場合、それは学生さんにとってどういうことになるのか、若い人にとってどういうことを意味するのかをときどき考えることがあります。
類推の方法が一つあります。皆さんにとって僕が発生の時期の戦後文学についていろいろ考えたりしゃべったりすることは、僕にとって言えば明治初年の開化期の文学を論じるのと同じことではないのかという疑いに襲われることがあります。僕らにとっては割に生々しい体験を踏まえ、割と同時代と言える時代なので生々しい感じがしますが、皆さんにとってはたとえば僕が明治初年の文学を考える場合と同じことではないかと思われることがあります。僕が明治開化期の文学について論じる場合には、その向こうにはちょんまげを結って刀を持った人たちがそこらへんをうろうろしていたということになります。
皆さんに戦後文学の発生期を論じることは僕にとってはそういうことであって、その前の戦争について何か考えるのは、皆さんにとっては僕がちょんまげ時代を考えるのと同じくらい遠いことなのではないかという一種の疑いに襲われることがあります。たとえば僕らのおやじのおやじ、祖父にあたる人が「日露戦争のときはな」と体験を語るとばかにして、「また始まった」と子どものときよくそういうふうに感じました。そんなことになるのかもしれないという懐疑をいつも感じます。
②
そういう懐疑を覚えながらも、そのことを論じていく。おじいさんが日露戦争について言うように、文学者が髷の時代についてしゃべっているのと同じようなことを「何しゃべっているんだ」という、過ぎ去った歴史、文学史ということではなく考えたり取り上げたりすることはできるだろうかということが、僕が持っている課題だと思います。
僕ができることは非常に難しいと思いますが、僕が戦後文学の発生期について論じることが単に文学史上のある時代を論じているにすぎないならば、すぎないようにしか論じられないとしたら、僕が課題を果たしていないことになると思います。逆に言うと、課題は一種の二重性を持っています。歴史、文学史として作品の時代を一種、完結しなければいけませんが、もう一つは完結しながら、しかしそれを現在の問題のように感じさせる一つの見方がなければならないはずだと思います。それをつくりあげることが、僕などがいま持っている課題ではないかと自分で思います。
それならば、皆さんが持っている課題は何だろうか。文学史を文学の歴史的知識として獲得するという意味で戦後文学の発生期の文学作品を取り上げるなら、たぶんそれは取り上げ違い、一面的な取り上げ方です。そういう取り上げ方であると同時に、それはいまの問題とどういうつながりがあるのか。どこまでいまの問題なのかを取り上げられたら、皆さんは宿題を果たしたことになると思います。
僕が持っている宿題と皆さんが持っている宿題はたぶん対照的ですが、宿題は相互に持っています。どこかで宿題を解こうとするモチーフがあれば、そこで話し合い、コミュニケーションが成り立ちます。もしそれがなければ……
【テープ交換】
……何をしゃべっているんだという批判は免れません。皆さんは、新しいと思ったけれどもそんなことは大昔というか前にやったことだと言われることを免れないみたいなことがあると思います。この課題はいつでも宿題としてあるということで、たぶんコミュニケーションが成り立つのだろうと僕自身は考えます。
(『文学A057 戦後文学の発生』「講演のテキスト」より 吉本隆明の183講演 ほぼ日)
講演日時 1980年11月29日
※①と②は、一連の文章です。
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
「発生」という概念について、「起源」と比べながらこの講演の最初の方で語られている。
3 〈発生〉ということ
「戦後文学の発生」としてありますが、発生ということについてお話ししてみたいと思います。
「発生」という言葉と「起源」という言葉は同じようなことを指す言葉としてありますが、起源という場合にはいわゆるルーツということです。戦後文学の根っこを探していったら何に突き当たるかと考えていく場合に、たぶん起源という言葉を使うのではないかと思います。発生という言葉は、ほんの少し違う気がします。ルーツということではなくて、発生という概念には二つくらいの局面があって、一つは何もないところからわいてきたと言いましょうか。つまり、ルーツがあって出てきたということは必ずしもよくわからないけれども、とにかくわくように新しい要素が出てきたような場合に、発生という概念が使えるのではないかと思います。
もう一つ、発生は非常に不安定な状態です。つまり、発生してそれがいつ消えてしまうかもわからない不安定な状態ですが、同時に何とでも結びつくことができる。どんなものとも結びつく活力というか活性力を持っている。しかし、それ自身はあまり安定していないから、何かと強力に結びついて持続するかもしれないけれども、結びつくものがなければそのまま消えてしまうかもしれない。そういう概念に対して、発生という言葉が使えるのではないかと思います。
ここで発生という言葉をその二つの側面から使ってみたいわけで、決してルーツということではない。ルーツに触れるということではなくて、発生、一種の不安定さと何かと結びつく発生を持っている状態の戦後文学の中に何があったのか。そして、発生が何かに結びついていまも持続している要素は何か。そのときにはあったけれども、もはやいまは跡形もなく消えてしまった要素はいったい何か、といったことを浮かび上がらせることができたらいいのではないかと思います。
たくさんの戦後文学の発生点については、昭和二十年、一九四五年を敗戦の年とすると、その年の八月以降から翌年にかけて作品が新しく生み出されつつありました。そのほんの数年の間の日本文学に出てきた作品を見てみると、敗戦を迎えて、戦争が終わって、さまざまな要素が同時に出てきたと思います。その要素を発生ということで取り上げることができるとすれば、大きく分けて二つあると思います。
二つのことをいくつかの作品で象徴させることができると思いますが、たとえば一つは何か。僕が頭の中で考えてきた作品で言えば、たとえば太宰治の『お伽草子』という作品は戦争が終わった年の十月ごろに出ています。『お伽草子』という作品と、その年かあるいは翌年かと思いますが、谷崎潤一郎の『細雪』という作品が出ています。もう一つ、同じようなところでまとめられる作品として、舟橋聖一の『悉皆屋康吉』という作品が出ています。『お伽草子』と谷崎の『細雪』は皆さんご承知だろうと思いますが、舟橋聖一の『悉皆屋康吉』という作品はたぶん舟橋聖一の最もすぐれた作品だと思いますが、あまりよく読まれていないのではないかと思います。この三つの作品を戦争が終わった数年間に置いてみると、ある一つの日本文学の流れ、しかもその戦後においての有り様が非常によく浮かび上がってくると思います。
この項目で取り上げた問題は、同じ同時代を生きているとしても、体験してきたものが違っているという一般化すると世代間のギャップという問題になる。あるいは、同世代だとしても、人と人との間には簡単にわかり合えないこともあるという問題でもある。そんなギャップが存在する中で「コミュニケーション」を成り立たせようとするなら、ギャップを貫く普遍の姿を、共通性を探るほかないと思われる。
ところで、この問題と直接につながるわけではないかもしれないが、この問題は以下の『母型論』の序で述べられていることと関連しているなと思い浮かべた。
おまえは何をしようとして、どこで行きどまっているかと問われたら、ひとつだけ言葉にできるほど了解していることがある。わたしがじぶんの認識の段階を、現在よりももっと開いていこうとしている文化と文明のさまざまな姿は、段階からの上方への離脱が同時に下方への離脱と同一になっている方法でなくてはならないということだ。
わたしがいまじぶんの認識の段階をアジア的な帯域に設定したと仮定する。するとわたしが西欧的な認識を得ようとすることは、同時にアフリカ的な認識を得ようとする方法と同一になっていなければならない。またわたしがじぶんの認識の段階を西欧的な帯域に設定しているとすれば、超現代的な世界認識へ向かう方法は、同時にアジア的な認識を獲得することと同じことを意味する方法でなくてはならない。どうしてその方法が獲得されうるのかは、じぶんの認識の段階からの離脱と解体の普遍性の感覚によって察知されるといっておくより仕方がない。わたしはじぶんが西欧的かアジア的かアフリカ的かについて選択的である論議の不毛さに飽き飽きしているし、現状で理解できる表面の共通性で、国際的という概念の範囲を定めている国際的と称する認識にも同調する気はまったくない。そこでわたしがやったのは、じぶんの好奇心の中心に安堵できる段階からの離脱と解体の普遍性の感覚を据え、孤独な手探りにも似た道をたどることだった。この本でたどりついている場所は、まだ入口近くの迷路のなかのような気がするが、すこしずつ確実に展望をひらきたいとおもっている。
(『母型論』「序」 1995年11月)
あるいはまた、
いったん〈言葉〉という次元に捉えられると、いままで確定的だとおもわれていた事実の世界は、いわば故意に単純化された近似値の世界におもわれた。そして近似値で充分に間に合う概念と近似値では済まされない、組替えが必要な概念の世界とが現前した。この体験はわたしを愕然とさせたが同時に尽きない好奇心を強いるものでもあった。そこを夢中で通過しながら、いまこの本の前にいる。
なかでわたしをいちばん惹きつけたことは、アジア的あるいは古典古代的な世界としてすでに完結した〈言葉〉の世界、その系は、いまここに現前として置きなおしたとき、現在の〈言葉〉の世界とどう接合されればよいのかという課題であった。事例的にはそれがもっとも重要な現在の思想的な課題にほかならない。この本はそれを提出したばかりだが、わたし自身はやっと解決の端緒についた気がしている。一般に宗教の形で現在あるものはアジア的あるいは古典古代的な言葉の世界を、現在に置きなおすある一つの仕方のことであり、科学的と呼ばれている理念は、近代以後の世界を宗教化した一つの仕方をさしている。現在の世界が求めているのは、この何れともちがったある一つの置きなおしの仕方を意味している。この本で〈言葉〉が思想とみなされる個所で遭遇したのはこの課題であった。
(『言葉という思想』(1981年1月)「あとがき」より P280-P281)
※言葉の吉本隆明① 項目131 「言葉という地平」
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 711 |
芸術の否定性 |
「一行の物語と普遍的メタファー ――俵万智、岡井隆の歌集をめぐって」 |
対談 |
『吉本隆明 詩歌の呼び声 岡井隆論集』 |
論創社 |
2021.7.30 |
「一行の物語と普遍的メタファー ――俵万智、岡井隆の歌集をめぐって」(『現代詩手帖』1987年12月号)
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 俵さんの短歌は、一行で物語を作っている |
つまり否定性を打ち消すことが文学・芸術の否定性の課題として成り立ちうるかどうかという情況が出現している |
俵さんの短歌がもっている否定性を打ち消す否定性 |
|
項目
1 |
①
皆さんは短歌の専門家の方が多いわけでしょう。皆さんのあいだでの俵さんの歌集の評価はさまざまでしょうが、『サラダ記念日』の何が特徴かというと、僕はやっぱり、一行で作られた物語だということじゃないかとおもいます。普通は相当長いスペースを取って起承転結を作らないと物語にならないみたいなんですが、俵さんの短歌は、一行で物語を作っているとおもうわけです。それから、なぜたくさんの読者を獲得しているかということをかんがえてみます。もちろん力量からして、ちょっと天才的なところがあるとおもいます。力量があるということ、短歌を物語にしちゃったということ。それから、挫傷感、屈折が少ないということ。すぐにいまの大勢の読者にうけそうな要素は数えられます。短歌だけに限らないんですが、文学の表現はいつも否定性ということを特徴とします。この否定性が言葉の中に、あるいは物語のどこかに何らかの形で必ず存在いたします。つまり否定性は文学・芸術の特徴なのですが、俵さんの歌はある意味で否定性を打ち消してしまったところに成り立っています。それはとても大きな特徴だとおもうんです。
そして、もしかするとこの特徴は短歌だけでなく文学全般が、現在当面している問題であるかもしれないのです。つまり否定性を打ち消すことが文学・芸術の否定性の課題として成り立ちうるかどうかという情況が出現していることが現在の大きな問題なんじゃないかなという気がします。そこに、俵さんの短歌がもっている否定性を打ち消す否定性というのが成り立ちうるかどうか、あるいは成り立ちうるんだというところで、新しい短歌的表現が打ち出された、そこがたいへんうけて、多くの読者を獲得している。『サラダ記念日』の問題はそこにあるような気がします。
②
短歌を物語にするというのはどういうことかかと申しますと、結局、三十一文字の表現であるにもかかわらず、三十一文字以上の物語がその中に含まれているという表現の仕方がなされていることだとおもいます。これは俵さんの短歌作品の特徴じゃないでしょうか。その他にも現在の若い人ふうの性やエロスの調和のとれた自由感みたいなものが感覚的によく表現されています。この歌集が読者を獲得する要因は結果的には、たくさん数えあげることができそうです。
この種の短歌の作り方のいちばん強力な始祖はもちろん石川啄木です。石川啄木の短歌がやったことは、一行あるいは三行の詩で物語を作ったことだとおもいます。その物語は、現実の物語であったり、虚構の物語であったりするわけですが、短歌を強力に物語にした最初の歌人は石川啄木だとおもいます。俵さんの短歌も同じです。俵さんの短歌にはフィクションも事実も混じっていますが、やはり一行で物語を作ったということでしょう。啄木の短歌と俵さんの短歌は、一行ないし三行の物語として同じじゃないか、というと、素材的に考えたり感覚的に考えると、冗談じゃないということにもなりそうです。主題主義でいけば片方は生活の苦労人が作った短歌であり、片方は安定した現代風の娘さんが作った短歌で、まるで違うじゃないかという理屈になるわけです。僕は根本的には同じなんじゃないかとおもいます。
(『吉本隆明 詩歌の呼び声 岡井隆論集』P244-P246 論創社)
「一行の物語と普遍的メタファー ――俵万智、岡井隆の歌集をめぐって」(『現代詩手帖』1987年12月号)
※①と②は、ひとつながりの文章です。
※ここはまだ、俵万智や石川啄木短歌の批評の前半部分。共通部分。
|
備
考
|
(備 考)
まず、あとひと説明ないために文学(芸術)の本質と見られている否定性ということがよくわからない。したがって、従来の文学が持っていた「否定性を打ち消す否定性」というのもよくわからない。
それ以前と比べて、近代の文学の主流はひと言で言えば、この新たな社会内での人の悩み苦しみにスポットライトを当てた「暗さの文学」ということになるか。それに対して、消費資本主義社会の前面化やサブカルチャーの浸透と対応して、主流が、不幸や暗さの文学から、文学も明るいとか面白いでいいじゃないかという流れに変わったように思う。俵万智の短歌の表現もそういう社会の推移を鋭敏に反映しているのは確実である。
上記の「文学の本質と見られている否定性」とその「否定性を打ち消す否定性」は、この文学の主流が「暗さ」から「明るさ」へ変位したということと同列に見ることができるか。できないような気がするが、無関係ではなくある対応があるような気がする。前者は、もっと文学の本質レベルの問題のように感じる。文学の主流が「暗さ」から「明るさ」へ変位したということは、その後には、暗かろうが明るかろうが別に文学の本質には関係ないということになりそうだ。文学概念の拡張である。その点、「文学の本質と見られている否定性」とその「否定性を打ち消す否定性」は暗さから明るさへの変位と対応して、文学概念のある拡張に当たりそうにも思われる。
文学の表現の本質的な特徴としての「否定性」をわたしなりに捉えてみると、文学の表現は私や私の結ぶ関係や社会などの現在的な有り様に対する批評、すなわち否定性を秘めている。これは、別の言い方をすると、文学は人やこの世界の有り様に対する理想のイメージへの欲求を内在させている、そしてこのことは時代性を超えたものである、ということになる。
ところで、この文学が表現する「否定性」、すなわち現実の有り様に対する理想のイメージは、一般的には「永続的な課題」に属する。そう簡単に理想のイメージを現実化することは難しい。とすれば、「現在的な課題」としては現実の有り様は「否定性」ばかりとはいえないから、ちょうど暗さの文学から明るさの文学に主流が変位してきたように、「肯定性」としての表現も可能ではないか、生き生きと生きている表現を表出することもいいではないか、ということだろうか。
故事成語の鼓腹撃壌(こふくげきじょう)の、老人が腹つづみをうち、地面をたたいてリズムをとりながら、太平の世を謳歌する歌をうたっているような、肯定性の表現もあり得るだろう。特に、飢餓がメインの課題から退いてきた(現在の社会の貧困化は、揺り戻しの状況だが)現在の、純文学もサブカルチャーも融け合った状況は、新たな文学表現を促しているのかもしれない。
★結論としては、吉本さんの言う「否定性」の問題がまだよくわからないから、わからないままに残しておくことにする。
上のこととはあんまり関わらないかもしれないが、参考までに、P246-P249に引用されている俵万智と石川啄木の短歌と吉本さんの考察を見てみる。(強いて言えば、下の赤字の部分が関係ありそうに見える)
思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみ
という歌があります。同じように帽子のことを歌った啄木の歌をあげて並べてみましょうか。
六年(むとせ)ほど日毎日毎にかぶりたる
古き帽子も
棄(す)てられぬかな
これが啄木の帽子についての短歌です。これを二つ並べてみれば、同じ主題、同じ素材をかなり似たような状況で使っているんですが、片方には、六年もかぶった帽子を捨てられないという言い方で、(もっとちゃんと黙読されたり、それ相当の人が朗読されたりすると、もっとはっきりすると思うんですが)生活の疲れと翳りがちゃんと感覚的に出ているように思います。俵さんの短歌は恋愛中の明るい感覚の心理的瞬間を捉えたいい短歌だと思いますが、ふたつは少しだけ違うといえるでしょう。でもおおげさにかんがえるほどの違いではないことがわかります。
他にもいくつかあげてみましょう、これは夕方のある瞬間を主題にした歌です。俵さんの歌だと、
この部屋で君と暮していた女(ひと)の髪の長さを知りたい夕べ
というものです。いくらかの淡いジェラシーを含めた瞬間の心理の物語がとてもよく把まえられています。啄木のその種の歌を読んでみましょうか。
新しきサラドの皿の
酢のかをり
こころに沁みてかなしき夕(ゆふべ)
このふたつの場合も、片方の方にも淡いジェラシーのようなものがあるんだけど、そんなに深刻でもなく、かなり淡々とした明るい感覚で述べられています。啄木の歌の方は何となく生活の臭い、疲れといいましょうか、ある生活の澱(おり)の溜まった蓄積感がどこかにうかがえます。これが、ふたつの一行の物語のちがうところだとおもいます。もう少しやってみましょう。
我だけを想う男のつまらなさ知りつつ君にそれを望めり
という、これもものすみ゛く見事な恋愛の歌だとおもいます。女性の側の主導権、自分が恋愛の主(あるじ)だという感じがとても自然に出ているとおもいます。同じような啄木の歌をあげてみましょう。
女あり
わがいひつけに背かじと心を砕く
見ればかなしも
これは、自分におどおどしながら生活の中で仕えているように見える女性を憐れがっている歌です。このふたつの相違は決定的なもののような気がします。啄木も女性にシンパシーをもっているし、またかなりな程度女性解放論者でもあったわけです。それでも、こういうふうにしか女性を表現できないということが時代的な制約としてあります。一方、これもいい歌だとおもいますが、俵さんの、自分だけを想っている男っていうのはつまらないということはよくわかっているんだけれども、そう想ってもらいたい、という、女性が恋愛の主だといっている時代の(現在の)歌です。つまり、この歌になってくると、啄木と現在の俵さんの歌は、同じ一行ないし三行の物語ですが、まるで違う感性と違う主題の扱い方がされていることがわかります。時代の相違ということをもし取り出すことができるとしたら、それができているんじゃないでしょうか。
「一行で作られた物語」について
普通一般の短歌的な表現を、個の心の場面の描写や自然描写の場面の描写とすると、短歌の「一行で作られた物語」という表現は、〈私〉自体でも〈私〉が他者と関わる場面でもいいけど、その場面の中には物語同様の関係の起伏やドラマ性を内蔵しているということか。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 729 |
固有値としての自分 |
「江藤さんについて」、「固有値としての自分のために 3」 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集181』 |
猫々堂 |
2018.12.30 |
・「江藤さんについて」、聞き手 大日方公男 インタビュー日:2011年9月9日
・「固有値としての自分のために 3」、聞き手 菊谷倫彦 インタビュー日:2011年6月24日
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 個人より狭い「固有の個人」 |
時代性と時代の現実と事物との間で物事は決まっていきますから。主なものはそこで決まっていきますね。 |
自分の固有性っていうのは、自分の自分にたいする考え方ですから。 |
|
項目
1 |
①
―― 「戦後と私」(六六年)や『一族再会』(七三年)で、江藤さんが生まれた山の手の大久保界隈が戦後の都市化で猥雑な街になったことへのつらい郷愁を吐露し、軍人であった祖父への思い入れがあったりする。それが江藤さんに戦後民主主義や大衆文化への、曰くいいがたい違和感を抱かせた。その虚構や喪失感が、江藤さんに文学への手応えを失わせ、自分を公然と認知できるような政治評論や政治史研究に向かわせた理由と言えますか。
吉本 そう捉えることもできると思います。個人の育ち方や家のあり方もいろいろ異なりますし、それぞれの地域の風土で違うところがありますが、それを一緒くたにすることは実はできないのではないか。個人より狭い「固有の個人」を意識しなければうまく解けないことがあり、そこが問題だという気がします。身体を捻らないと通れない道があるように、孤独な個人が通る狭い道があって、それを設定しないと風景の中にも社会の中にもうまく入っていけない要素があると感じます。それはとても大事なものですが、僕には明瞭には分からないもので、絶えず悩まされるものです。
山の手ばかりでなく、東京の下町もとても様変わりしましたし、その時に僕が何をどう感じてどう言葉にしたいのか、そのことを本当は知りたいわけです。しかしそこへ積極的に踏み込んでいくとうまく伝わらない。自分にとって寄る辺である故郷や記憶が確かにある気がすることと、そんなものどこにもないやという気が同じ地平で感じとれる。戦後の日本はそれが本当に分かりにくい空白として残ります。スキーで滑るあれあれという間にまったく自分が辿り着くと思ってなかった場所に辿り着いてしまう感じによく似ています。江藤さんもそういう迷路に入りこんでいたのかもしれません。
(「江藤さんについて」、P49『吉本隆明資料集181』猫々堂)
※聞き手 大日方公男 インタビュー日:2011年9月9日
②
―― 詩でもやっぱり、本能的な部分というか、自分の内面に下りていくっていうことが必要ですかね。そういった点はいかがでしょうか。なかなかいま、そういう時間がないということもあって、自分の本能というか、内面に降りてくるということが出来づらいのかな、っていうふうに思いますが。
吉本 なかなか大変ですよね。ある程度の環境はそれぞれもっているということは前提としまして、そのうえに環境プラスなにかっていうのが、その人の固有性っていいますか、固有の個性になってきている。それで、どんな事情があろうと、厭になったら、もうそんなの見るのも厭だっていうふうにもなりますし、はっきりいって、飽きてきたら、やっていることが全部つまらないことに思えるときもあるわけです。そういうことをさまざま経験していくわけでしょうし、ただ、天才的な詩人、歌人とか、あるいは俳人だとか、そういうことっていうのはあり得ない、というふうに思いますね。時代性と時代の現実と事物との間で物事は決まっていきますから。主なものはそこで決まっていきますね。
それで、根気がいい人もいるし、根気がよくない奴もいるし。気に入った娘さんとか息子さんが出てきたら、そんなことはつまらねえことに見えて、辞めちゃうこともありますし。そういうさまざまな難所をやっぱり、それなりに一人ひとりくぐっていくわけじゃないでしょうか。そういうことが身についてくれば、それは大したもんだと思いますね。
多少うぬぼれとか、自己過大評価とか、そんなことを人に言われたり、そういうのに反発したり、色々な問題が出てきますけど、でも、基本的なところは、自分と自分の環境とのかかわり方に左右されることになりますし、どうやったら詩がうまくなるのかっていったら、それは、いっぱいなんでもいいから、書いて書いて書きまくればいいんだって言われたら、そうしますって言っておいて、あまり反発しないで、黙って怠けて継続すればいいし。百人いれば百通り、ちゃんと固有性っていうのが違いますから、環境が同じ環境であろうとも、違ってくる部分が沢山出てきます。複雑な社会であればあるほどそうですよ。自分の固有性っていうのは、自分の自分にたいする考え方ですから。外からの考え方じゃなくて、自分の自分にたいする考え方とか感じ方ですから。
(「固有値としての自分のために 3」、P81-P82『吉本隆明資料集181』猫々堂)
※聞き手 菊谷倫彦 インタビュー日:2011年6月24日
※初出『kototoi』第3号2012年7月30日発行
|
備
考
|
(備 考)
①と②は、だいたい同じ頃のインタビューである。①の「個人より狭い『固有の個人』」ということは、割りと社会学的な抽象性や一般性を持った「個人」ではなく、固有の地域や家族との関わり合いの中から生まれ育ってきた具体性を持った生身の「個人」ということを考えないと解けない問題がある、スルーしてしまう微妙な問題があるということだろう。普通は、「個人」という時、その抽象性と具体性とが二重化した形で使われているような気がする。
たとえば、批評を含めて、文学作品を読み味わう場合、その時代性としての共通する個人とともに、作者固有の個人も考えないと深い所までたどれないということだろう。
以下の1.と2.を上の「固有値としての自分」(個人より狭い「固有の個人」)の背景として置いてみると、ひとつながりの関係が、イメージできるように思う。
1.『言語にとって美とはなにか』(「試行」連載は、1961年から1965年。初めての単行本Ⅰ・Ⅱの刊行は、1965年。)より
わたしがここで想定したいのは、・・・中略・・・言語が発生のときから各時代をへて転移する水準の変化ともいうべきもののことだ。
言語は社会の発展とともに自己表出と指示表出をゆるやかにつよくし、それといっしょに現実の対象の類概念のはんいはしだいにひろがってゆく。ここで、現実の対象ということばは、まったく便宜的なもので、実在の事物にかぎらず行動、事件、感情など、言語にとって対象になるすべてをさしている。こういう想定からは、いくつかのもんだいがひきだされてくる。
ある時代の言語は、どんな言語でも発生のはじめからつみかさねられたものだ。これが言語を保守的にしている要素だといっていい。こういうつみかさねは、ある時代の人間の意識が、意識発生のときからつみかさねられた強度をもつことに対応している。
もちろんある時代の個々の人間は、それぞれちがった意識体験とそのつよさをもっていて、天才もいれば白痴もいる。それにもかかわらずある時代の人間は、意識発生いらいその時代までにつみかさねられた意識水準を、生まれたときに約束されている。これとは反対に、言語はおびただしい時代的な変化をこうむる。こういう変化はその時代の社会のさまざまな関係、そのなかでの個別的な環境と個別的な意識に対応している。この意味で言語は、ある時代の個別的な人間の生存とともにはじまり、死とともに消滅し、またある時代の社会の構造とともにうまれ死滅する側面をもっている。
(吉本隆明『定本 言語にとって美とはなにか』P46-P47 角川選書)
2.『「すべてを引き受ける」という思想』(2006年7月~10月の対談・吉本隆明/茂木健一郎)より
まだ熟した考えではありませんが、最近ぼくはこんなことを考えています。
人類史というのは、人間がおサルさんと分かれたときから現代までずっと続いていて、ふつうはわれわれの身体の外にある環境(外界)、つまり政治現象や社会現象などの歴史も一応、「人類史」と考えられています。ところが、このあたりのことをもう少し細かくいうと、これまで考えられてきた古代史以降の環境の歴史というのは、いわば文明史あるいは文化史にすぎない。人類史全体ではないということになります。したがって人類史を探るにはやっぱり人間がおサルさんと分かれたところまでさかのぼる必要があるのではないか。
それからもうひとつ、「人類史」にはそうした人類史のほかに、もう一種類あるのではないかということを考えています。別種の人類史とは何かといえば、個々の人間がそれぞれの身体性のなかにふくんでいる人類史です。個々の人間の身体性の範囲のなかで行われる精神活動や身体の運動性は人類史を内包していて、文明の移り変わりとか社会の変遷といった一般的な人類史とは別個のものとして考えられるように思います。
そうしたふたつの人類史を媒介するものが、身体性の順序からいえば、種としての遺伝子の変化、風俗習慣の変遷、地域的差異に基づく言語の発展の仕方の違い、文明・文化の進展具合と、その根底にある自然へのはたらきかけ方……これをつづめていえば、種、住んでいる地域的環境、言語、この三つがふたつの人類史を媒介している。いまはそんなふうに考えています。
(『「すべてを引き受ける」という思想』 P70-P71 対談・吉本隆明/茂木健一郎 2012年6月)
歴史というと、前にもいいましたように、未開や野蛮な時代からどのように進展してきたか、すなわち文明・文化の進歩の度合がどうなっているかといった「外在史」を意味するのがふつうですが、個々の人間の身体性もそれぞれ現在までの人類史を内包しています。身体性の順序でいえば、種としての遺伝子の変化、風俗習慣の変遷、地域的差異に基づく言語の発展の仕方の違い、文明・文化の進展具合と、その根底にある自然へのはたらきかけ方……といったものが、身体性の「内在史」と、ふつう一般にいわれる「外在史」としての歴史を媒介する項目だと思いますが、この媒介項が「思想」だと、ぼくは考えたわけです。
言い換えれば、思想は、種の問題や遺伝子の問題を別とするなら、かなりの程度において地域的差異に基づいている。ひとつは地域的な風俗習慣の違い、もうひとつは地域的な言語の違いで、主としてこのふたつの差異に基づく考え方の違いと言えます。
( 『同上』 P192-P193 )
だからぼくはいま、おサルさんと分かれたときからの歴史をやる以外にないよと考えているわけです。そうすればはっきりと見通しがきくというか、これから未来のことについてもわりあい誤解・誤用が少なく観測できるはずです。それ以外のやり方では、世界がどう展開するか、ちょっとわからないのではないでしょうか。また、わかるようにいってはダメだともいえます。ましてマルクス主義のように情況論だけしかないのはもうダメだ。つまり精神の問題として、あるいは精神活動の問題として、人間の歴史をぶっ通しにわかっていなければ多分間違えるだろうと思います。これが、ぼくがフーコーと対談したときに思ったことであり、それを契機にして考えはじめたことです。
( 『同上』 P179 )
※ この対談は、茂木健一郎の「まえがき」によると、二〇〇六年七月~十月にかけて行われたものとある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 732 |
無限遠点からの視線の獲得の意味 |
「マス・イメージからハイ・イメージへ」 |
講演 |
『吉本隆明の183講演』 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
1987.7.16 |
A101「マス・イメージからハイ・イメージへ」の「講演のテキスト」より 吉本隆明の183講演 フリーアーカイブ
講演日時:1987年7月16日
※収載書誌:河合文化教育研究所『幻の王朝から現代都市へ──ハイ・イメージの横断』(1987年)
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人工衛星にによる地上900kmから地上百数十kmとかの範囲の軍事的いえば制空権のしのぎ合い |
無限遠点からの視線を一般大衆が獲得したら、それは具体的じゃないですけど、一種の理念的には、米ソというか、両大国というか、そういう軍事大国を超えたことになります。 |
一般大衆のレベルとして、それを獲得したときには、その手の理念というのは、だいたい遥か下のほうになってしまうんだ。つまり、遥か時代遅れなものだということがわかってしまうんだということ |
|
項目
1 |
①
10 権力の解体に向けて-無限遠点からの視線(引用者註.講演のテキスト本文の小見出し)
もうひとつは、文学というのは、言葉の芸術なんですけど、文学というのも、一種の高次映像の論理から、逆に文学というのを照らし出すことができないか、それから、もっと基本的にいいますと、言語、あるいは、ほんとは学問じゃないですから、言語学といいませんけど、言語の問題というのが、やはり、高次映像の問題から逆に展開したり、また、解析したりすることができないだろうかということの、ぼくなんかのハイ・イメージ論のテーマになってきたわけです。
そういうテーマで現在もまた展開しているところではあるわけですけど、やってみないとどこまでできるかというのはわからないわけですし、この場合のように技術的に、ここでは、民間の一介の物書きには、技術的にいってここで止まりだといいますか、これ以上のことは、組織といいますか、そういうあれがないとか、学校とか、そういう場所がないと、それ以上のことはできないよといいますか、技術的にここでストップだと止まってしまうテーマももちろんありますし、それから、理論的にといいましょうか、じぶんの考え方が至らなくて止まってしまうというようなことも、もちろんあるかもしれないわけなので、そこのところももちろん、まだどこまでやれるかということはわからないのですけど。それが大きなテーマになっていったわけです。
②
もうひとつ、申し上げますと、これは一種の理念的なテーマになるわけですけど、現在、ランドサットの映像は、先ほど申し上げました、地上から900kmのあたりで飛びながら映像をつくっているというようなことになるわけです。それで、これはランドサットですからアメリカの人工衛星です。そういう地表の映像を通過したときに撮っているわけですけど、もちろん、これは軍事映像としても、もちろん使えるわけです。
たとえば、軍事映像の場合、ぼくはデータだけしか知りませんけど、『宇宙から見た日本列島』という本ですけど、この本に書いてありますけど、軍事映像の場合には、150kmぐらいの上空から15cmくらいまでなら見えるという、たとえ話がここに書いてありますけど、静岡から東京にあるラグビーボールぐらいの大きさが点としてなら見えるという、そういう緻密なものです。だから、そういう軍事的な目的にも使えるわけだとおもいます。
そうすると、こういう鳥瞰視線といいますか、それが900km上空であれ、150km上空であれ、上からの鳥瞰映像というものの機能が実に多種多様であるわけで、もしそれを現在のように軍事的に対立している、典型的なのはアメリカとソ連ですけど、アメリカとソ連がこういう鳥瞰映像の得られる人工衛星についていうならば、地上900kmから地上百数十kmとか、その範囲の軍事的いえば制空権をどっちがとるかというのが、たぶん、軍事大国であるアメリカとソ連の、現在の、ぼくらにはわからない、しのぎ合いといいましょうか、競争の競り合いの舞台になっているんだとおもいます。
ところで、ぼくらが富士通館の映像では、瀕死の人間の映像から、ぼくらが考えました、上から垂直に下ってくる視線が同時に加えられているという、その視線というのは、どういう視線かといいますと、イデアールにいいますと、理想的な視線として設定しますと、それは無限遠点ということになります。無限遠点から垂直におりてくる視線というのが、ぼくらが理論的に設定した視線であるわけです。
ですから、軍事大国である米ソは、いずれにせよ、900kmから150kmか、そこらへんの範囲で争っているということになるわけで、こんなのは、両方とも否定したほうがいいとぼくはおもいますけど。両方とも否定するにはどうしたらいいんだというのを、鳥瞰視線だけについていいますと、ようするに、無限遠点からの視線というのはありうるんだということ、考えうるんだ、ありうるんだよということ、それから、それは人間の立体的な視覚像に対して、同時に行使されるという、そういう無限遠点から下ってくる視線というのはありうるんだということを、もし、もちろん皆さんが獲得し、それから、皆さんが獲得するだけじゃなくて、川崎徹流にいえば一般大衆ですけど、一般大衆が無限遠点から上のほうからくる視線というのが、人間の立体的な目の高さの視線に対して、同時に行使されるという、そういう映像は作れるんだし、可能であるし、それから、そういうところから見るという見方というのは成り立ちうるんだよということを、もしそういう人たちが、一般大衆が獲得したら、そうしたら、それは具体的じゃないですけど、一種の理念的には、米ソというか、両大国というか、そういう軍事大国を超えたことになります。超えられたことになります。ぼくはそれを求めます。
皆さんはもちろん簡単に、いまでも、それからまた、大学に行かれたらすぐにそういう視線は獲得する可能性を持てるでしょうけど、知識的にも持てるでしょうけど、そうじゃなくて、ごく普通の人が、そういう無限遠点からの視線から見ると、ようするに、米ソの900kmから150kmで争って、どっちが大国だとかいっている、そういうあれなんていうのは、だいたい下のほうに見えるんだよという、一般大衆がそういう視線というのを獲得していったとしたら、それはつまり、理念としては究極の理念であるわけです。
そうなったら、理念的といいますか、理論的にはその手の軍事大国の対立が醸し出している様々な緊張と歪みと、それから、共犯関係と、それから、対立関係とが醸している様々な問題というのは、ぜんぶ理念的にだけならば、それで解体してしまうというあれで、ぼくらだけがそれを持ってたって、ちっとも解体しないわけです。
だけれども、一般大衆のレベルとして、それを獲得したときには、その手の理念というのは、だいたい遥か下のほうになってしまうんだ。つまり、遥か時代遅れなものだということがわかってしまうんだということ、一般大衆にわかってしまうんだということ、そういうことが理念というものの究極のひとつのあり方だというふうに、ぼく自身は考えております。
だから、そういうことも映像は物語るわけです。この映像を相対化することによって、そういう視線というものを獲得しようとおもえばできるわけですし、そういう問題というのもつながっていくわけです。
残念ですけど、現在のところ、皆さんがうんと勉強されていい学校に行かれても。そこで流行っている考え方はどっちかです。つまり、アメリカ的であるか、ソ連的であるか、アメリカシンパシーであるか、ソ連シンパシーであるかというのが、だいたい全体的にそのどっちかじゃないかとおもうんですけど、だから、あんまりよくはないです(会場笑)。
でも、そんなことを言うと、意欲を失くしてしまうから、うんと勉強されていい学校に行かれて、そうすると、いい学校にどの程度の先生がいるかという、どの程度の考え方の人がいるのかというのが、よくわかりますから、それは非常に貴重な体験だとおもいます。河合塾の先生のほうがいいかもわかりませんから、それはそういうことを体験されたほうがいいとおもいますけど。
③
このハイ・イメージ論の問題というのは、依然として、ぼくは、イメージとしてはどこが究極かというようなのがわかるような気がしますけど、現実はなかなかそういうところにいかないのであって、その前で、様々な問題が起こったり、様々な歪みが起こったりしているのが現状だっていうふうに、ぼくにはおもわれます。
しかし、理念として、あるいは、理論としてならば、その問題は解くことができるわけですし、また、それは自分たちの力量にもよりますから、どこまでできるかわかりませんですけど、しかし、その問題は、ぼくらにはひとつの大きな主なテーマのひとつですから、その問題をこれからもできる限りは展開していきたいと考えております。
皆さんのほうも、うんと勉強されて、目的の学校にいかれて、まだもって勉強されて、もっと先までいっていただけたら、大変よろしいんじゃないかとおもいます。そんなに勉強されなくてもいいんですけど、それはしかし、勉強しなくてもいいという建前で塾にいるというのは矛盾でありますから、勉強するという建前で、あくまでも頑張って勉強されて、やっぱりでも、どこが壁なのであるか、それから、壁を超えたら、どこにまた壁があるのかということについていいますと、それはちょっとキリがないですから、ここで終わりみたいなことは、その手の問題はありえないですから、だから、やれるんだったら、どこまでも先へ先へといいましょうか、あるいは、どういう恩恵を受けるかわかりませんけど、先へ先へ勉強されていってくだされば、たいへん、ぼくらはつまんない話をしたけど、すこしぐらいの意味があることになります。どうかなんか頑張って、うんと勉強していただきたいというふうにおもいます。いちおうこれで終わります。(会場拍手)
(A101「マス・イメージからハイ・イメージへ」の「講演のテキスト」より 吉本隆明の183講演 フリーアーカイブ)
講演日時:1987年7月16日
※収載書誌:河合文化教育研究所『幻の王朝から現代都市へ──ハイ・イメージの横断』(1987年)
|
備
考
|
(備 考)
関連として、
そもそもテクノロジーの役割というのは「一部の特権階級だけが独占していた能力を民主化すること」にほかなりません。
(佐藤航陽『世界2.0 メタバースのあり方と創り方』P63 2022年3月)
ここで吉本さんが、米ソの人工衛星による軍事的な制空権争いを無効化する無限遠点からの視線を一般大衆が獲得したらということは、吉本さんが断っているように具体性としてではなく理論的な形で語られている。具体性のイメージが欲しいところだ。以下の記事は、その具体像にあたっていると思う。
グーグルマップでロシアの「軍事施設」が丸見えに
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から約2カ月(掲載当時)。当初、2日以内に首都キーウ制圧を目指したプーチン大統領だが、思い通りにいかなかった。4月21日には、南東部マリウポリを制圧したと宣言したが、ウクライナ側は認めず、苦戦が続く。そんなプーチン大統領の焦りと苛立ちを加速させているのは、21世紀に飛躍的に発展した「衛星画像」「SNS」という2つのテクノロジーだ。
「ロシアの軍事施設がはっきり見える」「OSINT(オープンソースインテリジェンス、オシント)しよう」――。4月下旬、こんなツイートと衛星画像がまたたく間に世界に拡散した。
オープンソースインテリジェンスとは、公開された情報を突き合わせて分析すること。衛星画像をもとにロシアの軍事能力を皆で分析しようというSNSの呼びかけは、ロシアにとってはさぞ腹立たしいものだっただろう。
きっかけとなったのは、ウクライナ軍を名乗るツイッターアカウントによる投稿だ。グーグルの地図サービス「グーグルマップ」で「誰もがさまざまなロシアの発射装置、大陸間弾道ミサイル」などを「約0.5メートルの解像度で見ることができる」とツイートし、戦闘機や艦船が鮮明に写った高解像度の画像とともに公開した。その後、このアカウントは停止されたが、くっきりとした画像のインパクトは大きかった。
衛星の威力がプーチン氏の狙いを打ち砕いている
衛星画像とSNSは、ロシアにとって大きな脅威になっている。
ウクライナへ向かうロシア軍の車列、キーウ近郊のブチャ路上に放置された多数の遺体などの画像が次々と公開され、ロシアが何をしようとしているか、あるいは何をしたのか、どれほど残虐なことをしているのか、などが目に見える形で人々に示される。
この多数の遺体をめぐってロシアは、ウクライナ側の「挑発だ」と応酬。「ロシアがブチャを掌握していた時に、地元住民が暴行を被るようなことはなかった」と主張した。
だが米メディアなどが衛星画像の撮影日時を分析し、ロシア軍がブチャを占拠していた時にすでに遺体があった、と判定。ロシアの主張が虚偽であるという見方が世界に広がった。
4月21日には、マリウポリの市長顧問が、「死亡した住民が大量に埋められた場所を長い時間をかけて捜索・特定した」と通信アプリ「テレグラム」に投稿。メディアも衛星画像つきで、多数の墓と見られる穴が発見されたことを報じた。ロシアが民間人攻撃を隠蔽(いんぺい)するために、ここに埋めた可能性があることが分かった。
宇宙から地上を監視する衛星の威力と、それを世界に拡散するSNSが、プーチン大統領の狙いを次々と打ち砕いている。
ロシア海軍黒海艦隊の旗艦「モスクワ」がウクライナ沖で沈没した、と4月14日にロシアが発表したのも、隠していてもいずれ衛星画像付きで報じられると考えたためとみられている。
・・・中略・・・
「マクサー・テクノロジーズ」の一人勝ち状態
かつては地上の3~5メートルの物体を識別できるレベルの画像が軍事機密になっていたが、今では商用でも数十センチの物体を識別できる。ひと昔前なら軍事機密レベルのものが、商用画像として世界の人々の目に触れる。米国家地理空間情報局は、少なくとも200の商業衛星の衛星画像を使用しているとしており、膨大な数の衛星画像が毎日生まれている。
自社の保有する衛星で地表を撮影し、その画像を販売している会社は多数あるが、今回、圧倒的な強さを見せているのが、米マクサー・テクノロジーズ社(本社・米コロラド州)だ。地上30センチの物体を識別できるといい、商用としては最高レベルの画像を誇る。メディアの話題をさらっている衛星画像のほとんどは同社のもので、一人勝ち状態になっている。
同社は、「通信、地図作成から防衛や諜報(ちょうほう)まで、世界中の数十の業界にサービスを提供している」「米政府の不可欠なミッションパートナー」などと自社の業務を説明している。
1992年にデジタルグローブ社として発足し、合併などを経て、2017年に現在の社名に落ち着いた。ダニエル・ジャブロンスキーCEOは、宇宙関連シンポジウムで、ロシアの軍事侵攻後、米政府機関からの衛星画像の需要が倍以上に増えたことや、報道機関からも1日に約200件の需要がある、と語った。
米国の“援護射撃”にプーチン氏は苛立っている
今回、米国は衛星画像が拡散することを望んでいるようだ。
ステイシー・ディクソン米国家情報長官代理は4月、「米政府は商業画像を細かく管理していない」「世界で起きていることをもっと共有したい」と発言した。ウクライナへの支援、民間企業振興に加え、21世紀の新しい「武器」という意識があるのだろう。
かつては軍事機密レベルだった詳細な衛星画像が公開され、宇宙から丸見えになるリスクを伴う時代に行われたウクライナへの軍事侵攻。そのもたらしたものに、プーチン大統領は苛立っていることだろう。
当然ながらウクライナ側の動きも衛星で見られている。4月上旬にポーランドが保有する旧ソ連製戦車などが、ウクライナに向けて車両で運ばれる様子を撮影したとされる映像がSNSで出回った。
一方、衛星は地上のすべてを絶えず撮影できるわけではない。北朝鮮は、米国などの衛星が自国の上空を飛行する時には、ミサイルや発射台などに覆いをして衛星から見えるのを防止しているという。宇宙からの目をだますこともできるのだ。
相互監視ともいえる時代。どのように衛星画像を活用、あるいは宇宙から丸見えになることを防御していくか。戦略が重要になっている。
・・・以下略・・・
(プーチンの嘘を次々に打ち砕く…ロシアの軍事機密を丸裸にする「民間衛星会社マクサー」の超技術 初公開日:2022年4月28日 プレジデントオンライン 知野 恵子)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 734 |
技術とは何か |
「私の青春時代 ― 技術者として」 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集182』 |
猫々堂 |
2019.1.30 |
初出 ※『Think tank 〔LAB〕』第4号 1986年9月10日発行
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 技術者とは手仕事のイメージ |
観念の体系が技術の本質 |
技術とは観念の働きで、その起源は、一種自然力に依存している。自然力の延長上に根ざしている。 |
|
項目
1 |
①
技術者とは手仕事のイメージ(引用者註.これは、本文の小見出しです。)
―― 当時の吉本さん達の若い頃の技術者のイメージっていうのは、具体的には、どういう風なイメージでしたか。
吉本 完全に手仕事のイメージなんですね。そこが僕らの技術者としての時代性、年代性の限界だとおもいます。
つまり、化学っていうのは、特にそうなんですが、技術者は、工場にいて、実験はこういう風にやろうっていう計画を立てて、手仕事で実験装置を組み立て何時間、何度で反応させて、とか、根気よく実験を手仕事でやる。それを結晶させて取り出したとか、そういうことを文献を調べてやって、うまく出来た時には、少し大きな装置で、現場でやつてもらう、そういう型が技術者のイメージなんです。
だから、手仕事のイメージから外れてしまうと、技術者ではないみたいな感じに、どうしても捉われるんです。 机上で装置を操作しているとか、大きな電子的装置の前で自動制御しながら観察していればいいとか、そういうことは、どうしても技術者のイメージにならないですね。
「手仕事の現場を離れたら技術者ではない、それで第一線の生命はそこで終わってしまうんだ」っていうイメージが強く僕らには、頭に叩き込まれていたと思います。
現場にいて、あくまでも、手仕事で装置を組み立てて、実験して、結果を出して、それを現場で、少し大きい規模で実行していく、そういう技術者のイメージは今ではまるで違うんだと思います。
化学っていうのは、どうしても手仕事の部分がないことはないけれど、メインな部分ではなくなっているように思えます。やっぱり、装置の面で、自動化されている部分がとても多くなっています。
だから、そこがまるで違うんじゃあないでしょうか。僕らが手仕事と思っていたことが、今は、自動的に出来上がった装置で、あるいは電子的な装置で出来ているから、多分手仕事の部分はないことはないでしょうが、技術的な要じゃないという気がします。
だから以前技術者がやっていたことは、ほとんど現在工員さんがやることになって、技術者っていうのは、デスクワークじゃあないでしょうけれども、プランナーといいましょうか、「企画を練る人、作る人」みたいなものに変貌しているんじゃあないでしょうか。
②
自然力に依存する〈幻想〉の体系としての技術(引用者註.これは、本文の小見出しです。)
―― 技術とは、一言で言うと何ですか。
吉本 これを定義するのは、たいへん問題なんでしょうが、僕流の言葉で言えば、技術っていうのは「幻想」なんじゃないでしょうか。つまり観念の体系です。観念の体系が技術の本質であると僕には思えます。
だから、技術とは、物のシステムでもなんでもない。物のシステムとは、物のある具体的な顕われではありましょうけれども、技術の本質ではないような気が致します。
技術とは観念の働きなんで、観念の働きの由来といいますか、原因といいますか、起源といいますか、そういうものは、一種自然力に依存しているのです。一般の観念―精神的なものとか、心理的なもの―と違うのは、そのへんの所だけで、観念の働きであることには変わりないように思えます。
ただ、より自然力の延長上に根ざしていることだけが違うと思います。
(「私の青春時代 ― 技術者として」P91-P93、『吉本隆明資料集182』猫々堂)
※『Think tank 〔LAB〕』第4号 1986年9月10日発行
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
まず、吉本さんが化学技術者だった時代の手仕事のイメージだった技術者像から、現在はその手仕事が「机上で装置を操作しているとか、大きな電子的装置の前で自動制御しながら観察していればいいとか」、別の形に置き換わって、技術者の仕事のイメージが変貌していることが語られている。
次に、技術の本質を問われて、「技術とは、物のシステム」と見えたり捉えたりしがちだが、そんなものではなくて、技術の本質は観念の体系だと思うと語られている。
わたしなりにこのことを捉え返してみる。
何でもいいけど、例えば稲作の田んぼに水を導き入れる技術にしても、
①まず水源に近いところに田を作る。
②次に、斜面の田やそうでなくても、水を田に次々に導き入れるためには田に段差があった方が望ましい。
③田に水を保持したり効果的に水を流して行くにはどうしたらいいか。取水口や排水口の形や取り付ける場所。
このようなことをあれこれ知恵を出し合って考えて(観念的な作業、ひとつの観念の体系)、水を導き入れる実際の工事に取りかかる。もちろん現実的には、後者からの前者へのフィードバックやそこからの修正もあるだろう。実際の工事などを見ると「技術とは、物のシステム」と見えがちだが、それは技術が実践されるまでの過程の一部に過ぎない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 736 |
家族の現在 |
現在への発言「家族・老人・男女・同性愛をめぐって」 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集182』 |
猫々堂 |
2019.1.30 |
初出『吉本隆明が語る戦後55年』第10巻 2003年3月10日発行
聞き手 内田隆三・山本哲士
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 三世代同居がいまでも理想的な状態になっている |
西洋でそういう理想をいえば、たいていのご老人たちは、ずばりそれは宗教だというんですね。 |
家族あるいは家庭の形態というのは、いかなるものをもって理想とするか |
|
項目
1 |
①
吉本 いやあ、大変難しいことを考えてるんだなあと思って、いまお話を聞いていたんですが、僕は実感的なことだけでとくにそんなふうに考えたことはないんです。あなたがおっしゃる「家庭」が、どういう意味で使われているのかわかりませんけれども、「家族」という概念でいえば、それは壊れかかっているなあとか、いやもう壊れたとか、そういうことを思いますね。
家庭といわずに家族というのは何かというと、男女の対幻想を核とする関係の世界ということになります。一対の男女を核として、一世代後の子ども世代があり、一世代前の世代があり、この三世代が一つの家庭として同居することは、いまではめったにないわけです。しかし、日本人の生涯を考えると、三世代同居がいまでも理想的な状態になっていると思います。アンケート調査などから見ると、それはかなりはっきりしています。日本だけじゃなくて、広くいえば東洋ではそれが理想だとなっているように思います。
とくにご老人だったら、それはなおさら切実な問題ですね。三世代同居の生活なら、自分が暇なときは孫の相手をして遊んで、ということがあり得ます。それが宗教の代わりというと少し飛躍しすぎなんですけども、ご老人ならご老人の親愛感の理想になっていて、これはいまでもアジア的な社会に共通することだと思います。
西洋でそういう理想をいえば、たいていのご老人たちは、ずばりそれは宗教だというんですね。宗教だという人が一番多いんですよ。これは、我々の実感では不可思議なことですが、おそらく世界的な規模でいえば、老人の理想的な状態は宗教に求められているといったほうがいいと思います。宗教を介してお年寄りと孫の世代のきずなを深め、その中間にいる家族の中心である夫婦のきずなを深めていく、そうすると一番けりがつきやすいんだ、ということになっていると思うんです。
(「家族・老人・男女・同性愛をめぐって」P42-P43、『吉本隆明資料集182』猫々堂)
聞き手 内田隆三・山本哲士
初出『吉本隆明が語る戦後55年』第10巻 2003年3月10日発行
②
吉本 核家族というか、夫婦の同居だけが家族に重要なことだということが、戦後早くからいわれました。それでいまは、もう親と子の関係にも親和感はほとんどなくなっていて、僕の実感では家族はもうほとんど壊れている、あるいはどこでも壊れそうになっていると思うんです。その最も極端な現れ方が、最近大きな社会問題となっていますが、親が子どもを殺したり、子どもが親を殺したりという事件ですね。直接的な親子ではなくても、親の年代の者を子どもの年代の者が、ちょっとしたきっかけから襲撃して殺しちゃったという事件もあります。
その手の事件の根本にあるのは、家族における親子の距離感が余りにも大きくなってしまったということじゃないかと思います。何よりも親和感がなくなっています。親としての僕の実感でいっても、僕と僕のおやじやおふくろとの間に介在していたような親和感は、いまの親と子どもの間にはないと思えます。それが極端なことになると、親子でも話しもしないとか、もう親子で一緒には住めないという感じになってしまいます。そこからさらに、子どもなんて踏みつぶしちゃっても、夫婦という男女の愛情だけあればいいことになっていって、子殺しというのも出てくるんでしょう。
つまり、家族における親と子の関係のものすごい離反というのがあるわけです。離反とまでいわなくとも、きわめて希薄になってしまっています。なぜそうなったかを実感でいうと、あなたのおっしゃる六〇年代、僕は七〇年前後のことじゃないかと思いますが、そのあたりの時期に急激に日本の社会構成が変わってしまったことに、大きく起因していると思います。時代の変化には、子どもの方は感覚的についていけますが、親のほうはなかなかそうはいきません。それで、親の方から子どもに対して「こうせい、ああせい」とか、「こういうのはよくないぞ」とか、「これはいいぞ」とかいうことが、ほとんどいえなくなっちゃったと、僕の実感ではそう思います。そんなふうにいえなくなったし、いってもムダだと感じるしかなくなったと思います。
そうなると、年をくったときに、子どもが自分の身体の不自由というか老齢の不自由さをうまくカバーしてくれるとは、ちょっと期待できないな、となってきます。それくらい親と子の関係は離れてしまった。
(「同上」P44-P45)
③
吉本 一世代前の僕らの世代だったら、親から「こうせい、ああせい」と何かにつけていわれたもんです。それで「おやじは、なんてわからんこといってんだ」とか文句をいいながらも、そういう親の権威とか経験というのを何となく認めていたような気がします。でもいまの僕に、僕の親がそうだった程度の権威があるかといったら、何もないというしかない。ただ「子どもはこういう気持じゃないか」とは、なんとなく自分なりに推察するんだけれども、それはあってるかどうかもわかんないし、ましてや子どもに「ああせい、こうせい」とか「こう生きろ、ああ生きろ」なんてことは、まったくいえなくなっちゃっています。
もう少し前の距離感では、子ども世代への違和感は、それほど強くはなかったんですけど、いまの距離感では、「そんなこといったって、だいたい通ずるわけがねえや」って(笑)、はじめからそう思ってるからいわないんです。いわないだけじゃなくて、いえないですね。「そんなことはしらねえ、勝手にしろ」とか「勝手に生きろ」というほうが、自由度からいっていいのかなって思っていますが、ある意味では逃げているといえば逃げているんです。どっちにしても、真っ正面から向き合って「お前こうしろ」とか「お前のこういうのはよくねえ」とか、そういうことをいう権威がこっちには、まるでなくなっちゃっているんですね。
(「同上」P45-P46)
④
吉本 僕は必然的にそうなったと思っています。家族あるいは家庭の形態というのは、いかなるものをもって理想とするかと考えていって、それが終局までいって、これ以上の家族の有り様はないよという所を考えると、全然そこまではいっていない。さればといって、一世代前まではかろうじてまだ残っていた家父長の権威というのは、もはやほとんどなくなっている。ちょうどそういう地点に、日本や先進的な社会は立っている、ということじゃないんでしょうか。
僕には、もう家父長の権威がないというのは実感的にわかりますね。先にもいいましたが、僕の親たちはこどもに対して「こうしろ」ということをいい続けてきました。それに対して、子どものほうには「それは間違いだ」とか「そんなのは嫌だ」とかいう反発はありましたけれども、制度がもたらす権威といいましょうか、家庭の長に対する権威というものを認めていました。でもいまは、どんなに子どもや家庭に対して理想的な思い入れをもっている親でも、まず権威だけはないんです。よくて、友だちみたいなもんだというところです。つまり家父長の権威だけは、はっきりとなくなってしまった。それじゃあ、家父長の権威がなくなった後、家庭的あるいは家族的に何があるんだというと、かろうじて夫婦の対幻想だけがある。あるいはそれを一番重いとする考え方だけがあるというしかないわけです。これが家族としては一番強いといえば強いのかもしれません。
(「同上」P47-P48)
※②と③は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
①の出だしにある吉本さんの言葉、「 いやあ、大変難しいことを考えてるんだなあと思って、いまお話を聞いていたんですが、僕は実感的なことだけでとくにそんなふうに考えたことはないんです」。これは、吉本さんが家族や対幻想などの現在や未来について、主要に日々の生活者の実感から感じ考え反芻していることを示している。
ここに切り出した部分は、家族や対幻想の現在が具体性として語られていて、誰もが思い当たるものだと思われる。そして、現在を生きる者はみなその渦中にある。また、吉本さんが語っている、制度として家父長の権威があった時代から現在の兄弟関係みたいなフラットな家族関係への転換は、わたしにも実感的だが、同時代にあっても世代によってその家族や対幻想の分節や転換の体験は一様ではない。特に若い世代ほど現在の有り様しか知らないということになりそうだ。
少し前、SNSで男の家父長制的な権威とか権力性を追求するようなフェミニストの言葉に出会ったことがある。わたしには、今どき家父長制的な権力性とか関係ないだろうと思った覚えがある。これを好意的に理解しようとすれば、家父長制的な権力性が制度として廃止されても、男は長らく男中心社会ともいうべきものの具体性になじみ自然性として身に染みてきたものが今なおあるはずだという主張なのかもしれない。それは、家族内での食事当番の意識ひとつとってもありうるような気がする。しかし、そんなことを突(つつ)けば、それ以前には人類の生み出した知恵でもあるだろうが母権制社会が長らく続いてきていたという事情もある。そうして深く突いていくほど、男と女の問題は難しい曲面になりそうな気がする。
わたしたちの現在が人類史の紆余曲折の歴史性の負荷を免れることはできないとしても、それぞれが自らの家族や職場などで、現在的な〈平等〉の観点から具体的に解きほぐすしかないように感じる。
それは、家族や対幻想がどこへ向かうのかはよく見えないとしても、わたしたちの家族の現在への対応についても同様だろうと思う。
|
聞き手 芹沢俊介
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 原始・未開時代の化粧の仕方の根本的なモチーフ |
自己表出の変位とともに化粧への意識も変位してきた |
動物的な自然性と超越的なものへの志向 |
動物性にたいする異和感 |
項目
1 |
①
吉本 ところで、化粧とはなにかということをかんがえてみますと、たとえば、原始時代に、変な色を目のふちに塗ったり筋をつけてみたり、真っ白いのを塗ってみたり ―男も女も、とくに女の人はそうかもしれないけれど― そういう化粧があったでしょう。あるいは、もっと極端にいえば、入れ墨をするというのがあったでしょう。それはなんなのかといったら、信仰(宗教)に帰着するわけです。どっちが神(宗教的な対象)に近づきやすいかということで、化粧が決まってくるということがあるわけです。もっと普遍的な云い方でいえば、化粧とは自己表出なんだ。そして、宗教的な段階まで自己表出を高めるといいましょうか、尖鋭化してしまうというのが、原始・未開時代の化粧の仕方の根本的なモチーフだったとおもいます。
ところが、そういう自己表出はどんどん宗教性から脱却して、共同体の原理に(神に代わる宗教性として)向かうのですね。そして、それが解体していけば、次に一対の男女にたいして向かうわけです。そこでの自己表出が誰を対象とするかといったら、女性なり男性なり、異性なんですが、でも、女性が男性のためだけに化粧するのかというとそんなことはなくて、たぶん、自己表現にちがいないとおもいます。でももはや、神とか共同体を対象として化粧するということはなくなっていく。
そういう段階を経て、究極的にじぶんのために化粧することしか残らなくなったなら、化粧してもしなくても同じじゃないかということになっていく。でも、たぶん、そのなかから、また、新しい宗教性(現在のところ、なにが新しい宗教性かということはわからないけれども)でしか立ち向かえない差し迫まったものがある気がします。
たとえば、嫌煙権を称える人などがとても身近に差し迫ってきている。公害問題とかも、全部そうです。つまり、食物のなかに零点何グラムなにが入っていたということがたいへんなことで、食べる物も安心して食べられないぞということも、ある共同性をもって云われるようになってくる。そうするとそうとう緊迫とした情況になってくる。おまえ、たばこを吸ったら、おれは気にくわない、というふうに云うやつが出てきちゃったら、どうしようもないくらい緊迫してくるでしょう。
そういうものにたいして、どうしても自己表現せざるをえないことになってきて(たとえば、かつては政治的イデオロギーがいっしょなら、そこのところでやればいいじゃないかというものとしてあった共同性が、そんな共同性なんかからっきしだめだとなると、なんで宗教性というものを保っていくかといえば)、原始時代とは違うけど、そうとう色濃く化粧しないとやりきれないよ、ということがありうる気がするんです。何回でもそういうのが再生してくる。また、それとは相矛盾するようですが、原始時代ならほとんど局部しか隠さなかったのが、だんだん着物を着て被うようになった。それがまた、もう一度、裸のほうが美的だみたいになっていく。いまの女の人が泳ぐときの水着なんかは、ほとんど原始時代とおなじぐらいしか隠していない。それが超近代的なことになっていくでしょう。それは一見、不可解な自己表現におもえますが、しかし何度でも回帰していくでしょう。
そうすると、原始時代の女の人のヌードと、今の女の人のヌードと、どう違うかといえば、たぶん位相が違う気がするんです。けれども、形としてはなにかへ回帰する以外にないので、着ては脱ぎ、着ては脱ぎする以外にないし、化粧だって、塗ったり落としてみたり、それ以外の循環の仕方はないわけです。ですから、それは循環するでしょうけれども、その意味はそれぞれの時代によって違いましょう。
だから、化粧するとか飾るとかいうことが、どこまで無意識な自己表出で、どこから意識的な自己表出になるのかは個人的な差異もあるでしょうし、さまざまでありうるわけです。ただ時代的な水準を想定すれば、ある共通の時代的な自己表出の水準があって、そこで、化粧や服装の流行の問題とか、美的感覚の水準とかは、一般論として想定できるんじゃないですかね。
(吉本隆明『対幻想 ― n個の性をめぐって』P100-P102、春秋社)
※聞き手 芹沢俊介
②
芹沢 ・・・略・・・つまり、化粧することじたい、身を飾ることじたいにもともと性的なものが含まれているのであって、そういうものが世界の枠組が変化するにつれて顕現してくるのか、あるいは化粧というものが性的な意味をひきよせてしまうのか、そのへんはどうなんでしょうか。
吉本 肉体的に、どういうふうにじぶんを美とみせるかという問題でしたら、動物のなかにすでにあることですね。雌であるか雄あるかということで、身体じたいをある特定の時期に限って、とても美的な目立つ姿を異性にたいしてすることは、自然としての肉体のなかには、すでにあるんだという見方はできますね。だからたぶん、人間の身体の自然性といいましょうか、生理的身体としての男女といいましょうか、そういうもののなかに、異性にたいする肉体による自己表現みたいなものが、自然性としてもうできているわけでしょう。
そのうえに、なぜ布を覆うかとか、首飾りをするかとか、変な色で化粧してその顔をかたどるかという問題は、すでに、エロス的に異性に向かう身体がもっている表現というのとはちがって、一種、超越的なものに向かう表現というふうになるんじゃないですかね。超越的なものは、氏族の神である段階もあったでしょうし、信仰が強固でなくなってしまえば、共同体の規範の象徴である首長とか、そういうものであるばあいもあるわけです。それにたいするひとつの表現として、服装を決めたり化粧を決めたりという自己表現があった。
それが、だんだん共同体規制がなくなって、こんどは自然の身体がもっていたエロス(異性)に向かう。自然表現というものと、自己表現としての服装とか化粧とかを異性に向かって飾り立てるということとは、同じことになっていく。つまり、二重にそういう形で出てくるということにだんだんなっていく。
そういう二重の契機には、動物のときから身体表現がエロスそのものとして存在するのにたいして、いかに人工的なものを加味してそこへ向かうかという過程があるんじゃないでしょうか。
(『同上』P102-P104)
③
芹沢 現在だけでみていると、たとえば化粧品のコマーシャルなんかは化粧は性的表現なんだ、それはいわば異性へ向けての挑発、アピールなんだ、という思想を流通させています。
でも、化粧したり衣装をつけたりすることは、そのような強調であると同時にもう一方で隠していることでもある。〈隠す〉という動機からみるなら、化粧とか服装はまた別の理解の仕方が可能ではないかとおもえるのです。それは、いま吉本さんがいわれた超越的なものへ向かうということと違う局面が出てくることになるのか、ならないのか、そのへんはどうでしょうか。
吉本 化粧とか服装を〈隠す〉という視点からみていくと、換言すれば、動物的なアピール(身体の性的なアピール)というものにたいする異和感とか矛盾とか、としてみられることになるんじゃないでしょうか。逆なことをいえば、動物性からの無意識が、ある文明(あるいは文化)の段階で、どれだけ傷を負ったかとか、どれだけ傷を負った無意識をまた解消したかというようなことが、もし、〈隠す〉ことを主体にかんがえれば、化粧やファッションの問題として出てくることになります。
原始時代に局部しか覆っていなかった(あるいは、局部を覆った)ということのなかには、動物性にたいする異和感みたいなものがそうさしていたということがある。そして、どんどん動物性にたいする異和感の意識が増大していって、ほとんど服装で覆うようになった。ところが、その観点からだけみていくと、少なくとも現在は、女性のヌードというのは、原始時代にほとんど近くなっています。それは〈隠す〉という段階からいえば、隠すことが減ってしまったことです。それはなぜかといえば、無意識の傷(無意識の異和感)がそうとう解消していったという意味になりそうな気がします。だから、特定の時間とか特定の瞬間なら、太古から今まで、動物的にいえば平気だったんだけれども、公共的な場面で隠す度合が少なくなった、あるいは原始時代に近くなったということは、少なくとも、無意識の異和感だけは解消していったということの象徴になるわけでしょう。
芹沢 そのばあい、無意識の傷が解消していくことと、宗教的なものや共同体の枠組が緩んできていることとは、どんな対応関係があるのでしょうか。それから、こういう問題にたいして家族はどういう位置をとることになるのでしょうか。
吉本 無意識の傷が解消していくことは、受胎や生誕から乳幼児期にかけて、部族神や共同体からうけたさまざまな宗教的な傷(たとえば出産、割礼、その他の儀式的な呪縛)を解消したことからはじまります。つまり受胎や出産や割礼や聖人の折目にたいして、部族神や共同体から刻みつけられる聖痕の傷を解消したということでしょう。その問題が解消されたあとで、家族関係からうけとるエディプス的な傷が問題になってきます。べつの言葉でいえば、部族神や共同体からの傷は第一次的なもので、家族内で形成される傷は第二次的なもので、二重の拘束から一重の拘束へ、そして機械的にいえば、無拘束へとゆく過程が描けるとおもいます。
(『同上』P104-P106)
※①、②、③は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
芹沢俊介も批評界を長年渡り歩いて来ていて対象に迫る視点やその言葉の鋭さには感心するが、吉本さんの場合は、上に語られたことからすれば、今まで必死に黙々と渡り歩いてきた全業績の成果が、語られる言葉に込められている。その一貫した透徹した視座には驚くほかない。
「原始時代に、変な色を目のふちに塗ったり筋をつけてみたり、真っ白いのを塗ってみたり」(①)からは、吉本さんが何度か触れたことがある次のことを思い起こした。
吉本さんは、『初期歌謡論』(1977年6月)で、歌の古形、はじまりの形を論じて、それは言われてきた「八雲たつ・・」の歌ではなく、以下のような伊須気余理比売と大久米命の応答歌、問答歌を歌の古形として論じていた。そこでそのような「化粧」の問題が出て来た。
「あめ鶺鴒(つつ) 千鳥真鵐(ましとと) など黥(さ)ける利目(とめ)」(記17)
「媛女(おとめ)に 直(ただ)に逢(あ)はむと 我が裂ける利目」(記18)
1.この部分を読んでいて、鷲田清一のファッションや化粧について述べた文章を思い出した。『ひとはなぜ服を着るのか』や『ちぐはぐな身体―ファッションって何?』を以前読んだことがある。身近でとても難しく見える問題に果敢に取り組んでいるのに感心した。吉本さんも、鷲田清一に触れている。以下の文章である。
2.ALL REVIEWS(書評)より
書き手:吉本 隆明
『モードの迷宮』(中央公論社)
『マリ・クレール』に連載中から、この未知の著作家のファッション論は、感心しながら読んでいた。どこに感心したかといえば、まず姿勢だ。ファッションについてまともに、本格的にぶつかっていることだ。つまり本邦ではじめてまともに本格的に腰をいれてファッションについてかんがえ、論じた文章があらわれたといっていい。いままでも現場ファッション・デザイナーの鋭いメモや感想のたぐいはあった。またいわゆるファッション評論家が年度ごとのファッション・コレクションの動向を紹介し、解説した文章のたぐいはあった。でもそれらはわたしたちがイメージするファッション論とはちがうものだ。わたしたちがイメージする本格的なファッション論はどんなものか易しく言ってみれば、例えばここにモデルが着込んだ一枚のファッション写真がある。それがファッション・ショーの場面のなかの、ひとりのモデルが着込んだ生身の姿態であってもいい。言葉がそのファッションに限りなく肉迫し、その実態をつかみだしながら、しかもそれと拮抗し、緊張関係を保っているようなファッション論が、まず最初に、そして最後に欲しいものだということになる。ファッションは言葉だ、あるいは広義の言葉としての記号だという認識にたっしたファッション論を、日本語で読もうとすると、ロラン・バルトとボードリヤールの訳書しかない。しかもこれらの哲学者たちの論考は、とうていファッション・ショーの現場やファッション・デザインの現場までおりてゆく気はないところで書かれている。それくらいファッションの世界では、「本格的」ということと実態に肉迫するファッション論の距離は距たっている。そしてこの距たりのすべてにわたらなければ、わたしたちのイメージは充たされることはない。もちろんさしあたって「本格的」を志向するだけであっても、一枚のファッション写真や、ファッション・ショーの一場面のモデルに肉迫するだけの言葉であってもいいのだ。
この本の著者がやっているのは、はじめての「本格的」なファッション論だという意味で、とても高く評価さるべきだとおもえる。著者のファッションにたいする基本的なコンセプションは、ファッションとしてみられた衣裳の構造が、裸の魅力を隠すようにしながら、じつはそれを強調する、また肉体の魅力で誘惑しながら、きわどいところで拒絶する、肉体を保護しながら同時に損傷させる、といったような二律背反の作用だという点にある。そしてこの背反する運動がやっと均衡しているところで、ファッションのスタイルが決定されているが、やがて身体がもつ根源的な不均衡のなかに入りこみ、その不均衡に動かされて反復移動してゆく。この基本的なコンセプションは、著者によってさまざまな形で強調されて、この本の背骨になっている。男性のカラー、ネクタイ、ベルトは首や胴を締めあげ、拘束するものだ。だがそれは同時に気品とか儀礼とかに叶うものとされる。女性のタイト・スカート、コルセットなどは腰を締めつけて内臓障害をもたらすほどだし、タイト・スカートは歩くこと、活動することを極端に不自由にする。だがそれは身体の美しさ、人格の貞淑さ、慎み深さを表現するものとされて、十九世紀ファッション史を飾った。こういったファッションのもつ二律背反の構造をつきつめてゆけば、ファッションの原則が、モデルを身体に合わせるのではなく、身体をモデルに合おせるのだということがわかると、この本の著者は強調する。シンデレラ物語は、のこされた靴にあうような足の持主を探し出そうとする王子の願望が発端になるのだし、中国の封建時代の纏足の風習は、幼児のときから足を畸形にまるめて細く小さな靴に合わせようとする飽くなき欲求に発したものだし、日本の吉原花街の太夫おいらんは高く重い木履をはいて、重力の拘束に身をゆだねることが、美と忍従と華やかさの象徴であった。この非合理、拘束と解放の二律背反と共存、禁忌と煽動の背中あわせ、そのあげくに身体を損傷し、内臓が病におかされるまで締めつけて、そのときそれが美であると信じられた。そんな何の客観性もない拘束に身をゆだねる不可能な変形、逸脱、畸形。そうとしかいいようのない美意識に従属してゆく逆説的な本質がファッションだと著者はいう。
もう一度だけ、合計三度この著者はファッションの二律背反と、不釣合、不均衡の根源的な欲求とが皮膚や衣裳の表面で演ずる逆説的なドラマについて伝えている。それは隠しながら見せるということについてだ。胸もとのボタンを外したシャツ、シースルーのブラウス、乳首が浮きでる薄手のセーター、深いスリットの入ったスカート、すれすれのミニスカート、身体の線がくっきりと出るニットのワンピース等々。著者は秘匿さるべきものへの関心を掻きたて、貞淑の焦点を逆に想像させる挑発になっているファッションの原則の例としてあげながら、しだいにファッションの本質を性的な欲望論に結びつける西欧的な衣裳論の系譜に近接してゆく。眼線から眼ざしによる皮膚や衣裳の表面への接触感をふくめて、あらためてこの本の著者のファッション論、禁止と挑発の二律背反を原則とするファッションの変遷と反復の論議をふりかえってみると、それが性的な欲望の禁忌と解放の原則にゆきつくことがわかる。人間はなぜ衣裳をまとい、しかもつぎつぎと衣裳の歴史をファッションとして循環させ反復してゆくのか。それは性的な欲望を挑発し、挑発しながら禁止するという二律背反の作用を実現するためだ。なぜ人間はそんな手のこんだことをするのか。人間の存在の根拠にはたがいに相反するようなふたつの原動機があって、このふたつの根源的な不釣合によって移動し、釣合に達し、またそこから不釣合の方へまた駆りたてられてゆく本質があるからだ。もしこの不釣合と釣合との存在論的な運動を、視線の表面性や性的な欲動の皮膜での眼ざしの接触というところからみていけば、ファッションの本質ともいうべきものに到達する。これがこの本の著者のファッション論の核になっている考え方であることがわかる。この考えはひとつの岐路に立つことになる。ファッションの表現論の方へ下りてゆくか、身体論の一般の方へ上昇してゆくか。そして著者は身体論の方へ上昇してゆくようにみえる。
まず仮面ということ。顔にマスクをつけることは衣裳の類型化を極限におしすすめることと同義だから〈私〉や〈私〉の表情がかくされ匿名化するために「顔さえ隠せば何でもできる」という欲動の解放とおなじことになっている。たとえば秘密の性的パーティでは仮面さえつけていれば、それ以外の衣裳はみんな脱ぎすてることもできるし、またドアのかわりに仮面を備えつけたトイレもあった。これはおしすすめてゆけばエロティシズムの問題に帰着する。秘部=性器自体はエロティシズムを喚起しないし、顔の写っていないヌード写真はべつにエロティックではない。このばあい背反しあう一方のヴェクトルである〈私の〉という禁忌を表象するものが欠けているからだと著者はのべている。そしてもうこのあたりから欲動の表面性と皮膜性から視られた身体論の方へはいってゆく。人間の身体のなかでそこに眼ざしを集中していると妙な気分で、視ている眼ざしの根拠から浮きあがって客体的になってしまう個所があると著者はいう。たとえば脚や髪や生殖器など。著者によればこういう部位は、仮面やマスクとおなじように〈私〉が少ない部分だからだ。髪とか生殖器とかは〈私〉の意志をはみだし、ざんばらになったりぶらぶらしてしまうし、脚は〈私〉の意志とかかわりなくある姿勢で歩きだしたり、とまったりしているようにみえる。そしてひとはなぜコスメティックに髪をセットしたり、マニキュアを塗ったり、ストッキングをつけハイヒールをはいたりしてじぶんの身体を拘束するかといえば、〈私〉の薄くなった身体の尖端の部分を、ことさら際立たせて〈私〉性を回復し、身体の輪郭をはっきりさせようと志向するからだ。このコスメティックな行為が極端になり、病的な領域に入りこんでゆけば、〈私〉の身体から〈私〉を鮮明に確かめようとして、局部を鏡に映してみたり、肛門に物体を突っ込んだり、路上で女性にペニスを見せびらかしたりする行為になってあらわれる。これは眼ざしを行使する方の側からもいえることだ。
いわゆるフェティシズムが脚をつつむストッキング、靴、髪、性器や乳房をつつむ下着などに集中されるのは〈私〉の稀薄なもの、〈私〉のないものと、〈私〉の集約的なもの、〈私〉の濃いものとが、そこで背反的に集まり、その果てに分割され、身体と意味のつながりが破綻をきたすことができるものだからだ。これは身体部位の整形というコスメティックな行為の極限にまで人間の原衝動を走らせることになる。ひとはなぜ整形美容の行為にむかうのか。著者の理解を延長してゆけば、整形美容の欲求には、あらかじめ身体から〈私〉を稀少にしてゆく極限が同時に〈私〉を極大にすることになっている身体像のイメージがあって、それに向ってそれぞれの部位に整形手術がほどこされることだからだ。仮面やマスクをつけ〈私〉をなくしてしまう身体の行為が、〈私〉を解放することがあるように、整形によって身体の部位を入れ替えてしまう行為が、身体の全部にわたったとしても、〈私〉は〈私〉でありうるのだろうか。コスメティックな行為の極限はこの本の著者のかんがえをアレンジしてゆけば、そういう問題にゆきつくことになる。そしてこれは著者によれば反復的ではあるが不朽の問題なのだ。〈私〉が〈私〉を解釈している像と〈私〉が〈私〉としてある存在とのあいだにずれ、矛盾、背反があり、〈私〉が〈私〉の眼ざしをもてあまし、〈私〉の近さと遠さのあいだに不釣合があるかぎり、ファッション行為とコスメティックな身体行為は廃棄不可能な現象だからだと著者は結語のように書いている。
この本の意義深さもおなじところにあると思う。何よりもファッションとコスメティックを不朽の現象として真正面から真摯に本格的に論じて、どこにも悪ふざけやけれんを感じさせない最初の邦書のモード論なのだ。ただ著者がいささか途中で照れたためにファッシヨンの現場の表現論におりてゆかずに身体論一般の方に上昇してしまったが、ほんとは著者みたいな人がファッション・コレクションの現場批評に乗りだす場面を空想したい気がする。
(吉本隆明 『言葉の沃野へ―書評集成〈上〉日本篇』所収 中央公論社)
※ 以下は、山極の発言は、吉本さんも触れている動物性からくる化粧の捉え方に、鷲田の「起源としての化粧や装飾とは、宇宙や大自然を相手にしていたはず」という発言は、吉本さんの触れている「一種、超越的なものに向かう表現」(②)に対応している。
鷲田 本来動物は、基本的にオスがきらびやかなはずです。人類も近代革命が起こるまでは、男の装いのほうが華美だったのです。
山極 おつしゃるとおりで、ファッションの起源をたどればやはり男性、要するにオスですね。ゴリラやライオンでも、オスだけが変更不可能な装飾品を身にまとっていますからね。ライオンのたてがみやゴリラの背中の白い毛などは、取り外しできません。それを人は変更可能なもので補った。それがボディペインティングだったり、羽飾りだったり、毛皮を着ることもそうですね。
鷲田 そういうものを身にまとうことで変身する。
山極 変身すると、それまでの自分とは違うものになったような気分になれます。これは大きな認知革命で、おそらくは言語の発達と軌を一にしていたのではないでしょうか。
(『都市と野生の思考』P150-P151 鷲田清一・山極寿一 インターナショナル新書 2017年8月)
鷲田 僕は昔、化粧をどうして「コスメティック」というのかとても気になったことがあって・・・・・・。
山極 それはもしかするとコスモスですか。
鷲田 そう、コスモスつまり宇宙なんです。コスメティックは、宇宙へのあいさつなんです。現代のコスメティックは、他人に自分の姿をよくみせるための行為です。要するに見せる相手は他者ですね。けれども起源としての化粧や装飾とは、宇宙や大自然を相手にしていたはずです。変身して、人間にとっては恐ろしい他の種の生き物になったりして、とてもパワフルになった気分を味わうというか。変身することで、宇宙にあいさつするというか、あるいは挑発するというか。
山極 なるほどなあ。自分が装飾した姿を見せる相手として、誰を設定しているのかが重要なわけですね。
鷲田 衣服が本質的に持っていた意味としては、社会性よりも先に、宇宙や自然、あるいは他の生命との応答があったのではないでしょうか。その延長線上として、権威ある王様と同じ装いをしてはならないという社会的な意味を帯びてくるようになった。
山極 そう考えると、衣服は神との応答性から生まれた可能性がありますね。
(『同上』P151-P153)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 739 |
〈記憶〉の取り上げ方 |
Ⅴ 心的現象としての発語および失語
Ⅵ 心的現象としての夢 |
論文 |
『心的現象論序説』 |
北洋社 |
1971.9.30 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 〈記憶〉という概念はわたしたちの考察にはそぐわない。 |
フロイドは、人間の心的な領域を、年齢とともにつぎつぎに年輪を重ねていくものと見なしている |
幼児の体験が、心的な現存性としてあらわれるとすれば、かならず〈現在〉の心的なパターンとしてだけ意義をもっている。それは〈記憶〉ではなく心的なパターンというべきである。 |
|
項目
1 |
①
ここで、まず、ひとつの問題がおこる。
〈入院ですか〉という場合、〈です〉というとき前の〈入院〉という言葉の概念を〈記憶〉しているのだろうか?また〈か〉と発語するとき、その前に発語した〈入院です〉という語の概念は〈記憶〉されているのだろうか?
ベルグソンのようにいえば意識の持続の変化する線に沿って〈記憶〉が現在化されることは承知するだろう。しかし〈記憶〉という概念はわたしたちの考察にはそぐわない。
わたしのかんがえでは、このばあい〈入院ですか〉という発語が可能なための条件は、だいいちに〈入院〉という概念の心的な自己抽象の度合、いいかえれば時間化度がある〈水準〉をもち、けっしてたんなる〈点〉でないならば、そしてつぎに〈です〉という助動詞の概念の心的な自己抽象の度合がある〈水準〉にあるならば、……<入院ですか>という発語が可能であるとかんがえる。
もうひとつは〈入院〉〈です〉〈か〉という言葉の自己抽象の時間化度の相異が心的に受容されるならば、〈入院ですか〉という発語が可能であるとかんがえるのである。このばあい〈入院〉と〈です〉と〈か〉のあいだの自己抽象の時間化度が相異していることが、心的に受容されるならば、それは〈変化〉が心的に受容されるために、〈入院〉のつぎに〈です〉がやってきて、そのあとで〈か〉がやってくるというような〈順序〉を可能にするものであるとかんがえられる。つまりかれはこの意味では〈失語症〉ではありえないのだ。
もし、反対に〈入院〉という概念の自己抽象の度合と〈です〉という自己抽象の度合と〈か〉という自己抽象の度合の相異が、心的に受容されないならば、〈時間〉はのっぺらぼうであるために〈入院ですか〉という発言の〈順序〉が不可能である。このばあいには、〈入院〉という発語だけが可能であるか、あるいは発語自体が不可能なものとなるだろう。
このようにして、わたしたちは心的現象としての言語の意味を自己抽象の時間化度の水準であると定義することができる。
(吉本隆明『心的現象論序説』P194-P195 北洋社 1971年9月)
※この文章は、以後大事なことにつながっていくが、ここで引用を止める。
②
フロイドの方法では、人間の幼児期の心的な体験は、〈無意識〉に、少年期の心的な体験は、〈前意識〉に対応させられているから、夢が〈無意識〉を源泉としているとかんがえるかぎり、幼時期や少年期の心的な体験に重要な意味があたえられるのは当然である。フロイドは、しらずしらずのうちに、人間の心的な領域を、年齢とともにつぎつぎに年輪を重ねてふとくなってゆく樹木の切り口と、おなじようにかんがえている。もっとも幼時期は心的な領域のもっとも奥深くしまいこまれ、そのうえに幾重もの皮がかぶせられてゆく図式になぞえられる。この心的なモデルは危険なものというべきだが、ある種の課題については有効なモデルといっていい。そして夢のばあいも有効な例にかぞえられる。
しかし、フロイドの方法に依存するためには、どうしても〈記憶〉とか〈無意識〉とか〈前意識〉とかいう概念を、げんみつにフロイドが想定したとおなじ意味で認めなければならない。
わたしたちは、〈幼児記憶〉が〈無意識〉のなかにしまい込まれていて、何十年もあとで夢のなかにあらわれるといった心的系統発生論をそのまま認めがたい。幼児の体験が、心的な現存性としてあらわれるとすれば、かならず〈現在〉の心的なパターンとしてだけ意義をもっている。それは〈記憶〉ではなく心的なパターンというべきである。
(『同上』P227-P228)
③
〈わたし〉が子供の時にみた夢で、現在も鮮やかにパターンを覚えている夢がある。フロイドのいう「子供の時分に見た夢で、何十年も経つて猶、まざまざと記憶に残つているような夢」にあたっている。
《子供の〈わたし〉はいつも遊んでいる横丁の露地で近所の遊び仲間の子供と集まっている。なにかとりかえしのつかぬことをみなでしてしまったらしい。仲間の子供たちはつぎつぎに仕方がないからみなで腹を切ろうと叫んでいる。だんだんと仲間の雰囲気は腹を切るという点に集中し高まってきて、もう腹を切ることが当然のような熱気が支配している。ところで〈わたし〉だけは腹を切るのは嫌だとおもっている。とうとうたまりかねた〈わたし〉は、おれは腹を切るのは嫌だと口に出す。すると仲間はそんならお前は勝手にしろ卑怯だと口々に罵って、皆、短刀を出して抜き身をきらめかせる。そこでわたしは嫌嫌ながら仕方なしに刀を抜いて皆にならつた。では腹を切って死のうとたれかが云って刃を腹の方へ向ける。わたしは思い切って腹をつきさした。ところが仲間をみわたすとどうしたことか仲間のたれも刃を腹に刺したものはいない。〈わたし〉はもう刃で腹をつきさしてしまっている。〈わたし〉は黙って妙な顔をしている仲間の子供にむかって〈おまえたちは卑怯だぞ〉と叫びながら息がだんだん苦しくなってゆく。仲間は〈わたし〉を嘲笑するのでもなくただ奇妙な沈黙のまま刀をもっているだけで腹に突き刺そうとしない。》
〈わたし〉は、この少年時の夢を、細部の不確実さはべつとして、基本的なパターンとしてはよく覚えている。その理由は〈わたし〉とこの世界との関係についてなにか切実なものがこの夢にあるとかんがえてきたからである。
・・・中略・・・
その後、現在までの体験のなかで、幾度か、この少年時の夢をおなじパターンだなとおもって思い浮かべたことがある。
〈わたし〉は、この少年時の夢を、〈わたし〉の倫理的な面での発生点とかんがえてきた。いつもこういうような矛盾を、他の人間とのあいだ、他の事件とのあいだに感ずるので、その典型的なパターンを、この子供のときの夢が保存しているとかんがえてきたらしい。しかし〈わたし〉のこの夢の解釈はもっと疑ってみたほうがよいようにおもわれる。
フロイドの方法によって、この〈わたし〉の幼時の夢を解釈すれば、まず〈わたし〉の〈父親〉にたいするリビドー的な関係の異変として了解されるとおもう。〈なにかとりかえしのつかぬこと〉というのは、〈わたし〉の〈リビドー〉的固着の仕方の表現である。それは〈恐怖〉であるのか〈羞耻〉であるのかわからないが、そういうことに関係している。〈わたし〉は、リビドー的な〈父親殺し〉をどうしてもやりたくないとおもっている。しかしそれをしなければ成長することができない。そのためらいを跳びこしたとき、〈わたし〉はもっとべつのなにかをも、相伴してとびこしてしまった。この〈べつのなにか〉は、すくなくとも〈わたし〉とこの世界の関係にとって重要ななにかである。仲間の子供たちは、〈わたし〉とちがってスムースに〈父親殺し〉をやり、だから同時に〈べつのなにか〉をも跳びこしてしまうことはない。〈わたし〉が、この幼時の夢を何十年も経た現在もまざまざと保存しているとすれば、〈わたし〉のこの世界にたいする異和は、〈父親〉にたいする〈リビドー〉的な関係の異和に発祥していることを示している。なぜならば、この夢のなかの異和がその後、いく度もおなじパターンで繰返されたために、〈わたし〉は何十年もたった現在も、まざまざとその夢を記憶しているのである。
(『同上』P228-P232)
④
ところで、〈わたし〉がフロイドの方法を捨てて〈わたし〉自身の解釈によってこの幼時の夢を分析すれば、どんな問題が提起されるだろうか?
第一にこの夢は〈わたし〉の〈わたし〉自身にたいする関係づけの失敗を語っている。そしてこの関係づけの失敗は〈わたし〉の〈身体〉にたいする〈わたし〉の観念の関係づけの失敗に根源をおいている。だから〈わたし〉は〈わたし〉の〈身体〉についてある部分にたいしては過剰に執着し、ある部分にたいしてはほとんど無関心である。そこで〈わたし〉は〈他者〉(あるいは他の事象)にたいしても、ある部分については無関心で、ある部分については過剰に執着している。〈わたし〉にとって〈わたし〉は、どこまでも了解可能な底無しの沼のようにおもわれるために、〈他者〉(あるいは他の事象)にたいしても、どこまでも了解可能なものとおもっている。しかし、じじつは〈他者〉(他の事象)なるものは、〈わたし〉と関係づけられている丁度その度合でしか了解可能性をあらわさない。この〈わたし〉の〈わたし〉にたいする了解可能性と、〈わたし〉に関係づけられている〈他者〉(あるいは他の事象)にたいする了解可能性の異和が、〈わたし〉の幼時の夢の基本的なパターンである。いいかえればこの夢は、自己にたいする過剰な執着と自己にたいする過少な関心との両価性を語っている夢である。
ところで、フロイドは〈幼時記憶〉というように、〈記憶〉という言葉を便宜的に無造作につかっている。しかし、〈記憶〉というものは、幼年のときにじっさいあったことを、何十年もあとで覚えているといった意味ではもともと存在しない。一般に〈記憶〉とよばれているものは、心的なパターンということにほかならない。そしてわたしたちが心的なパターンをもっているのは、それが世界にたいする関係の結節を意味しているからである。つまり、わたしたちはなんらかの意味で世界に対する関係づけのキイ・ポイントとしてしか〈記憶〉を保存しないし、逆の云い方をすれば〈記憶〉されるものは、それが夢であれ、言葉であれ、出来事であれ、すべて世界にたいする人間の関係づけの結節だけである。
〈わたし〉の子供のときの夢で、いまも覚えている〈夢〉は、しばしば現実体験のなかでおなじパターンとして繰返されたとかんがえてきた。そうだとすれば、この〈夢〉は、いわゆる〈正夢〉【ルビ まさゆめ】に相当している。なぜならこの〈夢〉は、その後で〈わたし〉がぶつかる〈他者〉(あるいは他の事象)との関係を〈予言〉していたことになるからである。ふつう〈正夢〉というときは、夢のなかの情景や出来事が、やがてそのように実現されるというふうになっている。〈わたし〉の夢では情景の細部の形像が実現されるのではなく、その夢の基本的なパターンが実現される。しかし〈正夢〉としての本質的な性格はかわりないのである。ただ形像を主とする夢であるか、非形像が優勢である夢かというちがいにすぎない。
ここで、もしひらき直れば、いくつかの困難な問題が介入してくる。〈夢〉が〈記憶される〉(心的なパターンとして現存する)ためには〈正夢〉でなければならぬ。いいかえれば覚醒時の心的な体験によってなんらかの意味で現実的に裏付けられなければならない。そうでなければ〈夢〉は何十年も保存されるはずがないのである。
(『同上』P232-P234)
※この文章も、次節の「夢を覚えているとはなにか」に展開していくが、ここで引用を止める。
※②と③と④は、ひとつながりの文章である。
|
備
考
|
(備 考)
まだ若い頃に、この『心的現象論序説』をよくわからないながら読んでいて、世間に普通のありふれた概念のように流通している〈記憶〉というものを、吉本さんは慎重に考え、取り扱っているなということが印象に残った。吉本さんの〈夢〉というものへの入り方を項目として取り上げようかと思いついて『心的現象論序説』を開いたら、またそのことを思い出した。
記憶という言葉は、わりと普通に使われているし、「記憶細胞」の実在をとなえる学者までもいるが、吉本さんは自分の方法的な世界把握(註.1)から、記憶という概念を使うことなく退けている。
(註.1)
2 心的な領域をどう記述するか
心的な領域を、個体が外界と身体という二つの領域からおしだされた原生的な疎外の領域とみなすという了解からなにがみちびきだせるか。
つぎの課題はどうしてもそうならざるをえない。いまのところ心的な領域はもやもやとした塊りであり、かろうじてその輪郭を判別できるだけである。そしてこの輪郭たるやどんなものでも観念の働きに属するかぎりはそのなかに包みこめるわけだから、そんなものはあってもなくてもおなじだとかんがえられても仕方がないのである。実在することが疑えないのは、いまのところ人間の<身体>と現実的な環界だけであり、観念の働きはなんらかの意味でこの二つの関数だということである。
それには心的な領域をささえる基軸をみつけだすことが必要である。さしあたって、わたしたちはひとつの仮説をもうけることにする。その仮説は、
生理体としての人間の存在から疎外されたものとしてみられる心的領域の構造は、時間性によって(時間化の度合によって)抽出することができ、現実的な環界との関係としての人間の存在から疎外されたものとしてみられる心的領域の構造は、空間性(空間化の度合)によって抽出することができる。ということである。 (P52-P53)
・・・中略・・・
この仮説は、つぎのようなことを意味する。
たとえば、古典哲学が、<衝動>とか、<情緒>とか、<感情>とか、<心情>とか、<理性>とか、<悟性>とかよんでいるものを、身体から疎外された心的な領域としてかんがえるばあいには、それらは心的時間の度合とみなすことができるということである。たとえば、<衝動>とか<本能>とかよばれる心的な領域は、有機的自然に固有な時間と対応させることができる。<情緒>とか<心情>とかよばれるものは、もはや有機的自然の時間性と対応させることができないし、そこでは時間化度はより抽象され、この時間化度の抽象性は、<理性>とか、<悟性>とよばれるものでは、もっと高い。
おなじように、心的な領域を現実的な環界との関係においてみるばあい、空間化の度合は、たとえば視覚的な領域では、対象となった<自然>の空間性とある対応をもうけることができるが、触覚のとりこむ空間性は、もはや対応というよりも接触とみなされる特異な空間性であり、また聴覚の空間性となると、その抽象性は高い、とかんがえることができる。 (P53-P54)
(『心的現象論序説』P52-P54)
『言語にとって美とはなにか』での基軸概念としての自己表出と指示表出のように、ここでは時間性(時間化の度合)と空間性(空間化の度合)という基軸概念が使われ、今から滑りだそうとしている。そうして、それは古典的な哲学概念を包括するものと見なされている。
②で、フロイドが、人間の心的な領域を時間軸では年輪のイメージで考えていると捉えて、吉本さんは、次のように述べる。
しかし、〈記憶〉というものは、幼年のときにじっさいあったことを、何十年もあとで覚えているといった意味ではもともと存在しない。一般に〈記憶〉とよばれているものは、心的なパターンということにほかならない。そしてわたしたちが心的なパターンをもっているのは、それが世界にたいする関係の結節を意味しているからである。つまり、わたしたちはなんらかの意味で世界に対する関係づけのキイ・ポイントとしてしか〈記憶〉を保存しないし、逆の云い方をすれば〈記憶〉されるものは、それが夢であれ、言葉であれ、出来事であれ、すべて世界にたいする人間の関係づけの結節だけである。
このような問題と対応するのは、『定本 言語にとって美とはなにか』(P46)の次のような個所である。
わたしがここで想定したいのは、・・・中略・・・言語が発生のときから各時代をへて転移する水準の変化ともいうべきもののことだ。
言語は社会の発展とともに自己表出と指示表出をゆるやかにつよくし、それといっしょに現実の対象の類概念のはんいはしだいにひろがってゆく。ここで、現実の対象ということばは、まったく便宜的なもので、実在の事物にかぎらず行動、事件、感情など、言語にとって対象になるすべてをさしている。こういう想定からは、いくつかのもんだいがひきだされてくる。
ある時代の言語は、どんな言語でも発生のはじめからつみかさねられたものだ。これが言語を保守的にしている要素だといっていい。こういうつみかさねは、ある時代の人間の意識が、意識発生のときからつみかさねられた強度をもつことに対応している
このことはさらに、次のような言葉や内面というものに対する吉本さんの捉え方とも対応していると思う。
吉本
ぼくは言葉というのは、表現しかないと思ってるわけです。表現されなければ言葉はないと思うわけね。だから、ぼくが言葉って言うときの言葉は、表現された言葉になるんですよ。
ぼくの論理で、言葉っていう場合には、表現された言葉っていうふうになるんです。表現された言葉っていうのは、何が違うかっていいますと、表現する途端に内部ができるということだと思うんです。つまり、内部がここにあって、言葉が何か言われるっていうことは、ほんとは全く嘘だと思うんですけど、しかし、表現された言葉っていうのができたときに、同時に内部ができるっていう、そういう対応の仕方になると思うんです。
表現された言葉だけが問題なんで、表現された言葉というのがあると、言葉を表現した途端に、反作用で、自分は言葉から疎外され、疎外された分だけ内部がそこに生じる。なぜ内部が持続的に生ずるように見えるかっていうと、そういうことを人間は繰り返しているから、何となくいつでも同じ内部が子供のときからずーっと連続しているみたいな気にさせられるわけです。それは全く幻想なんだけども、どうしてその幻想が生ずるかっていったら、やっぱり表現する途端に内部ができるから。表現しなければ内部なんかないんだけど、途端に内部ができるみたいな、そういう対応関係があるところで、内部と言葉っていうものとの関係が出てくるというところで扱いたいわけなんですよね。
ぼくは、内部っていうのが持続的、実体的に人間にあるっていうふうにちっとも考えてないんですけれども、言葉を表現した途端に内部は生ずるものだ、同じ言葉を何回も発してると、内部がいかにも形あるように見えちゃうもんだよっていう意味合いで、内部というのを問題にするわけなんです。
(「内なる風景、外なる風景」(後編) 鼎談 吉本隆明・村上龍・坂本龍一
月刊講談社文庫『IN★POCKET』1984年4月号)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 746 |
「言葉」ってなんだ? |
「言葉」ってなんだ? |
対話 |
『悪人正機』 |
朝日出版社 |
2001.6.5 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 今っていうのは、社会の変化が言葉を変えてきている |
僕は自分の考え方として方言と民族語の違いは、地続きになっていると思ってるわけですよ。 |
要するに言葉っていうのはね、全部根拠がないんですよ。 |
ある言葉は偶然でしかない |
項目
1 |
①
こういうこと(引用者註.「日本語のリズムが変わりつつあるんじゃないか」)と、専門領域のカリスマみたいな言葉が一般領域に入り込んできている、つまり言葉の使われ方が変わりつつあるってことは、関係があると思うんです。
言葉が変わるということでいうと、僕自身も、勝手に「造語」してますね。「共同幻想」っていうのも造語ですね。あれは流行りましたね。あとは「位相」とか「固有時」とか、数学や理工系の言葉の使い方を広げるってのが多いかなあ。もともと工学系だから、そっちの言葉が鍛えてあるんでしょうね。
まあ、それはさておき、特に、今っていうのは、社会の変化が言葉を変えてきているということでしょうね。それは、非常に面白いことと言っていいんじゃないでしょうか。
(吉本隆明『悪人正機』P242-P243 聞き手 糸井重里 朝日出版社 2001.6.5)
②
僕は、もう、全然ダメです。
できるとかできないっていう領域までもいかない。何言ってるんだかわかんねえ(笑)。特許事務所に勤めてた頃に外国人とモメたことがありましてね。要するに何か怒ってるのはわかるんだけど、どのくらい怒っているのかはわかんないですよ。
戦争中は英語は敵性国家の言葉だからあまりやらなくてもいいっていうことになってたんですよ。そして僕は、やらなくてもいいっていうのは結構なことだから、やらなかったんです。
それからこれも実感なんですけど、僕は自分の考え方として方言と民族語の違いは、地続きになっていると思ってるわけですよ。ずっと方言を延長していくとね、違う民族語になるって。で、そこに断絶はないと思ってるわけですよ。
秋田弁とか、青森弁っていうのはあるでしょう。それと要するに韓国語とか、中国語とか、あるいは英語とかね、それとは地続きなんだと思ってるわけです。
今だと地方に行っても、あんまりコトバがうまく通じないってことは少なくなりましたけどね、僕の学生時代なんか、山形にいたんだけれど、買い物だけでも難しかったっていうくらい、コトバが通じませんでしたね。向こうの人は、聞くのはわかるんですよ。ラジオとか、新聞とかで、標準語ってやつに接しているからね。でも、こっちが向こうの人のコトバを聞き取れないんです。方言がきつくてね。
つまり、方言だからわかるなんてウソだって、そのとき思いましたよ。だから、その地続きのところに外国の民族語があるんだって考えです。
民族語に分かれて十万年単位っていうふうに言われているんですけど、十万年単位で、わざわざ分かれちゃったんだから、それを今さらゴッチャにすることも、一緒にすることもないじゃないのって思います。ただ、強い国の、利用度を持ってるコトバがだんだん別の国のコトバに入り込んで占めてきたのなら、それでいいじゃないのっていう考え方になっていっちゃうんですね。そうしてコトバがなくなっていっちゃうんならいいじゃないのっていう。まあなくならないで残るつていうんなら、それはそれでいいじゃないのって思うし。
なんか、なるに任せるってことでいいんじゃないかなと考えますけどね。
(『同上』P244-P246 )
③
それから、もうひとつ、要するに言葉っていうのはね、全部根拠がないんですよ。つまり、例えば年上の肉親の女の人を「姉」って呼びますよね。じゃあ、どうして「姉」って呼ぶんだって。これをね、「妹」ってどうして言わなかったんだとか思いますよね。そういうことには根拠はないんですよ。何も。なぜお米のことを「米」って言うのかに根拠なんて、全然ないんです。コメって言わないでソメって言ったってよかったはずなのに、なぜコメって言ったのかといったら、それは偶然でしかないでしょう。だからコトバっていうのは、先述した民族語の違いでもいいんですけど、あまり根拠がないんですよ。つまり、民族語であるとか、方言だとか言ってるけど、そんなものは何の根拠もないよって。あるとき偶然、誰かが「シスター」って言い出したから「シスター」になっちゃったということでしかないんですよ。そのくらい曖昧というか、不確定なものですから。・・・中略・・・
人間そのものが持っている根拠のなさと同じでね。生まれたことっていうのには根拠がないんですね。生まれたことには根拠がなくて、それで親の方からいえば、産んだことにも根拠がないってなるんですよ(笑)。
動物はそんなこと考えなくていいわけで、これは、人間のつらいところですよねえ。
(『同上』P246-P247 )
|
備
考
|
(備 考)
②には、吉本さんの語学力が語られている。
言葉について、吉本さんが考え詰めてきたことが語られている。言葉というのは、全部根拠がない、偶然でしかないということについては、昔この吉本さんの言葉に出会った時、(うーん、どうだろう・・・)とそれをそのまま受け入れがたく思ったことがある。今もそのことは保留としておこうと思う。
その問題と直接の関わりがあるかどうかはわからないが、「プーバ/キキ効果」というのがある。
それぞれ丸い曲線とギザギザの直線とからなる2つの図形を被験者に見せる。どちらか一方の名がブーバで、他方の名がキキであるといい、どちらがどの名だと思うかを聞く。すると、98%ほどの大多数の人は「曲線図形がブーバで、ギザギザ図形がキキだ」と答える[2]。しかもこの結果は被験者の母語にはほとんど関係がなく、また大人と幼児でもほとんど変わらないとされる。
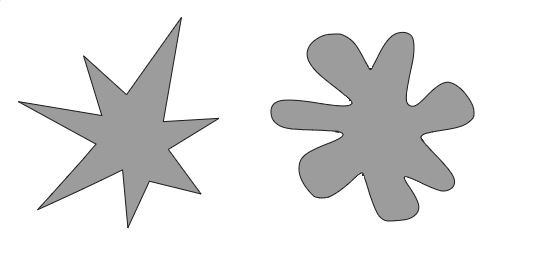 |
テストに使われる図形の例。この図を被験者に示して、どちらがブーバで、どちらがキキかを聞くと、
大多数の人間が「左の図形がキキで、右の図形がブーバだ」と答える。 |
(ウィキペディア「ブーバ/キキ効果」より)
これは図形(対象)と言葉の対応関係の問題であり、それに対してはこちらの言葉の方がしっくりくる、というようなことである。これは人種や民族や老若を超えた、人間に共通の内臓感覚的なものが介在する対象と言葉の関係の問題だろうと思われる。言葉に根拠はないという吉本さんの言葉に初めて出会った時、わたしがすでに「プーバ/キキ効果」を知っていたかどうかは覚えていない。現在であれば、この「プーバ/キキ効果」の存在が、言葉には根拠がないという吉本さんの考えへのためらいの根拠となっている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 748 |
「株」ってなんだ? |
「株」ってなんだ? |
対話 |
『悪人正機』 |
朝日出版社 |
2001.6.5 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 株というのは、(経済)社会の一種の呼吸作用 |
国家の呼吸作用 |
平べったい |
|
項目
1 |
①
株っていうのは一体何なんだっていうことですけども、大ざっぱな言い方をすれば、この社会、特にこの経営経済体制をとってる社会における一種の呼吸作用だと思うんですよね。
まあ、東京にもロンドンにもニューヨークにも株式の市場はあるんですけど、結局それは世界経済の社会的な呼吸作用っていう機能が、第一に考えられたことだと思うんです。
これに対して、国家の呼吸作用っていうのはまたちょっと別にあると思うんですよね。じゃあ国家の呼吸作用というのは何なのかっていったら、非常に簡単に言えば、例えば貯金を増やそうみたいなことで、それが増えるか減るかっていうことによって、国家が呼吸を営んでいくっていうようなことですね。
現在は、資本主義っていうのと、社会主義をとっていたソ連とか中国みたいなところとかが、ほぼ同じくらいな呼吸の仕方に近づきつつあるというふうに思うんです。
資本主義の側は、国家が社会から酸素を吸い上げて、それをまた吐き出して社会に戻してたりってかたちで呼吸作用のバランスをとるようなことをしていくし、社会主義のほうは、株に象徴されるような呼吸を取り入れてバランスをとっていくという具合にね。
要するに、国家の呼吸管理がある程度必要だっていう部分と、全部を国家の呼吸にしてたら行き詰まっちゃったよ、という部分とが、両方から近づいているということですね。そういう全体的な変化というのは、現在の前提としてあると思うんですね。
(吉本隆明『悪人正機』P268-P269 聞き手 糸井重里 朝日出版社 2001.6.5)
②
どっちにしても、今までの伝統だとか老舗だとかに影響されている大会社では、物事はなかなか変わりにくいけれど、もっと新しい平べったい会社だったら、株みたいな呼吸作用を取り入れたかたちをとりやすいと思うんですね。平べったいって言い方は、上下の安定した組織じゃなくて、という意味です。伝統的な会社に比べたら、上と下がすぐくっついちゃってる会社ですね。そういう会社は株式も、いろんな下の人に分散されていくんですね。社員が、自分とこの株を持って間接的ではあっても経営参加していくとか、そういうことをやっているところは、ずいぶん出てきていますよね。そのへんのことは、僕にとってはまだ未知の領域なんで、実感を伴った言い方はできないんだけれど、資本制度はそっちの方向に行くんだろうということは思いますね。
日本の呼吸作用が停滞している時に、アメリカなんかはグズグズしていられかみたいな、ね。日本ももっと平べったくなれっていうか、早急に社会自体の呼吸作用をもっと活発にするようにしろって主張ですよね。(註.1)国家なんてのは、もう、半分はなくなっちゃってもいいんだっていうか、開いちゃってかまわないんだって言い分じゃないでしょうかねえ。
(『同上』P269-P270 )
③
それで、自分で株をやるかって言われたら、僕はやったこともないし、やる気もないし、余裕もない (笑)。それは、なんでなんだろうなあ。警戒心とかじゃないんだけれど、つまり、本気でやらないとやっぱり儲かんねえぞっていうか、儲かるまでいくためには、やっぱり本気になっちゃうもんなって思うからですね。片手間でやってるくらいなら、たいして儲かりもしないだろうしね。株に、本気になってもいいじゃねえかっていう気持ちになれば、それでいいですけどね。
だから、株をやろうとしている人に、損はしねえからどんどんやれって言うことはできませんけれど、株っていうのは経済の呼吸作用なんだ、と。それから、社会が、今までの頂点の小さい三角形の構造から、いろんな場面で平べったくなっていくんだということで、株を普通の社員だとか家族だとかが持つようになるんじゃないかってことは、言えるでしょうね。
(『同上』P271-P272 )
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
これはアメリカが日本に突き付けた「年次改革要望書」のことだろう。
それは「日本政府とアメリカ政府が両国の経済発展のために改善が必要と考える相手国の規制や制度の問題点についてまとめた文書で2001年から毎年日米両政府間で交換され、2009年(平成21年)に自由民主党から民主党へと政権交代した後、鳩山由紀夫政権下で廃止された。」(wiki)という。
これに関しては、日本の経済社会がアメリカに見透かされているとして吉本さんは確か別のところで批評していたと思う。
経済のことになると、吉本さんは少しゆっくりめに、キチッキチッとしゃべるように思う。特別に得意なジャンルでないからなのかもしれない。だからこそ、できるだけ正確に話そうとして、ゆっくり丁寧になっていたのだろうか。ま、印象だけのことなんだけどね。
株というものを「社会の呼吸作用」と言ったのは、オリジナルの表現なのかなぁ。聞いていて、ずいぶんイメージのつかみやすい言葉だった。
株そのものの説明以上に、これからの企業のイメージだとか、投資の大衆化だというあたりに、ずいぶん予言的な発言が顔を出すのがおもしろかった。
それが、大づかみに当たっていると思うので、また、いま読むとおもしろい。「平べったくなっていく社会」というイメージは、ぼくも実感的によく語っていた。(『悪人正機』P267 糸井重里の前書きより)
この糸井重里の前書きの言葉は、自身がほぼ日刊イトイ新聞の経営者として体験していることから来る実感の言葉だと思う。
最近、わたしは、糸井重里が主宰する『ほぼ日刊イトイ新聞』の「糸井重里が毎日書くエッセイのようなもの 今日のダーリン」やその道の「有名人」との対話(最近のものでは、「マンガ編集者、林士平の即答。」、「後藤達也さんはなぜ、SNSで、すごく元気に活動できてるんだろう?」、「笑顔で戦うジャパンラグビー」、「MOROHAと9つの相反するもの。」など。)をよく読みたどっている。その対話の中で会社の代表者としての経験からの言葉を時々もらすことがある。因みに、「1979年に糸井重里の個人事務所「有限会社東京糸井重里事務所」として設立され2002年に株式会社へ組織変更」「1998年6月 『ほぼ日刊イトイ新聞』を創刊」(wikiより)とある。この対談は1999年頃である。
この糸井重里の言葉で、備考としての註に代えてもいいと思えるが、ひとこと記しておきたい。
「(経済のことが)特別に得意なジャンルでないからなのかもしれない。」という糸井重里の吉本評について、確かにそうだねと感じ取れる対談がある。
「言葉の吉本隆明② 563 庶民感覚」で取り上げた 「世界金融の現場に訊く」 『吉本隆明資料集178』猫々堂2018年9月10日
※投資銀行社員 村山信和・聞き手 吉本隆明 (2000年12月15日)という対談である。これを読みたどると、あー、なんだ、吉本さんの株などについての具体的な理解は自分と同じだという気がした。つまり、株などのトリビアルなことはよくわかっていないということ。たぶん人は、人間的ないろんな分野に目配りや関心があったとしても、すべてのことをよく知ることはできない。吉本さんは、文学や思想は主戦場だが、それ以外のことは文学に置き換えて理解するということをしばしば語っていた。経済についても、具体的にはトリビアだらけであるが、その本質と動向さえつかめば、まあ良しとしようということではないだろうか。
このことから、わたしが思ったのは、例えば、身近に利用するスーパーのことである。このスーパーを小社会と見なせば、もちろん他の小社会や社会との流通や諸税などの連関の中に存在し、活動している。このスーパーの活動を対消費者の経営の面から考えると、1週間に1,2回新聞広告を打ち、何々セールを行ったりして商品の値段を上下させ、消費者に誘いをかけている。これもまた、消費者との関係でなされるスーパーという小社会の経営的な呼吸作用と見なすことができるように思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 749 |
「家族」ってなんだ? |
「家族」ってなんだ? |
対話 |
『悪人正機』 |
朝日出版社 |
2001.6.5 |
関連項目 672 「家族とは何か」(家族の深層論から)
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 永続的に円満な家族なんてものはないんですよ。 |
「家庭内暴力」 |
未知の領域 |
おそらく、いろんな人や家族の数だけ「実験」が繰り返されていくようなことになっている時代なんですね。 |
項目
1 |
①
結婚というか、家族の問題は、まずね、世の中には立派な、円満な家庭なんてものがあることになってますけどね、吉本さんとこも家族が仲良くやってていいですねとか言われることもあるけど、そんなことはないんでね。
ないんですよ(笑)。どう考えたって、経験上、実感上から言っても、そんなものはねえよって思うから、たいていはウソをついてるんじゃないでしょうか。
だからまず、そこんとこを、信用しちゃいけないんですね。
ある期間だけを見ればうまくいっているようでも、もう次の瞬間には全部がぶっ壊れそうな争いが起こるかもしれないし、永続的に円満な家族なんてものはないんですよ。みんな、しょうがないからウソついて体裁よくしているんです。
理想の社会でもできて、他の制約がなくて、本当にひとりひとりの人間が自由にいられるとすれば、一緒に生涯を貫くことは、そう難しくないのかもしれませんが、でも今、現実にはそういうことになってないんだから。
その現実のなかで、夫婦とか家族とか、決まったひとりの相手と生涯を貫いてる人もいることはいるんだけど、それはいいことでも何でもないわけでね。相当ガマンをしながらって感じでやってるんですよ。
ガマンをして結婚生活が壊れなかったというのは、別に立派なことでもなんでもありません。むしろ、お互いに、「そんなんじゃイヤだ」とか「また違う相手とやってくさ」とかを繰り返していくほうが正直というか、本当なんだと思いますね。間違った選択だったと、しまったと思った時にガマンして耐え忍んでやっていくというのは「ひとつのやり方」にしかすぎないわけですから。
これは、どっちがいいっていうことじゃなく、うまくいってる時もあるし、もうダメなんじゃないかと思ったら離れてもいいんだし。夫婦や家族でも同居せずに、好きな時に会うっていうやり方も、今という時代なら、非常に現実的な方法だと思います。
だいたい、日本だと「親子三代の家族が一緒に暮らす」っていうのが老人の理想だって、統計なんかで出てくるけど、西洋の場合だと宗教ですね。家族ではなく、教会につながりを求めてるんです。
(吉本隆明『悪人正機』P145-P147 聞き手 糸井重里 朝日出版社 2001.6.5)
②
今、日本で家族って問題に即して言えば、結局「家庭内暴力」の状態が、いちばん一般的で普遍的な状態だってことです。親が子に対してとか、夫が妻に対してとか、いろいろ組み合わせはありますけれどもね。
例えば、親は子供に対して、家父長として、おまえは子供なんだから「ああしろこうしろ」と言える、できると思っているわけです。子供が一人前になるまで自分が食べさせてやっているんだからって、いうことなんでしょうが、もうとっくに、食べていけるいけないというのは切実じゃなくなってるのにね。
そういうふうに、何かしらのカタチで親の風を吹かすというか、親の権限を発揮しようとする。母親が教育ママになって、この学校へ行けとか塾に通えとかも含めて、そういうことする。
だけど、子供のほうは、ちっともそう思っていない。平等だとか対等だとか思っている。
こういう状態のなかでは、もう家庭内暴力は一触即発ですよ。
親と子と同じように、男と女の関係もそうですよね。
男が昔のルールのままで乾元を発揮しようとすると、女のほうは男女同権で平等だとかって思ってますから、そこで問題が生じてきます。
対等のところに立っていると考えている人と、そうじやないんだって考えようとする人が一緒に暮らしているところに暴力の可能性が充満しているんだっていう、そういう時代にいるわけです。
・・・中略・・・
いずれにしても、家庭内暴力の問題というのは、事件として吹き出さなくても、ありとあらゆるところに可能性として存在すると考えたほうがいいでしょうね。
こういう状況のなかで、どういうのがいいんだなんて言ってったって、これが通用するなんてことは、ひとつもありゃしないんです。
(『同上』P147-P150 )
③
何しろ僕の歳になっても、こりゃあ未知の領域だっていうのが、どんどん増えているんですから。例えば、老人になってからの家族がどうやって生きていくかなんてことも、全然、見えてないし、高度資本主義社会になってからの、歳をとった家族の在り様なんてものは、どこにも例がありませんからね。
もちろん、男女の問題だけじゃなく、当然そこに出てくる子供の問題は、これまた大変です。どうすればいいかというより、とにかくやっていきながら手直しを続けていくっていうことなんでしょう。
おそらく、いろんな人や家族の数だけ「実験」が繰り返されていくようなことになっている時代なんですね。だから、上手くいくこともあるし、こりゃあ失敗だったということもある。でも、だいたいは、そうは上手くいくわけはないんだってところで、これも何とか凌いでいくしかないんですね。僕の知ってるのは、ウチの場合だから、普遍的かどうかわからないけどさ。
(『同上』P150 )
|
備
考
|
(備 考)
家族は、例え結婚しなくて単独者であっても、一度は家族の渦中を潜り抜けてきているし、自分が大人になっても濃度が薄くなっていたとしても元の家族とも、何らかの関係のなかに生きている。そういう意味で、誰もが家族との関わりを生きている。
吉本さんは、たぶん、家族の現在の渦中で誰もが感じていることに触れている。そうして、老いてなお「未知の領域」が到来する中で、必死に考え続けている姿が思い浮かぶ。ほんとうに、〈現在〉の渦中で、一般の評論家やカウンセラーなどが言うように、カッコ良く事態を切り抜けることは誰もが難しそうに見える。
家族を取り上げて、家族の有り様を問うことは、人間の本質性を問うことでもあると思われる。
|