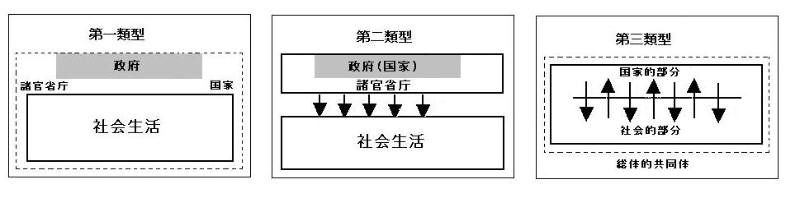サ行
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 411 |
社会と国家の三類型 |
さんるいけい |
第三章
国家と社会の寓話 |
論文 |
|
中学生のための社会科 |
市井文学
|
2005.3.1 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| 基本の類型はなぜ単純なものになるのだろうか |
理由と条件 |
|
項目
1 |
① 「国家」と「社会」の関わり方は、世界の地域民族まで触れると世界中のあらゆる「国家」や風土、政治制度などによって全部違っている。けれどここでは三つの類型に触れれば、おおよそ世界中のどこでもその三つの類型のどれかに入れることができ、細部をつけ加えればどんな「国家」と「社会」の関係にも当てはめることができるとおもう。
第一類型
住民は無意識のうちに「国家」というものは「社会」やそこで日常生活を送っている人々をすっぽりと覆いつくしているものとみなしている。日本「国家」を例にとれば、日本「国家」というのは日本人を中心に集まっている日本「社会」やそのなかに住んでいる日本人も、耕している土地も日常生活を営んでいる地面もすべてそこに含まれている施設も含んでいるものと考えている。
だから「国家」という概念を二種類に使い分けるような「国家」観は、日本「国家」が近代になってはじめて生み出されることになった。
第二類型
この類型は西欧の先進国が典型であるといってよいが、「国家」といえば「政府」およびその実務機関である諸官省庁だけを指し、「社会」はその下にあって人々が日常の生活を営んでいる場所で、はっきりと「国家」とは別のものであると考えられている。
言い換えれば「社会」は「国家」の下に「国家」とは別に人々が日常の生活を具体的に営んでいる場所だとみなされている。よほど特殊な場合でないと、「国家」が「社会」もそこに生活している人々も諸施設も住んでいる土地もすべて包括しているものを指すとは考えられていない。別言すれば、第二類型では「国家」イコール「政府」、その実務を司る諸官省庁のことであり、第一類型のように「国家」イコール「社会」、そのなかの人々、諸施設、地面もすべて含むものとはみなされていない。
この第一類型の「国家」観と第二類型の「国家」観は、非常のとき(例えば戦争のような)の「国家」行動では恐ろしいほどの相違となって表れる。
第一類型の「国家」では「国家」のために「滅私」の奉公をすることは最高の美徳とされる。そして「滅私」でないものは恥辱として排されるという考え方は、日本では太平洋戦争まで実行されていた。これに背く考え方は、「国家」の機関である軍隊でも村落の共同体でも「村八分」の扱いを受けた。
第二類型の「国家」では単に社会人が個人として勇壮かそうでないかの口実にされたかもしれないが、「国家」や「社会」が個々の社会人の行為の如何を排斥や美徳の問題に置き換えることは、まず少なかった。なぜなら「国家」とは政治支配権や決定権をもつ場合でも、「社会」とは切り離されたものとみなされているからである。
第三類型
ここで「社会」と「国家」との関係について第三の類型ともいうべきものに少しだけ言及しておく。それは「国家」と呼びながら「国家」としての明確な輪郭をもたず、「社会」と呼ばれていても「社会」としての明確な輪郭をもたない関係だというのが共通点だといっていい。近代の民族国家が成立する以前の時代には、どこでも大なり小なりそうだった。
例えば原始時代の「社会」を例にとれば説明しやすい。そこではまだ「国家」と「社会」とはそれぞれ明確な輪郭をもっていない。また明確に分離もしていない。「国家」と「社会」がはっきりした境界をもたないで、総体として一つの共同体になっているイメージを思い浮かべると理解しやすい。
「国家」的部分はやがて政治、軍事的な「国家」に、「社会」的部分はやがて日常生活を主体とする「社会」に分離してゆく。機能としても政治や軍事を司る長老会議から政府へと発展する部分と、成員が日常生活を営む「社会」的な部分とに分離してゆく。村落の共同体があって上層に村の長老たちの集まりがあって、それが村の運営や方針を決定すると、村人たちはそれに従って行動したり、義務をもたされたり、規則や懲罰や禁止事項を守らされたりしている。
この状態が発達してゆくと長老会議が政府の役割をもつようになり、村人たちはそれに従属する一般社会人というまとまりや共通性をもつようになる。もっと発達すると単に年齢の多い者が長老として威力をもつ年齢階程的ななものが壊れて、富をもつ者や能力とか強制力とかを巧みに行使したり人をまとめて従属させることが得意な者とかが、長老たちに取って代わるようになる。また暴力の強い者が威力を増して長老に代わる。
これが極まれば宗教的な威力も加わって王様と直属の配下が村落共同体やその連合を支配し、村人たちは服従するようになる。つまり王権とその直属の配下が支配する集団として、一般の村落民やその連合した社会を支配下に治めるようになる。
ここまでくれば王権と直属の配下が「国家」(政府)を作り、村落社会やその連合体がその下に「社会」を作り、先述の第二類型の民族「国家」に成長してゆく。「国家」の部分が輪郭をはっきりもっても、裾野のように「社会」を包み込むような共同体の性格を拡げて存在していると第一類型の民族「国家」に成長する。「国家」と「社会」とが明確な輪郭をもたず、まだ分離していない部分をたくさん残したところでは全体が一つの共同体で、その上層が支配する部分、その下層が従属する部分で、共同体が「国家」の役割をしたり「社会」の機能をもったりというあいまいな部分を多く残したまま民族「国家」にまで成長する。そうすると第一類型の「国家」になるといえよう。
このことからいえるように、現在でも民族「国家」にまで成長していない未開、原始の地域では「国家」、「社会」などと
呼ぶよりも「共同体」と呼ぶ方がふさわしいような第三類型も地球上には存在している。
けれどわたしがいちばん誤解して欲しくないことは、第一、第二、第三の類型に分けた方が考えやすいところがあったとしても、これらは価値の上下や善悪の区分けとは一切関係がないということだ。
(P109-P122)
|
項目
2 |
② 「国家」「社会」の関わり方は、二、三の類型に分けられるような形で現在の民族「国家」まで展開してきた。もちろん細部にわたれば、それぞれの「国家」と「社会」の関わり方は千差万別で、これらの類型は基本線を語っているだけだ。この単純な基本の類型はなぜ単純なものになるのだろうか。たくさん理由と条件が数えられるが、ここで大切なものを少しだけ挙げてみる。
①人間はもともと「社会」的な生き物だから集団を作りそれを発展させてきた。
②人間はほかの生き物(例えば猿の集団)のように単数または少数の強大な首長の下に家族も単独のものも集団としてまと まってゆく生き物である。
③人間は個別的に生きることを好む生き物だが、仕方なしに(不可避的に)集団を作りそれを発展させることになってしまっ た。
わたしたちは動物の種としての本質を現在まではっきりと解明し得ていないから、この三つのうちどれが「国家」や「社会」を現在の類型にまで展開させたのか、確かにいうことはできない。さしあたっては、この三つの要因の全部が部分的に当てはまりそれぞれの要因が混じり合い、その要因の大小によってさまざまな「国家」や「社会」を少数の類型に帰することができると考えおくのが穏当だとしよう。
人間は「社会」的な動物として、言い換えれば「社会」で日常生活をしている限りは、人種や「社会」の発達の度合いが違っていてもすぐに仲よくなれる存在だが、「国家」が介入してくるとなかなか親和力をもち得ないで、対立したり戦争をしたり、争いを繰り返して、未だそこから脱出できないでいる。これが歴史の実状で、心ある人々が現在でもどうすれば「国家」と他の「国家」のあいだに戦争とか争いとかが起こらないようにし得るかを探求しているのである。
(P123-P126)
|
| 備考 |
註 ②について、データベース項目関連 57,58
他に、DBNo364など(『マルクス―読みかえの方法』)西荻南教会・講演
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 413 |
自由な意志力 |
じゆうないしりょく |
第三章
国家と社会の寓話 |
論文 |
|
中学生のための社会科 |
市井文学
|
2005.3.1 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| 個人の「自由な意志力」の集まりだけを「社会」の公共性というべき |
|
|
項目
1 |
① 資本主義、社会主義いずれにおいてもそうだが、優等者は劣等者よりも上位だという共通した二十世紀の精神秩序が作り上げられてしまった。また「国家」や「社会」の公共性が私的な権限や事情と矛盾するとき、集団的な公共性の方が優先するという大小の権益順序がひとりでにでき上がってしまった。ファシズム、ロシア=マルクス主義、資本優先主義が、まるで競い合うようにこんな秩序を仕上げていったといえる。「国家」や「社会」や「産業」の利益は個人の私的な利益に優るという概念はまるで普遍性でもあるかのように流布されていった。また「国家」や「社会」の営業と私的(民間的)な企業経営とが矛盾するときは、国営、公営の方が優先するという理念を作り上げていった。
順序の論理からすればこの順序は逆だというべきだ。公共性、集団性、大秩序は個人の私的な「自由な意志力」(この「自由な意志力」の意味することは後ほど説明する)の総和の意味をもつときだけ成り立つ。個人の「自由な意志力」が減殺される場合には、公共性、集団性、大秩序は成立しないとみるべきものだ。二十世紀の歴史が問題性、教訓性、倫理性について未来へ残るとすれば、それが最大の点だ。
戦争、革命、産業が西欧キリスト教の倫理と合致する限りにおいて、「国家」、「社会」、「産業」は個人を超えて拡大してゆく場面ばかりに遭遇したのが二十世紀最大の特色であり、人間の精神もまたそのように順序づけられた。キリスト教的な倫理もやむなくそれを是認して、真の倫理は精神の内部の誰にもその存在の姿が伝わらないような内奥に生きる場所を見つけるほかないところに追い込まれた。「国家」、「社会」、「企業集団」は外部からこれを助長した。
② これは人間が利己心を捨て得ない存在で、「聖書」のいうように「神」だけにしか私的利害の問題を放棄できないからだろうか。これが二千年前も、二千年後の現在も「社会」が孕んでいる疑問である。わたしが現在いえることは、個人の「自由な意志力」の集まりだけを「社会」の公共性というべきで、そのほかが「国家」とか「社会」とか「公共機関」と偽証することを許すべきでないということだけだ。
(P155-P159)
|
項目
2 |
(註 島尾敏雄の体験、自分の勤労動員の体験の紹介の後 )
③ 統率力のある指導者というのはファシズムであっても、ロシア=マルクス主義であってもダメな人物であるといっていい。そしてわたしたちが学生どうしでこの暗黙の相互理解に達したとき、軍国主義の命令に従いながら、確かにファシズムとロシア=マルクス主義を超えたということを信じて疑わない。「自由な意志力」以外のもので人間を従わせることができると妄想するすべての思想理念はダメだ。これはかなりの年月、本当は利己心に過ぎない「国家」「社会」「公共のため」の名目のもとに強制された経験と実感の果てに、わたしなどの世代が獲得した結論だといっていい。わたしはこれ以上の倫理的な判断に出会ったことがない。
(P163-P164)
|
| 備考 |
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 415 |
宗教 |
しゅうきょう |
まえがき |
|
|
還りのことば |
雲母書房 |
2006.5.1 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| 宗教というのは人間(人類)の精神的活動の始源になったものだ |
|
|
|
宗教というのは人間(人類)の精神的活動の始源になったものだ。これは様々な形をとって現在(二〇〇六年)まで至っているが、大別すればその変遷は二つにわかれるといえよう。ひとつは外形を著しく変化させて倫理道徳になったり、さらに法律になったり、民族国家やその下の日常的な生活社会になったりして現在に至っている。もうひとつの精神活動は外形は宗教の形をとりながら、キリスト教、仏教、イスラム教、ヒンズー教、儒教や神道など、地域種族のちがいによって、さまざまな宗教を生み出している。また宗教の内部でもさまざまな宗派の別を生み出している。また宗教と政治の中間で区別しにくいことになっていたり、宗教と国家や法律が区別しにくい地域も種族もある。けれど古代・原始・未開の時代までさかのぼれば、その始まりは人間(人類)の精神的活動の営みだった。科学者や唯物論者にも宗教的な奥底がのこっていたり、宗教家でも迷信を信じていない面もある。ここから多様な問題が噴出するが、わたしがここで云いたいことはひとつだ。それは人間(人類)の精神的活動の始源としての宗教の意味を、政治権力や社会権力をもって禁圧するのは誤りであり、また不可能であり、自分で自分の首をしめているのとおなじことだ。ただ相互批判が自由だというだけだ。また何が信じられようと、権力によって人間の精神活動の始源性を断ち切るのでなければ自由だと言える。これは世界の多くの政治権力が宗教に対して失敗していることだ。
(P2-P3)
② わたしは信仰がないから形態的僧俗にことさら関心をもっていない。けれど人間の精神活動の始源としての宗教という意味への考察は持続している。それにもかかわらず、宗教家自体は衰弱を加えるばかりのように思える。現在の状況では、宗教家が宗教を解体できる言葉で考え、現在にこだわる思想が精神活動の人類的な始源に対する考察を深めてゆくことで、接点を明確にするよりほかに方法がないと思える。一言「まえがき」をはっきりさせておきたい。
(P4-P5)
|
項目
2 |
|
| 備考 |
註 十万年、数百万年への遡行する言葉から、繰り出されていると思われる。猿から人間へつなげてみたいという。
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 418 |
宗教とは何か |
|
① 還相の視座から |
インタヴュー |
|
還りのことば |
雲母書房 |
2006.5.1 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| 『アフリカ的段階について』を書いたときのモチーフのひとつ |
宗教の段階と地域特殊性 |
<段階>というのはどうやって区別するのか |
項目
1 |
① アメリカがテロでやられた。この出来事をめぐって、キリスト教徒イスラム教では宗教的なかんがえ方が違うからだという人がいます。しかしぼくはそうではないとおもいます。これは「宗教とは何なんだ」という問題なんです。
確かにキリスト教徒イスラム教、あるいはキリスト教徒仏教でいくらでももいいわけですが、ふたつは全然違うんだということができる。なるほど半分は地域も違うし、信仰している種族も違う。国家の現状も違う。違うということをいいたいなら、違う面を拾上げることができる。
だけどそれはヨーロッパ人の観点です。われわれから見れば、全然違うというかんがえ方と、引きずっている段階が少しだけ違っているだけだというかんがえ方と両面がありますね。つまりアメリカも、いまのイスラム教が主張している特徴を一部は通過して現在に至っているところがあるわけです。段階の名残りが違うだけなのです。半分はそういうふうにいい返すことができるし、いい返したほうがいいのではないか。
こういうかんがえ方をとると、宗教というのはかたちが変わる部分と、かたちは変わらないけど段階が変わる部分とがあることになります。宗教一般、信仰一般というのはかたちが変わるとどうなっていくのかというと、宗教のある部分を法律的なものが代表するようになってくるんです。さらにそれをもう少しつめると、法律のある部分は民族国家や国民国家が代表するようになります。
② マルクスのように経済的な構図だけをいえば、国民国家とはアメリカのいうグローバリズムみたいなもので、みんな同じようなものなんですね。資本主義化していって、同じようなものじゃないかというふうになるわけです。ぼくは世界性というのはこれを追いかけるようにして実現していくとかんがえていました。つまりみな同じようなものなら国民国家、近代国家が解体して世界性へ向かうだろうとかんがえていました。ところがそうならない。国民国家、近代国家というのは、なかなか強固なもんだねという感じですね。
ではどうして強固七日としきりにかんがえたことがあります。やはり宗教のかたちが変わったものとして国民国家、近代国家はわりと最終的な形態じゃないかとおもいます。
経済的な世界性が普遍的に影響して、そのあとを追いかけて、「世界はひとつ」というふうなことがいえるはずなのです。しかし一国の国家というのは経済的にグローバリズムでは解体しない。マルクスは「国家、民族というのは経済制度さえ変えれば徐々に、急激に変わるんだ」というけど、そうわいかないよと実感的におもうわけです。「なかなかよくならないですよ」ということになる。これが前は不思議でしょうがなかったんです。
やはり宗教がかたちが変えながら最終段階のところに到達しているということでしょうか。宗教は人間の精神の深くに食い込んでいて強固だから、経済のように歩みは早くないんです。
③ 宗教のかたちがどこから変わるかというと、強固なところからだろうとおもいます。戒律的な部分が変わって、法律なら法律というかたちになるとか、法律よりももっと強固で根本的なかたちというのは、民族国家として残っていまに至っています。これは宗教が地域性と不可分であったこととかかわりがあるのでしょう。
これに対してマルクス流にいえば、経済だけが普遍性かつ唯物的にできるんだということになりますが、それはちょっと違うのではないか。政治としての国家ではなく宗教としての国家というのは、そう簡単に経済制度が変われば変わっていくというようになものではないとおもいます。
(P38-P41)
|
項目
2 |
④ ヘーゲルがいうように、文明というか道具の発達変化で人類の歴史を段階づけてしまっては、あまりに進歩史観的すぎて無惨ではないか。このことに対してマルクスは原始と古代社会との中間に<アジア的社会>というのを入れるべきではないかと主張し、歴史的に修正しようとしたわけです。しかし入れたからといって修正したということにはならないんですね。地域的にどう変化するかということが抜けているのが、マルクスの根本的な欠陥ではないかとおもっています。
単に<アジア的段階>のようなものを原始と古代の間にかんがえるというのは、ヨーロッパから見ればいかにもごもっともだとおもいますけど、そのごもっとも性はここ一、二年になってだめだということが相当はっきりしてきました。やはり一種の進歩史観ですからね。
ブッシュの見方もそうです。キリスト教徒イスラム教が違うのだったら、ほんとうは地域が宗教にどういう影響を与えるかについてかんがえなければいけないんです。「地域的特殊性がまるで違うんだ」ということ。でもマルクスは本気でかんがえずに、とりあえずアジア的と入れとけというくらいでかんがえを止めています。これは少し違うのではないかという感じをぼくは持っています。
ぼくが『アフリカ的段階について』(春秋社)という本のなかでかんがえたのはこういうことだったのです。要するに宗教は宗教としてというふうに<段階>を歴史的にかんがえると、イスラム教徒がもっているものとキリスト教徒がもっているものとが、地域として引きずっているものとして残っている。だけどこの地域特殊性が宗教にもたらしている違いを明らかにしてしまえば、宗教自体としては見かけほど違うものではないということがいえるとおもいます。これをちゃんとかんがえないとだめだというのが、ぼくが『アフリカ的段階について』を書いたときのモチーフのひとつでした。
⑤ もうひとつは、ヘーゲルのいう未開野蛮の時代と現代とでは何が違うのかとかんがえていった場合、<死>ということに引っかかってくるわけです。
<段階>というのはどうやって区別するのかといったとき、生死の<死>をどうやってできるだけ普遍的にかんがえるのか。段階の違いを入れてかんがえるべきではないかとおもう。ぼくらが知っている段階でいえば、原始未開野蛮の時代には自由主義みたいなものがあって、天然自然は精神的威力をもってすれば変わってしまうのだというぐらいにかんがえていた。それが日本にも残っていて、たとえば奈良地方の雨乞いというのがそうです。あれは人間が祈ると天然自然は変わるよというかんがえを根本に引きずっている。これは宗教としたら現代とは段階が違う。
ヘーゲルが未開、野蛮というところは、呪術師がいて王様に絶対的な権力があってという段階です。そこからいまみたいに文明、デモクラシーを標榜する社会になったと、つまりそれを進歩としてアメリカやヨーロッパではかんがえています。実際にそうなっているかどうかは別ですが。
そうじゃないんです。未開、野蛮といわれるアフリカ的段階と近代西欧とでは全然違うかんがえ方をしています。<死>についても違うかんがえ方をしているんです。アフリカ的段階の前にも歴史がある。つまり人間と猿たちが別になったというのは百万年単位で、百万年前から繰り返し繰り返し段階があったわけです。われわれはヘーゲルがいう未開野蛮の段階から、いまの近代文明の時代までのことは知っている。だけど<死>をどうかんがえるかによって段階が区切られるわけですから、それ以前にも違う段階があったし、それ以後にも違う段階がくるとかんがえた方がいいんじゃないかとおもいます。
(P41-P44)
⑤ 言葉が民族語になったのは、大雑把にいえば十万年単位の前です。しかし人間と猿では違うよということになったのは、百万年単位の前です。その間はどうしたのということをはっきりさせたい。そういうことをモチーフに込められたらとおもっているんです。
テロ事件以後かんがえたことがあります。<生>はこういうもので、<死>はこういうものというふうにいまはかんがえています。しかし<現在>という世界が段階としてどこで終わるかということは、まだ全然わからないのです。先の段階になると、かなり違うかんがえ方をするのではないかということです。実際、その徴候が少しずつ表れてきていますね。
たとえばいまは偶然に道で出会った人を刺し殺しちゃうというようなことがさかんにありますね。こういうすさまじい事件が起こると、すぐに法律家や医者が出てきて発言する。法律の言葉で裁くか、そうでなければ経験的な道徳性のようなもので解釈する。それができなければ医者が出てきて病気だというふうにしてしまう。ほんとうをいうと、ちょっと違うんではないか。むしろ国民国家とか法が基本的に危なっかしくなっているといえるのではないでしょうか。
(P44-P45)
|
| 備考 |
註 ⑤について ハイイメージ論のころ(?)「現在の死」「社会の死」とかいわれていた言葉のイメージが、大分はっきりしてきた。
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 419 |
存在倫理 |
|
① 還相の視座から |
インタヴュー |
|
還りのことば |
雲母書房 |
2006.5.1 |
項目
1 |
① ぼくは最近、この問題について<存在倫理>というようなものを設定するしかないのではないかとかんがえているんです。社会倫理でも、個人倫理でも、国家的な倫理でも、民族的な倫理でもなく、人間が存在すること自体が倫理を喚起するものなんだという、まったく別な倫理がある。つまりそこに<いる>ということ自体が<いる>ということに対して倫理性を喚起していく。この存在倫理を設定してみると、テロの巻き添えを食って死んだ人と、乗客を降ろさなかったこととは、同じに見えてもまったく違うことなんですね。
菅瀬 存在倫理を設定する、そこに親鸞の思想が関与してくるのではないかとおもえるのですが。
そうだとおもいます。キリスト教(新約聖書)では父母兄弟をを自分より大切にする者はわれに相応しからずというふうにいっています。また親鸞も『歎異抄』のなかで、父母の供養のために念仏をしたことはないといういい方をしているわけです。「親鸞ハ、父母ノ孝養ノタメトテ、一返ニテモ念仏マフシタルコトイマダサフラハズ。ソノユエハ、一切ノ有情ハミナモテ世々生々ノ父母兄弟ナリ、イヅレモイヅレモ、コノ順次生ニ仏ニナリテタスケサフラフベキナリ」(第五章)というところです。
ふたつはどう違うのかということを関連づけながら、ほんとうはテロの旅客機の乗客を降ろさなかったことにいちばん引っかかっていたので、そこをどうにかわかりよくできないものかなとおもって書いたのです。
また親鸞はここで順次生という言葉を使っています。それはたぶん還りの言葉なのだとおもいました。生まれてきたことだって偶然だし、生んだ側からいっても偶然なんです。だけど順次生や縁や機縁などという言葉を入れたりしていくことによって、偶然性が超えられようとしているのです。どんな生も必然性ということになれば存在倫理の基礎は成立するということになります。
しかしこれはわりあい仏教的なかんがえだといっていいとおもいます。キリスト教のかんがえ方と非常に似たいい方をしているけど、違うんですね。そこのところを親鸞のかんがえで説明できないかなということだったのです。
(P54-P55)
|
項目
2 |
|
| 備考 |
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 421 |
思想 |
しそう |
第一章 思想とはなにか |
対談 |
|
思想とはなにか |
春秋社 |
2006.10.30 |
対談者 笠原 芳光
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| 理念と情念の中間 |
|
|
項目
1 |
① 曖昧だけど複雑な領域が「情念、感覚」と「理念、イデオロギー」のあいだにあって、それを考えたいというときに特に「思想」という言葉を使っているようにおもいます。それでおおよそのところは尽くせるところがあって、それでいいんじゃないでしようか。
(P7)
|
項目
2 |
|
| 備考 |
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 422 |
思想家の条件 |
第一章 思想とはなにか |
対談 |
思想とはなにか |
春秋社 |
2006.10.30 |
対談者 笠原 芳光
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| 手を動かす |
表現の価値について |
|
項目
1 |
①
文学も人文科学に属するわけですけど、そういう学者というものと自分のちがいをどこで区別するかというと、結局、象徴的な言い方になってしまうかもしれないけれど、わかりやすくいうと、つまり手で考えるんだ、手を動かして文字を表現しない限りは、想像力によるものであろうと経験的なものであろうと浮かんでこないことがあるのです。とにかく手を動かして初めて浮かんでくるというのが、小説家でも評論家でも、そういうものが必ず入ってくる。
もちろん学者が文献を調べ、ものごとを考えるとか、科学者が実験をするとか、そういうことも手を動かさないとだめなわけですけれど、手を動かすことでしか絶対といっていいほど出てこない問題とか、出てこない考えとか、出てこない想像力とか、そういうのは必ずあるわけで、それを本質的な仕事としているのが文芸家といいますか、文学の創造をやっているとか、小説を書いているとか詩を書いている人はそれで区別されるのです。学者というのは手を動かす場合は、メモをとるとかそういう意味あいでは動かしますけど、手を動かさなくても本を読んで考えれば、実験してその結果を考えればどんどん先に進むことも、深めることもできる。そこが区別のしどころです。
もし思想家とか思想者という言葉が成り立つとすれば、そこがちがうのですよ。ただ考えて実行することは政治家でもやっていますし、社会的な指導者もやっているわけですし、また人間は一般的にそうやっているということがあるわけです。そうではなくてなにか手を動かさなければ、体を動かさなければどうしても浮かんでこないんだ、ヒントが得られない、先に進めない要素がどうしても入ってくる場合、自分はそこが一番区別しやすいところです。
(P17-P18)
|
項目
2 |
②
「手を動かす」ことは文字で言葉を書くことが身体の運動といっしょになって表現ということになるわけでしょうけれど、ぼくが重要で一番基本だとおもっていることは、一種の「価値」の問題に関連するわけです。
つまり言葉における価値とはなんなのかということになると、ぼくが一番ひっかかったことは、言語をやっている人、あるいは言語学者はどこから表現の価値を作ってきたのかと考えると、経済学から価値の概念を作ってきているとおもうのです。そうすると言葉の価値と経済的な価値がどこで分けられるかという点がひっかかるのです。「資本論」をよく読みますと、これはマルクスが余計なことを書いたなといえばいえるところがありまして、貨幣と言語の価値形成の仕方はよく似ているんだと書いているところがあるのです。
ぼくは言語学者の考え方からそれを学びまして、これは古典経済学の考え方から編み出しているんじゃないかとおもって、自分で「資本論」の価値論をなぞらえながら言語(表現)の価値を考えればいいんじゃないかとおもいました。
「資本論」のなかで「使用価値」といっているものは「指示表出」といって、「交換価値」は「自己表出」といっていいんじゃないかな、と考えていったわけです。片方は物で片方は言葉で、いろんな言い方でいえますけど、いまおっしゃったことでいいますと「表現」ですが、それらはどこでわかれるのかということが問題でした。
(P22-P23)
③
そこになってくると物として表される価値というよりも自分自身の精神活動との関係で表される価値と考えないと芸術の価値論にならない、とおもったわけです。そうでないとおかしいわけです。マルクスだってギリシアの芸術がいいのはなぜなんだろうかと考えたのです。価値論でいえば、時代が進めばすすむほど価値が大きくなるのが一般的です。彼もそこで突き当たっているわけです。
ぼくもそうおもうから自己表出というのが価値であって、指示表出が表現の価値に関与するところがあるとすれば、指示性の複雑さとか明瞭さを介するときだけれど、指示表出自体が芸術の価値に関与することはないんだと徹頭徹尾考えて、自己表出が芸術の価値なんだと。
そうするとおっしゃるようにそこのところでは手を使うか使わないかは二義的な問題になってきているわけです。
(P24)
|
| 備考 |
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 423 |
世界性 |
|
第一章 思想とはなにか |
対談 |
|
思想とはなにか |
春秋社 |
2006.10.30 |
対談者 笠原 芳光
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
| 柳田国男と折口信夫 |
日本の固有性として世界性を持つ |
|
項目
1 |
① そうすると鴎外・漱石を日本の近代文学の代表者とすると、これはどんな立場の人でも認めるとおもうのですが、それと同じように折口信夫と柳田国男を日本近代における思想家だよ、というといまのところ認める人は少ないかもしれないけど、それに匹敵するだけのことはあるとぼくはおもいます。整理したり分類したりする論議は下手だけど、あのエッセイみたいに積もっているものを濃縮していくと、これは大きな、ちょっと無視しがたい思想家だといえるとおもいます。折口さんはそれに比べれば文学的な意味での思想家だといえるかもしれないけれど、やっぱり思想家だとおもいます。そういわないと、世界性をもてないのですね。
つまりナショナルなことを一所懸命に考えて、それを一行くらいで書いたか、ひとつの論文として書いたかは別として、それがないと、つまり本当の意味のナショナルなものがないと、世界性をもつことができないとおもうのです。留学して向こうの哲学を研究してきた、近代以前だったら中国、近代だったらヨーロッパ、戦後だったらアメリカで研究してきました、これでは思想家とはいえないので、もしそれを思想というのだったら日本は永久に世界性を持ち得ないよ、という気がするのです。
ナショナルな根底というものがないとだめなのです。そうすると鴎外・漱石は文学的な意味での思想家だとおもいますけど、この人をもってきて、明治以降の人文系の科学を代表できるかというと、どうしてもそうじゃなくてもう少し掘り下げて、それを身につけて個性もつけてという人がいないと。どうも日本の思想が永久に普遍化というか、つまり世界性を持つようにはならんだろうとぼくはおもうのです。
だからこの人達を入れないとこれは世界性にならないよ、よく読めば世界性のあることをいっています。折口さんもちゃんといっています。刑法の始まりみたいな「天津罪」「国津罪」という概念にたいしてつっこんでいったのは折口さんが最初なんです。・・・・・・略・・・・・・
折口さんはウルトラ・ナショナリストで右翼的だというわけですけれど、大間違いです。ナショナリズムをあれだけ根底的に世界性のあるところまで到達していっている、規模の大小でいったり、論理性の大小でいったりすればまた別な評価がでるかもしれないけど、ちゃんと到達しているわけです。
② 要するに保守的な思想があって進歩的な思想があってとか、ぼくはそれをまずブチ壊さないといけないということがありますね。それをやらないと日本の固有性として世界性を持つことはありえないなとおもいます。・・・・・・略・・・・・・
そこまで行くためには日本も柳田国男と折口信夫の仕事とやりかたを持ってこないと、漱石・鴎外ではやや不足というか、かれらだけでは日本の固有性を主張できないとおもいます。固有性を主張できないと世界性も主張できない。だから日本の世界性はいつまでたっても本当の世界性になっていかない。政治思想、社会思想、文学思想、芸術思想を含めて思想という場合には、柳田国男や折口信夫は無視できないような気がします。
(P30-P33)
|
項目
2 |
|
| 備考 |
|
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 426 |
絶対 |
ぜったい |
日本人の宗教観
―宗教を問い直す |
対談 |
『中外日報』2006年 |
吉本隆明資料集165 |
猫々堂 |
2017.5.25 |
対談者 笠原 芳光
項目
1 |
①
笠原 親鸞のいわゆる阿弥陀如来絶対信仰から自然法爾へというのは、ある意味では絶対から相対へのプロセスであるというような気がするのですが、吉本さんの場合は「関係の絶対性」という概念が最初にあったわけですね。
あの「マチウ書試論」(一九五四年)でおっしゃった「関係の絶対性」というのは、やはり相対と絶対との関係を表していると思うんですけれども、関係というのは相対的なものですよね。それが絶対だというのは一種のパラドックスなんですけれども。親鸞の場合も、絶対から相対へという単純なプロセスではなくて、絶対であって相対であり、相対であって絶対であるという逆説のようなものが生まれていると思えるのですが。
吉本 僕はそう思っているわけですね。親鸞は何か絶対を信じたんだけど、だんだんいろいろなことに目覚めるにつれて人間の関係とか信仰とか真理とかいうのは相対的なものだというところまで行ったんだというふうには、僕は今まで理解しないできました。それから僕自身がやはり絶対的なものに惹かれるというのも事実で、戦争中もそうでしたし、今でも絶対的なものというのはあるんじゃないかと思っています。
笠原 実体としてあるというよりも・・・・・・。
吉本 関係としてあり得るんじゃないかと。僕の書いた『言語にとって美とはなにか』(一九六五年)という言語論では、ある作品を一、二回読んだというと各人個性や好みもあって評価の仕方がちがうんだけど、いろんな人がそれぞれ百回読んだとすると、必ずあるところに一致する、それはたぶん作者の全意図といいますか、全モチーフを残りなくあらわしたところに収斂する、そこが終着点だという考え方がその中にあるんです。
普通、文学作品というのは、どういうふうに何回読んでもいいというのが特色なんだけど、もし絶対的な評価を求めるというなら、すべての人に百回読んでみてくださいといえば必ず作者の意図したところに収斂すると思っています。
笠原 吉本さんの本は百回読まなければならんなあ(笑い)。
吉本 だから絶対というのは、僕にとっては割と捨てがたい概念なんです。
(P76-P77)
|
項目
2 |
|
| 備考 |
この「絶対」という概念は、「普遍性」と言い換えてもいいように思われる。 |
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 430 |
自己としての自己と社会としての自己 |
夏目漱石を語る |
インタビュー |
『森』第8号2005年7月 |
吉本隆明資料集165 |
猫々堂 |
2017.5.25 |
聞き手 笠原芳光・安達純
項目
1 |
安達 吉本さんは、「文学の初源性」ということをおっしゃっていますね。文学とはもとを正せばこういうものなんだということで、漱石の作品では、『虞美人草』にそれを感じると。文学の初源性について、もう少し詳しくお話ください。
吉本 普遍性はないんだけれども、最終的に言えば、そういうふうにしか言いようがないないんだけれども、人間の存在感と言ったらいいのか、存在の倫理が、それだけが保存されていることが文学の初源性であり、たぶん最後の問題だなという感じを持っているんですよ。それをいろんな言葉で言っている。「自己慰安」という言葉で言ったり、フーコーは「自己への配慮」と言っていますね。個人としてどうであるかということから、個人が善悪に関係したり、社会に関係したり、人によっては政治に関係したりとかいうふうに全部を含めて、フーコーは配慮と言う言葉を使っている。全部を含める言葉としていい言葉だなと思う。僕としては、「自己としての自己」という変な言い方で、意味にはならないのですけれども、まったく自由である、学者を志そうが、ライブドアのように大富豪になろうと、そんなことは自己としての自己という面で言えばまったく自由であって、いけないとかいいとかそういう論議とか理念が成り立たないと思っているわけです。社会としての自己という観点からは、ある場合にはよくないよということもあり、極端を言うと、人を殺したり、近頃いろんな事件があるけれど、そこまでいくと、社会的な自己として何か言われることがあるかも知れないということとか、法律にひっかかって、そこでは何か問われることがあるかも知れないなとは思うが、ただ自己としての自己として、自由に自分の思い通りのことを思って生きること自体には別に善悪の問題はひっかかってこない、関係してこないという意味合いで、自己慰安と言う言葉を使って、自己慰安は文学や芸術にとっては少なくとも、いちばん根源にある問題で、最後にそれだけが残る、あとは残らないというふうに僕は思っている。それが自分の文学観の基本になっていて、最終的には自己慰安しか残らない。それ以外のことは何か残ったとしてもおまけで、それを当てにすることはできないふうな程度のものと思っているんです。 (P22-P23)
|
| 備考 |
※この引用文は、項目429「文学の初源性」の引用本文と同じ部分である。この項目が大切だと思われたから、独立させた。
「自己としての自己」≒私人、「社会としてのの自己」≒公人と見なせると思う。人は、現実的には様々な日々の場面で「私人」度と「公人」度のある度合いとして存在しているように思う。例えば、会社で仕事をしているときは、公人度90%、私人度10%というように。この場合、私人度は、後景に退いている。あるいは、心の深層に沈んでいる。例外的な存在として、天皇は公人度100%の存在であろう。 |
| 項目ID |
項目 |
よみがな |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 455 |
少年の世界 |
|
「銀座の思い出」 |
|
『銀座百店』2007年2月号 |
吉本隆明資料集169 |
猫々堂 |
2017.10.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| うろぼえの流行歌 |
記憶には思い込みやイマジネーションがひとりでにはいり込んでくる |
|
|
項目
1 |
①
昔恋しい銀座の柳
あだな年増を誰が知ろ
ジャズで踊ってリキュルで更けて
明けりゃダンサーの涙雨
女給商売さらりとやめて
可愛い坊やと二人のくらし
抱いて寝かせて母さんらしく
せめて一夜を子守唄
このうろぼえの流行歌(はやりうた)は少年のころ新佃島の悪がきだったころ口ずさんだもので、正確かどうか全くわからないが、曲はいまでも覚えている。ただこの歌詞の雰囲気だけは、確かに少年の日の銀座通りの古い情緒を伝えている。
勝鬨橋ができる以前の月島渡しに乗って明石町通りに出るか、佃渡しで大川をわたり真直ぐ三吉橋のわきを通って銀座通りへ出るか、どう余計な寄り道をしても、銀座四丁目と二丁目のあいだで通りに行きつく。少年よ、お前はそこでなにをしていたのかと問われると、恥しながら最初の記憶は次のようなものだと言わざるを得ない。
四丁目の辻を中心に三越・松屋・松坂屋とあったデパートの売場のケースの上に、広告ビラがおいてあるのを三、四枚ずつ失敬して歩いた。趣味ではなくて、翌日学校へ持ってゆき、屋上から紙ヒコーキをとばして仲間たちと遊ぶためだった。広告ビラで作った紙ヒコーキは悠々と風にのって民家の屋根におりたり、学校わきの道路に落ちて、道行く大人たちをびっくりさせて、学校の屋上を見上げさせたこともある。それがおもしろくて仕方がなかった。なぜわたしが銀座通り四丁目あたりのデパートで広告ビラ集めを仲間の悪童たちからおおせつかったのか、よくわからないが、ときどき月島・佃島うちから川向こうへ行って、独り渡し船でおもしろがって渡ってみたりして、馴染んでいたからだとおもう。わたしの記憶にはかすかだが、いまの中央区役所(そのころの京橋区役所)と堀割を隔てて反対側のところに貸ボート屋さんをひらいていて、母に連れられて店番をしていた幼年期があったそうだ。そんな潜在的な追憶もあったのかもしれない。この銀座二丁目裏と四丁目への直線路は好きでその後もたびたび往き来した。
記憶には思い込みやイマジネーションがひとりでにはいり込んでくる。学校(佃島小学校)から帰るとカバンをほうりなげてすぐ遊びに出かけ両親から「そんな暗くなるまで遊びほうけていると人さらいにさらわれるよ」脅されても怖くなくなり、夜まで遊んでいても叱られなくなったころだから、十代半ばにならないときだとおもう。
(「銀座の思い出」P2-P3『銀座百店』2007年2月号に掲載。『吉本隆明資料集169』)
|
備
考 |
これは、吉本少年の証言ではなく、晩年の吉本さんの記憶が呼び寄せた少年時の自己像に当たっている。誰でも通りすぎて遙か後にしか、過去を何らかの意味をたどるように追憶することはないように見える。広告ビラを集め、学校の屋上から紙ヒコーキをとばして仲間たちと遊ぶのは、後振り返ればたわいもないものに見えるのかもしれないが、少年たちはそのこと自体をわくわくしながら生きていたのだろうと思う。現在から見れば、そんなたわいもないような小さな世界に見えるが、そんな世界内に生きている〈少年〉というものがあったし、現にあり続けている。後振り返れば、誰もがそのような〈少年〉を生きていたのだと思うが、追憶からはその〈少年〉の内に入ってその世界内のわくわくした生動感そのものを味わうことはもはやできない。
この〈少年〉そのものと後の追憶ということを、一般化すると〈わたしたちの生そのもの〉と〈内省としての生〉とはいつもずれた時間の関係にあると言えよう。つまり、〈内省としての生〉は〈わたしたちの生そのもの〉からいつも遅れてやって来るというふうに。
この文章の始まりに挙げられた「このうろぼえの流行歌(はやりうた)」は、ネットで調べてみると、一連は「東京行進曲」の一番で、二連は「女給の歌」の二番である。事の真相を厳密に追究する意図はわたしにはないが、別々の歌が少年時にくっついたのか、あるいは、たぶん大人になってもときどき吉本さんは鼻歌を歌っていたようだから、「うろぼえ」で大人になって記憶をたどる時連結されたか、よくわからない。そういうことはよくあることとして受けとめるほかない。ちなみに、いずれの歌にも「銀座」という言葉が含まれている。
付け加えれば吉本さんの文章やインタビューなど読むと、吉本さんは、もう行方がわからなくなった自分の遙か昔の詩の言葉とか、割と人並み以上の記憶力、再現力を持っていたように見える。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 456 |
社会での目の置き所 |
インタビュー「まだ考え中」 |
インタビュー |
『論座』2007年4月号 |
吉本隆明資料集169 |
猫々堂 |
2017.10.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 社会を見る上で |
中の中以下の人たち |
この人たちの視点でこの日本の社会を捉える |
|
項目
1 |
①
吉本 僕がこの社会を見る上で一番関心を持っているのは、中の中以下の人たちです。自分を離れて、この人たちの視点でこの日本の社会を捉える。もちろん僕は、為政者が持っているような特殊な情報や世界情勢なんか全然分からないけど、そんなのは無視します。自分でつかんだ実感や理念が正しいんだと考えています。だから朝日新聞がいくら「いざなぎを超える好景気」と書いても、「ウソつくなよ」と言うだけです。(笑い)
(インタビュー「まだ考え中」P10『論座』2007年4月号、『吉本隆明資料集169』)
|
備
考 |
戦争・敗戦体験の内省から若い頃吉本さんが述べていた「社会総体のイメージ」ということ。吉本さんはこれを生涯持続してきたと思う。そのイメージを獲得する上で、社会の「中の中以下の人たち」の場所と視点は大切だということ。それはなぜかと言えば、社会の「中の中以下の人たち」にこそ社会の矛盾や重圧がより大きく作用し、生き難さがより強く感じられるからだと思われる。現在で言えば、派遣社員などの労働を強いられている人々はそれに当てはまるだろう。また、離婚などによる片親の家庭や単独の老人家庭などもそれに当てはまるだろう。
「自分を離れて、この人たちの視点でこの日本の社会を捉える」ということは、難しいことであるが、一般的に言うと他者理解ということになる。他者の置かれた経済的・精神的状況をいろいろな条件や現実を踏まえて、実感と創造力によって把握するということだろう。
「為政者が持っているような特殊な情報や世界情勢なんか全然分からないけど」に関しては、吉本さんは誰もが手に入る新聞を読むことを大事にしていて、それを中心的な素材としているとどこかで述べられていた。現在は、吉本さんの世代の情報(獲得)世界からずいぶん情報世界が変貌してきている。誰もがネットに接続することによって、情報の大きな渦の流れに出入りしてさまざまな情報を発信したり受信したりできるようになってきている。しかし、こういう状況だからこそ、情報の大きな渦の流れに流されないようなわたしたちの主体としての対象選択やそれらを素材とした自己対話などがいっそう重要になってきたと思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 463 |
政治に対する見解 |
「政治権力と社会の成り立ち」 |
インタビュー |
|
『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 |
春秋社 |
2012.10.20 |
※ このインタビューは、2008年5月から6月に4回に渡ってなされたと巻末にある。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 内密に決められて行われるということ |
相互関係 |
|
|
項目
1 |
①
自分なりによく知っているからいえますが、政治に対する見解のようなものだけは、普通の社会的な生活をしている人が判断すると、必ずまちがうような気がします。
政治というものは、その中間に、どうしても内密に決められて行われるということがあって、それに従わざるをえなくなっていく、ということが必ずありますから、その「内密に」というところが、一般の生活をしている人にはなかなかわからないのです。
正確な判断ができるという人がいるとすれば、それは社会的な上層にいる知識人とか、ある程度情報を得ることができるような場所にいる人ぐらいのもので、一般的な人はまずそうはいかない。
だからそれは逆にいえば、政治権力を獲得して、しかる後に革命をするとか保守的にするとか考える政治家とか政治運動家というのは、一般の庶民の考え方には届かないよということだと思います。
それはある意味、相互関係のようなもので、庶民とか民衆の方が政治について判断すると、たいていどこかまちがえているというのとまったく同じことです。
②
極端にいえば、政治がやることや、政治家たちの言動の広まり方というのは、庶民たちのそれに比べて格段に大きいわけですから、政治の方がまちがえれば、それが倍増して庶民の方に入ってきてしまうということになります。
政治のように上の方から決まっていくということには、どうしてもそういう問題がありますし、ある場合には、われわれはそれに従わざるをえないということが起きてしまいます。
下から決まっていく親子関係とか親族関係というのは、個々のメンバー同士の考え方が集まって、だいたいひとつの雰囲気が出てくるわけですが、政治のように上の方から下の方へと及んでいくというものはどうしても違ってきます。
※①と②とは、連続した文章です。
(『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 P15-P16 2012年10月)
※本書は、2008年5月~6月のインタビューより構成
|
備
考 |
(備 考)
例えば、都議選で小池百合子率いる「都民ファーストの会」が、従来の古臭い自民党行政とは違うことをやってくれるかもしれないという東京都民の支持を取り付けて圧勝した。都議選といってもわたしとはほぼ無縁な地域選挙だから、わたしはふしぎな気持で遠目で見ていた。そのふしぎな気持というのは、日本会議の役員もやっている小池百合子がまともな行政をやれるのだろうか、さらには、石原都政時以上に教育行政などに手を突っ込んでくさびを打ったりするのではないか、あるいは、日本会議の役員や今までの発言は自民党という政党の中にいたからで、そこは政治家というのは臨機応変の自由度を持っているのだろうか、それにいろんな政党を渡り歩いてきているし、など政治や政治家に通じていないわたしにはよくわからない疑問とともにふしぎな気持だった。しかし、都議選後に「都民ファーストの会」の都議にマスコミに出ないようにということが上からの統制として来ているということを知って、ああやっぱりなと思い直した。
そして今回の衆議院選挙である。わたしは、都議選で小池百合子率いる「都民ファーストの会」が圧勝したのは、自民党に代わるものが「都民ファーストの会」しかなかったから都民は都民ファーストの会」を選択したのだろうと思っていた。だから、都民を欺くような姑息なことをしたらはねかえされるだろうと思った。
今度は国政にも手を伸ばして、小池百合子らが希望の党を打ち出し、「排除」や選別とやらを得意げに言ったとき、自らの正体とともに、都民の選択の意味を理解できていないことを公然とさらけ出してしまったのである。つまり、都民の消極的な選択を積極的な選択と勘違いした、あるいは、自分たちの政治行動をすべて支援してくれるものと勘違いして図に乗ってしまったのではないか。その勘違いを、国政のレベルでやってしまって反発を食らってしまったのである。現在では、情報は瞬時に伝わってしまう。しかも、大衆の情報力と判断力も高度化してきている。つまり、政治や政治家の振る舞いを隠しようがないような状況になってきている。
「内密に決められて行われるということ」は、政治の外に日々生活しているわたしたちには確かによくわからないことであるが、その「内密」を想像させるものが漏れ出してくることがある。例えば、「都民ファーストの会」の都議にマスコミへのコメントをさせないとしていたこと、その後、「都民ファーストの会」内部の問題を指摘して二人の都議が離党したこと。国政の希望の党では、「排除」ということを言い出したこと。わたしたちは、こうしたものによって政治や政治組織を推し量るほかない。一方で、公明党の宗教とアイドル性が混じったような選挙応援風景もあったようだ。集票が功徳であるとか、代表への「なっちゃん」コールには驚いた。自民党の丸山和也参院議員が岩手県一関市で19日夜にあった衆院選岩手3区の自民候補者の個人演説会で、「相手候補に投票する人は脳がおかしい」と発言したそうだが、わたしはその公明党の選挙応援をそのようには思わない。ただわたしたち大衆の自立度からすれば、宗教性やアイドル性にイカレていてまだまだ迷妄だなと思うばかりである。
また、選挙直前にツイッターで民進党の前原代表と希望の党の小池代表との関わり合いが本当のところはどんなだったらしい、というツイートを目にしたことがある。それ以前にも、今回のふしぎな政党間の劇の真相についてのツイートを目にしたことがある。もちろん、この件はわたしが直接触れ得るものでもないから、(ふーん)くらいの気持で目を通しただけだった。吉本さんが指摘した、「一般の庶民の考え方には届かない」政治運動家と「政治について判断すると、たいていどこかまちがえている」庶民との「相互関係」は、今後当分続いていくだろうけど、政治家や政党の「内密」ができ得るかぎりはオープンにされていくならば、その「相互関係」はいくらかマシなものとなっていくだろう。
たぶん、集落社会から一歩抜け出た太古の巫女やシャーマンたちも、集落の普通の成員からはうかがい知れない「内密」を抱え始めたに違いない。
ところで、わたしの政治や政治家に対する原則は単純だ。この社会内における悲しみと喜びとが混じり合ったわたしたちの日々の生活が、できるだけ穏やかでいい感じであればいいと思うだけである。つまり、それを大枠として支援しない政治や政治家は無用だと思う。わたしの理想のイメージは、学校で学ぶ漢文に載っていることがある、誰が政治をやっているか知らないで平和で安楽な生活を喜び楽しむ「鼓腹撃壌」(こふくげきじょう)のイメージに近い。そうして、柳田国男がその文章の流れの中で時々見せているが、村々の風景に佇み、ほっとくつろいだ表情を浮かべるとき、柳田の視線はそのようなイメージの具体性を発掘していたのだと思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 466 |
詩の世界から |
「情況への発言」(一九八六年十一月) |
論文 |
「試行」66号1986.11.25 |
『「情況への発言」全集成3 1984~1997』 |
洋泉社 |
2008.5.22 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
サブカルチャー的なものに、
詩は『追いあげられてる』 |
じぶんの詩の自己評価 |
じぶんがいる場所とそこから視える世界を至上とおもわないこと |
項目
1 |
①
客 きみのいうメッキが剥がれたでおもい出したけど、ついでに松浦寿輝と朝吹亮二の「現代詩がサブカルチャーに媚びるとき」(『ユリイカ』一九八六年五月号)の発言にも触れておこうよ。「"大衆"コンプレックスでかんじがらめになった吉本隆明氏の状況判断が、詩の世界を締めあげてきたわけだよね。サブカルチャー的なものに、詩は『追いあげられてる』って言うわけでしょ、彼は。だけど本当にそうなのか。僕は稲川さんみたいに政治的陰謀だとまでは思わないけど、とにかく僕自身はそんなものに全然『追いあげられて』なんかいないわけですよ。」なんていって、きみは凄い腕力の持主で「詩の世界」を絞殺しつつある犯人だってことになってるぜ。
主 冗談じゃねえよ。おれは徒党的に物を書いたり、正義や倫理を背負ったつもりで脅迫やテロをやる連中をいちばん憎悪してきた人間だぜ。「詩の世界」を絞り上げたり、詩人を締め上げたりするために物を書くか。この阿呆は。勝手な被害妄想だ。たぶんおれは詩についても、じぶんの考え方の流れを尊重してきたほうに属する。おれはじぶんの考えの根拠を示さずに、突拍子もないことをいった覚えはない。この連中はじぶんたちの書いている詩の苦心の仕どころや成果を、おれが評価しないということが不満なんだ。正直にそういえばいいんで、この連中の書いている詩なんて、べつに難解でもなんでもないから、じつに誤解しようにも、しようがないものだ。だが松浦や朝吹には現代詩の全体像などわかるはずがない。じぶんたちが書いているような言葉の〈抵抗〉が現代詩だとおもい込んだ観点から、それ以外の詩法の詩が幼稚だとおもっているだけだ。ましてサブカルチャーの世界の詩はそうだとおもい込んでいる。ある重要なものが現代詩についてか、「"大衆"でも何でもないただの普通の人」についてか、誤解して視えていない一点があるとだけいえば、松浦や朝吹については充分だよ。この人たちはもっと本当に、サブカルチャー的なものに「追いあげられて」、「"大衆"でも何でもない、ただの普通の人」などと口に出す余地もなくなるほど、心的に急迫したほうがいいんだよ。
客 朝吹亮二のほうは「吉本さんは思想家としては超一流の人物だと思うけど、詩人として秀れた仕事をしたとは思えないんだよね。」なんていってるぜ。これもひとこと、感想ないかね。
主 いや、おれも詩についてはそうおもってるよ。いやしくも批評文を売って喰っているおれが、じぶんの詩の自己評価で誤差をもったら眼もあてられねえや。でもほんというと、中原中也と立原道造を除いたら、あとの昭和期の現代詩は五十歩、百歩だとおもっている。もちろんおれの詩なぞ二十歩だとしてもいいんだよ。さてこれから三十歩くらいまでいけるかどうか、わかんねえな。時間がなく、そして走りつづけなくちゃいけないモチーフが急迫しすぎているよ。
詩は自己慰安から出発するので「同時代の日本の詩人たちが営々と築いてきた詩の営み」とかけ離れたって一向にさしつかえない。そんなものは結果にしかすぎないんだ。・・・中略・・・だけど松浦や朝吹にいっておくけど、たしかに「知力を傾けて」詩が書かれているけど、君たちの詩には性的な魅力が無えんだよな。じぶんがいる場所とそこから視える世界を至上とおもわないこと、その場所にいながら、そこを「脱」している眼をもちつづけること、これ以外に「追いあげられてる」じぶんのゆく道はないとおもい込んでいるほど、おれは急迫しているんだ。松浦さんや朝吹さんよ、貴方がたはせめておれくらいは「追いあげられてる」べきだ。
(「情況への発言」(一九八六年十一月)P147-P150『「情況への発言」全集成3 1984~1997』洋泉社)
※主客の対話の行間は当方が一行空けています。
|
備
考 |
(備 考)
調べてみると松浦寿輝と朝吹亮二は、2017年の現在ともに六十代半ば近くだから、上の話はかれらが三十代の若い頃ということになる。ネットでチラ見した程度では、確かに「知力を傾け」た詩を書いているようだ。わたしは二人とも名前は耳にしたことがあるがその詩を読んだことはない。詩の世界の少しノー天気な住人のようだ。しかし、詩の世界にも吹きさらしの現実の風は、言葉という場に変換されて侵入してくる。したがって詩の世界でノー天気でなければ、詩人は、言葉の表現という世界で、その世界に自らを開きつつ自らの言葉の総量で自己解放の表現を成し遂げようとする。
二人は、引用された端々の言葉から見ても若いといってものんきな現状分析しか持てていないように見える。吉本さんの中には、当然現在とは規模が違っていたとしても、新古今の時期の俗謡などに追い上げられた詩(和歌)の世界との共通性という認識も念頭にあったのではないかと思う。吉本さんはすでに、西行や実朝や良寛などの詩人(歌人)の考察や、『初期歌謡論』(1977年)や『戦後詩史論』(1978年)などの詩史の考察も成し遂げてきている。
ちなみに、この頃の吉本さんは、後に長編詩の『記号の森の伝説歌』(1986年12月)にまとめ上げられていく詩、「遠い自註(連作詩篇)」(『吉本隆明資料集57』猫々堂)を書き継いでいた頃に当たっている。また、数年後には、『言葉からの触手』(1989年)も出されている。これは、最初手にしたとき批評だろうか、いや詩のようでもあるなと思ったことがある。詩集とは銘打ってないし、「あとがき」の吉本さんの言葉も「この断片集は」となっている。しかし、高橋源一郎だったか、『言葉からの触手』を詩集であると述べていたような気がする。またそれは、『吉本隆明全詩集』(思潮社
2003年7月)にも収められている。『言葉からの触手』は、考察する手の詩とでも呼べるような作品である。
吉本さんは、思想や批評の世界の深みに入り込みすぎて、腰を据えて詩に取り組めないことに焦りやあきらめなども抱いたりしたことがあるのかもしれない。人が二つ三つのことを同時にそんなに深く取り組むことは難しいからである。しかし、このことは吉本さんに限らずだが、詩以外の表現も根底的なレベルでいえば、そこでは短歌や俳句や詩や物語や批評などの各表現の形式は溶けてしまって、〈詩〉の表現と見なすことも可能だと思われる。すなわち、濃縮された表現というイメージという位相では、人間の、人間的な、共通の有り様の場に収束していくからである。もちろん、このことを直ちに具体的な表現形式や表現世界と結びつけることはできない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 469 |
三人以上いれば |
「よりよい理想社会をつくるために」 |
インタビュー |
|
『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 |
春秋社 |
2012.10.20 |
※ このインタビューは、2008年5月から6月に4回に渡ってなされたと巻末にある。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 現在の段階の国家 |
鎌倉幕府も、室町幕府も、戦国時代の武将も、考え方としては |
庶民の方は |
まったく考え方の経路が違う問題 |
項目
1 |
①
ぼくの考え方でいえば、現在の段階で国家といわれているものは非常に強固なもので簡単にはなくならないと思っています。
強固な理由はいろいろあり、氏族的な統一性、同一民族だという理由もあるでしょう。風俗・習慣が似通っていて、共通の言語をもとに考え方が似てきたためということもあると思います。けれども、それらはすべて問題の裏返しともいえます。つまり、ほんとうに同一の民族といえるのか、それぞれの地域性の違いの問題はどうなるか。
だから、国家として存在するかぎり、それらはそういうものとして存在させるということだと思います。それでまとまり、矛盾しないで考えられる場合には、いまの可能性のある考え方としては、国家は国家としてそれぞれの利益を持ったまま、存続していくと思います。
その代わり一時代前、一~二世紀前のように、国家が国家として閉じてしまうことは避ける。つまり、国家はいつも開きながら、現在の段階では、そのなかで国家を基準として、国家に付随する風俗、民族の血縁関係とか、そういう地域性の違いをそれなりに保有しながら、少なくとも政治その他の問題に対しては開いておく。それで、それを拡大していく。グローバルというのは、そのように必ず開かれたものだろう、ぼくなんかそういう考え方です。
では、国家はどうすれば開くのだといえば、ほんとうはそんなことはわかるわけがないですから、まず国家を国家と考えるから難しいのであって、もっと身近なことで考えていけばいいと思います。
②
それぞれは違うだろうけれども、それを望む個人が、会社の同僚や親密な仲間、あるいは親戚など、三人以上の人間で日常的なことに取り組んでいくということから始めていくということでいいと思いいます。それなら平等で自由にできるし、自由にならない問題は外して、自由になる問題から、進めばいいのです。
つまり、三人以上というのは、同じ集団の問題が本質的に三人の問題の中に必ず入ってきますから、そこから始めて、そこをうまく運営できるくらいなら、開かれたものがやりようによってはできるはずではないか、と思うのです。やってみて、まちがえたらまちがえたでだめになるでしょうが、まずは、できるはずではないかと考えるほかに、いまの段階では方法がないといえます。
③
ぼくはそう思いますが、柄谷行人さんたちはそうではないと思っています。まず衆知を結集して、そういう望ましいと思っている人たちで政党を作って、それが権力を取って主導して、一般の人たちをそういうふうに導いていくのだという考え方をされています。
それで、どちらがよいかとなれば、なんとなく三人の仲良しから始まった方がいいわけで、それで開いていった方がいいとぼくは思います。
つまり、鎌倉幕府も、室町幕府も、戦国時代の武将も、考え方としては、自分たちが他人よりも大きい権力を握るということがまずいちばんの問題で、権力を握ってから後、よい政治をするか悪い政治をするかという問題が出てくる、という考え方なのです。
けれども、その考え方と、当時の一般的な庶民が望ましいと思っていたことや、願っていたことは、まったく次元が違います。
庶民の方はようするに、自分と仲良しの人や、同じ信仰を持っている人同士で、お互いに助け合おうではないか、というところから始まっていくわけです。庶民は庶民同士で、三人以上いたらその中では少なくとも開いているという、外に向かってなにも特権もないし、特殊性も主張しないところから始めるという考え方を持っていたのです。
まったく考え方の経路が違う問題だから、別に鎌倉幕府を作ったからといって、一般庶民が幸福になるとか、そんなことは関係ないわけです。幕府ができたとか、何々政党に勢いがあったりなかったり、そうひうしていることは、前段階の問題であって、庶民一般がそのためにどうよくなったか、という問題はその後にしか来ないのです。
そのうえ、おれたちが政権を取ったら開放されるぞ、というけれども、なにも鎌倉幕府ができたからといって、当時の侍や一般庶民が解放されたというわけではないのです。
また幕府を作った人間の方も、まず幕府を作ってから庶民の平等について考えよう、なんて日頃考えているわけではない。まず、自分たちの勢力の拡大に最大の焦点を当てているわけです。そこは考え方の違いだけれども、それらを混同するとだめなのではないか、という気がします。
(「よりよい理想社会をつくるために」P151-P155 『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』) 2008年のインタビューで構成。
※①、②、③は連続した文章です。
④
だから、誰かがなにかをしてくれるはずだとは思わずに、自分たちで精いっぱい考えて、圧縮するというか、縮小して、気心の知れた友達同士で同人雑誌を作るみたいな感覚を持ち、三人以上いればしっかりした集団ですので、そこでいろいろなことをやってみる。つまり、ここだけはすこし自由・平等なんだという、三人ぐらいでそういうものを作っていく、といったことがたくさんできていけばいいと思っています。
ほとんど空想のように思われるかもしれませんが、そういうことでしか可能性はないのではないかとぼくは考えています。
(「同上」P156-P157)
|
備
考 |
(備 考)
この「三人以上いれば」という吉本さんの言葉は、はじめて出会ったとき、わたしはふうんという気持ちで唐突でよくわからないなという印象を持った覚えがある。その後、その言葉はどこにあったかなと、ずっと探している言葉だった。吉本さんの晩年の考えである。
①の終わり部分の「国家を開く」ということに対しては、今までの吉本さんは例えば以下(★)のように述べていた。ここで語られていることは、過去の歴史と現在を貫き、現在の情況を踏まえたもので、「国家を開く」ことの困難さからの少なくとも現実性を持つと考えられる別の視角からの捉え方であろうと思われる。アジア的な世界における政治と生活世界の大きな断層は、故事成語の「鼓腹撃壌」(こふくげきじょう)にも現れている。ここの吉本さんもそうしたアジア的世界の残滓の現在に立っているような印象がある。そして、そこからの、この吉本さんの具体性のイメージは、「鼓腹撃壌」の中の民衆のイメージとは違って、透徹した認識のまなざしとしぶといつっぱりの力を秘めているように見える。
わたしたちも、無益な対立や無用な旅をしないためにも、この社会や歴史は、どこでどのように変わり、変貌してゆくのかということをしっかりとつかんでいくことが大事なことだと思っている。ちなみに、その「歴史の無意識」の流れを含んだ歴史の主流を意識的に変革しようという理想社会を追い求める意識的な運動(革命)は、血塗られてことごとく失敗に終わっている。
(★)
吉本 いまおっしゃったことに関連することで、ぼくが考えているマルクスに対する関心を申し上げます。一つは、社会主義というモデルで基礎的な条件は、いくつかで言い尽くせるとぼくは考えます。ぼくの考えている社会主義のモデルの骨組みは、ひとつは賃労働がなくなること。なくなるということの意味あいは、賃労働的なものはあっても、それが何かに取られてしまうとか、よけいに働き過ぎるとかということがなくなること、これが一つです。
もうひとつは、やはり先程の問題に関連して言えば、つまり非政治的な大衆の同意なしに動かせるような軍隊、警察、大衆弾圧力を持たないこと。それから第三には国家が「開かれている」こと、つまり、非政治的な大衆が、いつでも政府や国家を直接リコール出来ることです。この三つの条件で十分だと思うんです。あと一つだけ条件をいえば、市民大衆、労働者というものに、そうしたほうが利益になるという生産手段に限って、社会的な所有といいましょうか、社会的な管理とする。そのくらいの条件があれば、十分社会主義のモデルが作れるとぼくは考えるんです。そうすると、現在の社会主義国は、だいたい全部の条件で落ちると思います。
(「国家と言葉」P176-P177『「反核」異論』1982年)
※「国家と言葉」は、J・P・ファーユとの対談
(★)
国家なら国家を開くことができれば、だいたい過渡的にはそれで成り立っていくんじゃないか、労働者の解放ということは言えるんじゃないかと考えるわけです。
国家を開くというのはどういうことかというと、ソビエトでも資本主義国でも同じですが、要するに国家を労働者も含めた一般大衆、われわれみたいに普通の人の過半数なら過半数、3分の2なら3分の2の直接投票でリコールすることができる。
つまり、直接投票で3分の2以上が政府に対して不信だとなったらば、その政府は替わらなくてはいけないという法的な規定を設けておけばかろうじて、労働者自体の国家でなくても、一般大衆自体の国家でなくても、官僚が事務的には支配している国家であっても、それは労働者あるいは大衆の国家だと言えるんじゃないか。議会ということではなくて、そのことだけは一般大衆の無記名の直接投票で、たとえば3分の2以上の人たちが、この政府は気に食わない、取っ替えたほうがいいとなったらば、その政府はやめなくてはならないという法律規定をひとつ設けておけば、だいたいにおいて過渡的には大衆、労働者の解放された国家と言えるんじゃないかと僕らは現在までのところでは考えています。
(「3国家を開くこと」『甦るヴェイユ』講演1992年12月19日/20日 「吉本隆明の183講演」の「講演テキスト」より)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 472 |
精神の病 |
「Ⅱ 現代を超える視線」 |
質疑応答 |
|
『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』 |
河合文化研究所 |
1987.12.1 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 歴史の経路 |
精神の病について二つのこと |
|
|
項目
1 |
①
それから精神の病ということですけれど、ちっとも正確ではないのですけれど、大雑把な意味では前からわかっていることが少しあります。それはひとつは精神の病になった時のふるまい方とか、精神の世界の広がり方とか、幻覚のようなものをまじえての内面世界のできあがり方についてです。人間の歴史の中で人間が動物と同じように、一人一人がメチャクチャに獲物を探して喰っていたという時代から、なんとなく家族を作って子供を作って、それだけが同じ所に同居するようになって、そういうのが沢山いて、それでまた集団への共同体ができて、またそれが村になってというような歴史の経路があります。その経路のある時期に、人間が考えていたとか感じていたことと、精神の病気の時のふるまい方は、大雑把に言いますと対応させることができると思われます。つまりどんな異様な精神の振舞いも、かつて歴史のどこかの時代に人間が振舞ったこと以外の振舞い方はしないものだということです。もう一つあります。
②
大雑把な言い方をしますと、精神の病気が起こりやすい人と起こりにくい人と、どこで決まるかと言いますと、一つは胎児、つまりお腹の中にいた時。それから乳児、つまり、自分では生きることができなくて、母親から授乳されて初めて生きていくことができた時期、また移動することも自分ではできないので、母親が移動させてくれなければ移動できない。そういう、乳児の時とか胎児の時の母親との関係の仕方と、思春期のはじめごろ、今なら中学の高学年のころの周辺の人たちとの―自分と第一次的に接触する人たち、特に接触する異性ですけれど―関係の仕方に、もし沢山の失敗があると、精神の病にかかりやすいということがいえそうに思います。それは純粋に、精神的に考えてそうだと思います。
ただ、生理的―遺伝の要素が、どのパーセントあるのかというのが、なかなか確定しにくいことです。というのは、精神の病に生理というものを―脳細胞のあり方がどうだとかいうことや、脳細胞にこういう要素があるからということと―関連づけるということは、今のところ、とても難しいのです。何らかの関連はあるのでしょうけれど、関連づけることは大変難しいから、うまく確定されていないということがあると思います。
つまり精神の病については大雑把にその程度のことはわかっていて、人間が精神の病になったからといって、全く奇想天外に、かつて人類がやったことのない行いやふるまい、考え方とか、幻覚をとることはないのです。必ず人類は、ある未開の段階か原始の段階か、あるいは古代、もっと前かも知れませんけれど、その時に考えたり感じたりしていた、その経験のある考え方でしか、精神の病にかかった時のふるまいとか心のあり方は、成り立っていない。そのことくらいは、大雑把に言えると思います。全然メチャクチャな精神の病はあり得ないので、必ず自分や自分の両親は体験していないけれど、かつて人類が原始時代であった時とか、自分の祖先が原始時代であった時に、必ず体験しているというか、そういう精神のふるまい方をしているとか、そういうものの見方をしているとか、そういう幻覚の世界をちゃんと持っていたということであることに違いないということくらいまでは、大雑把に言えそうな気がします。
③
しかしまだ、やればもっと分かるということが、沢山精神の医学の中にあると思います。それがある限り、たとえば今の質問をされた方だけではなくて、誰でもが専門家は勿論ですけれど、追求することをやめないだろうと思います。もっと人間の精神について、あるいは肉体について、生理について追求することをやめないだろうと思います。
(『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』P76-P78 吉本隆明 河合文化研究所 1987年12月)
※この引用部がある「Ⅱ 現代を超える視線」は講演後の質疑応答。
※①、②、③は連続した文章です。
|
備
考 |
(備 考)
③の人間が「分かる」という観点からすれば、人間の歩みは、個の生涯においても人類においても、分かろうとする絶えざる旅の途上にあると言うことができる。人類が獲得したというか、押し上げてきたというか、そのような世界認識や世界了解の現在的な地平の上に立って、人は少しでも新たな「分かる」ことを付け加えているのだろうと思う。
人間の精神の病は、今までに人類がたどってきた精神の振る舞い方以外はしないという吉本さんの認識は、もうずいぶん昔のことであるが、人間の生み出す文化や文明の下での人間の考え方や思想についてもそれと同じようなことを述べられていたように記憶している。それに関しては、わたしは(ほんとうにそう言い切れるのだろうか?)と疑問に思った覚えがある。
わたしたちは、まだまだ精神の病の高じたものとしての「統合失調症」について、その内在的な世界について、十分に分かっているわけではない。しかし、この日常の関係的な世界で汲々と追い詰められれば、閾値(いきち、しきいち)の差はあっても誰もがそういう世界に落ち込む可能性を持っているはずだ。
ところで、わたしたち人間には、心臓の拍動のような、自分の意思で制御できない、知らない間に動いている不随意運動がある。このことは、そのような生理的なものに限らず精神的なものについても言えるように思う。つまり、「分かる」ということには、上の③のような外に取り出して分析的に目で見てもはっきりと分かるということ以外にも、わたしたちの心身の内でなんとなく分かるということもありそうに思っている。前者については、太古の人々と現在のわたしたちとでは、分かることの歴史的、段階的な差異がある。そのことは進歩という言葉で語られたりもする。しかし、後者の分かることに関しては、太古の人々も現在のわたしたちも同一ではなかろうか。その不随意的な内面知とでもいうものは、人間の本源的な性質に規定されているように見える。太古の人々も現在のわたしたちも、その人間存在の根っこのようなものから照射されているから、姿形は変わっても、吉本さんが述べたように、その内面知に関わる人間の考えや思想は古代あたりまでに出尽くしていて、新しいものはないと言えるのかもしれない。
②に関わることで、子の内面の原型を決定するものとしての母の形式に直接、本格的に吉本さんが触れるのは、「母型論」(雑誌『マリ・クレール』1991年5月号)である。『母型論』は、1995年11月に刊行されている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 473 |
三人以上いれば・続 |
「吉本隆明インタビュー」 |
インタビュー |
|
季刊誌『kotoba』2011年春号(第3号) |
小学館 |
2011年 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| アンチテーゼなんか終わったんだ |
戦後の農地改革に相当すること |
普通の人が |
|
項目
1 |
①
ご社会の変革は可能か(引用者註.小見出し)
― たとえば明日から総理大臣をやれ、と言われたら、やる準備はありますか?
(吉本) 面倒くさいから寝転んでいたほうがいいよ、と本音では思います(笑)。でも、お前はこれま
で大きなことを言ったり書いたりしているけど、本当にできるのか、と言われれば、それはできるのは当たり前です。左翼の中には、いまだに何かのアンチテーゼで考えているやつらがいるんですよ。だけど、僕らはもうアンチテーゼなんか終わったんだ、とずっと言ってきた。次にどうすればいいか、俺にさせてくれたら、翌日からでもちゃんとやってみせるぞ、と思ってます。
戦後、アメリカが日本に占領軍としてやってきて、一つだけいいことをしたんですよ。それは小作人を解放したことです。アメリカの軍人にそういう思想があったわけじゃなくて、占領軍と一緒に来た日本学者が教えたとおりにやった。日本からも然るべきいい学者を集めて協議させて、地主の畑を耕していた小作農をぜんぶ解放して自作農に変えちゃった。それでも誰も文句を言えないんです。これは胸がすーっとするほど、たいへん見事なものでした。アメリカはそれだけのことはやって日本を
占領した。日本の政治家が考えもしない戦後のいちばんの大変革、いわば革命です。ただし、アメリカが日本でいいことをしたのは、それだけですね(笑)。
― いまの日本も、戦後と同じくらいの大きな変化が必要な時期だと思います。
(吉本) ある意味では、当時とそっくりですね。民主党はもっとやると思っていたけど、自民党と何
も違わなかった。知恵なんか何もなくて、素人が考えるようなことしか考えていない。
戦後の農地改革に相当することがあるとしたら、いまであれば失業者とか、家を取られてしまった
人に、お金をいちばんに与えることです。金持ちの会社からふんだくって与えればいい。そういう
人たちがちゃんと働ける場所に直すということは、黙ってたってせざるを得ない。もし僕が総理大臣
だったら、多少の抵抗があったって、それを強行します。どんな人が総理大臣になっても、それは
やらなきゃお話にならない、それを真っ先にやって、それからが本当の変革だということですね。
― こんどは日本人自身の手で社会を変えられるでしょうか?
(吉本) できるか、できないかといえば、それぞれの境遇や運命があって、誰もなかなか大口は叩け
ない。でも、もし自分にその番が来たら、まずは世の中を平らかにして、何か開かれたな、と思え
るようにする。隠れて背後で何かをやるみたいなことは絶対にしないで、開かれた場でちゃんとや
ってみせる。普通の人の誰もがそう思うようになったらたいしたもので。そのときは本当に社会は
変わります。そうじゃなければ、決して変わらない。共産党を頼ってとか、社民党を頼ってとか、
そんなことで変わるわけがない。それは自明の理だから、そんなことはあてにしないほうがいい。
心の中で、普通の人が「俺が総理大臣になったらこうしようと思っている」ということをもてたな
ら、それでいいんですよ。あとは何もする必要ないから、遊んでてください (笑)。
(終わり)
(「吉本隆明インタビュー」 季刊誌『kotoba』2011年春号(第3号) 小学館)
※ 項目469 「三人以上いれば」は、『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』(2008年のインタビューで構成)の「よりよい理想社会をつくるために」という章から引用した。
|
備
考 |
(備 考)
項目471 「〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉」に関係づけて、「三人以上いれば」問題を捉え返してみる。
前回の吉本さんの「国家を開く」ための方策で、その「備考」で引用した吉本さんの以前の考えは吉本さんの言葉で言えば「永続的な問題」であり、今回の「三人以上いれば」という考えは、現在の状況を踏まえた「現在的な問題」と捉えることができると思う。2014年8月にわたしがネット上で開始した「消費を控える活動」の呼びかけも、そのような現在的な状況と無縁ではない。こんなにもだらだらと現政権が続くことになるとは予想できなかったので、わたしの活動も自然とだらだらになってしまった。そのことは、活動自体の現在的な現実性とわたしの構想力の不十分さとが関わっている。しかし、わたし個人の「消費を控える活動」という日々の意識と行動は、文学的な表現と同様持続している。これはそろそろしめくくりをするべきだと感じている。
今回に引用した「吉本隆明インタビュー」は、以前別の文章で触れた覚えがある。しかし、何度読んでも味わい深い言葉として再度取り上げてみた。この引用部分を底流しているのは、吉本さんが深く考え続ける者として、あるいは表現者として現在まで奮闘を重ねてきた、そこからの眼差しであり、たぶん、状況というものはどこでどのように変わり、推移していくかということについての積み重ねられた考察から来る深い視線である。いいかえれば、「現在的な問題」と「永続的な問題」とがわたしたちに混乱を引き起こすように現象する〈現在〉というものに対する、吉本さんの透徹した眼差しがある。 社会運動家などは、何をのんきなことを言っているんだとかいう反発の反応をするかもしれないが、表現者や思想者としてはこの〈社会〉を駆動する主流を押さえておけばあとは「面々の計らい」で「あとは何もする必要ないから、遊んでてください」ということになるのだろう。そして、社会運動家ならデモや集会や署名などをすぐ想起するかもしれないが、時間がかかるかもしれないとしても〈社会〉を駆動する主流に対面する「普通の人が『俺が総理大臣になったらこうしようと思っている』ということ」、つまり自覚過程こそが、別の言い方をすれば、生活者の自立ということが、より本質的な課題だということであろう。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 474 |
視線の在所 |
「Ⅱ 現代を超える視線」 |
質疑応答 |
|
『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』 |
河合文化研究所 |
1987.12.1 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 内を見ている余裕をもってない |
この言い方の中に入っているのです |
自分をこしらえてきたから |
孤独なことをしているんだ |
項目
1 |
①
問 今日の講演についてですけれど、結局、ハイ・イメージ論というのは人間としてのものすごい能力というのか、そういうものを解明していくことなんだと、僕は理解したのですけれど、そういうとらえかたでよろしいのでしょうか。
吉本 ある意味では、いいのではないでしょうか。というのは、自分で本音を言ってしまえば、僕はハイ・イメージ論というのを今もやっていて、本屋さんがよせと言うまではやっているつもりです。それをやっている自分―書いたり考えたり調べたりといった時の自分は、あまり内を見ている余裕をもってないと思います。つまり外のほうを向いていると思います。外の方というのはおかしい言い方なのですけれど、内部・外部という言い方をしますと、外のほうをむいて、誰も見ていないでやっているような気がします。ですから、おっしゃる通りでよろしいのじゃないでしょうか。
僕は、その前にマス・イメージ論というのをやっているのですけれど、その時は内側ばかり見てやっていたような気がするのです。内側の問題―身のまわりの問題とか、日本の狭い文化の世界の動き方といったものばかりを見ながら、それらをいかに緻密に分析して理論化し、それがもしかしたら割と普遍的なことにつながり得ることができるか、というようなことをやっていたような気がします。
そこから、いきおいそれも一種の理論づけと言いますか、原理づけとして、ハイ・イメージ論というのをやってきたわけです。今度は内を向いていないで、外を向いているような気がします。内を向いているようなふりをしているけれど、外を向いているようです。それは、どういったらいいんでしょう。内を向いているようなふりをして外を向いているっていう言い方の中に本当は大衆とか身近な人たちとか、大衆文化の問題が、この言い方の中に入っているのです。入っているつもりですけれど、本当に外を向いているだけで―本当は外を向いていないのかもしれないのですけれど―割合にそういう狭い所をスーッと走っているというか、歩いているというような気がしています。
だからおっしゃるようなとおりで、いいのじゃないでしょうか。
ただ僕は、自分をそういうふうに慣らしてきたから―自分をこしらえてきたから、そうなんですけれど、外を向いているふりをして、外を向いているという人。外を向いていて外を向いているふりをしている人。内を向いているふりをして内を向いている人。皆さんの所に来てお話をしたような人で、いるじゃないですか。
僕は両方とも(引用者註.『マス・イメージ論』と『ハイ・イメージ論』とを指しているか)、自分のやり方と違うやり方をしてきたので、僕はいつでも外を向いているふりをして本当は内を向いているとか、内を向いているふりをして本当は外を向いているとか、そういうやり方をしてきたと思うのです。ですからおっしゃる通りでもいいですし、存外僕は、今内を向いているふりをして本当は外を向いているというふうに言っていいと思っています。
(『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』P58-P60 吉本隆明 河合文化研究所 1987年12月) ※この引用部がある「Ⅱ 現代を超える視線」は、講演後の質疑応答。
②
問 ・・・こういうことを言っても否定なさるかも知れませんけれど、僕らのほうにベクトルが向かっていて、何か新しい次元に導いていってくれるのじゃないかな、そういう刺激を与えてくれているのじゃないかというようなイメージを、僕はずっと抱いているのですけれど、・・・・(前後略)
吉本 おっしゃるようなことは、多分、僕が今言った内を向いているような顔をしているけれど、本当は外を向いているんです、と言ったこととあるところで関連があるのじゃないかと思うのです。そういう観点から言いますと、おっしゃったように、あまり僕は他者に自分の考えについて刺激を与えようとしているというふうに、お考えにならないほうがよろしいんじゃないかと思います。それよりも、もっとあいつのやっていることは孤独なことをしているんだというふうに思ってくれたほうが、よろしいんじゃないかという気がします。
(『同上』P67-P68 )
|
備
考 |
(備 考)
この「視線の在所」の問題は、別のところで吉本さんが述べているのに初めに出会った印象があり、それがどこに書いてあったかずっと探していたものである。そのときは、言われていることがまったくわからなかった。ここでは、おそらく予備校生に対する講演で、割と親切、ていねいに語られている。それでも十分に理解することは難しい。ただ、吉本さんが、表現者として書くという世界に赴くとき、どのような眼差しの感情や意識を秘めているかということが語られているように思う。吉本さんが表現者へ変身して、『ハイ・イメージ論』というすぐれて抽象度の高い言葉の森に入り込んで論理や概念やイメージを探索したり駆使したりしている、その〈わたし〉の眼差しには、当然に携えているあるいは潜在している眼差しや表現の価値の像があるということだと思う。例えば、わたしがある書類を書き上げようとしている最中には、その言葉の眼差しとでもいうものの中には、書類を提出する先かあるいは個人的な事情か、同様の何らかのイメージや意識が沈んでいるはずである。
わたしたちは誰でも、人と人とが互いに関わり合うという人間界、関係世界に生きているから、表現を専門にしていた吉本さんに限らず誰でも、このような内を向くとか外を向くという問題が起こってくるのだと思う。わたしがツイッターなどのSNSに入り込んでいろいろ表現を始めてみて、吉本さんの語っていることがクリアーにではないがなんとなくわかるような気がしている。ということで、これはわたしの中ではまだ保留事項でもある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 477 |
親鸞をたどる |
わたしと仏教1―思想家としての親鸞に向き合う」 |
|
『週刊 仏教新発見』2007.12.9 |
『吉本隆明資料集171』 |
猫々堂 |
2017.11.30 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 「歎異抄について」 |
『最後の親鸞』 |
|
|
項目
1 |
①
僕が最初に「歎異抄について」という文章を書いたのは学生のときで、今から考えれば「何もわかっていないじゃねぇか」って自分でも思います。ただ、戦後、一夜にして民主主義や文化国家に変わっていくことへの反発もあり、戦争中の思想的風潮、文化的風潮がそんな簡単に変わりうるかという懐疑もあって、自分の培ってきた古典や仏教の教養を確かめてみたいということがあったんですね。自分のなかの動機はともかく、とても論じきれるものじゃなかったですね。だから、しばらくは親鸞から遠ざかっていたんですが、ずうっと気にはなっていたんです、戦中の文化や思想の流れや、それに身を浸していた自分への反省があり、戦後の思潮にも向かい合えるようになってきてから親鸞にも改めて向き合うことができるようになったんです。『最後の親鸞』を書いたのは一九七〇年代の後のほうですから、時間を必要としたんですね。
僕は親鸞を仏教者というよりは、思想者として読むという方法を取ってきました。それは独断的な読みかたというか、親しみかただったわけで、そのために非難もされましたが、僕はそれをやってきたんです。僕は仏教に親しんできたわけですが、それは信仰としてではなく、思想としてということだったように思います。
(「わたしと仏教1―思想家としての親鸞に向き合う」P63-P64『吉本隆明資料集171』猫々堂)
|
備
考 |
(備 考)
わたしが調べた限りでは、春秋社版の『最後の親鸞』刊行までの吉本さんの親鸞についての論考などは次のようになっている。
「歎異抄について」( 「歎異鈔に就いて―亡吉本邦芳君の霊に捧ぐ―」(『季節』1947年7月掲載) )は、『吉本隆明全集1』に収められている。全集の巻末「解題」によると、副題にある「吉本邦芳」は、「府立化工時代の同級生で、『和楽路』の会員でも」あり、「四月三十日に急死した」とあるから、これは戦後の1947年辺りの文章と思われる。とするならば、この「歎異抄について」という文章は、上の吉本さんの言葉にははっきりと出ていないけれど、別のところで吉本さんが敗戦後の数年間の自分について何度か語っているところによれば、敗戦後の無惨に打ち砕かれた自己を抱えてもう生きた心地がしないような精神の荒廃を生きていた時期と重なると思われる。
この「歎異抄について」という文章について、「今から考えれば『何もわかっていないじゃねぇか』って自分でも思います」と吉本さんは語っているけど、そうでもないと思う。一方で小林秀雄の批評の文体的な影響や模倣が見られるが、後々の親鸞に対する吉本さんの捉え方の核の部分は、直感的、感性的にであれ、だいたい捉えられていると思う。
次に、ほぼ日刊イトイ新聞の「吉本隆明の183講演」で初めて親鸞についての講演が出て来るのが、1972年11月12日講演の『親鸞について』(吉本隆明183講演
A29)である。この講演では既に、次に刊行される『最後の親鸞』の中の次の有名な言葉は捉えられている。
〈知識〉にとって最後の課題は、頂を極め、その頂きに人々を誘って蒙をひらくことではない。頂を極め、そのまま(「そのまま」に傍点)寂かに〈非知〉に向って着地することができればというのが、おおよそ、どんな種類の〈知〉にとっても最後の課題である。この「そのまま」(「そのまま」に傍点)というのは、わたしたちには不可能にちかいので、いわば自覚的に〈非知〉に向って還流するよりほか仕方がない。しかし最後の親鸞は、この「そのまま」(「そのまま」に傍点)というのをやってのけているようにおもわれる。
どんな自力の計(はから)いをもすてよ、〈知〉よりも〈愚〉の方が、〈善〉よりも〈悪〉の方が弥陀の本願に近づきやすいのだ、と説いた親鸞にとって、じぶんがかぎりなく〈愚〉に近づくことは願いであった。愚者にとって〈愚〉はそれ自体であるが、知者にとって〈愚〉は、近づくのが不可能なほど遠くにある最後の課題である。
(『増補 最後の親鸞』 P5-P6 吉本隆明 春秋社)
そして、書き継がれたものをまとめて、1976年10月に春秋社版の『最後の親鸞』が刊行されている。吉本さん51歳の時である。吉本さんは、40歳代から50歳代のこの辺りで本格的に親鸞を捉えようというモチーフを駆動させている。つまり、「知識の最後の課題」は、吉本さんにおいても壮年過ぎに切実に訪れてきたモチーフだったと思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 485 |
自己劇化 |
「文学の芸術性」 |
インタビュー |
『群像』2009年1月号 |
吉本隆明資料集173 |
猫々堂 |
2018.3.10 |
※ 聞き手 田中和生
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 文学の芸術性 |
指示表出ばかり強くなって |
匹敵する作品を生むためには |
|
項目
1 |
①
― 吉本さんの言語論の言い方だと、言語の芸術性を決めるのは自己表出としての価値ですが、村上さんの世代は自分のことは語らないよという、否定のかたちで自己表出してきたところがあると思います。いまの作品には、そういう意味での自己表出性さえほとんど感じられないということですか。
吉本 「自己」の意味が質的にちがいます。僕のいう「自己」は「私」ということではなくもっと抽象的な意味ですが、そういうある意味で古典的な考え方を残している見方からすると、文学の芸術性を保障(ママ)するものは、言語の自己表出とか自己「表現」といった面だということになります。ところがメディアが変わってきたということもあるんでしょうが、最近ではそうじゃなくて、僕が指示表出と呼んでいる物語的な起伏みたいなものが作品の主体になっていて、詩の方でもそういう傾向があります。
吉本 なにがダメなのかというと、物語の起伏のように芸術性に間接的にしか寄与しない指示表出ばかり強くなって、メディアの自己表現性と指示表現性のかかわりぐあいが大いに逆転しているところです。そこがメディアの問題で、つまり文学の方が遠慮がちになって、テレビみたいに映像と物語進行の複雑さとかおもしろさを重視するメディアのものの見方があたり前になってきている。それが及ぼす影響が、文学の本質自体にも入ってきたと思えるんですね。
(「文学の芸術性」P61-P62『吉本隆明資料集173』猫々堂 )
②
吉本 僕なりに選択すれば、文学の芸術性は自己表現として読者の自己表現にどう呼応できるかというだけの意味しかない。つまり文学の無償性が偶然にでも必然にでもいいんですが、読者の無償性と出会わないと文学の芸術性は発揮されない。そういう意味で文学にはほとんど積極性はないというか、価値増殖の意味はないんじゃないか。だからいまみたいな状況は、文学全体の芸術的価値が変化しただけで低下したわけではないとは言い切れないと思います。
詩のような短い表現を考えてもそうで、万葉集なら万葉集、あるいは日本書紀や古事記の歌謡でもいいんですけれども、いまの詩人がそういうものの水準を保っているといえるのか。詩人でなくても、歌人とか俳人といわれている人たちのものでもそうです。俳句なら芭蕉、短歌でしたら万葉集に匹敵する作品を生むためには、作者が自己表出しているのはもちろんで、さらに自己劇化して、ドラマ化した自己を加えて意識的に作品として表現しなければ、古典に匹敵する作品を生むことはできない。文学の芸術性はだんだん落ちるだけです。時代が多岐多様になって文明が発達するほど人間の関心は分裂していくのだから、それしか言葉がなくて表現したらそのまま詩になった初期の万葉集とか古事記、日本書紀に載っている歌謡のような作品の質が、いまの詩人たちに保てるわけがない。それは初めからわかっているといっていい問題だと思う。
これは音楽にしたっておなじことだと思います。自己劇化できなければ、文学、芸術に関しては集約点がだんだんなくなって、ただ意味の起伏だけがどんどんふえていく。なぜ野蛮な文明時代の芸術作品がいまよりいいのかというのはその問題であって、これは科学なんかとまったく逆になりますね。
― 古井由吉さんが、小説から「私」という問題がどこかへ行ってしまったという言い方をされていますが、やっぱりおなじような指摘でしょうか。するといまの若い人の作品は、作者がいったいこの作品とどう関係しているのかわからないという意味で、自己表出性が希薄だといえるかもしれませ。だから吉本さんが若い詩人の作品についていわれた、自然がなくなったというのは、結局、書いた人の身体から発する言葉が作品のどこにあるのかわからないということで、それはいまの小説にも該当するような気がするんです。
吉本 そうだと思いますね。人間も自然の一部だとすれば、自然の一部としての人間と天然自然の自然そのものとの関係は、古典の芸術性の根源だと思いますし、宗教なんかもそうだったんだろうと思います。だからいまの宗教も、メディアの科学性というか発達というかそういうものに影響されてきて、やっぱり文学とおなじような傾向を生じてきています。
(「同上」P63-P65 )
|
備
考
|
(備 考)
この「自己劇化」という吉本さんの言葉には何度か出会っているがよくわからない言葉であった。しかし、その言葉には大切なことが込められているという感じはしていた。ここに、このように取り出してみると、大昔の万葉の頃の段階とより文明が発達し複雑化した世界の段階の現在とを、その中を生きる人々の、表現に向かう本質的な有り様として大きな視野で捉えられていることがわかる。また、時代が下るにつれて文明は高度化してきたかもしれないが、人間は堕落してきているのではないかと晩年の吉本さんがどこかで言われていたことも、これに関わっているように見える。
聞き手、田中和生の言葉は、この問題が吉本さんが現在の若い詩人たちを論じた言葉、「いってみれば、『過去』もない。『未来』もない。では『現在』があるかというと、その現在も何といっていいか見当もつかない『無』なのです。」(『日本語のゆくえ』P206 2008年)と関係するものとして触れ、吉本さんも同意している。この「無」ということは、おそらく表現者の〈現在〉に追いまくられた姿の自然な有り様と同時にある抗(あらが)いでもあるかもしれない。そうして、表現者に訪れている事態は、当然わたしたち誰にも訪れている事態でもある。
わたしたちは、〈現在〉すなわちある大きな変動の渦中にいるから、何が進行しているのかよく把握できていない。「自己劇化」ということを〈現在〉の渦中を生きるわたしたちに引き寄せれば、抗いながらも受け身の自然性として〈現在〉を受け入れるのではなく、〈現在〉という波風立つ海に自分の舟をくり出し操り進んでいくということになるだろうか。そこでは、〈現在〉の像をできるだけ把握しながら進路を取ることが大切になってくる。そして、自身の心の解放と。ひとりひとりの表現者が、実作で具体的に実践していくほかない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 487 |
視線の現在性 |
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』149 |
インタビュー |
「週刊 読書人」 1999年2月5日号 |
読書人 |
|
聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 価値とか意味をその視線に付属するもの |
近代主義的に解すること |
二重の見方 |
|
項目
1 |
①
吉本 たとえば未開や原始の人間にとって、自分の目の前に展開されている光景がどのように見えていたかを考えるとします。彼らが眼前の自然なら自然を見たとして、高次な視線や映像の風景として見えていたのか、あるいは現在の人類が見ているのよりもっと低次元のと言いますか、もっと粗雑な自然の光景として見えていたのかは実証が可能ではありません。ただ、価値とか意味をその視線に付属するものと考えると、これはもう考え方は二つに分かれてしまいます。たとえばアフリカの王様が自分の臣下の人民を好き勝手に殺したり、打ったりすることができるというとらえ方をしたとします。すると、殺したり、打ったりすることは、価値観や意味として考えると、野蛮で残忍で、まだヒューマニズムを知らなかった時代の人間の段階だからそんなことをやったんだというヘーゲル的な解釈が可能になります。
近代以降のものを、至上のもの、最上級のものと考えるヘーゲル的な解釈をもとにすれば、それ以前のいま言ったような行為は、野蛮で残忍で非人間的な行為になってしまう。しかし、日本でも同じような現象がありました。諏訪地方の神話時代からの伝承によりますと、そこの生き神様は多くの権限を持っていて、近隣の地域を支配していましたが、ある時期、今度は逆に民衆の方がその生き神様を殺してしまう。お祭りのときには大きな権力を与えているのですが、その期間が過ぎると、逆に今度は、民衆の方がその生き神様を殺すという風習があったといいます。(註.1)そういう場合、残忍だといえるかどうかはまた疑問になってきます。
臣下を勝手に殺す王様の行為を残忍で非人間的なもの見るヘーゲルの尺度は、近代主義的な尺度で、それは絶対に発展していく、それが人間の歴史だ、というのがヘーゲルの考え方です。もし、発展という考え方ではなく、認識の歴史として進化するという考え方をとれば、殺すという行為はそのときの民衆にとっても王にとっても残忍という意味は全くなくて、一つの共同体の持つ儀礼的なパターンとして理解した方が正当だということになってきます。残忍だと近代主義的に解することは必ずしも全体的な解釈にならない。一面的に解したにすぎないと今だったら僕は言えるような気がしています。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』149 週刊 読書人 1999年2月5日号)
※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三
②
吉本 つまり内田さんがおっしゃったような問題は、ある文学作品、言葉の作品にどんな意味があるのか、どんな価値があるのかを付加して、それを基準にして考えたときに初めて起こってくる問題だと思うんです。なおかつ、もう一つ言えることは、たとえば語りで伝えられたような原始時代や神話時代の物語に価値があるかどうかを問うとします。もちろん価値とか意味という概念を付け加えなくては駄目なんですが、付け加えた上で、正しい判断はどこで決まるかと言った場合に、差し当たって僕らが考えることは、自分らが現在持っている発達したイメージ、発達した意味から考える価値観と、これは本当に可能かどうかは別として、いま判断している自分がもしも原始未開の時代にいたら、言葉で語り伝えられているこの物語はどういうふうに見えるか、これは想像する以外にないのですが、この二つが二重に映った基準で、この価値観やイメージはこうだったと判断する以外にはないと思うんです。
その二重の見方が適用できるなら、かなり正当な価値判断ができるのではないか。もしわれわれが今持っている観点から未開原始を見て、未開で駄目な作品だ、あまり意味がないと言ったら、それはおそらく間違っていると思います。逆に、優れた価値を持っている、優れたイメージ喚起力を持っていると評価するのもまた間違いではないかと思います。今の時点からの視線と、その時代に自分が移行したと仮定した時に考えられる視線と、その二つを二重に行使しないと判断はできないのではないでしょうか。
(「同上」)
※①と②はひとつながりの文章です。
(註.1)
「諏訪地方の神話時代からの伝承」と儀式を追究した本に以下の三巻がある。最近安価な価格で文庫版で復刊されている。ずいぶん昔に吉本さん関係でこの本を知ったが、最近手に入れてやって読み終えた。『古代諏訪とミシャグジ祭政体の研究』の一巻だけでも大体のアウトラインはつかめると思う。縄文期、すなわち「アフリカ的な段階」にさかのぼるふるい伝承性と儀式性とを持っているようだ。
1.『古代諏訪とミシャグジ祭政体の研究』(日本原初考1)
2.『古諏訪の祭祀と氏族』(日本原初考2)
3.『諏訪信仰の発生と展開』(日本原初考3)
|
備
考 |
(備 考)
文学作品の理解において、作品はその背景・環境を巻き込んでくるが、その作品の意味や価値について論じられている。しかし、この問題はもっと一般化すれば、ここでも触れられているように、大きな歴史段階の違いによってそこに生きた人々間には容易には理解しがたい了解の水準の違いがあるという問題になる。この問題は、空間化すると、つまり同時代的な問題に変換すると、同一の世界了解の水準―あるいは同一のマス・イメージ―下に生きていても、容易には理解にたどり着けない他者理解の問題になる。
〈わたしたち〉は、一昔前でも二昔前でも同様であるが、太古の理解において、 この現在という時代の物質的・精神的重力下に無意識的にも存在しているから、言いかえると、歴史的に積み重ねられてきたといってもこの現在性というもののマス・イメージの強い影響下にいるから、どうしてもそのようなフィルターで太古を、太古の人々を、その感じ考えを見てしまうということを避けられない。また、〈わたしたち〉は、この現在という社会に共通に生存していて同時代の共通のマス・イメージの重力下に存在しているとしても、〈わたし〉は知り合いであれ見知らぬ者であれ〈彼〉の理解に到達できるとは限らない。
このような対象理解の問題性を吉本さんが明らかにしたが、これは人類の了解の歴史的な段階がわたしたちに促してきている問題のように思われる。
古典の評価で、②の末尾にある二重の視線の行使と同様のことをずいぶん前にどこかで吉本さんは述べていた。探し出せないでいる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 488 |
作品を解明する条件 |
『吉本隆明 戦後五〇年を語る』151 |
インタビュー |
週刊 読書人 1999年2月5日号 |
読書人 |
|
※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| パラ(Para)イメージ |
『ハイ・イメージ論』 |
|
|
項目
1 |
①
作品を解明する条件(引用者註.本文の小見出し)
吉本 もう一つ、地の文の問題を言われましたが、地の文とは何かということですね。現在のところ、ある一つの文学作品を解剖する場合にどれだけのことをすればいいかというと、その文学作品の中に登場する人物の性格や、心の動かし方他、人との関係の仕方の洞察が、登場人物のそれぞれにどれだけ個性的に与えられているかを分析すること、それが一つあります。もう一つは、登場する人物がこういう経緯によってこのように出会ったという一種の説明ないし解釈の文章が解剖できれば、作品をよく解剖したことの条件になります。
もう一つの条件は、登場人物の心の動かし方や関係の仕方や個性の持ち方と、地の文の説明や解釈や描写の仕方が、作者である人間とどのように関わっているかということです。現在までの文学作品ですと、だいたいこの三つを解明できれば作品を解明したことになります。地の文の働きを二重に考えて、つまり、作者のものと考える面と、登場人物その他、物語の輪郭を説明し解釈するためのものと考える面の二つの作用があると見做せば、だいたい登場人物と作者が持っている精神作用とモチーフだけを解剖すれば、さしあたって現在までの作品だったら解明したことになります。
②
吉本 けれども、宮沢賢治の作品のように、もうひとつ何か加えなければ解明したことにならない作品もあるんですね。
以上のことから、内田さんがおっしゃったことに答えるとすれば、一つは、言葉の意味とイメージはどう関係しているかということです。言葉で書かれているけれど、読む人にはイメージとしてしか受け取れない箇所が文学作品の中にはある。僕が『ハイ・イメージ論』で考えたことで言えば、それはパラ(Para)イメージだということになります。宮沢賢治の作品の中にそういう箇所がいくつかあります。とても鮮明なイメージなんですが、意味からくるイメージではない。意味する言葉は書かれているけれど、全面的にイメージとしてこちらに入ってきてしまう。それはなぜかと考えた場合に、僕はこれをパラ(Para)イメージだと考えて、映像でやった表現とまったく同じか、それに近いようなことが実現されているからだと理解するわけです。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』151 週刊 読書人 1999年2月5日号)
※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三
※①と②はひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
まとめて再確認すると、
「現在のところ、ある一つの文学作品を解剖する場合にどれだけのことをすればいいか」
1.登場人物の分析
2.登場人物などに近づいたり内面に入り込んだりして語る語り手の分析
3.1.と2.と関わる作者の分析
そしてこの3条件では解析し尽くすことのできない問題として
4.パライメージの問題が提出されている。
わたしは、上の3条件まではわかるけど、まだ4番目の条件はよく理解していない。ただしこの4番目の条件の提示は、作品理解や作品解析が従来的なものから新たな段階へ突入している、ということはわかる。
パライメージの直接関連としては、『ハイ・イメージ論Ⅱ』の「パラ・イメージ論」がある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 489 |
詩を書く内側 |
『吉本隆明 戦後五〇年を語る』152 |
インタビュー |
週刊 読書人 1999年2月26日号 |
読書人 |
|
※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| もう一つの視線 |
パラ(Para)イメージ |
無意識の状態に自分を置いて書く |
|
項目
1 |
①
内田 そのもう一つの視線というのは文学的なディスクールの主体が意図して実現することはできないというのはよくわかりますが、読み取る人にとって、そういうものが見えてしまう。この視線は、どういう視線だと考えたらいいのでしょうか。
吉本 よくわからないところが大部分だと言ってもいいのですが、たとえばシュールレアリスムの方法を考えてみますと、詩を書く人は、伝統的・古典的な言葉の使い方を意識的にしている人は別として、大なり小なり、作品のある行とある行のところは、できるだけ無意識の状態に自分を置いて書くようにしていると思います。僕自身も何行かはそうやって書いています。無意識の意識みたいなものですね。僕らはあまりシュールレアリスムの方法は知らないし、使っていないのですが、少なくとも部分的には無意識の状態を行使していますし、今の詩人たちもそうやって書いていると思います。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』152 週刊 読書人 1999年2月26日号)
※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三
②
待合室でも僕はずっと編み物。セーター第2号。編み物をしていると、いろんな人から声をかけられる。これもまた面白い効果。インゴルドさんの『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』を読んでいると、糸について研究したいという着想を得る。本を書くことだって編集って言うくらいで、テキストだってもとはテキスタイルである。すべてが糸からきているのではないか。ツェランの詩集のタイトルは『糸の太陽たち』だった。歴史を書物などで勉強するのもいいが、きっと一番効果的なのは、体を動かすことである。指先を動かすことで、太古の記憶につながることができる。歌もそうだが、こういった記憶再生装置についてもっと注目する必要があるはずだ。原稿を書くのも僕の場合は最近、そうやっている。自分が書こうとしていることではもう追いつかない。そうではなく、書かされること。自分の頭の中で浮かんでいる自分じゃないこと。それなのに存在すること。そういったものに焦点を合わせること。それが僕の次の仕事のような気がしている。まあ、どこでどうつながるかわからないが、とにかく頭に飛びこんできたものを片っ端から記録してみようと思っている。
(坂口恭平「僕の本当の欲望」2018年4月11日 、『 哲学と冒険』 https://cakes.mu/series/4089 「cakes」)
|
備
考 |
(備 考)
詩を書く内側のこととして、ここで吉本さんが述べていることは、わたしも思い当たることである。そして、「無意識の状態」や「無意識の意識」ということはわたしの詩の体験に引き寄せれば、詩を書いていて、よくはわからないにしてもある言葉やイメージの地平、あるいはある言葉の深度に、立っている、そこに向けてあるいはその地平から表出するというような体験をすることがある。
②は、坂口恭平の現在連載されている文章を読んでいるから、そこから引用した。「自分が書こうとしていることではもう追いつかない。」の「追いつかない」の意味はよくわからないけれど、この坂口恭平の表現の現場も「無意識の状態」や「無意識の意識」が訪れているように見える。
なぜわたしたちは、ある意図通りに言葉を表現できないのだろうか、ひとつは表現の舞台に、呼び出される、あるいはまとわりつく、正体のはっきりしない、わたしたちの意図を凌駕するような表現的な〈現実〉というものにぶつかること、もうひとつは、わたしたちは生まれ育ち現在に至る過程で言葉のない段階を潜り抜けてきていて、それがわたしたちの言葉の基層に位置し、わたしたちが表現するとき現在の表現的な言葉にその基層も参与しまとわりついているからである、というように思われる。
この項目は、宮沢賢治の「もう一つの視線」(パラ(Para)イメージ)と関わっていくもので、宮沢賢治におけるパライメージを表現の励起状態と見なせば、こちらは詩を書く誰にでも訪れる表現の定常状態と言えるだろう。
関連で言えば、わたしたちの日常の人間的な諸活動において、心や精神は太古以来のいくつかの層を成していると思われるが、現在的にそれはどのように発動しているのかということ、ひとつは安定的な状況において、もう一つは危機的な状況において、このことがわたしには切実な現在的課題だと思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 494 |
自分のやり方 |
「日本の現在・世界の動き」 |
講演 |
吉本隆明資料集174 |
猫々堂 |
2018.4.15 |
※1990年9月14日の講演
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 網をかぶせたような全体の把み方 |
社会の全体像 |
じぶんの方法 |
|
項目
1 |
①
まず、ここに「現在の日本の社会像」と書いてある図があります。こういう国家とか政治とかという制度や社会の具体像を、どこでつかんだらいいのかかんがえてみます。もちろん、どんなつかみ方をしてもいいのです。・・・中略・・・
けれど、通りがよくて、深い線じゃないけれども、だいたいの線がつかめるのは産業の構成が、どんな段階にあるのかだとおもいます。こんなことを調べてやろうと手をつけたときに、何にびっくりしたか申しあげてみます。ぼくがそれまでかんがえていた日本の産業構造のイメージと、現在の日本の産業構造とが、まるでちがっていることでした。そこからお話ししたいとおもいます。・・・中略・・・
ぼくらはひとりでに、日本の社会の産業構成のイメージとして、まず農村があって、それに対立する都会がある。農村では農業がなされ、都会では製造工業とか建設業とかいう第二次産業が都会周辺工業地帯では行われている。そういった姿を描いていました。そこでは製造業と農業とが、あるいは都会の人工的なビル街と農村の緑いっぱいの田園風景とが、対立しているみたいなイメージを、知らずしらずのうちにもっていたのです。でもよくよく調べてみると、まったくイメージがちがうことがわかりました。それと同時に、かんがえ方の枠組を変えていかなければダメじゃないかとおもいいたったのです。
日本の産業は人口構成でどうなっているか図像を描いてきました。見てくれるとすぐわかりますが、・・・中略・・・。つまり日本の産業構成は第三次産業が主要な段階になっています。
(「日本の現在・世界の動き」P2-P3 『吉本隆明資料集174』 猫々堂 2018.4.15)
※1990年9月14日の講演
②
こんな網をかぶせたような全体の把み方をぼくはよくやりますが、これがかならずしもいいやり方だとはかぎりません。人によってちがいましょうし、個性によってちがいますから、もちろん逆からいってもいいとおもいます。じぶんの生活状態・経済状態からいくと、一〇年前といまとではどれくらいちがっているかなとか、どれくらい旅行とか、遊びにいくとか映画をみるとか、あるいは体育とかにお金を使えるようになったかとか、子どもの教育費にどのくらい使ってるかなみたいなことを、一〇年前と比較してみることからはじまって、だいたいじぶんとおなじ人たちは、じぶんを中流の中とすれば、どのくらい周囲にいるかといったことをやりながら、しだいに社会の全体像に迫っていくやり方もあります。こういうやり方じゃなきゃダメっていうことは何もありません。それぞれの人の好みとかやり方とか資質とかがあるわけですから、それにしたがってつくっていけばよろしいんじゃないでしょうか。ぼくは、大雑把なところからまず始まってというのが、なんとなくじぶんの方法になっています。まずなんとなく大雑把にはじめから終りまでやっちゃわないと気がすまない、それから細かいところをやるみたいな、そういうことがなんとなく身についているので、そんなやり方をしてみました。
(「同上」P5-P6)
|
備
考
|
(備 考)
ここはまだ講演の入口付近で、ここから吉本さんは、おいしい水として天然水が売り出された時期の1973年から1975年の三年間を「社会像の転換点」として見定めていき、新たな日本社会像を分析していきます。ここでは、入口にこだわってみる。付け加えれば、吉本さんが戦争-敗戦後に何が駄目だったかとして自己の教訓とした社会総体のイメージの獲得は、ここでも貫かれている。
誰にでも癖のようなものがあるように、思考の振る舞いにも癖のようなものがありそうに思える。そして、その癖の固有性がどこに発祥しているのかを言い当てるのは、その人の性格が乳胎時期からどういう道のりで形成されたかを言い当てるのと同様に難しい。例えば、現在から振り返れば、ヨーロッパの近代自然科学や文化がわが列島に押し寄せた時期という絶妙な精神的環境という偶然性もあるだろうし、父親の熱心な仏教的な環境もあるだろうが、宮沢賢治がなぜ人間界のことが普通一般より希薄で宇宙銀河的な発想を生涯貫いたのかを言い当てることは難しい気がする。それは当人自身でも難しいことだ。ただ発祥の流れから癖として表現されるに至る、それを支えるもの、いくつかの要素は、あげつらうことはできそうに思われる。吉本さんの場合、少年期以後の自己形成によれば、化学学校での修練や発想の積み重ねが与えた影響が大きく強いと思われる。化学実験などから細かな反応の過程がわからなくてもとりあえずわかることを引き出す、など日々のやり方や修練の積み重ねは、その後割と習慣のように残存して影響を与えるように思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 498 |
自己概念による包括 |
(「大拙の親鸞」―「日本的霊性」をめぐって |
講演 |
吉本隆明資料集174 |
猫々堂 |
2018.4.15 |
※大谷大学宗教学会・第11回「大拙忌」1992年7月10日
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 鈴木大拙が霊性ということで何を言おうとしているのか |
大拙は宗教の信仰と結びつける |
|
|
項目
1 |
①
霊性という概念は、概念としては昔からあるのかも知れませんが、たとえば「日本的霊性」という言い方で、これを独自な使い方で使った。つまりそれぞれ民俗に固有な霊、あるいは霊性が人間一般、人類一般の中にあって、そこからいろんな文化や宗教、風俗、あるいは文明とかいうものがつくりあげられていくんだとかんがえる考え方を、はじめて出した思想家なんだ、とかんがえたらいいんじゃないかとおもいます。それで、鈴木大拙が霊性ということで何を言おうとしているのかということから申しあげてみたいわけです。
ようするに、物とか心とか二元的に分けないで考えられる考え方のなかに、われわれはしばしば当面したり、じぶんでひとりでに入ってしまったりすることがあるわけですが、そういう心の状態を全部表すばあいに、それを霊性といったほうがいい。そういう定義のしかたを大拙はしているとおもいます。
霊性という言葉で、大拙はたいへんおおきな精神の働かせ方を全部言おうとしているようにおもわれます。これを論理的につきつめていきますと、たいへん曖昧なこと、曖昧な概念を指して霊性といっているようにおもいます。これをなんとかして――つまり大拙は宗教の信仰と結びつけるわけですけれども――、そうではなくて、ごくふつうにわかりやすい言葉でいいかえてみたいわけです。
それで、いくつかの段階をかんがえてみますと、大拙が例に挙げているように、物質、あるいは目に見えるものと、目に見えない心の働きというふうに、二元的にものをかんがえる考え方を、ひとつ置いておきます。そのつぎに、それよりももうすこし大拙のいう霊性に近づいた段階の、心の働き方というのは、物固有のものであるのか、心固有のものであるのか分けられないで、両方が相互に浸透しあっているような、そういう精神の状態があります。そこの状態に無意識のうちにしばしば入ることがあるわけです。そういう状態のつぎにある最後の段階をかんがえてみますと、白熱した、とでもいうような霊性の状態があります。これはたぶん、仏教でいう悟りという状態にたいしてかんがえられています。そういうふうに分けたらいいんじゃないかと、すこしわかりやすくかんがえたわけです。
(「大拙の親鸞」―「日本的霊性」をめぐって P40-P42 『吉本隆明資料集174』 猫々堂 2018.4.15)
②
さて、それではもうすこし、固有の考え方で、大拙のいう霊性をいってみたいとおもうわけです。ぼくがいまかんがえている考え方によりますと、身体生理的にいって心の働きとか心の動き方と呼んでいるものは、たぶん内臓に関係する精神の働きのことを呼んでいるとおもいます。たとえば、だれでもそうですが、胃が悪くなると心がうっとうしくなるとか、憂鬱になってくるとかいうことがあります。それからそういう例を挙げますと、ぼくらが精神をあることに集中しようとするときに、たいてい無意識のうちに息を詰めたりしています。つまり、息を詰めてるとは、肺臓の働きを停止しているわけですが、停止しておいて、精神を集中することをやっています。それは無意識にやっていますけれども、内臓の働きに関係する精神の働き方を指して、ぼくらは心と呼んでいます。心と呼んでいるものは何なのか、それの生理的な基礎は何なのかといいますと、たぶん内臓の動きが表現されたものが心、と呼べるだろうとかんがえられます。
そうして人間の精神の働きにはもうひとつあるわけです。それは感覚です。目とか耳とか口とか、手で触れるとかそういう五感の働きによって外界のものにたいして反応する、そういう感覚の動きからくる、間接的な精神の働きがあります。つまり厳密にいいますと、人間の感覚的な働きというものと、心の働きというものとは分けてかんがえられるものです。感覚の働きというのは、視覚とか聴覚とかの五感と外界に関係する働きだとすると、心と呼んでいるものは、内臓の動きが精神の方に表現された働きとかんがえれば、よろしいとおもいます。そうしますと人間の精神の働きというのは、感覚作用とそれから心の働き、つまり内臓の動きからくる働きのふたつを混合したものです。
つまり、感覚の働き、五感の働きからくる動き、内臓の動きからくる働き、そのふたつが区別できない状態が、大拙がいう霊性にいちばんちかいのではないかなとかんがえます。
ぼく自身はそれを言語論の方に結びつけています。内臓の動きからくる心の表現は、ぼくの言語論では〈自己表出〉という言い方をしています。それから、感覚の働きから、つまり、外界にたいする感覚の反応からくる表現は〈指示表出〉と呼んでいます。つまり〈自己表出〉と〈指示表出〉とが区別しがたい持続状態というものをかんがえると、大拙の霊性というものにいちばんちかいところまでいけるんじゃないかとかんがえます。
(「同上」 P42-P43 )
③
ただ、この大拙の霊性ということをわかるためには、どうしても宗教、とくに仏教にたいする信仰がいるような気がするのです。〈信〉というものを避けて霊性というものを理解しようとすると、近づくことはできますけど、なかなか最後までわかりにくいことになるような感じがします。ぼく自身はじぶんの考え方から、霊性という概念に近づこうとすると、そういう内蔵の働きかける心の表現と、それからその感覚の動きからくる心の表現が総合されたものということに帰着するような気がいたします。
そして、あえてもうすこしぼく自身の考え方を付け加えますと、人間が一歳未満の乳胎児のときには、言葉というものを持っていないのですが、人間の心は無意識の核を形成しているとかんがえます。そういうものも時として、大拙は霊性のなかに含めている気がします。つまり、そういう言葉以前の無意識性、人間の成長史でいえば一歳未満で言葉を獲得するわけですけれども、その獲得以前に受けとった人間の心というものは、無意識の核に入るわけですけれども、それも、時として霊性ということのなかに、大拙は含めているようにおもいます。
つまり、大拙の霊性にうまく近づこうとすると、いつも堂々巡りになりますが、その堂々巡りのところでかんがえてみますと、大拙が霊性ということで言いたかったことがわかるような感じがしてきます。しかし、あくまでもこれは、非宗教的な、いってみれば大拙が霊性ということを言うときにもっとも嫌った、分析的な概念でありまして、信仰、あるいは悟りにゆきつくような言い方ではないわけです。あくまでも霊性ということの周りをぐるぐる回ってることになります。そういう回り方をしているうちに何を指そうとしているのかが、わかるような感じが出てきます。
(「同上」 P44-P45 )
|
備
考
|
(備 考)
この吉本さんの「大拙の霊性」探索は、まだ後に続いていくけど、この辺りで止めておく。吉本さんが親鸞を論じた場合も、ときどき自分には信仰がないからということを述べられていたが、ここでも、③にそのような信仰のあるなし問題が触れられている。
この項目498 自己概念による包括は、わかりやすく一般化して言えば、人が生身の他者を理解したり、他者の表現した作品や思想を理解しようとする場合の、最良の振る舞い方や捉え方とは何かという問題になる。日常的にも思想的にも難しい問題である。
人は誰でも、生まれ育ってくる中である感じ考え方の系を形造ってくるけれども、たとえ同時代に生きているとしても他人の感じ考え方の系の全重量とうまく出会うことは難しい。同じ人間的な感じ考えだとしても、その色合いや質感や流れ出すときの流量や跳ね方や屈折や・・・いろんなことが互いに違っている。上の吉本さんの引用で言えば、「信仰」の有る無しがこの場合の互いの系を隔てるものの喩になっていると見なすことができるように思う。
吉本さんは、自らの生みだした概念(自己表出と指示表出、『母型論』の言葉以前という概念)を携えて鈴木大拙の霊性という場へ降りていく。他者に付き従うとかではなく、人が他者の真の姿に出会おうとするとき、誰でもこのような出会い方しか可能ではないように思える。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 501 |
宗教と科学 |
「宗教」ってなんだ? |
インタビュー |
『悪人正機』 |
新潮文庫 |
2004.12 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| あやふやなところの極限に近いところ |
読む側の人 |
UFOは心理現象 |
|
項目
1 |
①
僕自身が書いたもののなかに、どうやって、どのくらい、そういう危なっかしいものを入れているかということですけど、僕の関心は、要するに「信ずること」と「科学的に明瞭なこと」をつなげたいってことなんですよ。その反するふたつのことが、矛盾なしにつながることはあるんじゃないかって思っているんで、それをつなげたいっていうことには一所懸命なんです。
だから、何とかしてつなげようっていうふうに考えると、あやふやなところの極限に近いところまで、どうしてもいっちゃうんですね。例えば、臨死体験みたいなものがあるかないかって言ったら、僕はあると思っているんだけど、それが科学的確信だって言い切ることはできないんですよ。信ずるっていうことで言えば、かなり本気で本当だろうと思っているけど、科学的にそうかって言われると、ちょっと危なっかしいってなっちゃいますね。でも、つなげようとしてるんですね。
それで、養老(孟司/解剖学者)さんみたいな人に会った時に、聞くわけですよ。そうすると、臨死体験みたいなことはあり得ると思いますって言うんです。「耳が聞こえれば、人間は目が見える」っていうふうに考えていい。つまり、死ぬ間際まで、意識がもうろうとしていく間際まで、目は見えるっていうふうに考えていいから、臨死体験みたいなことはあり得ると思いますよ、とか言うんだけどね。
でも、僕のどこかにやっぱり、そう言い切っちゃったらいけないかな、と思ってるところがあるんですね。だけど、僕の書いたものを読む側の人は、もうそれは言い切っちゃってるって思うわけです。
で、僕は、言い切る言い切らないは、どっちに転んでも構わないけど、要するに、「信じること」と「科学的に明らかなこと」とをつなげようとすると、あやふやなところっていうか、これはちょっと怪しいんじゃないかっていうところが、どうしても出てきて、引っ掛かってきますね。
(「宗教」ってなんだ? P123-P124 『悪人正機』吉本隆明/糸井重里 新潮文庫 2004年12月)
※ 単行本としては、2001年6月に刊行
②
きっと本当に科学的、唯物的に科学的な人からすれば、あいつ、ちょっと危なっかしいぜって思うでしょうし、自分でもそういう気はしますけども、僕の第一のモチーフは、信ずることと信じないこと、あるいはどちらともとれることをつなげたいんだってことなんですね。
それをつなげちゃえば、だいたい、宗教とか科学とかって区別をしなくていいっていうことになるんじゃないかなっていうモチーフはあるんですね。信じる信じないの信仰の問題と、科学的な知的な問題っていうのが、どっかでつながるはずだとね。それができないのは、今のところ、まだ発達段階がそこまでいってないから途切れたものに見えてしまって、なにか怪しげだってところに行っちゃうんでしょうね。
そういう意味では、そのつながるかどうかの接点にあるようなものもあるんですけれど、やはりどこかで選別しているんですね。
例えば、UFOみたいなものは、僕は心理現象だっていうふうに思うんで、見えるってことはあり得る、物体としてではなく心理現象としてあり得るとは思うんです。宇宙人に会ったとかいうのも、嘘を言ってるとは思わないですけど、このことで信仰的なことと科学的なこととがくっつくことはないでしょう。
(「同上」P125 )
※ ①と②は連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
この宗教と科学とをつなげるということは、宮沢賢治が『銀河鉄道の夜』のブルカニロ博士の挿話が載っている版で、ブルカニロ博士に語らせているテーマでもあった。ほんとうの考えと、うその考えとを分けてしまう実験の方法さえきまれば、もう信仰も化学と同じようになる、つまり無用の対立は解消されるだろうと語られている。
UFOといえば、あの無農薬リンゴの栽培の体験を記した『奇跡のリンゴ』の木村秋則さんも、UFOを見たり、宇宙人と出会ったということを別の本で書き記していた。わたしはそのことを別に肯定も否定もせず、ふーんといった感じで読んだ覚えがある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 506 |
詩の修練① |
『吉本隆明 戦後五〇年を語る』199・200 |
インタビュー |
週刊 読書人 2000年2月25日号他 |
読書人 |
|
※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 言葉が詩的にやって来る |
詩は手と感覚、手と思考との連携の問題 |
頭で詩を書く |
|
項目
1 |
①
吉本 今はそういう天才的な詩人はいなくて、なんとか食べているという感じだと思います。そこそこに良い詩人はいると思いますが、現代で詩で食べているのは谷川俊太郎だけだと思います。谷川俊太郎は良い詩人ですし、僕は現存している人だと吉増剛造と田村隆一(昨年死去)と谷川俊太郎の三人は詩人と言える詩人だと思っています。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』199 週刊 読書人 2000年2月25日号)
※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也
②
吉本 生活上から言うと、金銭的にも精神の問題としても、現代で詩人であり得ることと生活の時間性といいますか、第三次産業の時間性と詩の時間性とのギャップは著しくて、詩人として生きることはとても難しいことだと思います。
しかし、言葉の表現は最初にどう来るかというと、やはり詩的に来ると思います。それは無意識に来る。最初は詩の専門家だとか素人だとかいう区別はなくて、誰にでも詩的なものはやってくる。すごく極端に言えば、おじいさん、おばあさんで詩的な教養なんて全くなくても、自然に出てくる音律があり、今の沖縄にはなくても、少なくとも半世紀前まで行けば、そういうおじいさん、おばあさんが現にいました。(註.1)そこから出発してそれをどう抜けていくか、あるいはそこにどう留まっていくかという課題にどうしてもなっていくように思います。どういう詩のくぐり方とつくり方、そしてどういう抜け方がいいかと考えると、自分は決して模範にはならないのですが、ただ、自分で自分の詩の評価というのがあって、文芸とは全部、なかでも詩は手と感覚、手と思考との連携の問題であり、それ以外ないということです。
僕は一生懸命詩をつくっていた時期があり、これからもやるぞと言ってなかなかやれないでいるのですが、やるぞやるぞで良い詩を書こうなんていうのは虫がよすぎるんですね。それをやるためには何年間か他の表現をしないで、手で一生懸命詩の修練をしてやらないと、良い詩は書けない。そうでないと頭で書いてしまうわけです。それは良い詩であるはずがない。それはよくわかっているのです。手で書いている時期が抜けてしまっている。中間が抜けて、批評文は書いているけれど、批評文もまた小林秀雄みたいに凝れば多少は詩の修練にプラスになりますが、そういう凝り方はしないものだから、本当にそこが空白になってしまっています。詩を書くぞ書くぞと言っても、頭に追いつくところまで手の修練を一生懸命していないからどうしてもだめになってしまうのです。
(『同上』)
③
吉本 最後に典型的なそういう詩人を挙げておきますと、松浦寿輝さんや稲川方人さんが僕にはそういう詩人に見えます。松浦さんは批評文も書くそうです。僕は読んだことがないのでよくわからないのですが。今いる詩人の中ではこういった人たちが良い詩人だと思います。松浦さんは自分ではっきり「頭で詩を書く」と言っています。
しかし、たとえば藤村の『若菜集』の中のどれか一つの詩をもってきて、これと松浦さんの詩とどちらが良いかと言われると、答えるのがなかなか難しいですね。松浦さんの詩の方が良いと言い切ることはできないと僕は思います。藤村の詩の方が良いという例はいくらもありますから。しかし、苦心の仕方を現代性で考えれば、松浦さんは苦心していると思います。そして頭で書くようになっている。頭で書きますから、先ほどの言い方で言えば、こんなのは詩ではないと言いたくなるわけです。蒲原有明や薄田泣菫の詩のように、こういう苦心の仕方は詩ではないと言いたくなるのですが、松浦さんの詩がかろうじてそういったことを言わせないのは、意味がないからではなくて、意味が通らないように言葉を使ってねじ伏せているからで、それがなくて意味が通るようにできてしまっていたら、これは無駄な苦心だとなってしまうわけです。しかし、通らないようにつくられているから、他の傾向の現代の詩人が読んでも、公正に読める人だったらやはりこれは詩だと認めるしかないと思います。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』200 週刊 読書人 2000年3月3日号)
④
吉本 詩人というのは狭いところがあって、自分の仕事と同じようなことをやっている人でないとなかなか認めないのです。僕はそこからはずれていて利害関係がないから言えますが、この人は詩人だと思います。なぜ良いのか、なぜこれが詩なのかと言われれば、意味が通らないような極端なところまで言葉をねじ伏せているからだということになります。それがこの人の詩を成り立たせている。これを真似するのは意外にやさしいんです。これから詩を書こうという人は、多分、そんな言葉づかいから出発するのが一番適当なような気がします。誰でもたやすく真似ができる。難しそうに見えて難しくない詩ですから。
(『同上』)
※③の後半と④は連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
もう半世紀前くらいの、高度経済成長期以前で、まだ世の中に自給的なものが残存した自足的な社会では、人々は病院にかかることもほとんどなく、葬式や結婚式も現在のように専門の業者が介入することなく自宅でしていた。そんなわたしが小さい頃目にした光景によれば、自宅での結婚式では横笛に特に秀でた才能を持っている叔父さんがいて披露していた。たぶん結婚式などではその人の出番が当然のように待たれていたのではないかと思う。仕事は大工さんだった。歌でも技芸でも、そのように秀でた人が、現在もだろうけど、必ずいたような気がする。そしてその秀でた者を送り出す発祥の基盤は、その人の家族や地域の時間性ともいうべきものだと思われる。
詩に関心のない人や詩を書いていない人々には、この項目は無縁かもしれないが、どんなことでも人間的であるという一般性から見ると、この詩の修練の問題も他の修練と同質性も持っているはずである。
④に関して、吉本さんの功績はこんなところにも現れている。作品をほんとうに公正に見て評価できるということ、行使される普遍の言葉、わかりにくい修飾などなく誰にもわかるような言葉で語られるということ、ほんとうに惜しい存在を亡くしたなと思う。
松浦寿輝の詩集を買ってまで読もうとは思わなかったので、ネットで探してみた。批評で取り上げられた1篇の詩の一部しか見つからなかった。今の自分なら、吉本さんのような親切ていねいな批評はできないだろうなと思う。
太古に〈詩〉というものが発生し、その最初の動機(おそらく大いなる自然との対話)からどんどん深く掘っていったり、遠出したりして、その〈詩〉も多様になってきた。その人間の〈詩〉に込めた最初のモチーフは潜在する主流のように現在も流れているように思う。また、最初のモチーフ自体から言葉自体を疑うような、言葉のいろいろな試みもまた派生させてきた。
詩の修練は、良い詩やうまい詩を書こうということであれば、現在的で割と技術的な問題になる。しかし、遙か人類の起源の方から現在の詩の修練を照らし出せば、ここで吉本さんが取り出したような、重たい問題も様々に浮上してくる。もちろん、このことは詩の修練に限らない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 507 |
詩の修練② |
『吉本隆明 戦後五〇年を語る』203,205 |
インタビュー |
週刊 読書人 2000年3月24日号他 |
読書人 |
|
※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 普遍的な詩は何か |
詩のモチーフと言えるような手 |
不安定で未知で |
|
項目
1 |
①
吉本 僕はある時期からその考え方は違うのではないかと思いまして、もし僕らが詩を書くことをこれから意図的にやっていくとしたら、うまくできるかどうかは心許ないのですが、普遍的な詩は何かというのが課題になるのではないかと思ったんです。西欧の現代あるいは近代の詩の影響下に詩を書いて、言葉づかいに異化の感じがあれば、それは詩だというような時代はもう終わったと僕は思っているわけです。今は普遍的な詩とは何かというモチーフに向かって詩を書くことが詩の課題だと思っています。
そうすると、たとえば小野十三郎は詩でないものを詩と考えるという反自然を徹底した詩人だと言いましたが、今ではそれはあまり良い努力の仕方だとは思えなくて、そんなことはどうでもいいというか、「どうせそれはだめだよ」という感じ方を持っています。もちろん他の自然詩人に対してもそう思っています。また逆の意味で、たとえば松浦寿輝さんがいま書いているような詩とか、詩とは何かという感じ方、考え方を、本音を言うと僕は違うと思っています。違うところが日本の詩の問題だと思っています。そういう意味でいま、吉増剛造という詩人の詩に一番興味があります。
僕らなりに普遍的な詩を目指せば、詩のモチーフと言えるような手を持たなければなりません。頭でそう思っていることと手とは違いますから、手が連動せずに詩を書くのはまずいんじゃないかと思うんです。詩は頭で書くものだと言い切るほど僕は素養がありませんから、そういう言い切り方はしたくないんです。
そうすると、四季派の詩人はいろいろとボロが出ましたけれど、ボロが出てきて最終的にはまた音数律まで帰ってしまった。朔太郎も文語詩に帰りましたし、宮沢賢治も帰りましたし、中原中也だってそうです。立原道造にもそういう詩がありますが、彼の場合はそこまで行ったという以前に亡くなってしまいました。みんな危なっかしい詩人ばかりだということも含めて、自然詩人の問題、あるいは自然詩の問題は、依然として問題であるような気がします。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』203 週刊 読書人 2000年3月24日号)
※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也
②
吉本 僕もどういうことになるのかはわからないのですが、これはというふうにどんどん消去していくという意味で言ったら、やはり明治以降の詩から何かを消去していかざるを得ないのではないか。消去していったあげく、すこぶる危なかしいところしか残っていない、どこでどうつくろうと全部、危なかしいところしか残っていないではないかとなっても、僕はそれで構わないというか、良いのではないかと思います。
ただ、先ほどからの話で言えば、何らかの想定された、あるいは総合された秩序なしには言葉の秩序はつくれないと思ってくると、想定された秩序というのは本当はよくわからないと僕は思っています。だから安定したところで詩をつくることはまずできない。不安定で未知でというところだけを選んで、そこから何かをつくっていく以外にどうしようもないのではないかと思います。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』205 週刊 読書人 2000年4月7日号)
※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也
|
備
考
|
(備 考)
たぶん、〈詩〉のはじまりには、言葉が漂い集まり固まってきた固有のモチーフがあっただろう。そのモチーフは、日が当たったり影に入ったりしても、現在まで主流をなしていると思われる。吉本さんの言う「普遍的な詩とは何かというモチーフ」というのは、思うにこの人類史的な主流をなす潜在的な表現のことだろうと思う。言葉は、詩は、どんなことでも表現できるような幻想をわたしたちに与える、また、そのような自在に見える表現を許し、実際に様々な表現が存在する。しかし、実際には現在的に言えば人は現実社会やそのマスイメージと自分の固有の自己史とが出会う舞台で、なんらかの表現が可能なだけである。そしてそこには、おそらく連綿と続く人類史的な主流がまるで無意識的のように底流していると思う。
どんな表現をとろうと自由であるが、詩に限らず、考え方や思想でも、主流に沿うということは大切なことだと思っている。そして、詩に限らず表現の形式や有り様として時代的なものや段階的なものが想定できる。詩を表現する者は、表現の具体性として無意識的にそれを引き継いだり、改変したりしながら詩の表現を生きる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 508 |
世界への接続法 |
『吉本隆明 戦後五〇年を語る』185 |
インタビュー |
週刊 読書人 1999年11月、第2309号 |
読書人 |
|
※聞き手 山本哲士・高橋順一
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 江藤淳の堀辰雄批判 |
一種の上昇感性 |
|
|
項目
1 |
①
高橋 江藤淳さんが『昭和の文人』という本に書いていたことで、僕は非常に衝撃を受けた記憶があるのです。そこで中心的に扱われていたのは中野重治と堀辰雄だったと思いますが、江藤さんは非常に厳しく苛烈な調子で、特に堀辰雄を批判していました。江藤さんはなぜあれほど厳しく堀辰雄を糾弾しなければならなかったのか。・・・中略・・・
この問題は辿っていくと、吉本さんがお書きになった「芥川龍之介論」の問題にもつながっていくのではないでしょうか。吉本さんのお話をうかがっていて思ったのは、芥川にしても堀にしても、立原道造もそうですが、いわゆる下町の秀才ですね。この三人は共通して、さきほどお話しに出た府立三中の出身です。下町から府立三中へ進学して、一高へ行って、東大へ行くというコースを辿っています。そういう下町の秀才の成り立ち方、今回のお話でいうと、おじいさんやおばあさんやお父さんのことをお話になりましたが、そういう世界が一方にあって、他方に私塾の世界ではじめて触れた、ある意味では知的に上昇していく世界がある。知的な世界に入っていくことの解放感と後ろめたさ、気恥ずかしさ、要するに離脱と解放の間の微妙な境目みたいなものがどうしても出てくるのではないかという感じがするのです。それはある意味で芥川・堀・立原的な経験の質につながる問題だと思います。
②
吉本 江藤さんの堀辰雄に対する批判とは僕らと違いますし、もしかすると江藤さんは間違って読んだのではないか思うところがあるのです。
文学に魅かれる青年で、僕らとほぼ同じ年代の人はたいていそうなのですが、一番最初に堀辰雄とか、詩でいえば立原道造とか、小説は芥川も入りますし、全く違うはずなのですがやや似た感性で言えば中原中也とか、これは一番初めに文学に魅かれた時に読む人たちなのです。僕はどうして魅かれたかといったら、一種の上昇感性と言いましょうか、下町の貧乏で、濃密で、情念豊かな、ひとの良い人たちがいる世界の良さと、それは逆に言うと、息苦しさがある世界で、少し知的に上昇するとますますそう思えてくるところがあるのです。その息苦しさから逃れるというような感じで、僕らは、堀辰雄をはじめとして、立原でもそうだし、その続きで芥川や中原中也でもそうなのですが、その作品を読んだと思うのです。
江藤さんはおそらくそうでないと思います。都市銀行の課長さんとか部長さんとかの息子で、戦後すぐですから、貧乏で食い物に困ったり、お金に困って売り食いしたことはあるでしょうが、しかし、堀辰雄と違いわりあいに裕福な場所にいた。つまり、知識とか家系とかもまた富の一種なんだと考えれば、わりあいに豊かなところで育ったと思うのです。たとえば、おじいさんならおじいさんでいうと、海軍の中将か何かで、当時でいえば大変な秀才です。そのままいけば海軍の重要人物になるだろうというような素質を持った人で、中将ぐらいで死んだのですが、佐賀県出身の名士だということも含めて大変な人物でした。
そして江藤さんは堀辰雄の文学に傾いていくわけですが、おそらくその文学を自分の感性と同じだという意味で読んだに違いないと思うのです。僕らはそうではなくて、これは上昇感性だと読んでいるわけです。江藤さんははじめ堀辰雄の文学を自分たちの感性と同じだと思って読んだに違いないのですが、だんだん自分の家の社会的な地位とか、家系の持っている地方で占めている重たさとか、そういうのを自覚してくるにつれて、この人は面白くない人だ、本当は貧乏人のくせにこういうのは面白くないと思いはじめた。そうした点では、少し似ているところもあるのですが、最初の入り方はまるで僕らと違います。僕らの入り方が正しいとすれば、江藤さんはおそらく最初の入り方を誤解して、堀辰雄をかなり裕福な人たちを表現した感覚として読んだのだろうと思います。一生懸命読んだと思いますが、そのうちだんだんわかってきて、これは面白くないとなってきた。
(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』185 週刊 読書人 1999年11月、第2309号)
※聞き手 山本哲士・高橋順一
|
備
考
|
(備 考)
現在では、江藤淳の世代が育った家族や社会と比べて、家族も社会もより均質化してきている。それでも、人は、無意識のように家族や地域社会の固有性を背負ってひとり立ちしてくることには変わりはない。吉本さんがすぐれた文体論として評価していた若い江藤淳の『作家は行動する
』を読んだことがある。そこにはまだ家や家系や国家・社会との古びたつながりの意識は微塵も感じられない、若々しい江藤淳がいた。生活者はそうでもないが、知識世界に足を踏み入れた者たちは、国家・社会などとの抽象的なつながりの糸を繰り出しがちである。生活世界でも、知識世界でも、抽象的な不毛の糸に絡め取られるのは同時に自己の大切ななにものかを枯らす、あるいは失うことでもある。この江藤淳の挿話から、人はどんなに優れていても自分が育ってきた固有の、あるいは局所的な心身世界の影響の重力を振り切って、〈普遍の言葉〉を行使し続けることはとっても難しいことだなと思わざるをえない。
現在は、吉本少年の時代よりも割と豊かで均質化した社会になってきたから、吉本少年の時代の「一種の上昇感性」という動機はずいぶん薄らいで来ていると思われる。しかし、今から半世紀以上前のわたしの少年時代でも「一種の上昇感性」という動機は十分に生きていたし、私の中にもその動機はあったように思う。わたしたちは、誰もが生活世界に根を下ろしつつこの世界(社会)とのつながりの関係に入っていく。そして、家族や地域社会や学校などを通して育んだものを無意識的な素材として、この世界との接続法を作り上げていく。この人間的な関係世界で、できる限り自分の言葉やつながりの糸を〈普遍〉の方へ開いていくことは、この世界の有り様を捉え尽くすためにも大切なことだと思われる。吉本少年の時代の「一種の上昇感性」という動機は、現在ではもう少し一般化されて、わたしたちの日常的な生活世界の具体性とスポーツや芸術や政治や宗教や知識世界などの生活世界から割と抜け出た世界との間の齟齬(そご)の問題として残存しているように見える。ひとりひとりがその両者の間をどう踏み越えたり、戻ってきたりするかという問題として生きているはずである。
|
講演日:1995年7月9日 吉本隆明の183講演の「講演テキスト」より引用
関連項目520,522
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 仏教的信仰の問題 |
普遍的倫理 |
法っていうものに、即座に接触する接触面 |
接点 |
項目
1 |
①
9 宗教を普遍的倫理という面で切る (引用者註.「講演テキスト」の小見出し)
そうすると、ふたつの切り口があるわけで、ひとつは、普遍的倫理っていうのが、もし、ありうるとすれば、それは、法っていうもの、法律でもいいですけど、法っていうものに、即座に接触する接触面じゃないかっていうことが言えるわけです。
市民社会で、良い行いをしたとか、おまえはそれは悪い行いだって言ってる間は、ただの村の掟とか、町の掟とか、市民社会の掟に過ぎないのだけど、その、良い、悪いっていう問題を普遍的な善悪っていうところまで進めていきますと、それは、市民社会の、おまえは良いんだとか、悪いんだとか、具体的な生活のなかで言ってるよりも、もうすこし高度に、頭の上に置かれた善悪っていう問題になって、これはすぐに法、あるいは、法律の条文になったり、法律自体になったりっていうかたちで、たくさんの人が、この人は従うけど、この人は従わないとか、この人は善だと思ってることが、この人にとっては悪だったとか、そういう個々別々じゃなくて、普遍的な善悪っていうところで、掟が、法っていうようなかたちでつくれることが言えると思います。
そうすると、信仰っていう、信ずるっていう精神の状態、信じて信ずる境地を高めていって、悟りへ到達する仏教的信仰の問題は、やはり、普遍的な倫理の問題に移し変えられる。そうすると、そこの平面で切るならば、それは、法っていうことにつながっていく契機がありますから、そこで切る切り方でもって、宗教のあらゆるありかたっていうのを、そこの面で切るっていうのは、つまり、普遍的倫理っていう面で切る切り方を見つけ出せれば、つまり、宗派によってそれぞれ多少違うわけですけど、それでも、普遍的な倫理の問題の面で、ぜんぶ微少に違っている宗派の宗教信仰心っていうような問題を、そこで切るならば、それは、フーコーのいう考古学的な面っていうことになりうるんだって思います。
そういうふうに考えれば、フーコーの考え方っていうのは、そういう段階論的な、つまり、ヘーゲル・マルクス流の考え方と、接点を持てるっていうふうに、ぼくには思われます。
②
それを、たとえば、日本の浄土系統の元祖に源信っていう人がいまして、『往生要集』っていうのを書いて、比叡山の横川ってところに僧堂をくんで、そこで修業して、はじめて、『往生要集』っていう、浄土系統の法門を集めた本をつくった人ですけど、ぼくらもそういうことをやったことありますけど、源信の『往生要集』からいって、法然の『選択集』っていうのがありまして、法然の『選択集』へ歴史的に移っていく場合に、浄土系統の思想は、どこが変化したかっていうようなたどり方をすると、それは、浄土系統の歴史っていうものを解明するたどり方になります。
その解明するたどり方をやると、考古学的な意味での面は出てこないわけです。だけど、歴史的に、非常に緻密なっていいますか、源信の『往生要集』では、臨終のときに唱える念仏に、とくに重きを置いて、臨終のときには、仏像から五色の紐といいましょうか、布が出てて、死ぬ間際、臨終の間際になったら、五色の紐をつかまえながら念仏を唱えると、そうすると、そのまんま浄土へ往生できるんだっていうのが、源信の考え方のなかにありますし、『往生要集』の考え方のなかにありますし、源信は実際的に、そういうあれをつくって、やってるわけです。
それに対して、法然なんかは、いや、そんなことは、それほどの問題でなくて、言葉だけで念仏を唱えればいいと、そんなことをしなくても往生できるから、ことさら臨終のときの念仏に重きを置く必要はないんだって言いだしたわけです。
親鸞になると、なおさらもっと、移り変わりがありまして、つまり、人間っていうのはどういう死に方をするか、いつ死ぬかなんてのは、誰にもわからないんだっていう、そんなことはぜんぜん決まってないんだ。だから、念仏を唱えればいいとか、臨終の念仏がいいんだとか、そんなことを言ったって、病気次第によっては、口のきけない臨終だってありうるわけだから、そんなことを言ったって、そんなのはダメなんだ。だから、極端なことをいえば、至心っていう言葉を使ってます。真心から、自分は浄土にいけるっていうふうに信じて、一回念仏を唱えれば、それだっていいんだよっていう言い方に、親鸞の場合には、そういうふうになっちゃうわけです。余裕があるなら、もっとしたほうがいいですよ、だけど、ほんといえば、一念義でいいんだよっていうふうに、極端にいいますと、親鸞はそう言ってくわけです。
③
10 考古学的な層と段階( 引用者註.「講演テキスト」の小見出し)
そうすると、源信から親鸞まで、浄土系統がたどった、歴史的な経緯はどういうふうになっているかってたどることはできます。しかし、そういうたどり方をしても、考古学的な面っていいますか、そういうものは出てこないわけなんです、ちっとも。それだったら、そういうたどり方をするならば、そのたどり方をいつまでやってたって、はじまらないって、そんなこといくらやったってダメだってことで、段階っていう考え方をヘーゲルはあみだしていると思います。
(『 A172フーコーについて』吉本隆明の183講演 講演日:1995年7月9日)
※①、②、③は、連続する文章です。
|
備
考
|
(備 考)
わが国の批評の現在までの有り様としては、③に述べられているような「源信から親鸞まで、浄土系統がたどった、歴史的な経緯はどういうふうになっているかってたどる」ということが、一般的でなじみがあるものだと思われる。
そのことは逆に言えば、この列島では、ヘーゲル・マルクス流の段階論的な考え方もフーコーの精神の考古学的な面で切って捉えるという考え方も、ともに無縁であったということである。アフリカ的な段階のものやアジア的な段階のもので人類史や歴史は捉え尽くせない
のと同様に、ヨーロッパが生み出した優れた考え方や方法だけでは人類史や歴史は捉え尽くせないだろうという気がする。すなわち、あれかこれかではなく、あれもこれも包括するような考え方や方法が目指されべきだと思う。
わが列島は、古代においては、先進中国の言葉や思想や文化の大波をかぶり、その漢字文化圏のそびえる〈抽象性〉や〈論理性〉に驚愕したものと想像する。その驚愕は、とてつもないものだったろう。そして、この列島の文法や考え方の秩序のようなものにのっとってそれらを消化吸収・改変応用しようとしてきたのだろう。二度目の大きな大波は、明治近代になって押し寄せたヨーロッパの〈抽象性〉や〈論理性〉であった。一度目と違うのは、生活の感性や情緒に渡るまでまったく異質であったということである。それにしても、ヘーゲル・マルクスの段階論的な考え方やフーコーの精神の考古学的方法は、この列島の無意識的な感性や考え方とは異質だなと言う思いはわたしにも強くある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 532 |
死のイメージは変化する |
「二〇一〇年、吉本隆明が『人はなぜ?』を語る。」 |
インタビュー |
『BRUTUS』2010年2月15日号 |
吉本隆明資料集175 |
猫々堂 |
2018.5.25 |
聞き手 糸井重里
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 死というのは、自分に属さないんだ |
最近わかった |
|
|
項目
1 |
①
死というイメージは年齢によって変わっていく。 ( 引用者註.本文の小見出し)
糸井 僕は吉本さんから「死というのは、自分に属さないんだ」ということを学びました。そのときら、自分で、死ぬんだ、生きるんだ、ということを決めなくなったんです。それだけで、今日が楽しく、そして、意義を持ちます。年寄りはみんな自分で決めたかのように、もうダメだとか言いますけど、あれはダメですね。
吉本 本当にそうです。最近わかったことがあるんですけど、死というイメージは年齢によって変わるんです。昔は(註.1)、死というもののイメージが怖くてね。棺桶に入って、焼き場に行って、火をつけられて、じりじりと背中のほうから焦げていくというのが、死のイメージだった。そう思っていたときに瀬戸内寂聴さんに会ったら「死ぬの怖くないわ」って言うんです。坊さんだから、そういう話をするんだと思っていましたけど、でも、糸井さん、これは変わるんです。こういう風に考えて、こう考えて、今のことはどうでもよくなった、ということではないんです。今、思うと、おっかないイメージで、よく自分は死を考えていたな、と思えるぐらい。年齢に伴って、変わるんです。それがわかって、寂聴さんにもあんまり反感を持たないようになりましたね (笑)。
(「二〇一〇年、吉本隆明が『人はなぜ?』を語る」P72『BURUTUS』2010年2月15日号 『吉本隆明資料集175』猫々堂)
※①、②は、連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
吉本さんが、そんな恐い死のイメージを持っていたなんて、初めて知った。
(註.1)
吉本 僕が死について本格的に「怖いなあ。厭だなあ」と感じるようになったのは六十代後半、七十歳になる直前でした。不可避のものとしての死をはじめて切実に考えるようになったんですね。・・・中略・・・当時の僕の恐怖の正体は・・・・・・「自分が焼き場に運ばれて、棺桶の中でだんだんジリジリ焼かれていって」というイメージでしたね。これが頻繁に鮮明に浮かんだものだから、もう堪らなかった。・・・中略・・・では、現在、僕は「自分が棺桶の中でジリジリと焼かれるうイメージ」が怖いのか、と言ったらそうでもないんですよ。なぜ、怖くなくなったのか。これも、なかなか簡単に説明はできないですけど、自分の当面した感触を言うとしたら、七十歳を過ぎたぐらいの時期に、棺桶のイメージは、知らないうちに消えていったんですよ。
(インタビュー「吉本隆明さん、今、死をどう考えていますか?」P33-P34『吉本隆明資料集175』猫々堂、『よい「お葬式」入門』2009年8月25日刊初出
)
この「死のイメージ」に限らず、一般に誰もが歳を重ねてくると前よりは違った新たな地平に立っているような感じがして、過去のイメージとは違ってくることが多いような気がする。たぶん、これは誰にでも訪れる変容ではないかという気がする。また、身体的には、食べる味覚などの好みも変化するようである。例えば、若い頃はミョウガや梅干しとかあんまり食べなかったのに好んで食べるようになるなど。
また、歳を重ねるほかに、大きな経験をした場合にもイメージの変位は起こりうるように思う。立花隆の『臨死体験』によると、臨死体験を経験した人は死が恐くなくなる人が多いそうである。たぶん、なあんだあんな花畑や光に包まれたすばらしい世界を通って死へむかっていくのかと感じ考えたのかもしれない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 534 |
全共闘 ① |
「天皇制・共産党・戦後民主主義」 |
インタビュー |
『中央公論』2009年10月号 |
吉本隆明資料集175 |
猫々堂 |
2018.5.25 |
聞き手 大日方公男 インタビュー 2009年7月31日
※ 「論名」は正確には、歴史としての「全共闘」 証言●戦後の転換点と左翼の終わり 「「天皇制・共産党・戦後民主主義」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 一九七〇年頃がいろいろな意味で日本の戦後の転換点 |
左翼・右翼という概念や左翼・右翼という対立軸で考える日本の旧来の政治思想の死 |
彼らの行動を促すものには普遍性がある |
|
項目
1 |
①
― (略) 最初に、全共闘運動が高まりを見せた六〇年代後半から七〇年代初めの時期をどのように捉えられているのかお聞かせください。
吉本 一九七〇年頃がいろいろな意味で日本の戦後の転換点だと僕は捉えてきました。政治思想や社会のあり方、人間の身体の動きやその捉え方などが変わったのが、ちょうどこの時期だと考えています。
この転機を最も象徴した一つの例が、サッポロビールの天然水の登場です。最初は酒呑みがウイスキーや焼酎の水割りをつくるための業務用だったかもしれませんが、すぐに一般向けに市販され、すごい勢いで売れ行きを伸ばした。戦後の社会が大きな断層を持ったのがこの辺りの時期で、こうした資本主義の変化に既成の政治的なインテリ左翼が気づかないのは、致命傷になると感じていました。
ぼくは、教育や学問がどうであるかというような制度的な意味での大学には、当時もいまもほとんど関心がありません。しかし、全共闘運動という学生たちの反乱がちょうどこの時期に起こったことには意味があり、彼らの運動はそういう社会的変化に意識的にか無意識的にか対応した行動だったと感じています。左翼の政治思想からすれば、「そんなことはお前の独り合点だろう」ということになるのでしょうが、僕はそう思っています。
②
― 当時の学生たちを運動へと駆り立てたものは何だったと思いますか。
吉本 僕は、左翼・右翼という対立軸で考える日本の旧来の政治思想や、自分が勉強した古典経済学によって捉えられる左翼というのは、概念としても現実的にも、七〇年頃で終わったのではないかと思っていました。でも、「時期遅れだよ」と簡単に片づけられない。得体の知れないエネルギーが、全共闘の学生さんたちにはありました。
全共闘の学生たちの反乱の理由は、理屈として明瞭に分かるものではありませんが、僕らが戦後に政治思想を学んだ丸山眞男にあれだけの暴言を吐かせたものの本質は、よくよく考えたほうがいいよと感じました。
僕らは戦争中に天皇制にイカれて、目もあてられないイデオロギーや時代を突っ張って担いましたが、どこかで全共闘の学生さんたちに僕らと同じものを感じていたというのが正直なところです。しかし、自分たちの若い頃に重ね合わせて、彼らの行動に意味がないと断定するのは可哀想だよと思いました。
むしろ、大学の自治や学問の特権性を唱える加藤一郎や丸山眞男のほうに、戦時中は大学も学問も国家に従属していて、そういう時代をくぐり抜けたくせに、よくそんな宗教的なことを言えるなと、違和を感じていました。
③
吉本 急進的と呼ばれながら、一般の学生でもあった全共闘の人たちに、そういう感性(引用者註.インタビュアーの言葉に寄れば「一個の生活者、最初に自分の主体的な判断や私的利害を考える人間として行動する」)を感じ取って、僕なりの理屈をつけて関わっていました。
彼らが左翼のロクでもない指導者や理論家から吹きこまれる政治思想には、ほとんど見るべきものを感じませんでしたが、しかし、彼らの行動を促すものには普遍性があると感じていた。そういう評価をしないと、全共闘の人たちが意図的に、あるいは無意識の中で明らかにした重要なものがよく見えてきませんね。
六〇年安保のとき、一兵卒として反対闘争に参加して、学生さんがやることと同じことを全部自分もやるんだと思いましたが、僕らはオーソドックスな世代論の影響を受けて、それぞれの世代の特性や違いによって運動を捉えがちだった。それは歴史を馬鹿にした考え方で、古い左翼や知識人は、当時もいまも自分たちが戦争をくぐり抜けた体験を誤魔化して世代に理念を繋いでいく方法をとるわけです。でも、そんな誤魔化しが長持ちするわけがないというのが僕の考えで、戦後も戦中から自分なりに貫いてきた人間性や思想を持続しようとしたんです。
まず、明治憲法下の天皇は、「神聖不可侵」であり、五・一五事件や二・二六事件のような、左翼か右翼か分からない思想や思想家を取り締まる事件があり、そういう古層の天皇制を引きずる時代があった。つづいて、敗戦によってアメリカの民主主義を受け入れて、国や集団の規制より自分の人生や生活のほうが大事だよという考えが曲がりなりにも広まり、それを体現した全共闘の時代があった。相矛盾するような時代であっても、自分は生きてきたのだから、この二つの時代を繋げようとしたんです。
それができれば、日本の近代は底が浅くインチキだと言わないでもいいのではないか。欧米や国家に騙されたとばかり言わなくても済むのではないか。共産党は人民のための永続する党であると言わなくて済むではないかと、僕はもっぱら考えました。
戦争中に天皇制を信じ、日米戦争の意味を信じて青春時代を送り、情緒的なものも含めて天皇制を自分なりに煮詰めて考え、そのためには死んでもいいと東洋的な終末観に囚われたことを、どうしたら自分の中で矛盾ないように納得がいくのか考えた世代です。
同様に、団塊の世代の人たちが、六〇年後半に青春時代を迎え、何かに突き動かされるようにとった無意識の行動にも思想的な意味があり、それをどう、いまに繋げて考えればいいのかということが課題として残ると思います。
(「天皇制・共産党・戦後民主主義」P39-P44『中央公論』2009年10月号 『吉本隆明資料集175』猫々堂)
|
備
考
|
(備 考)
まずわたしは、全共闘世代以後だから、その渦中にいたわけではない。具体性そのもの、そして抽出すべき具体性としては、いろんな負の側面もあったろうと思われる。ここで語られているのは、抽出すべき積極性としての正の側面である。歴史の無意識に似た時代や社会の無意識的な動きを若者たちが敏感に感知し反応した点において、全共闘が評価されている。そのことはまた、吉本さん本人の戦中から敗戦後への歩みに重ねられている。
③の最後の部分に関して。
全共闘世代以後に属するわたしからすれば、相変わらず残存する「日本的なもの」、その負性の秩序感覚は、たぶん相当根が深いものだと思われる。それに全共闘は主に大学という場でぶつかったのだろう。これを何かの象徴と捉えるならば、彼らの背後には、敗戦で叩きのめされた「日本的なもの」の死が、再度の欧米(主に米)化の波による浸食の進行によってさらなる掘り崩しを受けていた時代や社会の状況があり、全共闘の若者たちは鋭敏にその現場に立ったのだと思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 535 |
全共闘 ② |
「天皇制・共産党・戦後民主主義」 |
インタビュー |
『中央公論』2009年10月号 |
吉本隆明資料集175 |
猫々堂 |
2018.5.25 |
聞き手 大日方公男 インタビュー 2009年7月31日
※ 「論名」は正確には、歴史としての「全共闘」 証言●戦後の転換点と左翼の終わり 「「天皇制・共産党・戦後民主主義」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 農地改革 |
自分の対立物は、天皇制と共産党だった |
天皇制の実質は昭和天皇の時代で終わった |
|
項目
1 |
①
天皇制と共産党の神話を壊す ( 引用者註.本文の小見出し)
― 全共闘が行動によって体現した普遍的な意味とは、どのような点に見出せるのでしょうか。
吉本 戦後、日本はアメリカ軍によって占領されますが、アメリカの軍政局にいた日本通と進駐軍が日本社会を革新した唯一の政策は農地改革です。一定以上の土地を占有し、所得のある地主や資本家から財産を没収し、小作農民を自作農にしたことです。現実的にはこれ以上の改革はほとんどありませんでしたが、これが第一の戦後革命だと思います。
第二の戦後革命は、安保闘争から全共闘の若い世代が担ったものだったと思います。僕らの世代にとっては、「神聖ニシテ侵スベカラズ」である天皇と、それに対して永続性を持とうとした共産党の二つが、神話性を与えられたものでした。
僕は六〇年安保のときに、日本の資本主義に異論を唱えることのできる最後の機会だと思って、運動に参加しました。その見込みは半分当たって、半分はずれました。そのために僕が何を自分の対立物としたかと言えば、天皇制と共産党です。
(「天皇制・共産党・戦後民主主義」P45 『中央公論』2009年10月号 『吉本隆明資料集175』猫々堂)
②
ところが、神話性があって、簡単に滅びることのない天皇制と、簡単に弱まることのない共産党を全共闘の世代はもろに壊したわけです。これは僕らから見ると大事件でした。何しろ僕らは、戦前は電車で皇居の前を通ってもお辞儀していたわけですから。(笑)、これは相当重要な戦後の転換です。
さらに言えば、天皇制の実質は昭和天皇の時代で終わったと考えています。その意味で、全共闘世代は天皇制に最後に付き合った世代だと思います。もう少し時間が経つと、そのことははっきりしてくると思いますね。
(「同上」P45-P46)
|
| 備考 |
(備 考)
関連として、吉本さんは、全共闘を含めていたかどうかはわからないが、共産主義者同盟(ブント)をはじめての「独立左翼」と呼んで評価していた。
(追記) 「独立左翼」関連として
吉本 だから、六〇年安保闘争当時、僕らは社共の主流派と行動をともにする場面は多かったのですが、闘争のモチーフも理論も、本当は画然と違っていたということがあるんです。僕らは、自分たちのことを日本ではじめての〝独立左翼〟だっていうふうに捉えていました。〝独立左翼〟として、アメリカを主とする資本主義国家圏に反対する―もちろん、日本資本主義にも反対するけど、同時に、ソ連を主とする社会主義国家圏にも反対するというのが、僕らの考え方だったんです。自分たちの中では、それは自明のことでした。
(『私の「戦争論」』P230 吉本隆明 ぶんか社 1999年9月)
②の「もう少し時間が経つと、そのことははっきりしてくると思いますね。」、こういう言葉が出て来る吉本さんの視線の場所を修練を重ねてつきとめることが大切だと思っている。対象を読むということ、見通すということ。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 536 |
心棒は思想 |
「天皇制・共産党・戦後民主主義」 |
インタビュー |
『中央公論』2009年10月号 |
吉本隆明資料集175 |
猫々堂 |
2018.5.25 |
聞き手 大日方公男 インタビュー 2009年7月31日
※ 「論名」は正確には、歴史としての「全共闘」 証言●戦後の転換点と左翼の終わり 「「天皇制・共産党・戦後民主主義」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 埴谷雄高「レーニンはレーニン全集の中にいる」 |
人間の個々の身体と絡み合って離れない思想 |
宗教的なものを見てしまう |
|
項目
1 |
①
どんな場合でも心棒は思想 ( 引用者註.本文の小見出し)
― 六〇年代は政治・社会情況が大きく揺れ動いた時期であり、吉本さん自身も熱気ある学生たちによって、さまざまな場所へと引っぱりだされてもいました。そのような時期にあって、吉本さんの仕事の中心は、『言語にとって美とはなにか』や『心的現象論』など思想の骨格をなすものが多く、まさに原理論的な仕事に沈潜されています。
吉本 かつて埴谷雄高さんは「レーニンはレーニン全集の中にいる」とよく言っていました。最初は、埴谷さんも何も現実に頼るものがなくなったから、そう言っているのかなあと聞いていました。しかし、そうではなくて、どんな場合でも僕らの心棒というのは思想であり、そして最も長く生きるのも思想であり、思想者なんだとという解釈に次第に変わりました。
それは文学のようなことをしている自分の病根かもしれませんが、自分の核心にあるものは現実の政治経済的な動きでもないし、文学的な空想や想像力とも違う、どこかでその人間の個々の身体と絡み合って離れない思想だと僕は思っています。
一般的には、その思想が政治や経済や芸術も包み込むわけですが、それが考察の対象となり、最も延命すると考えています。でも、進歩的な人でも保守的な人でも、本格的で優秀な人の思想には多分に宗教が入り込んでいると思ってしまうことがある。というより、思想やイデオロギーということを考えると、たいてい宗教的なものを見てしまうのが自分の病根かもしれず、それにはなかなかけりがつきません。
(「天皇制・共産党・戦後民主主義」P46-P47『中央公論』2009年10月号 『吉本隆明資料集175』猫々堂)
|
備
考
|
(備 考)
ロシア革命の影響があり、青年、伊東静雄の生きた大正末年から昭和初期は、社会主義やマルクス主義の思想が知識社会を席巻していた。そしてその風潮は、理論(考えること)より実践(行動)を上位にある優位なものと見なすものだった。そういう考えの残骸は、学生運動の時代にまで引きずっていたように思う。しかし、理論と実践の本質は、上位下位の概念ではない。また、そのような政治的倫理が介在するものでもない。この「心棒は思想」という捉え方は、それまでの日本の思想世界の流れからは、画期的な考えだったと言える。
思うに、理論と実践、わかりやすく言えば、考えることと行動することは、別物ではない。どちらも人間的な表現である。また、考えるということを精神的な行動と見なすことも可能である。傾向性として言えば、考えることがより精神性に関わるとすれば、行動するのがより身体性に関わるという相違があるだけである。
「思想やイデオロギーということを考えると、たいてい宗教的なものを見てしまう」のは、自分の病根かもしれずと吉本さんは内省的になっているが、このことは思想の局所性に関わることだと思う。局所的な利害や局所性を背景として持つ思想が、あたかも普遍の思想のように振る舞うことを指していると思う。そして、そうした思想がこの列島社会には瀰漫している。何ものにも囚われずただ真のみを目指す吉本さんの言葉は、〈普遍〉の思想を目指してきているから、その宗教性がよく見えよく感じ取れるのだと思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 539 |
親鸞と唯円の隔たり |
「親鸞の最終の言葉」 |
論文 |
『別冊太陽 親鸞』2009年5月 |
吉本隆明資料集175 |
猫々堂 |
2018.5.25 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 唯円の胸にひびいた親鸞の言葉 |
親鸞の思想 |
自然と名づけられた倫理、あるいは倫理と名づける自然 |
|
項目
1 |
①
『歎異抄』のなかで記述者唯円の耳にのこった親鸞の言葉で、わたしたちに現在に至るまで忘れがたく刻み込まれているのは、唯円の問いとそれに応えた親鸞の言葉であると言える。唯円は天台浄土や浄土宗派の僧侶たちは浄土は一日も早く生きたいところ、慕わしいところだと申しているけれど、わたしは浄土に早く参りたい心がわかないのはどうしたことでしょうと親鸞にたずねる。これに対して親鸞は「わたしもそうだ。現世は煩悩のふるさとで、自分たち煩悩の人間は、ふるさとが恋しく離れ難いように、煩悩のふるさとである現世が離れ難いのは当然なのだ」と応えた。そう『歎異抄』は記している。これはたぶん唯円の心をゆさぶって忘れ難く残された親鸞の言葉だったに違いない。唯円は素晴らしい弟子だとわたしには感じられる。あやまりなく師親鸞の思想を理解していると思えるからだ。わたしたち後世の者が親鸞の逆説と考えるようにさえ見える親鸞の言葉が、不朽のものであることを納得させる力を、唯円は記しているからだ。
②
だがこの『歎異抄』の記している言葉が、記されている他の親鸞の言葉と同じように唯円の胸にひびいた親鸞の言葉を、唯円の言葉に直したものだと考えると、少し私たち現代の者も考えなければならないことを余儀なくされる。それだけの力が、唯円の記した親鸞の言葉にも、唯円の優れた理解力にも含まれているからだ。『歎異抄』の言葉に一つだけ註をつけさせてもらえるとすれば、唯円は倫理(善悪)的な判断を媒介として混えながら親鸞の言葉を記しているのではないかとわたしは少し思えるようになった。わたしの考えが退歩したためか進歩したためか、わたしにはわからない。
③
『歎異抄』の唯円の親鸞の理解、そこ(引用者註.直ぐ直前の「悪人正機の逆説的な倫理の思想」を指す)に余りに多く力点をおきすぎていて、親鸞の思想をもっとも鋭く正確に受け取りながら、同時に親鸞思想の規模を小さく受けとって初期のそれにとどめているような気がする。親鸞の思想は『教行信証』の末尾においては名利と愛欲に迷って、定聚の数に入れないことを自然として是認しながら「自然即ざんげ」の根元に真宗の本質をみているのではないかと思えてくる。人間もまた他の生類とおなじく自然の一部分だとすれば、自然の全体性とは同値できなくとも、自然と名づけられた倫理、あるいは倫理と名づける自然とは同値できるかもしれない。
④
わたしには『歎異抄』のなかで唯円に反映したときの親鸞と『教行信証』の末尾に自身で述べられた親鸞自身の、煩悩のふるさとだから現世は自他ともに離れ難く、とても到達し難い「浄土」、そして到達できないということを、わすれ難いことを抱き続けるのが浄土真宗の本(もと)だということを〈ざんげ〉としてあきらかにしている晩年の親鸞とのあいだの隔たりこそが、唯円流派の本源ではないか、と思える。唯円はまだ浄土の信仰者であり、親鸞は到達できない浄土・浄土の信を、その上におくことのできた信仰者であったと言うべきか。信仰と不信仰のあいだに現世をすえる垣根をとり払ったと言うべきか。もはや言葉はない。(註.本文、ここで終り)
(「親鸞の最終の言葉」P20-P22『吉本隆明資料集175』猫々堂、初出『別冊太陽 親鸞』2009年5月 )
※①と②は、連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
吉本さんはここで、『歎異抄』の表現に、「唯円に反映したときの親鸞」と親鸞自身の言葉や思想を分離して考えようとしている。指摘されれば、そうだね、そういう問題があるなと思う。しかし、吉本さんとしては、親鸞の言葉や思想を追い詰めて、そういう微妙な地点にまで上り詰めてきたと言えると思う。
「人間もまた他の生類とおなじく自然の一部分だとすれば、自然の全体性とは同値できなくとも、自然と名づけられた倫理、あるいは倫理と名づける自然とは同値できるかもしれない。」という部分は、吉本さんが新たな概念の網である状況を捕捉するときによく感じるわからなさがある。人間は大いなる自然(宇宙)という全体集合のなかの部分集合であるから、両者は同値(等価)ではあり得ないが、「自然と名づけられた倫理、あるいは倫理と名づける自然」という言葉という幻想的な地平においては同値できるかもしれない、ということだろうか。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 541 |
作品(詩)を読む |
「変容する都市と詩」 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集176』 |
猫々堂 |
2018.6.25 |
初出 『現代詩手帖』1986年5月号
聞き手 樋口 良澄
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 理想型で言うと、イメージが全部解放されてしまう |
ぼくはそれを捜しながら読んでいるような気がしますね。 |
|
|
項目
1 |
①
― 文学における捉え方ということで、先ほどいい作品だったら必ず〈都市〉ということが入っているとおっしゃいましたが、そこでお聞きしたいんですが、なぜ吉本さんが都市のイメージを捜すのか、そして文学作品はそういった都市的なものが入っているということと、いい作品であるということの関係においてはどういう評価軸が成立して、それを理解することができるのかということです。
つまり、ある詩が書かれて眼の前におかれたとしたら、じぶんが書く書かないには関係なくたれがそれを書いたとしても、その詩は全面的にじぶんの持っている現在の生活感覚とか生活イメージとか、あるいは都市空間のなかに二十四時間のうち何時間かは必ずひたってゆくような生活の繰り返しみたいなところで出てくるじぶんの問題、もっと大袈裟なことをいえば、じぶんが持っている思想的な問題、日本の社会構成というのはどういうふうにこれから展開されてとか、どこが危機的なところかとか、どこが分析して報告しなければならない場所なんだという、つまりじぶんの中にあるそういうものも含めてじぶんが詩にたいして抱いているイメージが全部解放されてしまう、全部共鳴してしまう。そういう詩を想定しますと、どうしてもその中に重要な部分として都市がいまどういうふうな空間的な屈折とか折れ曲がりとか未知の部分を含んで変わりつつあるかということは含まれていきます。それが詩を評価するときのおおきな問題になってくるとおもいます。都市のそういう変化や折れ曲がりを掴まえるということは、ぼくの理解の仕方では、先進的な社会がこれからどう変わってゆくか、あるいは変わってゆくばあいに理想のイメージとしてはこういうイメージが描けるはずじゃないかということが基本になるような気がするんです。だからぼくなんかが思い描いているそういう詩を、たれかが出現させちゃったら、やはりこれだと共感もするし、じぶんも満たされるでしょうね。つまりじぶんの持っている思想的な問題から感覚的な気分までのあらゆるものが、そこで共感させられ、満たされちゃうということがあるとおもうんです。じぶんの理想形の詩ができたら満たされるに違いないけれども、そうじゃない詩は駄目かといえば、そうはおもってないですね。都市的なものの重要なものが表現されているかどうかは、詩の作品としていいかよくないかというのとは必ずしもおなじではないわけです。しかし一致するような詩の作品が出てきたら、じぶんはそこで満たされるだろうなという気はします。そのことは相当おおきな問題のようにおもえます。ぼくはそれを捜しながら読んでいるような気がしますね。例えば諏訪さんの『谷中草紙』を読むと、じぶんの中のある部分がとてもよく共感しますから、詩の作品としてこれはいい作品なんだという評価をしますし、またそういう評価がぼくにはできますが、でもぼくの中にあるあらゆる要素がいっぺんで解放されてしまうわけではありません。でもそんな詩の作品がもし出てきたら共感します。それを求めざるをえないようにおもいますね。またじぶんが書けるんなら書きたいとおもいます。しかしこれは意図して書けるものではなくて、じぶんながらどうしようもなく古いなあという感じがしてしようがないですね。だからじぶんでじぶんを満たすということはなかなかできないですけど、たれか満たしてくれてもいいわけですからね。
(「変容する都市と詩」P14-P16『吉本隆明資料集176』猫々堂、初出『現代詩手帖』1986年5月号 )
|
備
考
|
(備 考)
ふだんはあまりこのことは触れられないけれど――吉本さん自身もあまりそんなことには触れなかったような気がする。――、人間の具体的な表現には、本質的に言えばある人がこの世界内存在として生まれ育ち具体的な関係を結び関わり合ってきたその人の全重量が掛かっている。とは言ってもそこには、その人の意識的な部分と無意識的な部分があり、表現された言葉が作者の全面的な自己解放に当たっているかどうかは、作者も読者も一般的にはなんとも言えない。難しいことだが、その表現された言葉から、意識的な部分から無意識的な部分に渡って具体的にそれを判定するほかない。
この関連として思い出したことがある。吉本さんは、古事記の国生み神話の記述からこの神話を生み出した人々は海民ではないかと推定していた。神話を事実性と関連付けて論じるのが多い中で、吉本さんは慎重である。神話を生み出し記述した人々の意識的・無意識的な総体から、最低何が読み取れるかという位置にあると思う。例えば邪馬台国について吉本さんは、邪馬台国がどこにあったかということは、たいした問題ではなく、それがどれくらいの規模のものだったかやその宗教性などの組織性などは問題であり得ると述べていた。遠い未来から見た現在で言えば、例えば国会議事堂がどこにあったかなんてたいした問題ではないということになろうか。
「ぼくはそれを捜しながら読んでいるような気がしますね。」とあるが、若い頃から吉本さんの眼は、常人以上によく目配りされていて作品が素人玄人に関わらずずいぶんと行き届いていたように思われる。もちろん、目配りにかからず三木成夫の本や思想とはずいぶん後になって出会ったというようなこともある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 543 |
人工的な自然 |
「変容する都市と詩」 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集176』 |
猫々堂 |
2018.6.25 |
(関連項目542)
初出 『現代詩手帖』1986年5月号
聞き手 樋口 良澄
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 天然的自然 |
自然よりももっと本質的な自然 |
|
|
項目
1 |
①
― そういう無機質なイメージにどんどんなってゆき、都市的なものが浸蝕していった時に、諏訪さんの『谷中草紙』に象徴される、つまり吉本さんが言われるアジア的なものというのはどうなっていくんでしょうか。
吉本 ぼくは、しだいに払底していってしまうとおもいます。ただその時おおくの論者と違うことは、こういうふうにおもっているんです。自然よりももっと本質的な自然は人工的につくれるという考え方をぼくは持っているんです。つまり『谷中草紙』的なものがどんどん都市が払底していっちゃう、これを避けようとか自然を守ろうとかいう意味で自然が守られるとは少しもぼくはおもわないから、だんだん消滅していっちゃうに違いないとおもいます。そういう〈天然的自然〉というのは都市の膨張につれてしだいに退いていってしまう。それは避け難いことであるし避けようとすることは間違いだとおもっています。だけどもぼくはそういう人たちとは違うのです。マルクスがいう自然主義・人間主義とぼくが違うということ、マルクスはそこに時代的限界があるとぼくがかんがえていることは、天然的自然よりももっと自然である自然というものを人間は人工的につくれるとかんがえているからです。もっと具体的にいえば、天然的自然とは例えば『谷中草紙』のように地べたや原っぱに木の小屋を建ててしだいに街になっていくとか、その周りには欅の木や銀杏の木があってという、つまり自然がそういうふうに残ったというなんですが、しかし欅の林の隣に銀杏の群生があることが植物にとって最良の環境であるかどうかは疑問なんですね。つまりもっと植物学の認識を使えば欅の木の隣には、それまでは天然的自然としては銀杏の木だったんですけど、杉の木を植えることも可能なんですね。つまり天然がつくった自然よりもその人工的な自然のほうがもっといいんだということが可能だとおもうんです。
②
吉本 だから多分、人工的な自然というのは大都市のなかにつくられるとおもいます。大都市の中に人工的な自然をつくって。それは元の天然的自然より植物にとっていいという環境がつくられるとおもいますし、またつくらなきゃだめだとおもいますね。天然的自然を守れという考え方は絶対に滅びるとおもいます。それは必ず人工的なもの、都市的なものに被われていくとおもいます。では自然はどうなるんだという反論が出るでしょう。ぼくの理解の仕方は、元の自然よりもっといい自然を何らかの知識によって人工的に必ずつくる、そういうふうに人類はやるに違いないとおもいます。自然がどんどん滅びていったら人間は窒息して手を挙げちゃうなんてことは絶対にありませんし、自然が滅びて都市的なものが巨大化していくのが必然ならば、人間はまた土を集め植物を最良の条件で植えるとおもいますね。だからぼくは天然的自然というのが終末の自然ではないとおもっていますね。そこがいわば、天然的自然と街や都市との階級対立であり、そこから分業が始まりというふうにかんがえていた初期の社会主義者たちの考え方からは想像もできない未知の領域に入ったというところじゃないでしょうか。
③
吉本 今のぼくらの科学的な認識だったら、天然的自然よりももっと優れた自然を人間が人工的につくれるし、つくるというふうにおもっているから、ぼくの理念はそこではあんまりゆきづまらないんですね。しかし左翼的で自然主義的な人はそこでほとんど理念がゆきづまって、さらに反動化していくということがあるんじゃないでしょうか。なぜそうなっていくかと云いますと、都市的なものの中で未知の部分がマルクスなんかがかんがえた資本主義の初期から隆盛期にかけてとはまったく違って出てきたからじゃないでしょうか。そこのところで自然主義は少し変えないと必ずゆきづまるとぼくはおもいますねえ。・・・中略・・・
逆に云いますと、エンゲルスという人はよく大都市の没落は必然だと云うんですが、ぼくはそうはおもってないですね。それはやはり過去の自然主義だとおもいます。・・・中略・・・ぼくは大都市は没落せずにますます大都市化するだろうとおもいますが、ただしその中に天然よりもいい自然をつくって、農業もそこでやるとおもいます。地べたよりももっといい農業の地べた、それは土なのか液体なのか分かりませんが、それをつくるでしょう。だから農業も決して滅亡はしないとおもいます。ただ次元が違ってくるんですね。ぼくが描くユートピアというのはそうなりますね。
④
吉本 しかしそのへんのところがいろいろな人がお前のかんがえは承認しがたいと云うところでありましょうし、またいわゆる未知の部分でもあるんですね。断定的にこうだと決めつけはしませんし、ぼくはそうおもっているということです。
(「変容する都市と詩」P19-P21『吉本隆明資料集176』猫々堂、初出『現代詩手帖』1986年5月号 )
※①と②と③と④は、連続した文章です。
|
備
考
|
(備 考)
ここには、吉本さんの化学(科学)的な素養や認識が込められている。
ここで言われていることは、大多数の人々が一方で「自然を守れ」や「自然を大切にしよう」などをなんとなく受け入れていたとしても、日常見聞きする感覚として割と受け入れられやすい捉え方だと思う。歴史の変動期の正負のベクトルのうち、正のベクトルに当たる。それを支えているのは、もっといい環境で作物(植物)を育てたいとかもっと人間にとって質のいい作物(果物)を栽培したいとか花や樹木を人間社会の街路やビル内や自宅に持ち込みたい等など現在も推進されているような人間的な性向である。このことは、反作用として例えば心臓病であればそれへの補助的な対策として小さな機械を体に埋め込むということにもつながっていく。わたしたち人間は徐々にそうした事態を自然なものとして感じ受け入れていくのだろうと思う。
負のベクトルに当たるのは、おそらく突き進む現在がもたらす不安から湧き上がるもので、後ろ向きの「自然を守れ」や「自然に帰れ」などの感覚や考えであろう。
これらのことは、長い時間スケールの歴史の流れが証明するだろうけど、すなわち何十年何百年後には明白になるだろうけど、人類の「歴史の無意識」(吉本隆明)や歴史の真の主流に関わっている問題だと思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 553 |
戦時下の日本 ① |
第一章小林よしのり『戦争論』批判するを |
インタビュー |
『私の「戦争論」』 |
ぶんか社 |
1999年9月30日 |
※聞き手 田近伸和
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 大東亜戦争 |
軍隊 |
「侵略」とは何か |
|
項目
1 |
①
―(中略) 小林よしのりは、それ(引用者註.GHQの占領政策)に真っ向から異論を唱えるべく、『戦争論』では「大東亜戦争」という言葉をあえて使っています。日本が戦争をしたのは自衛のためであり、また欧州列強によるアジアの全植民地化を防ぐためだった、事実、日本が戦ったことでアジア諸国は独立できたじゃないか、というのが小林よしのりの主張です。
吉本 小林よしのりのいっていることは、東京裁判で日本の戦犯を裁いた判事の一人、インドのパル判事の考え方に似ていますね。キーナンというアメリカの首席検察官は、「日本は侵略戦争をやった」の一点張りで、東条英機たちに死刑を求刑しましたが、イギリスの植民地支配を受けていたインドのパル判事は、東条英機をはじめ日本の戦犯を全員無罪にしたわけです。
戦争中、僕は一七歳から二一歳ぐらいでしたが、そのときは「大東亜戦争」といっていました。今は、そういういい方はしません。「太平洋戦争」とか「第二次大戦」とかといういい方をしています。それはなぜかといえば、戦争中、僕は「大東亜共栄圏の確立」という日本政府のプロパガンダをそっくりそのまま肯定して、戦争を「やれ、やれ」というほうだった、それに対する後ろめたさが、いくらかなりとも今の自分にあるからです。
小林よしのりがいうように、日本が戦争をしたその余波として、アジア諸国の独立が促されたことは確かです。でも、一方では、「侵略」という面があったことも否定できないんです。中国の東北部を切り離して満州国を独立させ、傀儡政権をそこにつくった。日本政府のいいなりになるように、日本政府が顧問を派遣したりしてね。それが中国侵略のはじめであって、それは、やはり「侵略」なんだと思います。だから、小林よしのりのいっていることは、半面だけ捉えた調子のよいいい方なんです。
当時、フランスはベトナムやカンボジアなどを植民地にしていましたし、オランダはインドシナを、イギリスはニューギニア、マレー半島などを植民地にしていました。そういう時代状況の中で、日本が中国などに出ていった背景には、「西欧諸国がアジアで植民地をつくっていい思いをしているから、こちらもそうしたって悪くはあるまい」というモチーフがあったことは確かです。
(『私の「戦争論」』P21-P22 吉本隆明 ぶんか社 1999年9月)
②
吉本 結果的にはアジア諸国の独立を促したというのはその通りですが、そこで忘れてはならないのは、日本政府や日本軍、日本の官憲、それから日本の民衆が、占領下で何をしたかってことなんです。占領下の現地の民衆を大事に扱ったかというと、けっしてそうじゃないですよ。会社でも、ちょっと景気がよくなると、とかく日本人は上司が部下に威張ってというところがありますが、現地の民衆をケモノ扱いというか、とにかくひでえことをして、反感を買った。それで、現地の民衆が不信を抱いたんです。今でも中国や韓国の人たちが日本に反感を持っているというのは、それがあるからです。これは、やはり、非難されても仕方のない日本の弱点だと思います。どんなに立派なことをいっても、実際のふるまいがダメだったらダメなんです。
(『同上』P24 )
③
― 日本の軍隊というのは、それほどまでに威張っていたのですか?
吉本 日本国内でも、軍の将校が一般人に対して、やたら威張っているということはありました。また軍隊内でも、たとえば上等兵は一等兵などに対して、すごく威張っていて、上官が部下をすぐひっぱたくなんてことは日常茶飯事でしたね。戦争中、僕は米沢高等工業学校にという旧制の高等工業学校に通っていたのですが、軍事教練で軍人の教官が生徒をやたらひっぱたくんです。米沢高等工業学校には、日本名を持った二人の台湾の留学生のほか、日本軍の技術将校みたいなやつも留学していたのですが、その技術将校みたいなやつが、「俺をからかったな」とか難癖つけて、台湾の留学生たちをすぐひっぱたいていました。それを見て、僕は軍人がホトホト嫌になったということがあるんです。
だから、日本軍が占領下の現地の民衆に対して威張っていたというのは疑いのないところだと思っています。人道にのっとって現地の民衆を大切に扱っていたなら、これほどまでに恨みを買わなかったでしょうし、「日本は侵略国家だ」ってことをいまだにいわれ続けることもなかったと思います。どの程度の悪いことをしたのか、その規模まではわかりませんが、日本軍が相当悪いことをしたのは確かです。でも、日本軍がのべつまくなしに現地で悪いことをしたかというと、場所によっては、必ずしもそうじゃないんです。インドなんかに対しては、それほど悪いことはしていません。
(『同上』P25-P26 )
― なぜ、日本の軍隊はそんなに威張っていたのでしょうか?
吉本 それはよくわかりませんが、上等兵が一等兵などに対して威張っていたとかいうのは、わかるような気がします。一般社会の中では下っ端扱いされていたのに、軍隊では出身に関係なく等級別に扱われますからね。上等兵といっても、彼らは徴兵される前は、貧しい農家の次男坊や三男坊だったり、工場の肉体労働者だったりしたわけです。上等兵になれば、部下の一等兵などがどんな金持ちの息子であろうが、良家の息子であろうが、おかまいなく、ブン殴ることができた。だから、インテリにとっては、軍隊はなるほど悪いところだったけど、一般社会で下っ端扱いされていた人々たちからすると、軍隊はむしろ平等な社会で、開放感を与えてくれる場所だったという面(註.1)もあったんですよ。
(『同上』P27-P28 )
④
― 第一次世界大戦のあとなぜ、国際連盟ができ、国際連盟は総会で「すべての侵略戦争を禁止する決議」を行いました。ところが、「侵略」の定義がいまだにきちんとなされていません。それで、何をもって「侵略」というかが、今なお問題となっています。
吉本 そうですね。「侵略」とは何か?その定義をきちっというのは難しいですが、僕は一つだけしかいえない気がします。戦争をしている国同士があって、相手国の領土内で行われた戦闘行為があった場合、それはやはり、その相手国への「侵略」であると―それだけは、いえると思うんです。先の戦争では、日本軍が中国に出ていって中国で戦闘行為が行われたのは事実なわけですから、日本軍がやった行為はやはり「侵略」だと思います。
(『同上』P28 )
吉本 マルクスは、「侵略」という言葉を少なくとも倫理的な意味合いでは使っていません。「植民地化」って言葉を使っています。レーニン以降のマルクス主義者は、「帝国主義的植民地化は悪である」というふうに規定して、日本のマルクス主義者もそう思い込んできたわけですが、マルクス自身はそうはいっていないんです。
インドの植民地化を例にとれば、イギリスはインドを植民地化し、インドに紡績工場などをつくって、インドからさんざん富を収奪して、利益をむさぼったけど、一方では、インドの民度や文明・文化を飛躍的に高度化させたともマルクスはいっています。植民地化には害と利の両面がある、とマルクスはいっているわけです。(註.2)
「侵略」という言葉を使い、「帝国主義戦争を行って植民地化するのは悪だ」と決めつけるのは、ロシア・マルクス主義者の専売特許なんです。植民地化は悪であり、植民地化からの解放は善である、という単純かぎる善悪観は、ロシア・マルクス主義者が発明したものです。日本のマルクス主義者は、いまだにロシア・マルクス主義者がいったことを鵜のみにしているだけなんです。
― そうすると、当時の常識に照らしても、日本が韓国などを植民地化したこと、それ自体は絶対的に悪いことだとはいえないということになりませんか?
吉本 原則的にはそうです。植民地化には、いい面と悪い面の両面がありますから、だから、そこは小林よしのりも問題にしているのでしょうが、先程もいったように、要は日本政府や日本軍、日本の官憲、それから日本の民衆が、支配下の現地で何をしたかっていうことなんです。どんなにいいスローガンを掲げても、現地でのふるまいが悪ければ、やはり非難されても仕方がないんです。
(『同上』P29-P30 )
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
これに類することは、「丸山真男論」で触れられていたような、遠い記憶がある。
(註.2
マルクスは、1851年から1862年にかけて、アメリカの新聞、ニ ューヨーク・デイリー・トリビューン紙に、インドや中国などのアジアの植民地化された国などに関する論説を多く発表しているという。この吉本さんの言葉は、マルクスの「イギリスのインド支配」などを踏まえたものだろう。
④で、インタビュアーの「そうすると、当時の常識に照らしても、日本が韓国などを植民地化したこと、それ自体は絶対的に悪いことだとはいえないということになりませんか?」という問いに、吉本さんが原則的にはそうです。植民地化には、いい面と悪い面の両面がありますから」と述べていることに、敗戦後の世界を生きているわたしたちはたぶん異和感を持つような気がする。この吉本さんの考えの背景には、現在から見れば諸国家が出会う場合、歴史のある段階として植民地化というやり方を避けられなかったという状況認識があり、そんな追い込まれた状況から来る「当時の常識」があり、さらにこのマルクスの「イギリスのインド支配」などの捉え方の影響があるように思える。
この国の政治上層や知識層、そしてわたしたち生活者自身が、戦争-敗戦の負の遺産を未来に向けてきちんと受け止め放つことができなかったから、戦後七十数年も経っているのにわたしたちは今だに戦争-敗戦問題を引きずっている。だから、この項目を立てた。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 554 |
戦時下の日本 ② |
第一章小林よしのり『戦争論』批判するを |
インタビュー |
『私の「戦争論」』 |
ぶんか社 |
1999年9月30日 |
※聞き手 田近伸和
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 当時の一般的な国民感情 |
大東亜共栄圏の確立 |
知識層の振る舞い |
|
項目
1 |
①
―(中略) 小林よしのりは、『戦争論』の中で、インドのパル判事が述べたこんな言葉を引用しています。それは、「ハルノートのようなものを突きつけられたら、モナコやルクセンブルクでも戈(ほこ)をとってアメリカに立ち向かうだろう」という言葉です。ハルは当時のアメリカの国務長官です。一九四一年(昭和一六年)、日本に突きつけられたハルノートには、「シナ及びインドシナからの日本軍及び警察の全面撤退」「日独伊三国同盟の死文化」などが盛り込まれていました。また、当時、アメリカ、イギリス、中国、オランダの四カ国は、いわゆる"ABCD包囲網"を築き、日本への石油や鉄の供給を差し止めました。そのため、日本はやむをえず開戦に踏み切った。それで、小林よしのりは、「あれは自衛の戦争だった」と主張するわけですが、それは小林よしのりに限らず、いまだに根強くある主張ですね?
吉本 ええ。当時、僕は実感的にそうだと思っていましたし、今でもある程度はそうですね。今、アメリカはイラクに対して軍事攻撃を仕掛けたり、経済封鎖をしたりして、イラクを追い詰めていますが、あれと同じことを日本に対してやったんです。当時、アメリカは日本に対して、「満州国を撤廃しろ」「日本軍は中国大陸から全面撤退しろ」とも要求してきました。それは、日本が二〇年も三〇年もかけて積み上げてきた歴史的な歩みをすべて否定するものでした。"白紙に戻しちゃえ"という要求だったわけです。「そんな要求をのむことは、とうてい不可能だ」「承服できないよ」というのが、当時の一般的な国民感情だったと思います。僕もそうでした。だから、志賀直哉や谷崎潤一郎といった文学界の大長老をはじめ、みんな、戦争大肯定だったんです。当時の新聞を読めばわかりますが、新聞論調も朝日新聞をはじめ戦争大肯定でした。みんな、「戦争をやれ、やれ」だったんです。気分としては、「もう、やっちゃうしかない」と。日本中、そうでしたね(註.1)。
(『私の「戦争論」』P31-P32 吉本隆明 ぶんか社 1999年9月)
②
― 当時の日本国民の圧倒的多数は、インテリも含めて、「大東亜共栄圏の確立」という日本政府のプロパガンダをさして疑いもせず、そのまま信じたわけですか?
吉本 ええ。三木清のような進歩派も含めて、そうです。当時、僕を含め、多くの国民がそれをまっとうに信じたと思います。今にして思えば、そんなスローガンを掲げたって通用しない、世界の国々が本気でそれを信じると思うほうがどうかしているってことになっちゃうんですけどね。当時、日本はまだ近代文明にそれほど浴していない後進国にすぎませんでしたから、欧米の先進国にしてみれば、「何を寝ぼけたこといってやがる」と思ったに違いないんです。
今でいえば、韓国の統一教会がいっているのと同じようなことを、当時の日本はいっていたわけです。統一教会は、「イエス・キリストが再臨する東方の国とは韓国にほかならない」とか、「韓国の民族が新たに選民となる」とかいっています。現在の僕からすれば、「とんでもねえことをいうバカ野郎だ!」「なんという夜郎自大なバカ話だ!」ってことになっちゃうわけですよ。そんなバカ話が通用するはずはないんですけどね。
― 左翼も当時は戦争肯定だったのですか?
吉本 左翼だって、そうですよ。たとえば、三木清なんかにしても、「大東亜共栄圏の確立」といういい方はしないものの、「東亜共同体」という言葉を使って、戦争を肯定していました。「大東亜共栄圏の確立」とか、「東亜の解放」とかいうのは、理念としてはけっして悪いものじゃなかったですからね。ほとんどの左翼はそうしたスローガンにイチコロで、戦争賛成だったんです。
(『同上』P32-P34 )
※①と②は続いた文章です。
|
備
考
|
(備 考)
(註.1)
この「日本中、そうでしたね」という吉本さんの判断基準はどこから来ているのだろうか。新聞や周囲の見聞きするふんい気からだろうか。大衆の意識は、現在の錯綜とした状況とは違って、当時はもっと単相的に捉えることができたのかもしれない。
敗戦後に生まれ育ったわたしたちの視線には、戦争に至る過程や戦争の渦中はよくわかっていない。どうしても敗戦後の視線から戦争中を眺めてしまいがちになる。したがって、当時の世界をできるだけ実情に近く追究する場合は、小林よしのりのようにあれこれ資料を読んだりして勉強することになるだろうが、その場合大事なことは、この吉本さんの証言のようなその渦中にいた人々の肌感覚の言葉に触れることが必須だろうと思われる。また、当時の政治や知識上層と大衆意識とは分離した二層として、相互の関わり合いとして捉える必要があると思う。あくまでも、戦争へ傾斜する大衆意識を支えとして「大東亜共栄圏」などのイデオロギーを生み出し主導したのは、当時の政治や知識上層だからである。
「左翼」から「右翼」への転向は、吉本さんの「転向論」で追究されたが、要するに、自分の生活実感や生活世界から抜け出て、概念やイデオロギーの地平に入り込み、そこを滑っているから容易に相互変換される。このような転向は現在でも十分あり得る事態である。これは、次回の項目555 「戦争の本当のくぐり抜け方」にも関わる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 555 |
戦争の本当のくぐり抜け方 |
第一章小林よしのり『戦争論』批判するを |
インタビュー |
『私の「戦争論」』 |
ぶんか社 |
1999年9月30日 |
※聞き手 田近伸和
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 簡単に変わっちゃう |
一日の生活のうち、人間は大部分は、そんな小さな喜びや悩みの中で生きている |
そういう観点をちゃんと持つこと |
|
項目
1 |
①
―そうすると、ウソではない「戦争の本当のくぐり抜け方」とはどうなりますか?
吉本 僕は戦争中は天皇制軍国主義にイカれていて、戦争を肯定していた。共産党であれ誰であれ、「お前そうだったろう」といわれれば、「その通りだった」と僕は認めます。以前、僕は村松剛に「あの野郎、戦争中は天皇制軍国主義にイカれていたって自分で書いていたくせに、戦後は最左翼のようなことをいっている」って非難されたことがあるんです。そのとき、僕は「その通りのところがあるなあ」って思いました。共産党も日本のインテリも、そして大衆もそうですが、時代が変わると左翼が右翼になり、右翼が左翼になる。ボタンを付け替えるように、簡単に変わっちゃう。村松剛がいったように、自分にもそういう面がある、あったんです。なぜ、そうなるのか?そこが、僕が引っ掛かったところであり、戦後、自分のことも含めて、考えてきたことの一つなんです。
②
吉本 たとえば、石川啄木という文学者がいますね。左翼系の文学者たちは啄木を非常に高く評価するわけです。啄木の『時代閉塞の現状』のような評論や口語の短歌なんかを、「プロレタリア文学の先駆」といういい方で。でも、そういう紋切り型の評価はダメなんですよ。なぜダメかというと、そういう評価をしちゃうと、夏目漱石でも森鴎外でもいいですが、その小説でるる(念のための引用者註.「縷々」)描かれている人間関係の錯綜とか悩みとか、一見、小さなことのように見える情緒の大切さを見据える視点が、スッポリ抜け落ちちゃうからなんです。
漱石のような大文豪が、なぜ死にもの狂いになって三角関係のことを書くのか?三角関係なんて、つまんないといえば、つまんないですよ。三角関係が、なんでそんなに重大なのよってことになっちゃうわけです。でも、それは市民社会で生活している人たちにとっては、やっぱり、重大なことなんです。細君のほかに好きな女性ができちゃって、にっちもさっちもいかなくなっちゃった。どん詰まり状態になっちゃった。「これ、どうするんだ?」って。それは、やっぱり、人間の生死をかけた問題なんです。
ところが、左翼も右翼も市民主義者も、その構造すら似ていて、一見、小さなことのように見える情緒の大切さを見据える視点を、とかく、スッポリ抜け落としちゃうんです。見掛け上、"大問題"のように見える問題のときほど、そうです。でも、そこがスッポリ抜け落ちちゃった理念というものは、時代が変わると、左から右へ、右から左へと必ず変わっちゃうんです。
だから、そこを尊重する。つまり、市民社会における人間関係の錯綜とか、葛藤とか、男女間の悩みとか、失恋して悩んだとか、そういう人間のあり方、まあ人間の弱さといいましょうか
――そこには生産的なことは何もなく、そこにあるのは、むしろマイナスのことだったり、退廃的なことだったりするわけですが、そういう市民社会のスッタモンダを否定しちゃダメなんだ、そういうところに人間らしさを認めることができる観点を持たなければダメなんだ、ということなんです。
なぜなら、一日の生活のうち、つまり二四時間の生活のうち、人間は大部分は、そんな小さな喜びや悩みの中で生きているからです。そこが、戦後、僕が反省した点なんです。日常生活のうち、人間は大部分は、そういう小さな喜びや悩みの中で生きているのだということを忘れずに、その上で、戦争・平和・政治制度・社会といった"大問題"を考えるべきである。――「戦争の本当のくぐり抜け方とは何か?」といえば、反省を踏まえて、そういう観点をちゃんと持つことである、ということになりますね。
(『私の「戦争論」』P46-P48 吉本隆明 ぶんか社 1999年9月)
※①と②は続いた文章です。
|
備
考
|
(備 考)
この考え方は、吉本さんの若い頃の「転向論」(『吉本隆明全集5』、初出1958年12月1日 『芸術的抵抗と挫折』所収)から一貫していると思われる。知識人や政治集団の転向の必然性は、その大衆的契機、生活世界の有り様を繰り込めなかったということによる、と。この課題は、太古から連綿として続いている、おそらく吉本さんの言う「永遠の課題」(永続的な課題)であり、現在でも知識層や政治集団(政党含む)として依然として解決すべき課題であり続けている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 563 |
庶民感覚 |
「世界金融の現場に訊く」 |
|
『吉本隆明資料集178』 |
猫々堂 |
2018年9月10日 |
※投資銀行社員 村山信和・聞き手 吉本隆明 (2000年12月15日)
※『吉本隆明が語る戦後55年』第3巻2001年3月5日発行
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 金融問題の素人である一般の人たちは |
僕の同級生でプラスチック加工の小さな会社を経営しているのがいて |
「やっと家のローンを返したよ」 |
|
項目
1 |
①
吉本 僕はいつでも疑問に思っていることなのですが、たとえば僕らが家を建てるときに、銀行に金を借りに行きますね。そうすると、だいたい預金の倍ぐらいまでは貸してくれました。家を建てたら、こんどは月々いくらずつ返済してくれというシステムになっているんですね。で、別に銀行は脅迫はしないけど、否応なしに返済させることだけは間違いなくやりますね、仮にその人が返せなくなっても、家の権利書なんかを担保にとってあり、損をしないようにちゃんとできてる。つまり金融問題の素人である一般の人たちは、どうしてもお金が必要な場合はそういうやり方しかできないように思います。
でも、僕の同級生でプラスチック加工の小さな会社を経営しているのがいて、そいつの話を聞いてると「俺は借金が一億円ぐらいあるんだよ」とわりに平気な顔をしていってるんです。そこがよく判らないんですが、つまり僕に一億円もの借金があったら「俺はもう一生ダメだ」と思って、精神的にまいっちゃうわけですね。でもそいつは、あんまりそういう落ち込み方はしないで、「いつか返済は終わるから平気だよ」という感じです。これはいかなる理由によるわけですか?
村山 わかりやすく説明しますと、その社長さんは資産があるわけじゃなくて、キャッシュフローがあるんです。キャッシュフローというのは、ご自身が稼がれた税引き後のお金と、お金を調達できる能力があるということです。キャッシュフローがあるという意味では、アメリカという国は同じ状況にあります。たとえば、中国とシンガポールが商取引をすると、支払い通貨はドルです。アメリカが関係していない取引なのに、ドルが流通している。世界の決済通貨になっているから、ドルの価値が上がろうが下がろうが、自分たちにお金を返す気があろうがなかろうが、ドルを刷りつづければキャッシュフローはじゃんじゃんあるんですよ。
吉本 うん、うん、なるほど。
村山 その社長さんは、プラスチック加工のビジネスとしてお金を使って、どんどん金利をとってくれるから、銀行にしてみれば儲け口です。お金を調達できてキャッシュフローがあるという違いなんですよ。
吉本 それはいいことを聞いたというか、よくわかります。いくら考えても、これは僕には全然できないなあという感じでしたからね。どうしてやつはそう平気だという顔をしていられるのかって。僕らなんか「やっと家のローンを返したよ」というのが実情ですけどね。それも脅迫はされなかったけど、必ず払わざるを得ないようにできていて、やっと返済が終わってホッとするなんて、いかにも情け無い感じがしてたんですけど。
(「世界金融の現場に訊く」P40-P41『吉本隆明資料集178』猫々堂)
|
備
考
|
(備 考)
吉本さんの庶民的な感覚は、身近な交流をした人々からしばしば指摘されることでもあるが、ここでの吉本さんの質問と抱いていたイメージにそれがうかがえる。吉本さんなら、上に説明されているようなおそらく金融の初歩的なことについてはわかっているのではないかと思いきや、わかっていなくて疑問に思っていたということ。たぶん、吉本さんは日常の生活の具体性に関しては、普通の生活者たちと同様に振る舞っていたということだろうと思う。
しかし、現在のような知識・情報過多の社会では、仕事で金融関係に努めている人々に限らず、株や投資などに手を出すような人々は、上に説明されているような知識や理解が当然のこととしてあるのかもしれない。
わたしも若い頃に家を建てたことがあるが、吉本さんと同様の感覚を持った。ローンの借金は、高い利子のことを考えてできるだけ早く返してしまいたいものだと思った覚えがある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 570 |
思想家の意味 |
講演A042「竹内好の生涯」 |
講演 |
吉本隆明の183講演 |
ほぼ日刊イトイ新聞 |
|
※講演テキストと講演を文章化したものとの二つから。
講演A042「竹内好の生涯」の講演日は、1977.10.1。吉本隆明の183講演。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| あとの世代と脈絡がつくということ |
生涯にわたって考え続けなければ脈絡はつかない |
思想的な脈絡、歴史が何を物語るというような脈絡はそういう営為によってしかできない |
|
項目
1 |
①
ただ言うことは、思想なんていうもの、あるいは1人の思想家は、いずれにせよ生涯においてなしうることは大したことがなくてたかがしれているわけですけれども、何がために1人の思想家が存在し続けるかと考えていきますと、自分が労苦して考えに考え抜いたということが、後の世代の人たちはひとりでに身につけてしまっているとしか思えない。自然に身につけちゃっているとしか思えない。そういう比較対象ができるということが、ひとりの思想家というものが生涯にわたって存在し続けることの意味だと思います。
ひとりの人間が自分の青年のときにつかんだある考え方、ある行いというもの、その考え方というものを生涯にわたってなんらかの意味で持続的にひねったり部分的に捨ててみたりしながら、死ぬまでこねまわしていかないかぎりは、自分のあとの世代との対比はつかないということなんです。後の世代とは脈絡がつかないということなんです。あとの世代と脈絡がつくということはたいへんなことなんです。黙っていたら脈絡がつくと考えたらそれは大間違えでして、黙っていて脈絡がつくのは、自分が生理的に生んだ子どもくらいのものです。少しでも自分以外、自分の子ども、親以外のものと思考の脈絡、もっと突き詰めていえば思想の脈絡をつけるためには、人が青年期につかんだある契機を生涯にわたって考え続けなければ脈絡はつかないということなんです。
それを脈絡をつけるためにはどうしてもある世代のひとりの思想家は、青年期につかんだものを変えたって曲げたってどうだってかまわないけれども、つかんだもの自体を持続的に棺桶まで持ち越さなければいけない。その課題を何らかの意味あいで放棄するならば、自分のあとの世代との脈絡はまったく途絶えるということです。時代から時代へと脈絡をつけるということは、それくらい難しいことです。これはどこかで捨ててしまったら駄目です。捨てる理由も根拠も契機もあるでしょうけれども、しかし捨ててしまったら脈絡がつかないということは疑いがないんです。
それでも悲しいことに、ある時代の思想家、あるいは思想家でなくても、脈絡をつけるために一生懸命考えてきた、考え抜いたことは、やっと後の世代にごく自然に受け入れられるとなっているだけなんです。何らかの脈絡がつけえたらそれは大した思想だというふうに言うことができるほど難しいことだということが言えます。
そういうことを放棄するならば、それは自分の子どもと肉体的な脈絡がつけられるということくらいしか脈絡はつけられないと思います。それでもけっこうですし、それぐらいしかできそうにないですけれども、原則的にいえば思想的な脈絡、歴史が何を物語るというような脈絡はそういう営為によってしかできないと言えると思います。
そういう意味あいで、ひとりのある世代の思想家が息ある時代につかまえられた自分の契機というものをある表現にし、死ぬまでそれを持続したということの意味がもしあるとすればそういうところにしかないと思います。だから竹内さんの思想が本格的に検討されるのはこれからでありましょうし、そこから何かが後の世代の人が苦労しなくてもわかる、共感するところ、あるいはもう既に実現したところがあったとすれば、それは竹内さんの思想の功績に属するわけです。また強いていえばひとりの思想家がある時代に存在しつづけたということの意味につながっていくものだと考えることができると思います。
そういう竹内さんの思想の本格的な検討と、それがどういうふうに皆さんをとらえるか、あるいは皆さんが捉えられるかという問題は今後に属するわけですけれども、きっとそういうことがこれからなされるに違いないし、なされるに値する思想家だったということができると思います。これでいちおう終わらせていただきます。
(吉本隆明の183講演、ほぼ日、A042「竹内好の生涯」の「講演のテキスト」より)
②
ひとりの思想家が、いずれにしろ、生涯においてなしることは大したことはありません。しかし、何がためにひとりの思想家は、ある時代に存在し続けるかとかんがえてみますと、いわば、じぶんが一刻もそのことを頭から去らないほど労苦してかんがえにかんがえぬいてやっと掴まえたものが、後の世代の人たちにとって、何となく独りでに、自然に身につけてる、その地点に出遭うためです。それが、ひとりの思想家が生涯にわたって存在し続けることの意味だとおもいます。
竹内好さんの思想は、そういう徒労に値するものとして、今後、本格的に検討されることを信じて疑いません。
(①の講演部分に対応する部分、「竹内好の生涯」P175-P176、『超西欧的まで』弓立社)
|
備
考
|
(備 考)
①は、他の講演の「講演のテキスト」をいくつか読んできた印象からすれば、おそらく講演で語られたものに忠実な「講演のテキスト」(吉本隆明の183講演、ほぼ日、A042「竹内好の生涯」)だろう。一方、②はずいぶん切り詰められ凝縮された表現になっている。たぶん、吉本さん自身の手が加わっているはずである。本のページ数を切り詰めるなどの関係あったのか、あるいは吉本さん自身のもっとすっきりさせたいという欲求によるのかわからない。吉本さんには、講演を文章化したものも多いから、ひとつの参考として挙げておく。
しかし、この②だけから①のていねいな把握までたどるのは難しい気がする。
大宇宙から見た人類と同じく、人間界上空から見たひとりの人間、それは端から見た働きアリの徒労のようにも感じられるかもしれないが、人間界内部から眺めれば、吉本さんが書き留めた思想家の存在する意味が人間界の無意識的な主流に浮上してくるだろう。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 572 |
食・料理・味覚 |
「好きときらいと」「わたしが料理を作るとき」他 |
論文 |
『食べものの話』 |
丸山学芸図書 |
1997.12.15 |
「わたしが料理を作るとき」の初出は、1973年。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 幼児のときから思春期に入るまでの食習慣の味記憶 |
(両親との心的関係から)好ききらいがきまってしまう気がする |
〈料理は時間である〉という鉄則 |
|
項目
1 |
①
食べものの話をするのなら、好きなもの、きらいなものから本音を出さないとはじませない気がする。素材ものからいうと、永遠の好きは「じゃがいも」と「豆腐」だ。
素材の好ききらいも、料理の好ききらいも、幼児のときから思春期に入るまでの食習慣の味記憶にたくさんかかわりがあるような気がしている。
(「好きときらいと」P7、P9 『食べものの話』所収)
食べものの好き・きらいははっきりしていて、きらいなものは多いほうだ。たとえば煮魚はきらいだ。マヨネーズはきらいだ。もっといえば醤油のような色をした昔ながらのソースをのぞいて、洋風に作られた多様なソースはみなきらいだ。また、しゃぶしゃぶなどを酢をきかせた醤油で食べる風習もきらいだ。
このきらいは共通点でいうと、本体がびちゃびちゃとした醤油やソースに浸っていたり、酢をきかせたりしているものがきらいということになる・そのくせお鮨はまず好きだといえる。
こんなことにあまり根拠のある意味がないから、無理にこじつけてみれば、ほんらいは両親たちが愛好した食べものにたいする愛憎から幼ないときに好ききらいがきまってしまう気がする。大人になってその愛憎が薄れてきて、懐かしい味にかわったり、じぶんの好ききらいを超えて、食べものにたいする趣好をじぶんで拡大しようとつとめたりする。
わたしは、はじめにきらいなものをすこし並べてみたが、ほんとをいうと挙げたものはどれもまったく食べられないほどきらいではない。本気をだせば涼しい顔をして食べることができるものばかりだ。ふだんはできるだけ敬遠しているといった程度のきらいにしかすぎない。
(「きらい・まずい」P19-P20『同上』)
②
女性が、じぶんの創造した料理の味に、家族のメンバーを馴致させることができたら、その女性は、たぶん、家族を支配(リード)できるにちがいない。支配という言葉が穏当でなければ家族のメンバーから慕われ、死んだあとでも、懐かしがられるにちがいないといいかえてもよい。
それ以外の方法では、どんな才色兼備でも、高給取りでも、社会的地位が高くても、優しい性格の持ち主でも、女性が家族から慕われることは、まず、絶対にないと思ってよい。
(「わたしが料理を作るとき」初出は1973年、P86-P87『同上』)
③
ようするに、料理を繰り返しの条件に叶うものに限定していえば、〈料理は時間である〉という鉄則が成り立つように思われる。時間がかかる料理、それはどんなに美味しくても〈駄目〉である。ままごと料理、それも〈駄目〉である。見てくれの良い料理、それも〈駄目〉である。なぜなら、日常の繰り返しの条件に耐え得ないからである。料理の一回性、刹那性の見事さ、美味さ、それは専門の料理人の世界であり、かれらにまかせて、客のほうにまわればよいとおもう。
(「わたしが料理を作るとき」P90-P91『同上』)
|
備
考
|
(備 考)
おそらく好き好んでではなく食事当番をこなしてきた吉本さんの、具体的な体験を背景とした料理に対する考え方を取り出してみた。
②の女性の部分は、えっ?と思ったが、柳田国男が明らかにした家族の中の「主婦」の位置を思い浮かべれば、そうだろうなと言う気がする。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 577 |
自民党が大きく負ければいいのだ |
(「資本主義の新たな段階と政権交代以後の日本の選択」他 |
インタビュー |
『吉本隆明資料集 177』 |
猫々堂 |
2018.7.25 |
聞き手 津森和治 (2009年12月4日) 『別冊ニッチ』第2号 2010年6月10日発行
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| それなら僕も本気で答えます |
日本の現状のダメさ加減 |
まだ何かの可能性がある |
でも逆に、民主党政権がダメになったら、これから一〇年、一五年、いいことは何も起こらないでしょう。 |
項目
1 |
①
津森 このたび政権交代をして民主党が政権をとったということですけれども、吉本さんが今年(二〇〇九年)の八月に雑誌の「現代思想」のインタビューに答えられて、「選挙の直前なので、あまり言いたくはないけれども」とおっしゃって、今回の選挙は、「自民党が大きく負ければいいのだ」と、「自分は自民党の支持でも民主党の支持でもないけれども、今回の選挙は、自民党が負ければいいのだ、ということだけがいいたいことです」とおっしゃっていましたが、それが気になっていました。(註.1)
(註.1)
今度の選挙では自民党が負ければ負けるほどいいと思っています。民主党が勝てばいいというのではありません。そうではなくて、自民党が負ければいいのです。それが大衆の望んでいることだからです。それには理由があるのですが、今はやめておきましょう。
選挙の行く末と、それからの動向について批判的であれそうでなかろうと、いろいろと言いたいことがある人がいるのかもしれません。それはそういう人が知識人だからです。知識人は大衆を指導するようなことを言いたがります。
けれども彼らの望むようには大衆は決して動かない。選挙というものは、そしてその結果は、大衆が決めるものであつて、知識人はあれこれ言ってもむだなことです。それには誰も付いてこないでしょう。大衆はそれとは無関係です。しかも知識人も一票、大衆も一票ですよ。実際にはどうすることもできないでしょう。
自民党が負ければ負けるほどいいと思っていますが、私はしかし、選挙の結果には何の興味もありません。選挙などというものとはかけ離れたところで考えてきたからです。民主党が何を言おうが、何の関係もない。共産党とか社民党が何を言おうが、どうなろうが、それも関係ありません。だって、こちらは自立の思想でずっとやってきたのですから。そういう選挙の結果とか政党の動向とか、彼らが言っていることとは関わりなく、ずっと自立的思考を目指してやってきたことへの誇りがありますよ。そのことを言っておきたい。 (2009年8月17日)
(「現代思想」 インタビュー記事2009年10月号 )
(「資本主義の新たな段階と政権交代以後の日本の選択」P51-P52 『吉本隆明資料集 177』猫々堂 )
聞き手 津森和治 (2009年12月4日) 『別冊ニッチ』第2号 2010年6月10日発行
②
吉本 はじめにおっしゃったことは選挙の真近でしたけれども、編集者の方からこの問題も含めてどういうふうに考えているのかを聞かれました。それで普通の雑誌社的な質問でしたら答えたくなかったのですが、ですから「その質問は本気で聞いているわけですか」と確かお聞きしたと思います。選挙はもう真近にあるわけですから、選挙前はどうか選挙後はどうか、選挙後にこうなったらどう思うか、ということも含めてそれは本気でお聞きになられるのですか、本気かどうかも曖昧で区別はできないのですけれども、その編集者の方は、「本気でお聞きしています」というのです。僕が無理にそう言わせてしまったということなのかもしれませんが、「それなら僕も本気で答えます」というふうに言いました。
「選挙で、もし民主党が自民党に比べて圧倒的にどうすることもできないほど選挙の結果、勝ったら、日本の現状のダメさ加減というのは少し救いが残っているっていうふうに思います」と答えたのです。そしたら、偶然と同じ本当に圧倒的に勝ってしまったのですね。つまり、僕の常識的な考えでは、拮抗した票で民主党の方が少し落ちるくらいではないかとなというのが、僕の常識的な考えですね。普通におしゃべりしたり、会話したりするときにいう口調で、「だいたい接戦なんじゃないかね」と、「やや民主党が負けるのじゃないかね」というふうに常識的に考えていたのですけれど、編集者の方が本気で聞いている、と言うから、それなら本気で答えましょうと言って、それで民主党が圧倒的に勝利したとすれば、まだ何かの可能性がある、というふうに考えてます、と答えました。その前の僕の常識は、両者拮抗でやや民主党が少ないだろうというものですけれども、願望混じりで言いますと、そうなったらまだ可能性がある、というふうに判断するという言い方をしたと思います。
(「同上」P54-P55 )
③
――吉本さんは、最近のご著書で現在を「第二の敗戦機」と位置づけられ、貧困だけでなく、精神の問題も大きいと発言されています。
まずはじめに、いまという時代をどうとらえていらっしゃるか、そして、希望はあるのかということをお聞きしたいと思います。
吉本 戦争直後、占領下での小作農から自作農への転換を、戦後最初の大きな変革と考えると、現在は、戦後三番目か四番目の静かな変革期と考えています。
具体的には、いまの、民主党政権が、四年の間に自分たちの綱領を、ゆるやかにでも「静かなる革命」を実現していければ、そこから希望が出てくるかもしれません。でも逆に、民主党政権がダメになったら、これから一〇年、一五年、いいことは何も起こらないでしょう。
(「八十五歳の現在」P69 『吉本隆明資料集 177』猫々堂 )
聞き手 北村肇
|
| 備考 |
(備 考)
「真近」は、「間近」がただしいとあるが、調べたら次のような「真近」の用例が挙げてあった。
参木の常緑銀行では、その日の閉鎖時間が真近(まぢか)くなると不穏な予言が蔓延した。
(『上海』 横光利一)
①の (註.1)は特に、単独者としての吉本さんの本領が出ているインタビューである。
昔吉本さんが、どこかで、表現の公表においてなかなか本当のことが言えない、というようなことを語られていて、ふうん、そういうことがあるのかなと思ったものだが、その後具体的に編集部門からの語句の修正要求などがあったりするなどどこかで語られていた。②の常識的な答え方や本気の考えなど、振り返ってみれば、わたしたちも日常において使い分けていることである。軽い気持ちで聞かれても誰も本気の重たい考えを語る気にはなれないだろう。
③の「でも逆に、民主党政権がダメになったら、これから一〇年、一五年、いいことは何も起こらないでしょう。」、今まさにこの悪夢の渦中にわたしたちはいる。
民主党政権の崩壊後からわたしは選挙に行くようになった。つまり、政党などの動向にほとんど関心を持っていなかった。だから、民主党政権になって、小沢一郎が百数十人の民主党議員を引き連れて中国を訪問したときには何だこれはと驚いた。(この件は、その後吉本さんは評価すべきこととして触れていた。)また、小沢一郎が幹事長としてだったか、今での自民党的な地方と中央とのつながり(陳情の形式など)をばさばさきっているのには驚いたことがある。そこまでしなくてはならないのかと思ったが、悪夢の現状を見ると、それ以上にやらなくてはならなかったのだろう。つまり、自民党的な村政治の壊滅として。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 609 |
相互扶助精神の違い |
「資本主義の新たな経済現象と価値論の射程」 |
インタビュー |
『別冊ニッチ』第3号 |
『吉本隆明資料集 181』 |
猫々堂 |
2018.12.30 |
(「資本主義の新たな経済現象と価値論の射程 ―贈与・被贈与、そして相互扶助をめぐって」
※ 聞き手 津森和治 (2010年6月1日) 『別冊ニッチ』第3号 2011年7月10日発行
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 公的一個人と公的一個人の関係 |
日本式 |
|
|
項目
1 |
①
吉本 あまり大きな理念は日本には向かないという考え方が僕にはありますが、相互扶助ということは戦争中に体験も実感もありますから、相互扶助というのなら、僕にもできないことはないですね。
相互扶助というのはそれぞれの民族でやや違うのです。言葉の感じ方や解釈の仕方が違うのです。日本の場合には、お前タバコをもっているか、一本あったらちょうだい、というのが僕らの場合ですね。
ヨーロッパではそういうことはないと思いますね。相互扶助というのは、公的一個人と公的一個人の関係で相互を扶助する要素があるということを意味するものですから、僕らのような日本式とは違うのです。
僕は戦争中に実感として相互に助け合うということをやっていましたから分かりやすいのですが、死活の問題になってしまうと日本人はおっかない、というふうになってしまうのですね。だけど、僕は相互扶助くらいならできる、可能だと考えていますね。ヨーロッパではそんな曖昧なことではないですから、一〇〇円借りる、返済はいつ返す、とはっきり言って借りる、ということになるのでしょうけれども、日本で同じようにやったらかえって馬鹿みたいに思えちゃうということがありますね。ですから、相互扶助という考え方くらいに相互の互恵関係として考えるのが日本人的と言えば日本人的ですから一番できやすい考え方ですね。これは日本だからできるし、日本人ならできそうなやり方ですからもっと理想的なやり方は必ずあると思います。
(「資本主義の新たな経済現象と価値論の射程 ―贈与・被贈与、そして相互扶助をめぐって」P34-P35 『吉本隆明資料集 181』猫々堂 )
|
備
考 |
(備 考)
このヨーロッパでの相互扶助の具体性は、海外に出たことのなかった吉本さんはどこから仕入れたのだろうか。外国人からか海外に行った日本人から聞いたと考えるほかない。そういえば対談かインタビューの中で、何度か知り合いのだったかフランス人の女性(学者か学者の卵か)から日本のことを尋ねられたことがあると語られていた。このような人とのやりとりからの入手があったのかもしれない。
風俗習慣は、種族や民族などの違いによってこのように大きく異なることがあるものだろう。したがって、相互扶助ひとつとっても、その概念の輪郭や捉え方が違ってきて、例えば多国籍の人々から成る企業などでグローバルなものとして相互扶助を打ち出そうとしても、微妙に難しいものがあるのかもしれない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 613 |
『初期ノート』 |
「過去についての自註」 |
論文 |
『背景の記憶』 |
平凡社 |
1999.11.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| すべての思想体験の経路は、包括され、止揚されるべきものとして存在する。 |
現在のわたしの思想的原型 |
|
|
項目
1 |
①
だが、未成熟なじぶんの時代を、あばき出された本人にとって、何が感懐となるだろうか?
羞恥、自己嫌悪、といったものは、過去がすべて羞恥、自己嫌悪の別名にしかすぎないとかんがえているものにとっては、いまさら驚くべきことではない。謙虚も傲慢も、あるばあいには、メダルの裏表のように、ひとつであるとかんがえているものには、いま、ある愛惜の努力によって、必然的にじぶんの未成熟な過去が公刊されるという、傲慢さとまちがわれやすい事態に出遇っても、いうほどのこともなければ、管々しい弁明をも必要としないだろう。
あるがままの過去を、ないように見せかける必要から、わたしは遙かに遠ざかっているし、ことさら体裁をとりつくろわねばならぬ根拠も、もっていない。これは、わたしが虚偽から遠いからではなく、わたしの思想が、「自然」にちかい部分を斬りすてず歩んできたし、いまも歩んでいるからである。
すべての思想体験の経路は、どんなつまらぬものでも、捨てるものでも秘匿すべきでもない。それは包括され、止揚されるべきものとして存在する。もし、わたしに思想の方法があるとすれば、世のイデオローグたちが、体験的思想を捨てたり、秘匿したりすることで現実的「立場」を得たと信じているのにたいし、わたしが、それを捨てずに包括してきた、ということのなかにある。
(「過去についての自註」P14-P15『背景の記憶』)
②
一行の詩もかけない時期に、雑多な書物を読んでは、独語をノートにかきつけた。それが、わたしの『初期ノート』の主要部を形作っている。もし、わたし以外の人物が、このノートを精読されるならば、現在のわたしの思想的原型は、すべて凝縮された形でこの中に籠められていることを知るはずである。緊張度は可成り高く、ノートのこの部分を公刊することについては、わたしは、水準についてすこしもひけ目やためらいを感じていない。
(「同上」P33)
③
わたしは、いわゆる、はやすぎた自伝を素描しようと試みたのだろうか?
そうではない。ここ(『初期ノート』)に収録された断簡には、わたしの所有している思想の最良の部分が存在するとともに、その最良の部分にいたるまでの、少年期の手習いの基本が、現在の資料発掘者(川上春雄)によって可能なかぎりの努力で集められている。それが、思わずしてわたしを回想に誘うだけの愛着を感じさせただけである。
ひとびとは、こういう断簡、手習いの類いをあつめて公刊するという一種の愚挙に、傲倨(ごうきょ)さをみないで欲しい。むしろ、この場合にかぎってわたしは、いつもより謙虚であり、図々しくなく振舞っている。ひとつの時代を、表がわだけとって裏がわをすてることもなく、裏がわをとって表がわをすてることもなく、「類」としてのわたしと、「個」としてのわたしが、からみあってはなれない「存在」としての立場から、かんがえぬき趣向してきた軌跡の原型がここには保存されている。どんな改竄も加えてはいないし、すべては、現在の資料発掘者(川上春雄)の個人的な努力に負っており、いささか無責任ともとられそうな発言を敢てすれば、わたし自身が記憶から忘れさっていたものが、過去の亡霊のように目のまえにつきつけられたとき、驚き、赤面し、あるいは懐かしがる、といった様々な感懐を催したこともあった。戦争と戦後の混乱を、少年期から青年期にかけて走行し、彷徨したひとりの「個」を観察しようとする興味をもつものにも、かけ値のない素材を提供しているはずである。
(「同上」P36-P38)
|
| 備考 |
(備 考)
『初期ノート』初版発行は、 1964年6月30日。私の持っている『初期ノート増補版』、その初版発行は 1970年8月1日である。
巻末の「編集覚書」(川上春雄)によると、
Ⅰ 『初期ノート』は、吉本隆明の少年期から、大略、一九五〇年(昭和二十五年)まで(『固有時との対話』以前)の、初期作品を、すべて原本のまま収録した。
Ⅳ 「過去についての自註」は、編集が終了したのちに執筆された、著者の唯一の自伝的な文章である。
また、吉本さん自身によると、
研究生時代の後期は、詩集『固有時との対話』に、組合運動時代は、詩集『転位のための十篇』に対応している。研究生時代の前期がこの『初期ノート』や、時禱(じとう)詩集」に対応しているのである。(「過去についての自註」P34-P35『背景の記憶』)
『初期ノート』は、若い頃一度読み通した。もう何が書いてあったかは覚えていない。近年、依田圭一郎という方のブログ「『初期ノート』解説」(https://syoki-note.hatenadiary.org/)に出会った。定期的にアップされる文章とともに『初期ノート』からの引用とそのていねいな読み解きとを毎回楽しみにしていた。その依田さんが、平成29年6月18日に64歳の若さで亡くなられたという。まったく実際の交流はなかったけれど、残念な思いである。書き残された文章群は、上のブログに残されていて読むことができる。
①の「羞恥、自己嫌悪、といったものは、過去がすべて羞恥、自己嫌悪の別名にしかすぎないとかんがえているものにとっては、いまさら驚くべきことではない。」という吉本さんの言葉で、思い出す詩句がある。わたしの特に好きな詩の一つである。
まずかつたなあ
それはまずかつたなあ
来歴はいつもそう囁き
その都度
ああ まずかつたよ
ちようど今日のように後悔には
ちよつぴり沁みている紺青の布切れと
数すくない言葉を当てがい
ぼろぼろになるまでは
まだやれる
まだまだやれるよう
言葉からしたたる雫にまじつて
幽かなささめことの風が
きこえるかぎりは
(〈五月の空に〉第二連、『吉本隆明新詩集』試行出版部 1975年11月)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 622 |
思想者 |
第十七章『ハイ・イメージ論』 |
インタビュー |
『吉本隆明が最後に遺した三十万字 上巻 「吉本隆明、自著を語る」』 |
ロッキング・オン |
2012.12.24 |
関連事項 項目ID 422「思想家の条件」
関連事項 項目ID 570「思想家の意味」
第十七章『ハイ・イメージ論』は、SIGHT 第四十一号 2009年11月号に掲載。
インタビュアー 渋谷陽一
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| その頃、僕は上野や銀座のデパートにほぼ毎日出かけていた |
そういう一種の臨場感が僕には大きく作用して、自分の考え方を作っているように思いますね |
先進的な文明文化を持っている国では、産業でいえば消費産業が主体になってきていますから、国と国が戦争してどうこうしようという考え方はだんだん少なくなっています。 |
|
項目
1 |
①
― ・・・略・・・このように、吉本さんは、従来の西欧思想の手続きからは全く違うアプローチをするという、強い意志を見事に貫かれ、結実されていっているわけですが、こうした『ハイ・イメージ論』の方法論は、当初から強固にあったものなんですか。
吉本 明瞭な形であったわけではないですが、そういうことを考えないとダメじやないかなとは思っていましたね。というのはその頃、僕は上野や銀座のデパートにほぼ毎日出かけていたんですが、いろんな消費産業のあり方を見ているうちに、こうした問題は、うかうかと片付けられない問題になってくるな、という感じが形を持ってきたんです。というのは、僕は戦争を経験していますし、焼け焦げの都市が徐々に再建していく過程を見ていますから、何かといえば戦争で解決するようなやり方がどうしようもなくダメなんだとわかっています。では、どういう組織になったら理想的なのかということを、消費的な産業が全産業の半分に近づいていった時には、必ず考えざるを得ない。そういうふうに考えるようになったんですね。
― 今の、デパートのお話を伺って、やはり吉本さんは詩人だと感じました。臨死体験をきいたり、ランドサットやバーチャルリアリティの映像を観たりした時に、「要するに、世界というのは形だな」ということが、突然吉本さんの中でイメージとして浮かぶんですよね。詩を書くようにして、思想的な啓示が降りてくる。
吉本 そういうふうにも言えるかもしれませんね。ただ、自分の考え方としては、初めからそんなにまじめに考えているのではなくて、デパートでどんな新しい商品が出てきたのかと各階を見て回ったら、とにかく面白かったんですよ。そういう一種の臨場感が僕には大きく作用して、自分の考え方を作っているように思いますね。英語でいえば thinker っていう、「思想家」っていう言葉があるんですが、僕は思想家という言葉が好きじゃないから、 thinker に該当する言葉として、若い頃に「思想者」という言葉を発明したんです。思想家というと、公のことに言葉や考えを費やして、いろんな問題と知識を結びつけたりしないといけない。そういう人もいますが、僕はあんまりそうしたことは考えたことがないから、思想家って自分で言うのも、人に言われるのも嫌ですね(笑)。でも思想者っていえば、そんなに恥ずかしくない。遊び半分でデパートを見て歩いたり、どういう衣装が流行ってるかというのを見ているうちに、消費産業、第三次産業が全産業の半分に近づいたら、たとえば都市の問題や、住まいの問題などが必ず表出すると感じました。それも、西欧とは違った形で出てくるかもしれません。思想者として、そういうことをまじめな課題として考えないといけないと思ったんです。
②
― そうですね。だから『マス・イメージ論』で、サブカルチャーに関するいろいろな評論を展開された。そこで吉本さんが非常に強く主張なさっているのは、今現在、この時代が何であるかっていう、時代の断片を優れて表現している作品と向き合わなければ、永続性や永遠性なんか探せるわけがないということですね。現在があるからこそ、永遠があるわけですから、たとえ消費されていくものであろうと何であろうと、今という時代において一番ヴィヴィッドな表現みたいなものを見ていこうということですよね。それが『ハイ・イメージ論』になると、一気に視点が広がっていった。最初にご説明いただいたことですが、この作品は、芸術批評というものが、基本的な言語芸術からもっともっと対象を広げていくことが可能ではなかろうかという試みです。吉本さんにとってデパートというのは、まさに消費という形で現在が象徴的に展開されている、表現の現場だったんですね。さきほど、臨場感という言葉を吉本さんはお使いになりましたが、そこには臨場感溢れるシーンがある。文学シーンがあり、音楽シーンがあり、絵画シーンがあるのと同じように、まさに時代のシーンが存在しているんですね。そして、そこにいて非常に面白がっている吉本さんだからこそ、この『ハイ・イメージ論』において、そうしたシーンから永続性を見通せる視点を手に入れることができたんだと思います。この作品で作られた、あらゆる事象に対する批評的な姿勢、視点というのは、今現在の吉本隆明という思想者の基本となっていると考えてもよろしいでしょうか。
吉本 そういう傾向に重点が大きく移りつつあると、自分でも思いますね。先進的な文明文化を持っている国では、産業でいえば消費産業が主体になってきていますから、国と国が戦争してどうこうしようという考え方はだんだん少なくなっています。これはいい傾向だと思いますが、一方で、貧富の格差の違いに対する関心が少なくなっている。あるいは、地方ごとにそれぞれ分権をというようになっていくのはいい点ですが、同時にやっぱり危険もありますね。このあたりことは、早急な決めつけ方をすると成り立たないという問題が起こる可能性があります。それらが、今一番気に懸かるところですね。なんとか、こうしたことの見極めがつけられるやり方を持てないと、ダメだなぁと感じていますね。
(『吉本隆明が最後に遺した三十万字 上巻 「吉本隆明、自著を語る」』P305-P309 ロツキング・オン 2012年12月)
※①と②とは、一つながりの文章です。
|
| 備考 |
(備 考)
「上野や銀座のデパートにほぼ毎日出かけていた」や「そういう一種の臨場感が僕には大きく作用して、自分の考え方を作っているように思いますね」、ここにも吉本さんの実験化学者の修練から培われた考えの構成法が貫かれていると思う。
吉本さんは、ひとつのものをずっと考え続ける姿勢を持ってきたように思われる。『初期ノート』などに記された考えが少しずつ形を変えながらも晩年にまで及んでいることがある。「若い頃に「思想者」という言葉を発明した」とあるが、それが文章の中に残されていたのか、わたしにはちょっとそれは思い当たらない。
加えて、この「思想者」という概念・自己規定には、『最後の親鸞』で語られた非僧非俗の問題が内包されている。
日常の生活では、吉本さんに触れた人々が、吉本さんの書物や思想のイメージを携えて訪れたのだろうが、ほんとうに人のいいおじさんみたいで驚いたなどの証言を読んだことがある。たぶん吉本さんの生活世界での日常の振る舞いは、意識的な実践と言うよりも
―いくらかはそれもあったかもしれないが― 出身階層の生い立ちの自然性から自然に流露していたものだと思われる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 624 |
政治判断 |
第1章 現代社会の背景 |
インタビュー |
『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 |
春秋社 |
2012.10.20 |
※本書は二〇〇八年五月二六日、六月十三日、十九日、二四日の四回にわたるインタビュー。
インタビューアーは皆川勤
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 政治というものは、その中間に、どうしても内密に決められて行われるということがある |
下から決まっていく親子関係とか親族関係と政治のように上の方から下の方へと及んでいくというもの |
|
|
項目
1 |
①
自分なりによく知っているからいえますが、政治に対する見解のようなものだけは、普通の社会的な生活をしている人が判断すると、必ずまちがうような気がします。
政治というものは、その中間に、どうしても内密に決められて行われるということがあって、それに従わざるをえなくなっていく、ということが必ずありますから、その「内密に」というところが、一般の生活をしている人にはなかなかわからないのです。
正確な判断ができるという人がいるとすれば、それは社会的な上層にいる知識人とか、ある程度情報を得ることができるような場所にいる人ぐらいのもので、一般的な人はまずそうはいかない。
だからそれは逆にいえば、政治権力を獲得して、しかる後に革命をするとか保守的にするとかと考える政治家とか政治運動家というのは、一般の庶民の考え方には届かないよということだと思います。
それはある意味、相互関係のようなもので、庶民とか民衆の方が政治について判断すると、たいていどこかまちがえているというのとまったく同じことです。
②
極端にいえば、政治がやることや、政治家たちの言動の広まり方というのは、庶民たちのそれに比べて格段に大きいわけですから、政治の方がまちがえれば、それが倍増して庶民の方に入ってきてしまうということになります。
政治のように上の方から決まっていくということには、どうしてもそういう問題がありますし、ある場合には、われわれはそれに従わざるをえないということが起きてしまいます。
下から決まっていく親子関係とか親族関係というのは、個々のメンバー同士の考え方が集まって、だいたいひとつの雰囲気が出てくるわけですが、政治のように上の方から下の方へと及んでいくというものはどうしても違ってきます。
(『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』P15-P16 春秋社 2012年10月)
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
| 備考 |
(備 考)
①の「内密に決められて行われる」ということを除けば、このような外からはうかがい知れないということは家族などの小社会についても当てはまる。ただ、家族の場合は、誰もが家族経験を持っているから他の家族についてある程度の類推は利く。しかし、家族内の出来事が事件として現れる時、近隣のほとんどの者がそんなふうには見えなかったとか、いい人でしたよなどの証言をするということは、家族もまた外からはうかがい知れないものを持っていることになる。
(関連事項として)「片道だけの民主主義」
吉本 ・・・略・・・戦後、日本は民主主義の国家に変わったんだって言いますけど、確かに民主主義によって選挙して、その結果、大多数を占めた政党があって、その中から総理大臣や各大臣が選ばれて、っていうふうになっていますね。それは一見、いかにも合法的で、当然のように見えるけれども、本当に民主主義って言いたいんならば、政治を司る政党なり、大臣なり総理大臣なりになったとしたならば、今度は何か新しいことをする時には――たとえば少年法改正であれば、その理由を、選挙した人たち、つまり国民にちゃんと公表して説明した上で改正する、っていうことがないと、片道だけの民主主義のような気がするんです。で、それは何なのかって言うと、どうも日本にはそういう習慣がないっていうか、なかったんじゃないかな、っていう。僕はこれがやっぱり一番の問題じゃないのかなって思うんです。これは自民党だけじゃなく共産党でもそうで、肝心なことは国民に言わないで決めちゃって、それで済ましてます。どこの政党が政権党になっても、そうしちゃうんじゃないかっていうふうに思えてならないんですね。で、これはやっぱり、民主主義とは違います。(以下、アメリカ占領軍が東京に入った時、吉本さんが目にした占領軍軍政局の公開性、つまり新しいことを実施するときには声明を出し理由も公表していたことに触れている。)
(『吉本隆明が最後に遺した三十万字 下巻 「吉本隆明、時代と向き合う」』P41-P43 ロツキング・オン 2012年12月)
この件に関しては、わたしは不服に思ったことがある。いくら選挙-代議制と言っても、わたしたちの生活に関わる重要事項に関しては、国民投票のような何らかの対処を事前にとるべきではないかと思ったことがある。それは例えば、裁判員制度のことである。新聞の世論調査では7~8割の反対があったように記憶している。現在では、割と正確な世論調査などとして国民の判断や考えを政治は知ることができるのだから、それを無視して押し切るのは「片道だけの民主主義」と言うほかない。政治がわたしたちの方に開かれていない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 627 |
自己表出と指示表出 ① |
第3章 第二の敗戦期とはなにか |
インタビュー |
『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 |
春秋社 |
2012.10.20 |
※本書は二〇〇八年五月二六日、六月十三日、十九日、二四日の四回にわたるインタビュー。
インタビューアーは皆川勤
関連項目 「言葉の吉本隆明①」 項目ID408 項目 「自己表出と指示表出で織られた言葉」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 言葉というものは比喩でいえば樹木 |
言葉によるコミュニケーションは、幹から分かれた枝の先にある葉であるとか、咲いた花であるとか、実である |
樹木の幹と根、つまり沈黙こそが言語の本質 |
これでもって、グローバルな勝負ができるなと思っています |
項目
1 |
①
言葉というものは比喩でいえば植物、つまり樹木です。樹木にとっての幹と根ということが、言葉の本質にあたると考えるのが妥当だとぼくは思います。
そして言葉によるコミュニケーションということは、幹から分かれた枝の先にある葉であるとか、咲いた花であるとか、実であると見なすことができるはずです。つまり季節によって色が変わったり、冬が来れば落ちたりする樹木の先の枝葉のところが、言葉のコミュニケーション機能なのであって、樹木の幹と根は黙してそこにあるだけですから、沈黙こそが言語の本質なのだ、という考え方をするわけです。
(『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』P119-P120 春秋社 2012年10月)
②
樹木の幹と根っこというのは沈黙した言葉なのだと考えると、そのことにいちばん近いことは、ぼくの言葉でいえば自己表出ということになります。自己表出というのは、そういう幹と根っこのいちばん近いところに置かれている言語表現なのだ、という考え方をします。
そして言語というものは、そういう自己表出と、枝葉に実をつけたり花を咲かせたり、葉っぱをつけたりするコミュニケーション言語というものもあるわけです。これを指示表出といおうではないかと、両方を分けて考えてやろうとしたのが、ぼくらの言語に対する考え方の大きなモチーフでした。
ようするにいつでも言語というものは自己表出、つまり自己で自己に語るとか、外に言葉を発しないで、自分の中で発しているということになるはずなので、ほんとうはそういう言葉とそうでない言葉とに分けることなんかできないのです。いつでもそれは織物みたいにしっかりと絡み合って分けられないのだけれども、しかし分けようではないか、分けて考えようではないかとしたわけです。沈黙にいちばん近いところの言語を自己表出と考えようと、そのように考えていったわけです。
これは誰も認めてくれないから、ぼくだけしか認めていないのだけれども、ぼくはひとまずやったなと思っているわけです。つまり言語問題について、自分が考えて自分しか使っていない、そういう言語の理論を作ったなと思っています。日本語を基にしてそれをやって、だいたいできたなと、そんなに一級品ではないけれども、これでもって、グローバルな勝負ができるなと思っています。
(『同上』P122-P123 春秋社 2012年10月)
|
備
考
|
(備 考)
言葉の基軸としての自己表出と指示表出は、若い頃は特によくわからなかった。今でも十分にわかっているとは言い難い。その概念の理解がなぜ難しいのかははっきりしている。その言葉の基軸としての概念が、現在性だけでなく歴史性を内包しているからである。さらに、「これでもって、グローバルな勝負ができるな」と吉本さんが語っているように、それは世界のあらゆる言葉を包括するもので、いはば現在までの全人類史を相手にしているからである。
吉本さん自身も言っているように、『言語にとって美とはなにか』を書いた時期は言葉は自己表出と指示表出の二重性として捉えられていたが、後には言葉は自己表出と指示表出の織物として捉えられるようになっている。そのように少し修正されている所がある。ここでは、最晩年の考え方を持ってきた。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 628 |
実感に基づく思考 |
第五章「『新しい歴史教科書をつくる会』について」 |
インタビュー |
『吉本隆明が最後に遺した三十万字 下巻 「吉本隆明、時代と向き合う」』 |
ロッキング・オン |
2012.12.24 |
インタビュアー 渋谷陽一
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 経験上よくわかる |
リアルな認識 |
否定しようもない事実 |
|
項目
1 |
①
― 今回は、中国とか韓国から文句をつけられた「新しい歴史教科書をつくる会」の『新しい歴史教科書』(扶桑社)についてお話をお願いしようかと思っているんです
吉本 『新しい歴史教科書』については、とにかく一等最初、どうしても僕が前提として言いたいことは、要するに『新しい歴史教科書』の内容がどう中国と韓国に対して見解が違うかとか、認定が違うかっていうこと以前に――日本の場合には歴史教科書の内容を変えて学校で使うっていうこと、それから中国と韓国についていえば、そのことに文句をつけてるわけですね。それは内容以前の問題として、僕なんかはもう気に食わない(笑)。気に食わないっておかしいけど、前提として否定的だっていうことを言いたいわけですよ。どうしてかっていうと、それはリアリズムじゃないっていうか、学校教育制度なり教育制度の現実的な状態なりにいずれも反するからです。どう反するかっていえば、日本がそういう教科書を作った、その記述が勝手に日本にとって有利にしてあるかどうかっていうことを抜きにしても、それ以前に教科書を作り替えれば学校の制度として、生徒っていうのはそれを勉強して「なるほど」というふうに思う、と考えてること自体がおかしい。それが僕の前提にあります。これは経験上よくわかるわけだけど――自分がわかるっていうことは大部分の生徒がそうだと思ってるわけですけど――大部分の中高生にとっては歴史の教科書を―― 一般に教科書っつってもいいんですけど、歴史だったら特にそうだけど――読んだ揚げ句の認識に永続性があるとかね、長く認められるような見解とか考え方を形作るっていう考え方自体が僕は違う、と思っています。つまり、歴史の教科書なんていうのは自分の実感で言うと、試験の前日ぐらいに読んで年号とか主な事件のことを暗記したりして、試験が終わればそれはぺろっと忘れてしまうというのが実情だと思います。それがリアルな認識だと思うんですよ。だから教科書をこういうふうに記述すれば、教育的に、生徒の認識とか考え方が変わるだろうという考え自体がおかしいと思ってるわけです。だから、もちろんそれに文句つける奴もおかしい(笑)。つまり中国とか韓国とか、いやしくも現代の一国の政府が、他人の国で作ったそういうものに、ちょっと記述が現実と違うっていう考え方で、政府として抗議するとか直してくれっていうふうに言うこと自体が、また輪をかけておかしいと思います。だから全部そういうのはナンセンスであるっていうことは、僕は前提だと思いますね。エリート主義者どうしの空中戦になってしまう。
― なるほど。
(『吉本隆明が最後に遺した三十万字 下巻 「吉本隆明、時代と向き合う」』P103-P105 ロツキング・オン 2012年12月)
②
吉本 それからもうひとつは、中国も韓国もさ、日本のそういう教科書を作った奴もそうだけどさ、何となく、ウソをついてる気がするの。何がウソかっていうと、そういう時だけ割合に厳密な論理を使うんですよね。そういう時だけヨーロッパ的論理性って言いましょうかね、論理的整合性でもって、議論をやるんですよ。だから全部ウソになっちゃうんですよ。つまり、今、歴史教科書で問題になっているところを見ると、それはもういくら論議したって水掛け論になるだけで論議するに値しないよ、何の解決にもならないよ、っていうふうにしか思えないことなんですよね。つまり、どういうふうに論議したって、どれが正確かっていうことは限定することはできないっていうふうに思います。本当に事実を言うならば、中国は西欧からも日本からも、植民地を求められて勝手にそれを作られちゃったとか、また満州国をもしも傀儡の国家だと言うんならば、そういうのを、日本国が勝手に中国を分割して作っちゃったんだ、っていうことだけ言えばいいと思います。韓国だったら、何はともあれ明治以降、韓国は――朝鮮半島全体だけど――日本が植民地政策を取って植民地にしちゃって、韓国の国民は植民地の民衆として太平洋戦争が終わるまでは相当酷い差別を受けた、って結局それだけ言えばいい、と僕は思います。これは日韓両方とも承認せざるを得ない、否定しようもない事実ですから、それはそれだけのことを言えばいいっていうことなんです。
(『同上』P105-P106 )
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
吉本さんをよく読んでいる人々にとっては、「実感」という言葉はよく出会う言葉である。そうしてそれは吉本さんの思想の根幹に関わるとても重要なことである。その実感というのは論理や思想の肉体性に相当するもので、それを論理化した言葉にすれば、「大衆の原像」やその繰り込みなどという言葉になる。
「実感」といっても、ある事柄に対してひとりひとりは違ったイメージや感じの実感を持つ。そんな中でも、大多数に共通する実感というものがありうる。ひとりひとりの心や意識の底の方ではひとりひとりいろんな違いがあっても、心や意識の上の方ではひとつの共通性を持っているイメージとして想定できると思う。
①の
「これは経験上よくわかるわけだけど――自分がわかるっていうことは大部分の生徒がそうだと思ってるわけですけど――大部分の中高生にとっては歴史の教科書を――一般に教科書っつってもいいんですけど、歴史だったら特にそうだけど――読んだ揚げ句の認識に永続性があるとかね、長く認められるような見解とか考え方を形作るっていう考え方自体が僕は違う、と思っています。つまり、歴史の教科書なんていうのは自分の実感で言うと、試験の前日ぐらいに読んで年号とか主な事件のことを暗記したりして、試験が終わればそれはぺろっと忘れてしまうというのが実情だと思います。それがリアルな認識だと思うんですよ。」
こういうことは、ほんとは誰でも実感としてわかりそうな気がする。じゃあ、なぜそんな地点から出発して考えを形成しないかというと、それはほんとは間違ったあり方で、もっと教科書をよくして、生徒はしっかり教科書に書かれていることを身につけなくてはいけないなどと、その大多数の実感の場所から上昇していくからである。こうしたことは、知識の世界や「有名人」に対する意識に見られるように現在的なものであり続けているが、大衆は遅れている存在であるから指導されなくてはならないという過去の前衛-大衆の考え方と同じであり、さらに大昔からの流れであるように思われる。知や知識層の病ともいうべきものである。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 630 |
自己慰安 |
第四章 ぼくもひきこもりだった |
|
『ひきこもれ―ひとりの時間をもつということ』 |
大和書房 |
2002.12.10 |
※ 「本書は著者へのインタビューを編集・構成し、それに加筆したものです。」とある。
関連項目 項目629 「吉本さんのこと ⑫ ―話し言葉と書き言葉」。
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| ひきこもり性だった |
他人との付き合いに苦手意識のあった |
人が読む読まないは二の次で、自分の言いたいことが自分でわかれば安心する。つまり、書くことはぼくにとって自己慰安になっていた |
一九七〇年代、ぼくは「広場に出る」ということを考え始めました |
項目
1 |
①
ぼくが物を書き始めたのは、ひきこもり性だったからです。
たとえば、友だちと話をしていても、相手の言うことはよくわかるけれども、自分の言ったことが相手に通じていないように思えてならない。孤独好きで非社交的でしたから、うまく伝えられないのです。
どうしたら通じるんだろうと考えて、これはおしゃべりするよりも書いたほうがいいのではないかと思いついた。書いて、それを相手に読んでもらえればいいのだと。それがすべての始まりです。一四~五歳の頃でした。
最初は、童謡のような詩のような、そういうものを書いていました。自分の思い通りのことが書けた時は、「自分で読んでわかるんだから、他人もわかるかもしれない、自分のことを誤解しないでもらえるかもしれない」と思って満足する。そんなことをしょっちゅうやっていました。
書いて表現すると、自分で読んで、うまくないなあと思ったところは直すことができる。より自分の考えが正確に伝えられるわけです。他人との付き合いに苦手意識のあったぼくにとって、それは大事なことでした。
②
書いたものを他人が読んでくれればいいわけですが、読んでくれる人がいなくても、うまく自分の考えていることや感じていることが文章の中で言えていたら、それが自分の慰めになるということをやがて発見しました。人が読む読まないは二の次で、自分の言いたいことが自分でわかれば安心する。つまり、書くことはぼくにとって自己慰安になっていたのです。一六歳から一八歳くらいの頃には、友だちとわら半紙を綴じて雑誌のようなものを出すようになりました。
その頃は、文学者というのはきっとみんな自分のように他人におしゃべりが通じないと思って物を書き始めたのではないかと思っていました。少したつと、そうとは限らないことがわかってきましたが、いろいろな文学者の書いたものを読むようになったのも、そのへんのことがあったのかもしれません。
③
自分がわかればいい、ということを中心にして物を書いてきたのですが、ある時期から、ぼくは「広場に出る」ということを考え始めました。一九七〇年代のことです。顔の見えない読者に向かって書こう。その人たちにわかってもらえるような文体にできるだけ近づけよう。そう考えて努力してみました。
読みたい人は勝手に読んでくれればいいというのを、少し変えてみようと思ったのです。たとえば、一般の読者がたまたまぼくの本をめくってみて「あっ、そうか」と思ってくれる。そういうものを書くのもいいのではないかと。
ぼくの好きな小説家である太宰治が、自分は読者においしい料理を提供しようとして一生懸命心を砕いているというようなことを書いていますが、ぼくがやろうと思ったこともそれに近い感じです。
(『ひきこもれ―ひとりの時間をもつということ』P124-P127 吉本隆明 大和書房 2002年12月)
※①、②、③は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
①の背景には、もちろん吉本さんの「ひきこもり性」を含む資質的なものが関わっている。
①→②→③と、吉本さんの書くことの転位が語られている。特に①→②は、一般に当てはまる普遍的な書くことの有り様である。
吉本さんは、文学の本質は「自己慰安」であると語っていたように記憶する。遙か言葉の始まりから、次第に言葉は宗教性を獲得し、さらにそこから個の表現へと分化していった。吉本さんは、この個の表現としての文学の本質に「自己慰安」をみたのだと思う。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 631 |
西欧の大波のかぶり方 |
第二章 「少年法改正をめぐって」 |
インタビュー |
『吉本隆明が最後に遺した三十万字 下巻 「吉本隆明、時代と向き合う」』 |
ロッキング・オン |
2012.12.24 |
インタビュアー 渋谷陽一
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 西欧近代を模倣 |
北村透谷、国木田独歩 |
今の親子関係 |
|
項目
1 |
①
吉本 少なくともこれまでは、西欧のほうが意識も理念も政治も社会制度も進んでるから、これを模倣して早く追いつこうっていうふうにやってきたわけでしょうけど、そういう面と、そんなに過大評価する必要もないっていう面の二面あると思うんですね。でも、明治以降、そういうことをきちっと区分けして対処してきたわけではなくて、やっぱりなんとなく真似しているうちにそうなったっていうのと、なんとなく真似してるんだけど同じようにはいかなかったみたいなことで、済ましてきちゃったっていう意味合いでは、日本は成り行きでそうなってきたっていう(笑)。で、区分けして対処するっていうのは大変難しいことだとは思うんですよ。難しいことなんだけど、少なくとも明治の初めで極めて良心的かつ真っ当に西欧近代を模倣して早く追いつこうと思った人たちは、やっぱり多大な犠牲を払ってますよね。たとえば、極端な部類で言いますと、北村透谷でも国木田独歩でもいいんですけど、この人たちは男女関係から取り組んでいったわけですね。それで、基盤もないのに男女同権とか女性尊重ってやってるうちに自分のほうが追い詰められて(笑)、結局、国木田独歩だったら離婚しちゃって、家っていうのは破綻しちゃったっていうふうになります。透谷だったら、家が破綻しただけで収まらなくて、揚げ句は自殺して夫婦関係を解消する、という。つまり、それだけの犠牲というかっていうか被害っていうか、それはやっぱり自分で被っていますし、ある意味で自分で引き受けたっていうことがあります。
②
吉本 じゃあ、今だったら何を引き受ければいいんだっていうのは、すこぶる曖昧なわけです。で、その曖昧なものが一番出てくるのが、少年法じゃないけど、親と子の関係だと思うんです。それは今どうなってんだっていうと、僕に言わせれば、比喩で言うと自民党と共産党との違いよりも、親と子の違いのほうがすごくなってるんだよっていうふうに思います。それはなぜかっていうと、何か知らないけど今急速に何かが変わろうとしている基盤があるんだけど、具体的な制度とかその他のシステムとかが変わっていないわけです。だから片っ方では、昔の続きのまま変わらない親がいて、もう片っ方では、やることもやりたいこともえらく変わっちゃった、あるいは変わりつつあるっていうのを感覚的に身に受けちゃってる子供がいて、もうめちゃくちゃ距離が離れちゃってるんです。で、たいてい今の親子関係は、親と子供のどちらかが、あるいは両方が仕方なく妥協してるとかで、社会生活のうちの少なくとも家族生活っていうのは、それくらい我慢しなきゃ成り立っていかないっていうふうになってると思うんです。極端なことを言えば、殺すか殺されるかぐらいに全然了解はつかないよっていう。これでもって真っ正面からぶつかり合ったら、もうとてもとても話は一から十まで通じないぐらい違っちゃってるっていう。了解をつけるなら講和条約を結ぶぐらいじゃないと、っていうか(笑)、それくらい親と子の間で意識が違っちゃってるっていうのが今の現実です。で、それがどこに一番表れてくるかっていうと、やっぱりそれぞれの世代の違いみたいなところ、大人の世代と子供の世代の違いでもって表れてきます。
(『吉本隆明が最後に遺した三十万字 下巻 「吉本隆明、時代と向き合う」』P45-P46 ロツキング・オン 2012年12月)
※①と②は、ひとつながりの文章です。
|
備
考
|
(備 考)
「西欧の大波のかぶり方」というテーマで、①の部分は明治近代辺りのものである。若い吉本さんは、ずいぶん影響を受けた高村光太郎を批判的に取り上げて『高村光太郎』を書いた。その高村光太郎もまた、留学によって西欧の大波をかぶりその後の家族関係含めた生き方に大きな影響を受けた者だった。
②は、①とのつながりとして唐突に感じられるかもしれないが、たぶん、明治近代以降、さらに第二次大戦後と、西欧の大波をかぶり続けて、芸術や文化や思考様式までずいぶんこの列島社会に浸透してしまった。この列島で太古以来中国アジアの影響の層などいくつかの層を積み重ねてきた感性や精神の遺伝子とそれら欧米の影響とが 縒(よ)り合わされた現在がある。欧米の一般的な親子関係は知らないが、例えば、現在なら欧米からの影響が滲透している個の尊重や自由という概念の層、たぶん若者たちはその層に親近感を持つだろう。一方、親たちは、江戸期辺りのアジア中国の影響を受けた思想・倫理が壊れはてて破片のように無意識を規制しているというよりは、親子関係が友だち関係のようにフラットな関係になってきている現状は受け入れつつも、やはり保護者という概念、感覚、位置は、最後の砦のように手放せないということかもしれない。そのことに現実の家族のなかでの親子関係の齟齬(そご)は発祥するように思われる。すなわち、現在でも、欧米の大波を被った影響は意識の表層よりは下の方で継続しているのである。
①は、明治近代辺りの知識層の「西欧の大波のかぶり方」ということになる。②は、明治近代の西欧、第二次大戦後の欧米という二度の大波をかぶり社会にずっと浸透してきた状況での大衆レベルの問題になってきている。
たぶん、熱が高温から低温へ伝導するように、人類社会の文明や文化も一般にはより高度に発達したところから低い方へ流れ影響を与えるのだと思う。ただし、個別的には逆の動きもあり得る。例えば、ピカソがアフリカ美術から影響を受けたことや、日本の浮世絵などがヨーロッパの画家たちに影響を与えたことなどはよく知られている。こうした文明や文化の伝播や影響は、上に挙げられている北村透谷や国木田独歩のように、実際に人々に苦闘を強いる面を持つが、そうした振る舞いは人類史の必然であると言うほかない。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 636 |
書物の良し悪しの判断 |
「なにに向って読むのか」 |
論文 |
『読書の方法』 |
光文社 |
2001.11.25 |
※ 「なにに向って読むのか」は、1972.3.30
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| なにかの役にたてようとして読まれる方がほとんどなのだ |
小さな世界、その世界は書き手のもっている世界の縮尺のようなもの |
行きつ戻りつしたために、そこだけが踏み固められて広場のようになってしまった。 |
そういう場所に行き当った読み手は、書き手をつかまえたことになるのだ。 |
項目
1 |
①
図書館にゆくと、すべての書物は、誰かによって手をつけられていることがわかる。けれど、たぶんほんとうに読まれたのではなく、なにかの役にたてようとして読まれる方がほとんどなのだ。余裕もなく、はやく結論がみつけられないかどうかと焦りながら。そして、書き手もまた、読み手のせき込みに応じようとして、なにかに尻をたたかれながら書物をつくりあげたという書物が、ほとんどであるかもしれない。
②
ある書物がよい書物であるか、そうでないかを判断するために、普通わたしたちがやっていることは誰でも類似している。じぶんが比較的得意な項目、じぶんが体験などを綜合してよく考えたこと、あるいは切実に思い患っていること、などについて、その書物がどう書いているかを、拾って読んでみればよい。よい書物であれば、きっとそういうことについて、よい記述がしてあるから、だいたいその個処で、書物の全体を占ってもそれほど見当が外れることはない。
だが、じぶんの知識にも、体験にも、まったくかかわりのない書物にゆきあたったときは、どう判断すればよいのだろうか。
それは、たぶん、書物にふくまれている世界によってきめられる。優れた書物には、どんな分野のものであっても小さな世界がある。その世界は書き手のもっている世界の縮尺のようなものである。この縮尺には書き手が通りすぎてきた〈山〉や〈谷〉や、宿泊した〈土地〉や、出遭った人や、思い患った痕跡などが、すべて豆粒のように小さくなって籠められている。どんな拡大鏡にかけても、この〈山〉や〈谷〉や、〈土地〉や〈人〉は、眼には視えないかも知れない。
そう、じじつそれは視えない。視えない世界が含まれているかどうかを、どうやって知ることができるのだろう?
もし、ひとつの書物を読んで、読み手を引きずり、また休ませ、立ちどまって空想させ、また考え込ませ、ようするにここは文字のひと続きのようにみえても、じつは広場みたいなところだな、と感じさせるものがあったら、それは小さな世界だと考えてよいのではないか。
この小さな世界は、知識にも体験にも理念にもかかわりがない。書き手がいく度も反復して立ちどまり、また戻り、また歩きだし、そして思い患った場所なのだ。かれは、そういう小さな世界をつくり出すために、長い年月を棒にふった。棒にふるだけの価値があるかどうかもわからずに、どうしようもなく棒にふってしまった。そこには書き手以外の人の影も、隣人もいなかった。また、どういう道もついていなかった。行きつ戻りつしたために、そこだけが踏み固められて広場のようになってしまった。
じっさいは広場というようなものではなく、ただの踏み溜りでしかないほど小さな場所で、そこからさきに道がついているわけでもない。たぶん、書き手ひとりがやっと腰を下ろせるくらいの小さな場所にしかすぎない。けれどそれは世界なのだ。そういう場所に行き当った読み手は、ひとつひとつの言葉、何行かの文章にわからないところがあっても、書き手をつかまえたことになるのだ。
(『読書の方法』P9-P11「なにに向って読むのか」吉本隆明 光文社 2001年11月)
※初出は、「文京区立図書館報」50号1972年3月30日
※①と②は、連続した文章です。
|
| 備考 |
(備 考)
わたしも上のような判断を書物についてしたことがある。松岡祥男さんが書き留めている言葉からお薦めの本だと思えた北島正『こころの誕生』(ボーダーインク 2005年11月)を読んだ。中井久夫の『徴候・記憶・外傷 』を読んで記憶について少し考えたことがあったから、記憶の項目の所を読んで本書は優れた考察をしていると言えるなと思ったことがある。
②の書物のなかにある書き手の「小さな世界」、言われてみればなるほどと思うけど、このような吉本さんの把握には対象がそっくりつかみ取られているようでうーんとうならざるを得ない。
(追 記) 2020.10.18
『宮沢賢治 ― 素顔のわが友』(佐藤隆房 富山房企畫 2012年3月)を読んでいたら、宮沢賢治の「書物の良し悪し」の判断に関することが載っていた。吉本さんと同じようなことが語られている。
農学校職員の頃、畑にも出ず、標本室にも行かないひまな時間は、日当たりのよい窓ぎわに椅子をよせて足を組み、読書に余念がありません。
ある時、同僚の渡部教諭が
「あなたは本の善悪を見分けるのに、どんなにしていますか」とと聴いたことがあります。
すると賢治さんは
「そうですね、まず肥料の本に例をとって言えば、自分の最も得意とする下肥のところを読んで見ます。そこになるほどと思う点があれば、これは良い本ということにして、その他の項目も読みます」と言いました。
(同書 「34 読 書」)
昔、宮沢賢治の花壇設計の詩を取り上げた時 (宮沢賢治「花壇工作」から 2017年08月30日 https://blog.goo.ne.jp/okdream01/e/8bf69534c3b3ed7f9b04cc258e441765 ) 、確かこの佐藤隆房という医者が出てきた記憶があったので検索してみたら以下のものが見つかった。
農学校(引用者註.「賢治が奉職した稗貫農学校」)の跡地は現在は総合花巻病院の一部になっている。大正13年この病院の中庭に賢治花壇を設計したのだが、その情景が『花壇工作』に詠われている。その詩の中には、院長に対する賢治の心情が吐露されており、賢治の性格の新たな一端を知ることが出来る。その院長こそ佐藤隆房である。その後、隆房と賢治は親交を深めていったし、隆房は賢治の主治医になっていった。
なお、現在はその花壇がファンタジー花壇として復元されている。
また、隆房は昭和17年、その当時は賢治の生涯を知ることの出来る書籍は皆無だったので、自ら著書『宮沢賢治』を冨山房から出版したのだという。
地元の人たちからは『りゅうほう』先生と呼ばれて親しまれている佐藤隆房は大正12年に花巻共立病院(現在は総合花巻病院)を開き、この病院の院長・理事長であった。
隆房は宮沢賢治の最期を看取った主治医でもあり、第二次世界大戦時には宮沢家共々光太郎を花巻に招き、一時は光太郎を自宅の離れに住まわせていたとのこと。
(「宮沢賢治の里より」https://blog.goo.ne.jp/suzukikeimori/e/e077eaf254ae62d8dc8a1064c04e9cd7)
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 658 |
性・生命の表現としてのリビドー |
Ⅱ言葉の起源を考える |
|
『詩人・評論家・作家のための言語論』 |
メタローグ |
1999.3.21 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| フロイトの「リビドー」概念の解釈 |
身体、言葉とリビドー |
宮沢賢治の特徴 |
精神分裂病の妄想ないし幻覚が起きている状態は、言葉以前の言葉を発する乳児期のこころの状態、こころの世界に対応させることができる |
項目
1 |
①
精神の異常や病気について、たとえばフロイトは、自己表出性ないし指示表出性のどちらの側面をとっても、言葉を表現したいという人間の欲求は、広い意味での性的な欲望、性的な衝動、性的な関心と深く関係があると一生懸命に説明しています。フロイトは、それら人間の性的表現を「リビドー」という言葉を使って呼んでいます。「リビドー」は狭く解釈すると性的な欲動や衝動の表現になりますが、広く解釈すると「性的」よりも「生命」に近い意味に受け取ることができます。
つまり、人間の生命感の表現は「リビドー」だと理解することができます。言葉の表現には「リビドー」の意味あいが必ずつきまとうとするフロイトの説は、性がつきまとう意味と、生命の表現がつきまとう意味と、この広範な中間段階をすべて含んでいるとかんがえたほうがわかりやすいのではないでしょうか。あまり極端すぎないから、そのほうが理解しやすい面があります。「リビドー」には性の意味あいもあるし、生命の意味あいもあると理解すれば、言葉の表現には必ず「リビドー」が伴うことになっていきます。
② フロイトの考え方を人間の身体に結びつけてしまえば、心臓や胃など内臓器官の動きも、眼や耳や鼻など感覚器官の動きも、器官という器官の動きはすべて、生命表現あるいは性的表現という広い意味での「リビドー」を含むと理解すればよいとおもいます。人間が言葉を使って何かを表現するあらゆるケースが、そのなかに含まれるということができます。
たとえば、もし内臓に異常や病気があったら、それは必ず病的なこころの表現に関係してきます。病的なこころの表現は、言葉の表現にもかかわってくるとおもいます。つまり言葉には、指示表出と自己表出のふたつの軸があるということ、そして、あらゆる性的表現ないし生命の表現は、人間の内臓の動き、あるいは動物神経系の感覚の動きに全部かかわりがあるということです。
言葉は「アイウエオ」と分節されたかたちで出てくるばあいと、言葉以前の言葉で(引用者註.独り言や心の中でつぶやくなど)出てくるばあいとがありますが、いずれも性的表現ないし生命の表現を含んでいます。
(『詩人・評論家・作家のための言語論』 P101-P103 吉本隆明 メタローグ 1999年3月)
③
それは宮沢賢治の特徴で、多くのカッコを用いて違う精神内部の次元から表出されたことをあらわしています。ふつうは同じ詩のなかではそれほど多くの使い分けはしませんが、宮沢賢治は厳密です。その言葉を表現したい欲求がどの次元から出てきたか、あるいは視覚的にみえたか、とてもよく区別しています。童話でも同じように多く使い分けていますが、詩のばあいはとくに顕著に表現されています。
あまりうるさくやると作品の流れを切断してイメージを失わせるのではないかとおもわれますが、宮沢賢治には文学に対する一種独特の考え方があって、流れがよいかどうかは詩の本質ではなく、どの次元の、どんなところから言葉が出てくるかをうまく表現することのほうがはるかに重要だったのです。自己表出の出どころと段階で表現を区別しているわけです。
宮沢賢治はさまざまなことを統一的にいうよりも、彼のいう心象スケッチとして表現するための方法をもっているから区別しているのです。こうした段階の違いに区別をつけて表現することが芸術性だとかんがえています。
(『同上』 P106-P107 )
④
フロイト流にいえば、宮沢賢治の使い分けは生命表現がそれぞれ違っていて、おもわず違うところから言葉が出てきたということです。フロイトは、指示表出性が拡がってしまうイメージの異常や、指示表出性と自己表出性が塊のように分離できない病的な表現も含めて、広い意味での生命表現の異常が言葉以前の言葉には必ず伴うものだとかんがえています。
精神分裂病はいちばん典型的ですけれども、幻覚やだれかから命令されている言葉が聞こえる作為体験があります。指示表出性がない場面でも指示表出性がつくられ、ほんとうは聞こえるはずのない声が聞こえてくるわけです。
道を歩いている人を、縁もゆかりもない男が通りがかりにいきなり刃物でブスリと刺して、すこし行ったところでまたほかの人を刺すという事件がよく新聞に出てきます。(註.1) これはもちろん病気で、「あいつを刺しちゃえ、あいつはおまえを殺そうとしているから、おまえのほうが先に殺せ」という幻聴や幻覚があったり、被害妄想や妄覚があったりしているわけです。これは指示表出性がなくてもつくれます。視覚的には何もみえないのに、あるイメージがつくられてしまうのは、指示表出と自己表出が分離されずに出てくる状態です。言葉になる以前の世界が全部ひとまとまりになり、対象である相手とじぶんの言葉が分離されていない状態です。
(『同上』 P109-P110 )
⑤
精神分裂病の妄想ないし幻覚が起きている状態は、五~六ヵ月目以降の胎児期から生後一年未満のあいだ、つまり言葉以前の言葉を発する乳児期のこころの状態とよく似ているとおもいます。あるいは、その時期のこころの世界に対応させることができます。ですから、母親や母親代理を指示表出と自己表出の全対象としていた当時の状態までたどり着くことができたら、精神分裂病は治る可能性があるとおもいます。
フロイトは、言葉になる以前の世界がひとまとまりになった状態を人間の精神や感覚の範疇に入れようとしました。性エネルギーないし生命エネルギーが、人間のこころ、感覚、言葉につきまとっているものだと理解することで、得体の知れない精神状態とみえるものを理解し、治療できる範囲内に入れようとかんがえたわけです。
(『同上』 P110-P111 )
※①と②、④と⑤は、それぞれ一つながりの文章です。
|
| 備考 |
(備 考)
上記の「精神分裂病」は、現在では「統合失調症」と呼ばれるようになっている。
フロイトのリビドーの概念を受けとめ直すと、人間の心と精神の表現としての言葉は、性や生命感の表現としてのリビドーを含むということ。
内臓器官の動きや感覚器官の動きとしての身体の動きは、そのリビドーを含むということ。そして、言葉の表現はそのことの中に含まれる。
④では、幻覚や妄想時の指示表出や自己表出の特徴、すなわち生命表現の異常が語られている。そうしてそれは、精神分裂病の妄想ないし幻覚が起きている状態は、言葉以前の言葉を発する乳児期のこころの状態、こころの世界に対応させることができる、と捉えられている。ということは、わたしたちの幻覚や妄想などの病は、「母親や母親代理を指示表出と自己表出の全対象としていた当時の状態」、母の物語に根源があることにつながっていく。
こうした認識が何になるのかという問いがあり得るのはわかる。こうした認識が病からの事件を直接に防ぐことにはつながらないからである。しかし、わたしたちが、妄想や幻覚の病からの事件を自分とは関わりのない何か恐ろしいものと見なして済ますのでは事件の内に入り込むことはできない。つまり、事件を解きほぐし再び起こるのを防ごうとすることにはつながらない。こうした点で、ものごとの本質が明らかにされることは、問題への重要な入口であり、一歩である。もちろん、これは、本人や家族や社会の関わる気の長い永続的な課題でもある。人に緊張を強いる家族や社会のあり方が変わる必要があるというのは、永続的な課題ということになる。
この項目を考えている時に、たぶん幻覚や妄想から少年が起こしたと思われる事件に偶然出くわした。その概要を新聞記事から引用しておく。被害者の家族や知り合いには怒りと悲しみの痛ましいかぎりであろうが、上の吉本さんの追跡の言葉を借りれば、わたしたちは少年の心や精神の概要を追跡できることになる。
(註.1)
商業施設で20代女性刺され死亡 包丁所持疑いで男を現行犯逮捕 福岡
2020/8/28 21:30 (2020/8/29 2:14 更新) 西日本新聞
容疑者は15歳の無職少年と自称
28日午後7時半ごろ、福岡市中央区地行浜2丁目の大型商業施設「マークイズ福岡ももち」で、「刃物を持った男がいる」と多数の110番があった。福岡中央署によると、20代女性が1階の女子トイレで血を流して倒れているのが見つかった。女性は市内の病院に搬送されたが、約50分後に死亡が確認された。福岡中央署は、施設内で包丁を持っていた住所不詳、無職の少年(15)=いずれも自称=を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午後7時半ごろ、施設内で刃渡り約18・5センチの包丁を所持した疑い。署によると、少年は「刃物を持っていた」と容疑を認めているが、つじつまの合わない受け答えをしている。少年が女性を刺殺した可能性があるとみて捜査する。
署によると、少年は刃物を持って1階を歩き回り、警備員や客が取り押さえた。女性は施設関係者ではないとみられ、上半身を中心に複数の傷があった。
複数の目撃者によると、少年が手にしていた刃物には血が付いており、女性は頭や胸の周辺が血まみれだったという。
現場の施設は、市営地下鉄唐人町駅から約500メートル。プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの本拠地ペイペイドームに隣接し、近くには住宅街もある。
同じ西日本新聞の8月30日の記事では、捜査関係者からの話として、事件を起こした少年が被害者の女性とは面識がなかったと次のようにある。
少年は自身の氏名を名乗り、包丁を持っていたことを認めるなど、落ち着いた様子で取り調べに応じている。話す内容などから、女性とは面識がないとみられる一方、動機などについては、つじつまの合わない受け答えをしているという。
西日本新聞の8月30日のその後の記事では、
また、少年は26日に九州の少年院から福岡県内の更生保護施設に移っていたことも、捜査関係者への取材で判明した。少年は27日に施設からいなくなり、関係者が同日午後、行方不明者届を県警に出した。県警が少年の行方を捜していたという。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
初出 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 662 |
自己慰安 ② |
「移行する身体 ―歌や言葉のこと―」 |
対談 |
『舞台評論』第3号 2006年6月30日発行 |
吉本隆明資料集166』 |
猫々堂 |
2017.6.30 |
※ 「移行する身体 ―歌や言葉のこと―」 吉本隆明・森繁哉 対談
※ 関連項目 DB② 項目420「人間力」、項目424「人間力」、項目630「自己慰安」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 「自己慰安」は、フーコーの「自己への配慮」と対応する |
日本語ではなかなか説明しにくい概念 |
文学や芸術というものの起源は、この「自己慰安」なのではないか |
|
項目
1 |
①
森 『家族のゆくえ』の中で、芸術の根源は自己慰安を第一にすることだと書かれていますが、この自己慰安とは、身体や移行期とどう関わってくるんでしょうか。
吉本 自己慰安っていうのは、私流の呼び方なんです。人生には自分の思い通りにいかないことも多々あるわけです。人はそれぞれ自分を内省的に見つめ、自分の心をなだめたり、努力したりして不満や寂しさを解消していく。そうやって社会的な広がりを備えたものとして昇華していくことが、芸術の本源になると思うんです。
②
吉本 作家の夏目漱石は、生後まもなく養子に出され、乳幼児期からさんざんな思いをして育っています。個人としては不幸だったかもしれませんが、この苦しさを乗りこえようと努力したからこそ、すぐれた文学も残し得たわけです。
というのも僕は、自己慰安なしに書かれた文学は、人の心の深い部分に響かないんじゃないかと思っているんですよ。
だけど、現在の日本では、自己慰安の必要性を、ばっさりと切捨てているように思いますね。あるいは、必要以上に自分を大切にする方向にむかっているといいますか。非常に極端でアンバランスだと思います。
テレビなんかを見ていると、若者が一生懸命に手足を動かして踊ったり歌ったりしていますけど、そんなに無理しなくてもいいのにと思っちゃいますね。自己慰安というのは、結局、自分の気持ちを客観性をもって取り扱えるかどうかだと思います。
(「移行する身体 ―歌や言葉のこと―」 P52-P53『吉本隆明資料集166』猫々堂)
※対談 吉本隆明 森繁哉 初出『舞台評論』第3号 2006年6月30日発行
※①と②は、一つながりの文章です。
③
フーコーというフランスの哲学者がいます。彼は、ぼくの言う「自己慰安」に似た意味合いのことを、「自己への配慮」という言葉で表現しています。
自分を尊重すると言っても利己主義ではなく、社会的な意味合いを含んだ自分とのつき合い方とでもいうのでしょうか。自覚とか責任とか、そういうものを含めて、一個人としての自分に向き合い、大切にすることを「自己への配慮」と呼んでいるのです。
これは日本語ではなかなか説明しにくい概念です。ぼくは「自己慰安」という表現を使いますが、そうすると、自分をなぐさめるだけでいいのかということになって、誤解されてしまいます。もっと、内省とか、社会との関わりとか、そういうものを含んだ概念です。
皆さんの中に、自分は心が傷ついている人間だという自覚がある人もいるかもしれません。そういう人は、この「自己慰安」、あるいは「自己への配慮」ということを頭の片隅においておくといいと思います。
ぼくは、文学や芸術というものの起源は、この「自己慰安」なのではないかと考えています。
つまり、赤ん坊のときに母親から十分に可愛がってもらえず、そのためにいつも心が不安定だったりする人が、自分をなぐさめるために行うのが文学や芸術ではないかということです。
なぜそう思うかというと、ぼく自身がもともと、自分をなぐさめるために文章を書き始めたからです。最初は日記とか、詩のようなものでした。
ぼくもまた、育てられ方に問題のある、心が傷ついた子どもだったと思います。
(『13歳は二度あるか』P134-P135 吉本隆明 大和書房 2005.9.30)
|
備
考
|
(備 考)
吉本さんは、「自己慰安」については何度か触れている。フーコーについて触れたところでは、「自己慰安」はフーコーの「自己への配慮」に対応するというようなことを語られていたという記憶がある。ネットで検索してみたら、「自己慰安」や「自己への配慮」に関して以下のものがヒットした。
1.『13歳は二度あるか』(吉本隆明 大和書房 2005.9.30 )
2.『還りのことば ―吉本隆明と親鸞という主題 』(雲母書房 2006.5.1)
3.『思想とは何か』(吉本隆明・笠原芳光 対談 春秋社 2006.10.30)
4.『家族のゆくえ』(吉本隆明 光文社 2006.3.1)
この中で、、3.と4.とは自宅を探しても見つけ出せなかった。2.は、「項目420 人間力」と「項目424 人間力」として一度取り上げていた。そこでは、
「自己への配慮」が「人間力」と関わっており、「人間力」って何かって言うと、「人間が理想の可能性を考える能力」のことだと語られている。したがって、1.から該当部分を③に引用した。これで、②の「自己慰安というのは、結局、自分の気持ちを客観性をもって取り扱えるかどうかだと思います。」ということが、よりはっきりするだろうと思う。
自己慰安が、「日本語ではなかなか説明しにくい概念」ということは、私たちの列島社会ではそういう領域に自覚的であるということが歴史性として稀薄であったことを意味しているだろう。
「ぼくは、文学や芸術というものの起源は、この『自己慰安』なのではないかと考えています。」ということは、近代以降のことのように見える。しかし、太古の慈愛と猛威の二重の顔を持つ母のような大いなる自然との対話から生まれた宗教や芸術は、上のような意味での「自己慰安」や「自己への配慮」を含み持っていたとも見なせるような気がする。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 678 |
自閉症をどう捉えるか |
「心について」(上・下) |
講演 |
『吉本隆明資料集 130』 |
猫々堂 |
2013.11.25 |
A164 「心について」 講演日時:1994年9月11日
収載書誌:筑摩書房「ちくま」1995年1月号、2月号
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| つまり、脳のどこかに障害があるからこれが自閉症だといえるほど現在の医学は発達していません。 |
ようするに自閉症というのはなおるわけです。 |
いわば自覚的な自閉症の状態になったとき、なおったといえる程度に自閉が開かれるわけです。 |
自閉症は、いまのところわからないというのがいいとおもいます。 |
項目
1 |
①
最近、そういう例があるんです。たとえば上野千鶴子という人が河合塾かなんかの講演のときに、自閉症というのはマザコンで、母親があんまりかまうものだから自閉症になるんだみたいないいかたをしたわけですね。そうすると、自閉症親の会みたいのがあって、そこから抗議をうけたわけです。その抗議は、あなたみたいにマザコンだから自閉症になるといえば、ていねいに子どもを育てたら病気になるというふうになるではないか。そんなばかなことはない。自閉症というのは脳に器質的な障害があるんだと、学会ではそういう定説になっている。それを聞いて、自分たちは自分たちは自閉症の子どもを育てる場合に、さんざん苦労してきたけど、気分的に救われた感じがしている。そういうことをいわれて、上野千鶴子が、それは自分が軽率にいって悪かったみたいなことを弁解して、注釈と抗議の文章を全部載せて出したという事例があったんです。
ぼくからみると、両方ともだめだというふうにおもえます。つまり、母親が過剰にかまったから自閉症になるなんていうことは絶対にありえないわけです。その手の原因がぜんぜんないとはいいませんが、たいてい赤ん坊のとき、つまりお腹のなかに子どもを宿したときから、あるいは生まれてから一歳未満のときに、母親が、つれなく子どもを扱っているんです。子どもが胎内にいるのに、おもしろくないとおもったり、授乳するのにおもしろくないとおもいながら子どもに授乳したりするでしょう。もし影響があるとすれば、母親はその代償として子どもが四歳以上に育ってきてから過剰にかまうんですよ。上野千鶴子という人は、ようするに、環境論者なんです。つまり、マルクス主義者というのはたいていそうですけど、環境がよくなれば人間がよくなると思ってるんです。母親が授乳をしなければ、あるいは授乳に変わる牛乳だっていいですけど、それをやらなければ子どもは生きていけないというのは一歳未満のときだけなんです。だれかがかまわなければ、絶対的に死んじゃうわけですよ。だからそのときの扱いが重要なんです。もし環境が悪いというなら、そのときの環境だけなんです、ものをいうのは。そこがうまくいっていれば、たいてのことは大丈夫なんです。だからそれは上野千鶴子の言い方が間違いであることは言うまでもないことです。しかし自閉症というは器質の病だという母親たち意見も、間違いだとぼくはおもいます。つまり、脳のどこかに障害があるからこれが自閉症だといえるほど現在の医学は発達していません。定説でもなんでもない。
②
間違いだからこそ、『自閉症だったわたしへ』(註.1)なんていう翻訳書が売れたりなんかする。ようするに自閉症というのはなおるわけです。どういう状態をなおるといっているか、その手記を読めばひじょうにはっきりしますけど、自分は外界との連絡とか、人との関係の連絡がとれるようになったというふうにいっているわけです。おおざっぱにいうと、自分がやっていることをちっとも異常だとおもっていないし、自分がいうことも異常だとおもっていないんだけど、たとえばこういうことはいわなくても人にわかるはずだみたいにおもうと、口をきくのはいらないとおもうから口をきかない。そうすると、向こうのほうから見ると自閉症だというふうになってしまう。だけど自分は何も感受性がないかというと、そんなことはない。ちゃんとわかってるんだけどなんにもいわない。次第次第に自分でそういうことがわかってきますと、ふつうの人が外からみると、ああ、この子、なおってきたというし、自分のほうもなんとなく、ああ、こういうときには黙っていないでいえばいいんだというようなことがわかってくる。その人は見事にその状態の心の動きを書いてます。
③
そうすると、なおったということはどういうことかといえば、その人の自閉症的な素質がなおったということじゃなくて、ふつうの人との了解がとれるようになった。ふつうの人はこういうときには、こういう振舞いをするもんだというのがわかってきた。そういうふうにわかって、ひじょうに自覚的になってきたら、なおったということとおなじで、あと、きついことが残っているとすれば、その人の内面だけに残っているわけです。つまり自分が少し我慢して、多少抵抗感があるけども、それができるようになったというと、もうそれはなおったということとおなじことになります。いわば自覚的な自閉症の状態になったとき、なおったといえる程度に自閉が開かれるわけです。
(「心について」(上) P113-P115『吉本隆明資料集 130』猫々堂 )
④
自閉症が脳の器質のどこかの病であるかどうかを決定するのはたいへんなことです。そんなことを決定するほど世界の現在の医学は発達していないですから、いまのところわからないというのがいいとおもいます。[もしかすると、医学がもっと発達すれば、存外、器質の病だということが確定できるかもしれませんが、いまの段階でそういうことはとてもむりだといえましょう。そういう専門家もいるとおもいますが、定説じゃないとおもいます。]一個の人間の心ありかたを決定するの要因はふたつあって、ひとつはすでにいいましたように、胎内にいるときと、それから一歳未満のときです。このときの母親との関係、あるいは授乳したりおもつを替えたりなんかしてくれる、とにかく世話してくれなきゃ生きていけない段階での他者との関係がうまくいっているかどうかということと、それから思春期の入り口に、フロイト的にいえば、広い意味でのリビドーの異常体験があったかどうかということが、第二次的な決定力をもつとおもいます。でも、大部分は胎内のときにあるいは一歳未満のとき、決定します。それは人間の心の世界をほとんど決定的に運命づけます。
⑤
ぼくがそんなことをいうと、一種の宿命論じゃないか、この決定論というのはおかしいじゃないかということになりますが、ぼくはそうおもいます。決定論に近い片道決定論です。逆にいいますと、精神が異常だとか、病気だというふうにいわれている人の、たとえば一歳までとか胎内にいたときにどうだったかを聞けば、それは育てた人、あるいは母親との関係がかならず異常です。これは一〇〇パーセントノルマルじゃないです。だけども、そういう人はかならずおかしくなるかというと、そんなことはないとおもいます。どうしてかというと、人間の心の世界は、可塑性があるといったらいいでしょうか、人間の精神はじぶんを超えていけますから、自分の宿命を越えていこうとしますし、またある意味で自分の能力を超えていこうとしますし、また性格を超えていこうとします。そういうことが人間ということの定義ですし、人間が生きるということですから。それを人間は超えていかなくちゃいけないというのが、それぞれの人がもっている宿命であるわけです。
(「心について」(下) P116-P117『吉本隆明資料集 130』猫々堂 )
※①から⑤は、ひとつながりの文章です。
|
| 備考 |
(備 考)
吉本さんが、どこかで自閉症について触れているのは一度読んだ覚えがあった。今回再び出会ったので、ここにまとめておくことにした。現在の医学の段階を踏まえたもので、ここまでしか言えないという形で語られている。
参考までに、④の[ ]の部分は、講演では以下のように語られている。
もしかすると一個の細胞が違うだけだとかいうことになるのかもしれません。それは医学がもっと発達すればわかるようになるかもしれませんし、存外器質の病だということが確定できるようになるかもしれませんけれど、いまの段階でそういうことは無理、嘘だと思います。そういうふうに言っている人もいるかもしれませんけれど、定説ではありません。
(註.1)
『自閉症だったわたしへ』は、ドナ・ウィリアムズによるもので新潮文庫で何冊か出ている。また、自閉症と言われている人のよく知られた本には、吉本さんが挙げているほかに、テンプル・グランディン『動物感覚
―アニマル・マインドを読み解く』がある。
わたしは他にもいろいろ読んでいるが、そのきっかけは松本孝幸さんのホームページ『読書倶楽部通信』http://matumoto-t.blue.coocan.jp/ での紹介によっている。松本さんは、当然に自閉症を医学的には語られていない。
松本孝幸さんは、その<内側から見た自閉症>の~はじめに~で自閉症をどういう視点からどう見るかということについて記されている。http://matumoto-t.blue.coocan.jp/utigawajihei.html
僕の立場を、一言で言ってみれば、<内側から見た自閉症>ということだ。
<内側から見た自閉症>の原則は、とても簡単だ。
①自閉症の子は、恐怖が感情の中心である。それ以外の感情は、恐怖より少な
い。また、自閉症者にとっては、痛みの感覚よりも、恐怖の感情の方が強力だ。
②自閉症の認知の特徴は、過剰特異性、だ。過剰特異性の特徴によって、恐
怖は、猛烈に拡大して、自閉症者を襲う。
③自閉症者は、言葉よりも、視覚で考える。
<内側から見た自閉症>は、内面から見た自閉症と言い換えてもいいし、人間の起源をさか
のぼって、起源の側から見た人間、と言い換えてもいい。
僕は、テンプル・グランディンの理解の方が好きだ。
「自閉症は、動物と、人間との中間にある駅のようなものだ、(『動物感覚』)と。
僕も、それでいいのではないか、と感じる。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 698 |
思想の現実化―恋愛から実生活へ |
第1章 「終わらない恋愛」は可能か |
語り |
『超恋愛論』 |
大和書房 |
2004.9.15 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 恋愛と結婚は別ものという考え |
透谷とか独歩は、西欧に影響されて恋愛から始まる家庭を作ろうと考えた、日本で最初の人たち |
|
|
項目
1 |
①
「自分にはこの人しかいない」という、いわば精神の双生児みたいな相手を選んでも、実際にはその後の生活において、非常に雰囲気がまずくなっていくというか、駄目になっていく面があるんじゃないか、という問題は確かにあります。恋愛を実生活にどう着地させていくのか、という問題ですね。
たとえば文学者なら、明治時代の北村透谷とか、国木田独歩とかいう人たちは、理想的な恋愛――これは遊女とかそういうのではなくて、近代化した女性と精神的なつながりが基本の関係を築く、ということですが――をして、その延長線上に理想の結婚を夢見たわけです。
若い人たちには信じられないことかもかもしれませんが、恋愛と結婚は別ものという考えが日本の生活には長く根付いていました。
一緒に暮らすのに、相手を好きかどうかは重要視されない。恋愛といえば、周囲からは認められない男と女の間でしか起きない出来事のように扱われていたのです。
②
ですから前で挙げた透谷とか独歩は、恋愛から始まる家庭を作ろうと考えた、日本で最初の人たちともいえます。
そういう意味で、恋愛を実生活に着地させようとして苦労しているわれわれの先駆者であるのかもしれません。
そのかれらの結婚生活がどうなったかというと、これが、ことごとく破局しているんです。
自分たちは自立した近代的な男女だと思っていますから、恋愛を経て共に暮らすことになってからの男女関係というのを一生懸命つきつめようとしたわけです。
けれども結局、実際の生活はどうかというと、女性のほうは従来どおりの家事労働とか、子育てとか、そういうことに専念させられて、男は好き勝手なことをやっている。
男は勤め人ではなく、文学でもやろうというような人間です。だからこそ西欧に影響されて新しい男女関係ということを言い出したわけですが、金も稼がず理想論ばかり振りかざす。
女性にしてみたら、この生活のどこに理想の家庭があるんだということで、そうしたギャップから破局になるんです。
この時代とほとんど同じようなことが、今の日本でも続いているんじゃないかと、ぼくなんかは思いますけれども。
(『超恋愛論』吉本隆明 P47-P50 大和書房 2004年9月)
※①と②は、連続した文章です。
|
備
考 |
(備 考)
①は、恋愛や結婚を巡るその当時の日本の現状。「恋愛と結婚は別もの」という考えには若い頃テレビドラマなどで出会った記憶がある。おそらく、それは個人と個人の恋愛や結婚という考えではなく、家の存続や利害という制度的な名残を引きずった考え方から来ているのではないかと思う。
この北村透谷や国木田独歩の後には、高村光太郎、夏目漱石が取り上げられていくのだが、かれらの文学作品だけではなく、吉本さんは、見るべき所をよく見ているなと感心する。いいかえれば、これは思想の現実化という問題である。知の思想でも生活思想でも、単に言葉で考え思っているだけで日々生きていく具体性の中で、意識的に行動に生かされ実践されなければ生きた思想とは言えない。たとえその過程で妥協や屈折や挫折があったとしてもである。吉本さんの場合、そのような思想の現実化という問題はいろいろ語られているが、ひとつ例を挙げてみると、『吉本隆明全集37』(書簡集
晶文社)の中の「川上春雄宛全書簡」がある。ここには、吉本さんが雑誌『試行』に込めた思いや原則、そして、そこからくる具体的な対応が、川上春雄とのやりとりの中に語られている。
北村透谷や国木田独歩、高村光太郎が取り上げられていく中で、西欧思想に影響を受けた理想の恋愛や結婚という思想が、日本の現実とぶつかって破局に至るさまがたどられている。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 709 |
時間軸上から見た言葉 |
「『神の仕事場』の特性」 |
対談 |
『吉本隆明 詩歌の呼び声 岡井隆論集』 |
論創社 |
2021.7.30 |
「『神の仕事場』の特性」の初出は、『短歌研究』1996年6月号。
関連事項
項目708 「日本という構造」
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 方言と民族語は、全部連続と思う |
神話の理解ももっと違う理解の仕方をして、もう少し抽象化すればというふうにぼくは思ってる |
時期を確定していっしょに言わないと駄目なんじゃないかなと思います |
|
項目
1 |
①
吉本 もうひとつのモティーフと関係があるんですけども、このごろそう思いだしたんですが、以前は、たとえば方言っていうのがあるでしょ、各地方の。方言っていうのと異言語といいましょうか、ちがう民族語というのは断層があるんだと以前は思っていたんです。ですけども今はやっぱり連続だと思ってるわけです。
岡井 そうですか。
吉本 方言っていうのは中央に対してある地方でしゃべられてる同じ言葉なんだけど、民族によって濁音があって訛りがあってとかっていうふうに、方言と民族語は、まるで違うんだっていうふうに思われてるけど、それはたぶんちがうんで、全部連続なんだっていうふうに思いたい、考えたいというモティーフがありまして、そういうことと、これは岡井さんに言うと笑われちゃうけども、要するに人種が違うとか同じということも連続なんだ、というふうに思いたいというわけでしてね(笑)。
ただそれはたとえば各民族語がわかれたのが十何万年前だとすれば、十何万年という幅をとるか、じゃなければ五百年のうちで違う民族語だっていうふうにとるかっていう、それだけの違いだっていう。時間を十何万年にしたらみんな同じになっちゃう。まあ多少は違ってもほぼ同じ言葉になっちゃうみたいなことがあるから、言葉もそうだし、色が黒いとか赤いとかっていうことも、それも少し時間の幅をとれば同じになっちゃうんだから、こういうのもあまり絶対化して、違う人種、同じ人種、何人種と何人種の混血、ということも断絶的にいってはいけないんじゃないかな、という感じと、言葉の連続性の感じ、それをぼくはだんだんそういうふうに思うようになってきたんです。
②
そういったら神話を類型づけるっていうのは実にばかばかしい話だっていう、こんなことで、ここの神話とここの神話が似てるっていうことが何か他の意味があるというふうにもし理解するとすれば、まったく違うんじゃないかなっていう考えがあるんです。
そういうことを、そんなに大舞台じゃなくて、日本の南島と中央とか北の方との言葉の方言の違いとか濁音のつけ方の違いとか、そういうことをもう少し時間的な幅をひろげていけば、もう少し先までいけるとか、神話の理解ももっと違う理解の仕方をして、もう少し抽象化すればというふうにぼくは思ってるわけですね。そうすれば神話の類型づけで何か言うってことは全然違うっていうことをはっきり言えるんじゃないかなってことがありましてね、それがモティーフなんですよね。
岡井 それがずっといった場合に、例えば『万葉集』の解釈――『万葉集』はずいぶん手前の、われわれと近いところにあるわけですが――いわゆる初期歌謡的なものの解釈とかもいろいてろな点で変わってくるという可能性も出てくるんですか?
吉本 ぼくはくるような感じがします。特に少し自分がやったことがある「枕詞」っていうのの解釈はそうとう違ってくるし、もしはっきりとしたことを言葉について確定したいようであれば枕詞っていうのはやっぱりとてもやりやすい素材なような気がします。もっと違うふうになってくるし、確定もできるように思ってるんですけどね。
③
だからぼくは『人麻呂の暗号』みたいに朝鮮語との語音的な類似とか中国語との語音的な類似をいうのは、あれはたぶんある一部分しか当てはまらないんで、あれは普遍的ではないんですが、ああいうことは、ある時間たとえば今から一一一〇年前から八五〇年前までをとってくれば、というふうに時間をとってくればいいというふうに理解したいです。それから、例えば大野晋さんみたいな専門家が日本語とタミール語が似ているみたいな、以前だったら専門の言語学者がなんでこういうことをいうんだろうかっていう理解でやめたと思うんですが、今ぼくはそうじゃなくて、これは確定しないといけないと思うんですけど、例えば二六〇〇〇年から二九〇〇〇年の間だったらこういえるっていうような言い方ができそうだから、だからこういうのもたくさんあっていいんだ、という理解になってますね。
ただ、普遍的だと思ったら違うんじゃないかなと思いますけど。だから大野さんがそういうふうに確定したいんだったらば、時期を確定していっしょに言わないと駄目なんじゃないかなと思いますけども、あれはまったく荒唐無稽なことでやってるというふうには思わなくなりました。前はそう思いましたけどね。だからそうとう様相は変わるような気がしますね。
(『吉本隆明 詩歌の呼び声 岡井隆論集』P87-P90 論創社)
※①と②と③は、ひとつながりの文章です。
|
備
考 |
(備 考)
例えば、言葉ひとつとっても語彙や表現技法など細分化して差異化されてきた現在に対して、時間軸を導入して日本語を見る、捉えることは、大まかには新旧の日本語が存在してきているといわれているが、その他の色んな言葉がこの列島に打ち寄せ浸透してきて降り積もったものとして現在の「日本語」を見るということであり、そのような現在の「日本語」の複雑な構成の歴史を明らかにしようとすることと同義である。しかし、素人のわたしたちにそのことに寄与することは難しい。そのモチーフに対するネガティブな寄与として考えられるのは、現在の「日本語」や古典の「日本語」を「美しい日本」や「日本の伝統」と括られるものと対応するような単層で固定的なものと見なさないということくらいである。それとかぶるかもしれないが、もうひとつ言えそうだ。生活においても表現においても、言葉の概念を時代性を持つものと感じ考えて固定的なものと見なさないことである。
|
※講演「『最後の親鸞』以後」1977年8月5日
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 宗教を信じている人にはいい子になりたいという気持ちがあるんですよ。 |
ほんとうの思想がありうるとすれば |
自分に嘘をついていることと、正しい理念というものと、両方に橋が架かっているということ、それがなければ、思想はゼロに等しい |
|
項目
1 |
①
質問者1 先生が親鸞に興味をお感じになりましたきっかけがありましたら、うかがいたいんですが。
僕は昔から親鸞が好きでして、学生の頃に「歎異鈔に就いて」という文章を書いたこともあります。その関心が現在まで持続しているわけです。では僕は、親鸞のどこが好きなのか。みなさんはそうじゃないと思うんですが、宗教を信じている人にはいい子になりたいという気持ちがあるんですよ。そして僕自身にも、自分を偽ってでも正しいことをいいたいという気持ちがあると思うんです。ところが親鸞は、人間は正しいことをいうためになぜ自分を偽らなきゃいけないのか、ということを非常によく考えて、自分を偽ることと正しいことをいうことの間に橋を架けたような気がするんです。
②
これは僕の考えですけど、もしほんとうの思想がありうるとすれば、国家として共同体として組織として、あるいは自分として自分の内面に嘘をついているということと、正しいことをいうことの間に橋が架かっていなければいけないと思う。親鸞の思想には、橋が架かっている。橋が架かっていない思想を、僕は信じないわけですよ。そもそも僕は、正義なんて信じていない。理念的に正しいことをいうのはやさしいことです。人間は、そんなのは、ちょっとでも知識・教養があればできるんですよ。僕はそう確信します。しかし、そんなことはたいしたことじゃないと思います。
自分に嘘をついていることと、正しい理念というものと、両方に橋が架かっているということが、非常に大切なことだと思います。それがなければ、思想はゼロに等しいというのが僕の考えです。上代から現在まで全部合わせてでもいいですけど、僕には、日本の思想家のなかで親鸞だけが、程度はあるでしょうけれど、そうしているように思えてしかたがないのです。
③
僕のばあいは、思想として捉えています。橋を架けるということの意味ですけれど、現世流の言葉でいえば、自分の主体的な思想として、少なくとも自分が正しいことをいうばあい、「こういう言い方しかできないよ」というかたちで主体的に橋が架かっていなきゃいけない。つまり自分のなかで、嘘をつく自分と、正しいことをいう自分との間に、よく考えられていなければならない。自分は、ここのところは嘘で、ここのところはいつでもごまかしやすいんだなあという問題が、主体的に突きつめられていなきゃならない。もうひとつは、理論的にといったらおかしいでしょうか、理念的にあるいは教義的に突きつめられていなければならない。だから、その三つの意味あいで突きつめられていなきゃいけないと僕は思いますけどね。
(『吉本隆明 質疑応答集 ①宗教』P3-P6 論創社)
※講演「『最後の親鸞』以後」1977年8月5日
|
| 備考 |
(備 考)
「自分を偽ること」と「正しいことをいう」ことは、ここでは思想の問題として考えられている。しかし、この問題は、人間の関係的な社会を生きているわたしたち誰にも関わりがあるものだ。なぜそのような分裂が起こり、わたしたちは内面で分裂感を味わうのだろうか。
この世界が、わたしたちが内心で感じることとそれを言葉にして外に表すことの間に割って入ってくるからである。それは、現在ではそうとしかあり得ない世界の有り様であり、関係の絶対性ともいうことができる。だから、現実的には、自分が感じる「正しいことをいう」場合、現在の現実の壁にぶつかって、(これをそのまま言ったら誤解されたり反感を受けるかな)などと内省やプレッシャーを感じて、折り返し無難な言い方で済ますということがあり得る。たとえそうであったとしても、自分の内心では、自分の感じた正しいと思うこととそれを少し偽って言ってしまったことの間に筋道が付けられていなくてはならないということだろう。つまり、なぜ人はそうでしかありえないかをよくよく考え、人間社会というのはそんなもんさ、の気分や判断で終わらせないということである。
ちなみに、ここの問題に関わることとして太宰治の次の言葉がある。
じぶんで、したことは、そのように、はっきり言わなければ、かくめいも何も、おこなわれません。じぶんで、そうしても、他におこないをしたく思って、にんげんは、こうしなければならぬ、などとおっしゃっているうちは、にんげんの底からの革命が、いつまでも、できないのです。
(太宰治「かくめい」、青空文庫)
初出「ろまねすく 第一巻第一号」1948(昭和23)年1月1日発行
もうひとつ、聖書の中の言葉がある。
シモンが言った、「主よ、わたしは獄にでも、また死に至るまでも、あなたとご一緒に行く覚悟です」。
34 するとイエスが言われた、「ペテロよ、あなたに言っておく。きょう、鶏が泣くまでに、あなたは三度わたしを知らないと言うだろう」。
・・・中略・・・
54 それから人々はイエスを捕え、ひっぱって大祭司の邸宅へつれて行った。ペテロは遠くからついて行った。
55 人々は中庭のまん中に火をたいて、一緒にすわっていたので、ペテロもその中にすわった。
56 すると、ある女中が、彼が火のそばにすわっているのを見、彼を見つめて、「この人もイエスと一緒にいました」と言った。
57 ペテロはそれを打ち消して、「わたしはその人を知らない」と言った。
58 しばらくして、ほかの人がペテロを見て言った、「あなたもあの仲間のひとりだ」。するとペテロは言った、「いや、それはちがう」。
59 約一時間たってから、またほかの者が言い張った、「たしかにこの人もイエスと一緒だった。この人もガリラヤ人なのだから」。
60 ペテロは言った、「あなたの言っていることは、わたしにわからない」。すると、彼がまだ言い終らぬうちに、たちまち、鶏が鳴いた。
61 主は振りむいてペテロを見つめられた。そのときペテロは、「きょう、鶏がなく前に、三度わたしを知らないと言うであろう」と言われた主のお言葉を思い出した。
62 そして外へ出て、激しく泣いた。
(『ルカによる福音書』第22章)
※ 『マタイによる福音書』第26章にも同様の話がある。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 731 |
新新宗教の意味 |
「新新宗教は明日を生き延びられるか」 |
講演 |
吉本隆明『親鸞復興』 |
春秋社 |
1995年7月 |
※初出 講演A156「新新宗教は明日を生き延びられるか」
(講演日時:1993年6月17日 吉本隆明の183講演 ほぼ日 フリーアーカイブ)
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 常人にはおよびがたい修行をしないでも、易しい道をたどればいいというのが中世の新宗教の教祖である法然、親鸞の言い方 |
新新宗教は、一種の超人性、超能力性と、それを基にした幸福感を与えられることを教義として人々を惹きつけている |
欠乏感を中心に築かれた従来の倫理を超えるものを生み出さなくてはならない |
新新宗教は一時的な倫理の代用品 |
項目
1 |
①
先に触れたように、常人にはおよびがたい修行をしないでも、易しい道をたどればいいというのが中世の新宗教の教祖である法然、親鸞の言い方でした。じぶんは修行もし、仏典も読破した結果、それをやってもしようがないとかんがえたわけです。ようするに宗教は倫理の問題であり、ヴィジョン、イメージを思い浮かべられるようになるまでの修行をすることではない、と浄土の教祖たちはかんがえました。浄土へゆく、生死を超えるのは念仏だけでいい、それが鎌倉時代の新仏教の教祖たちがかんがえたことです。
ところが、いまの新新宗教の教祖たちは、麻原さんを含めてすべて逆のかたちをとっています。つまり、人間が世間でいう善悪に主眼をおくようないい生き方はどこに基準を求めていいのかわからない。それならば、生死を超えることができるような修行をする。そうなることが人間のいちばんの重要な倫理であり、またいちばんの幸福であるという結論になっているとおもいます。これら新新宗教の教祖たちは一様に、その現世的な倫理の混乱、混迷を逆転しようとして、何か超人的なこと、超能力的なことを体験の根幹に据えて、人々の幸福とは何か、そのための方法を編み出そうとしています。それが現在の新新宗教のいちばんの特徴になっているようにおもいます。
②
では、何が新新宗教を生み出し、また新新宗教に帰依する人を生み出しているのでしょうか。現在は、現実における倫理、善悪の基準、あるいは基準そのものを信ずることがとても危なくなり、しかもいままでの倫理を超えるにはどうしたらいいかということがよくわからない、という情況にあるとおもいます。
それにたいして新新宗教は、一種の超人性、超能力性と、それを基にした幸福感を与えられることを教義として人々を惹きつけ、また、それがある程度、受け入れられているのではないでしょうか。
ぼくのつかみ方にしかすぎませんが、従来の倫理は一種の人間の欠乏感を中心に築かれていたとおもいます。むろん現在でも欠乏感はありますが、それは決定性を失ってきたといえます。その欠乏感とは貧困です。つまり明日食う米がないという意味の貧困は、現在の世界の先進的な地域ではだいたい終わってしまったといえます。日本でいえば、所得の半分以上を消費に使い、家計に占める食費であるエンゲル係数は、二〇パーセント前後になっています。ほぼ九割の人は、明日食う米がないという意味の欠乏感はなくなってしまいました。あるのは精神の欠乏感だけということになるわけです。それをなんとかしようというところが、新新宗教が流行っている根拠になっているのだとおもいます。
③
いまは、どういう考え方を基に倫理をつくるのかをかんがえねばならない段階にきています。しかし、欠乏感が決定性を失ってしまった地域で、倫理観をいかにつくるのかについて徹底的にアプローチする考えは、残念ですがまだ生まれておらず、人々はそれを模索している段階にとどまっています。
すくなくともいちばんはっきりしているのは、マルクスの考え方です。マルクスの考え方では、第一次産業である農業、林業、漁業などと、第二次産業である製造業、工業とが対立している段階までの分析は『資本論』でなされています。現在の先進的な地域では、その段階を過ぎてしまい、サービス業や流通業など第三次産業に労働者の大部分は移ってしまいました。こうした段階では、欠乏を主体とした論理とか倫理が通用しなくなり、危なくなってきたとかんがえています。そして新しい、これまでとはちがう倫理をつくりあげていかなければならない、模索しなければならない段階にきています。
こういう模索の段階では、現在の新新宗教が一時的な倫理の代用品をしているのではないでしょうか。しかし、それは短絡的な間に合わせにとどまり、恒久的な救済にはならないだろうことは、とてもはっきりしているようにおもいます。
ただ、短絡的ではありますが、新新宗教は間に合わせの役割を現在果たしており、われわれがきちんと社会を、経済を、人間の精神の働きを、さらには文化を分析して新たな倫理を導いてこられなければ、最終的な解決にはなりません。日本でいえば、九割九分の人が明日食う米がないという物質的な欠乏感から抜け出たときが、一種の結節点、カタストロフィーのようにおもいますし、それはわりあい近いとおもっています。
(「新新宗教は明日を生き延びられるか―幸福の科学、統一教会、オウム真理教」、P205-P209 吉本隆明『親鸞復興』春秋社 1995年7月)
※①と②と③は、ひとつながりの文章です。
|
| 備考 |
(備 考)
欠乏・貧困を基にした倫理とは、身近な生活上の振る舞いから生き方までをも含むものだろう。例えば、物を粗末にしてはいけない、十分に使い切らないといけないとかから、人は限られた自然の恵みに感謝して謙虚に生きなければならないとかまである。このような倫理は、欠乏・貧困という経済社会的な避けられない状況がそこに生きる人間に強いる対応であろう。明治期の人々に強いた立身出世の倫理や夢も、新たな社会状況の出現が強いた倫理の自然性だったと思われる。
このように新たな社会状況の出現は、そこに生きる人々に新たな倫理を強いる。そして、その倫理には明治期の立身出世のような自然性とそれを反省するような意識性とがあるように思われる。
しかし、ここで語られている欠乏・貧困を基にした倫理とは、江戸期をも含むようなもう少し大規模の歴史の段階としていわれているように思われる。例えば、個人レベルでは嫌いな物は食べ残しても良いよとか、企業レベルではコンビニの時間が来たら弁当や食べ物を廃棄する、農業であれば規格に満たない農作物は出荷せず廃棄するとかに到るまで、従来の欠乏・貧困を基にした倫理とは明らかに反する対応や行動をしている。ただ、それらは吉本さんが述べているように、まだ新たな倫理として十分に固まったものではない。
③の吉本さんの言葉、「日本でいえば、九割九分の人が明日食う米がないという物質的な欠乏感から抜け出たときが、一種の結節点、カタストロフィーのようにおもいますし、それはわりあい近いとおもっています。」は、これは、1993年6月17日の講演であるから、1993年頃の状況を踏まえた予測ということになる。以下の時代の推移をはさんでみると、状況は揺り戻しで「それはわりあい近い」ということを今以て遅延させているように見える。
1.高度経済成長期の末期の1970年代に,国民の大多数が共有した「中流」意識が自覚され、「一億総中流」という言葉も生まれた。その当時が次のように描写されている。
経済学でいうなら、この時代(引用者註.高度経済成長時代)の日本はトリクルダウンが機能していた時代です。トリクルダウンは、大都市や大企業、富裕層などが得る利益が、器からあふれ出る水のようにして地方、下請け企業、一般庶民に波及し、結果的に全体が豊かになるという考え方です。
その後も日本は多少の浮き沈みは経験しつつも順調に成長し、世界トップクラスの豊かな国となっていきます。需要は伸び、労働力が不足し、賃金が上がり続けました。平均年収の推移を見ると、今から40年前(1975年)は200万円未満ですが、10年後(1985年)には300万円台、バブル経済を経た1995年には400万円へと増えています(国税庁)。誰もが資産を持てるようになり、まさしく一億総中流を謳歌するようになりました。
(一億総中流時代と呼ばれた「あの頃の日本」を思い出せるか? 納村哲二 2019.12.8 幻冬舎 GOLD ONLINE)
2.wikiによると、「バブル崩壊」は、日本の不景気の通称で、バブル景気後の景気後退期または景気後退期の後半から、景気回復期(景気拡張期)に転じるまでの期間を指す。1991年(平成3年)3月から1993年(平成5年)10月までの景気後退期を指す、とある。
3.「労働者派遣法」の成立(1986年に施行)はすでにあり、小泉政権の2001年~2006年あたりで、経済団体の要望や規制緩和の名の下に、「労働者派遣法」の規制緩和が進められ、派遣業務の対象範囲拡大や派遣期間延長が行われていく。
1999年 対象業務の原則自由化
2004年 製造派遣解禁
これらがこの時期の「労働者派遣法」規制緩和の中でも大きな変化をもたらした内容であり、これにより、営業、販売、一般事務、製造といった専門業務以外の業務でも派遣が可能になったという。そうして、現在のような派遣労働が一般化した状況になった。ちなみに、政府統計によると非正規社員の数はいまや労働者全体の4割近くを占めている(2018年)。
4.「格差社会」という言葉は、バブル崩壊後の不況下においてしばしば聞かれるようになった言葉という。派遣労働の規制緩和がその格差社会に大きく負の貢献をしているだろう。さらに、以前より容易に離婚するせいもあり一人親世帯となりまた老年世代の単身世帯も増え、世帯の経済状況が不如意になったという事情もあるだろう。今では、社会の貧困ということが大きな問題になっている。
最後に、『吉本隆明質疑応答集①宗教』(論創社 2017年7月20日)には、この講演の質疑応答が載っている。人類の滅亡の可能性について、吉本さんから今までに聞いたことがないなと思うことが語られていたので引用しておく。そういう意味で、質疑応答集も興味深いものがある。
質問者 1
私には三十年ぐらい前から、人類の最期を見届けたいという変な希望があるんです。「ノストラダムスの予言」によれば、一九九九年の七の月に人類は滅びる。・・・中略・・・僕は冗談でいっているんですが、ほんとうに予言を信じている人もけっこういるらしくて、そのへんのことはどう思われますか。
もし人類が滅亡することがあれば、遺伝子的に滅亡するだろうと僕は思います。従来でいえば、動物でも植物でも滅亡しなかった種(しゅ)はいない。僕は原子爆弾をめちゃくちゃに落とし合うなどといった外からの原因で人類が滅亡するとはちっとも考えていないけど、遺伝子的にいつか滅亡することはありうるだろうと思っています。でも、おっしゃるような意味あいでは人類の滅亡を信用していない。滅亡というのは、そういうかたちで来ないと思っていますから。
|
| 項目ID |
項目 |
論名 |
形式 |
所収 |
出版社 |
発行日 |
| 747 |
「仕事」ってなんだ? |
「仕事」ってなんだ? |
対話 |
『悪人正機』 |
朝日出版社 |
2001.6.5 |
| 検索キー2 |
検索キー3 |
検索キー4 |
検索キー5 |
| 人間の理想 |
それじゃ人間ってのは何だっていうと、要するに子供がいちばんの基準だと思いますね。 |
子供って、一日二四時間、全部遊びじゃないですか。生活イコール遊びなんですよ。あれが理想でね、そいつを歴史になぞらえてみると、未開原始の社会と同じなんですね。 |
働くってことは、あんまりいいことじゃない |
項目
1 |
①
結論から言ったら、人間というのは、やっぱり二四時間遊んで暮らせてね、それで好きなことやって好きなとこ行って、というのが理想なんだと、僕は思うんだけど。
ええと、ほら、僕らの世代の人たちで、ちょっと左翼っ気のある人なんかだと、「労働は大切だ」って言うでしょう?そうすると、その極まるところがどうなるかっていうと、清く貧しくっていう思想になっていくわけです。
清貧の思想、遊び心は持たない、ぜいたくもしない―どうしてもそうなるんですよ。
何でこいつら、こういうこと言うんだろうって思いますね。普通の人がぜいたくして、いい洋服着たりうまいもの食ったりっていう、そのテーマがなくなっちゃったら、歴史の半分がおもしろくねえってことになっちゃうんですよ。
あと、いわゆるボランティアっていう、ただで奉仕するんだっていう、あれも好きじゃありません。
(吉本隆明『悪人正機』P58 聞き手 糸井重里 朝日出版社 2001.6.5)
②
それじゃ人間ってのは何だっていうと、要するに子供がいちばんの基準だと思いますね。子供って、一日二四時間、全部遊びじゃないですか。生活イコール遊びなんですよ。あれが理想でね、そいつを歴史になぞらえてみると、未開原始の社会と同じなんですね。
みんなゴロゴロしてて、木の実採ったり、カヌーかなんか漕いで魚獲りに行ったりしてさ。それをみんなで分け合って食って終わりという・・・・・・あれが原型的な理想で。
つまり、働くってことは、あんまりいいことじゃないってことを言いたいわけです。
仕事をなんでするのか、に戻ると、僕なんかもう、苦痛でしょうがねえって言いながら(笑)。やんなきゃ食えねえからって。
そういうふうにキツイと思ってるから、息を詰める。これ、悪いことですよね。ずつと座卓で原稿やってるから、足腰痛めたのだって職業病だよと思えば、そうも言える。ことごとくよくないことで、しかもそれでもって食ってかなきゃいけない。
まあ、そうは言いながらも、もし僕が書くことを禁じられたら、怒るということはあるわけです。けど、やっぱりやだやだと思いながらやってるんで(笑)。
やだやだと思ってても、うまく書けたなって時は、ものすごい解放感ってあるでしょう。調子いいときは、うまく書けたという解放感があって、それで銭もらえるんだから、これほどいいことないやって思う時もありますね。
(『同上』P59-P60 )
|
| 備考 |
(備 考)
「清貧の思想」については、中野孝次が『清貧の思想』を1992年9月に出している。吉本さんは、これを批判していた覚えがある。
人類史も、その現在性に規定されながら生きるひとりひとりの人間も、吉本さんの言う人間的な理想からずいぶんズレてしまった生活をしていることになる。もちろん、人類史の現在がもたらした社会の有り様を肯定し、そこから人が勉強や仕事に果敢に挑むことを価値と見る見方は多い。しかし、吉本さんが人間の理想と述べたようなイメージを、誰もがかなわぬ夢のようにを自分の深みに沈めて持っているような気がする。
しかし、一般に企業の経営者や知識層は、そんなことを人間的な理想とは思わないような気がする。それでも、大多数の普通の人々は、そんな思いを深く沈めていて、時折ふと思い浮かべるのだと思う。
②の末尾の「やだやだと思ってても、うまく書けたなって時は、ものすごい解放感ってあるでしょう。」というのは、いくら人間的な理想とは違ったものであっても、人間には柔軟性や適応性があり、どんな状況にも喜びや解放感なども持ちうるということだろう
|