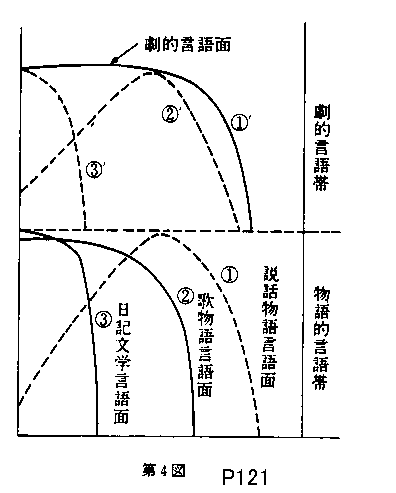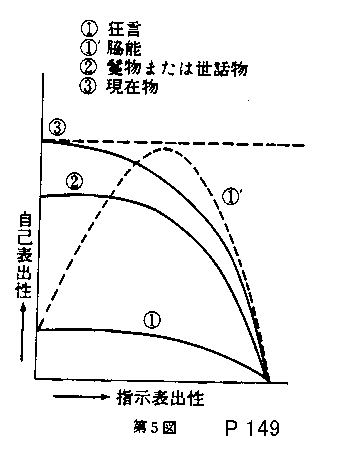1
亂侾丂慜採亃
嘆偄傑傑偱丄尵岅偦偺傕偺偐傜偠偭偝偄偺暥妛嶌昳傊偲傝偮偔偨傔偵昁梫側傕傫偩偄偼丄偍偍傛偦偲傝偁偘偰偒偨丅丒丒丒丒
丂偨偩丄婲偙傝偆傞崿棎偼偨偟偐偵傂偲偮偩偗傂偒偯偭偰偄傞丅尵岅偦偺傕偺偺壙抣丄尵岅昞弌偺壙抣丄尵岅寍弍偺壙抣偼丄偘傫傒偮偵偼傋偮偱側偗傟偽側傜側偄偺偵丄椺偲偟偰偟傔偡暥復偑暥妛嶌昳偱偁傞偨傔丄崿摨偺偍偦傟偑偁傞傛偆偵偁偮偐偭偰偒偨偙偲偩丅偩偐傜丄偘傫傒偮偵偄偊偽丄傢偨偟偼丄偄傑傑偱暥妛嶌昳傪偣偄偤偄昞弌偺壙抣偲偟偰偁偮偐偆偲偙傠傑偱偟偐榑媦偟偰偄側偄偲偄偆傋偒偩丅尵岅昞弌偺壙抣偺偍偍偒偝偼丄傕偪傠傫偦偺傑傑尵岅寍弍偲偟偰偺暥妛嶌昳偺壙抣偺偍偍偒偝偱偼偁傝偊側偄丅暥妛嶌昳傪尵岅寍弍偲偟偰偺壙抣偲偟偰偁偮偐偆偨傔偵丄傢偨偟偨偪偼側偍偄偔偮偐偺婑傝摴偑傂偮傛偆偩丅偦偺傂偲偮偼峔惉偲偼側偵傪堄枴偡傞偐傪偨偢偹傞偙偲偩丅
丂偁傞暥妛嶌昳偑丄昞弌巎偺偆偊偱偐側傜偢偦偆側傞偼偢偺偆偮傝備偒偵偦偭偰偄傞偐偳偆偐偑丄偦偺傑傑丄嶌昳偺寍弍偲偟偰偺壙抣偩偭偨傜丄昞弌巎偲偄偆奣擮偼丄偠偐偵暥妛巎偲偄偆偑偄偹傫偵側偭偰偟傑偄丄昞弌偺壙抣偼丄偨偩偪偵嶌昳偺壙抣傪堄枴偟偰偟傑偆偺偱偼側偄偐?偦偆偩偲偡傟偽丄昞弌偺偼傝偮傔偨椼婲傪丄偦偺帪戙偺尵岅悈弨偺偆偪偱傕偪偙偨偊偰偄傞嶌昳亅帊嶌昳亅偼丄夛榖傪傆偔傒丄愢柧偺昤幨傪傆偔傒丄嬝彂偒偺揥奐傪傆偔傓偙偲偑偝偗傜傟側偄嶌昳亅嶶暥嶌昳亅傛傝傕丄愭尡揑偵壙抣偑偁傞偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偐?偙偺媈栤偼傑偨丄偮偓偺傛偆偵丄偄偄偐偊傞偙偲偑偱偒傞丅(P10-P11)
嘇昞弌偺壙抣傪丄偝偒偵偁偮偐偭偨尵岅偺壙抣傪奼挘偟偨傕偺偲傒側偟偨偲偟偰傕丄攇偺偆偹傞傛偆偵丄傑偨偆偹傝偑偮傒偐偝側傞傛偆偵偍偟傛偣偰偔傞峔惉偺揥奐偼丄嶌昳偺壙抣偵娭梌偡傞偙偲偼側偄偩傠偆偐?
丂偡偱偵丄柍堄幆偵丄揮姺傪偁偮偐偭偨偲偒丄偙偺傕傫偩偄偼埫帵偝傟偰偒偨丅傢偨偟偺偐傫偑偊偱偼丄昞弌偺壙抣傪偦偺傑傑丄嶌昳偺壙抣偲偡傞偙偲偼丄敪惗巎揑偵偼丄偄偄偐偊傟偽丄帺屓昞弌偲偟偰偺尵岅偺楢懕惈偺撪晹偱偼丄偁傞惓摉惈傪傕偭偰偄傞丅偩偑丄暥妛嶌昳偺壙抣偼丄傑偢慜採偲偟偰巜帵昞弌偺揥奐丄偄偄偐偊傟偽帪戙揑嬻娫偺奼偑傝偲偟偰偺峔惉偵傆傟側偗傟偽丄偐傫偑偊傞偙偲偑偱偒側偄丅丂丂(P12)
2
亂俀丂敪惗榑偺慜採亃
亂俁丂敪惗偺婡峔亃
嘊偗傟偳偙偺懳徾偵偼丄妋偐側偙偲偑偁傞傛偆偵偍傕傢傟傞丅傢偨偟偨偪偑偮偒偁偨傞偺偼丄帺慠偑杺椡偺傛偆偵恖娫偵偍偍偄偐傇偝偭偰偄偨帪戙偺幮夛偵偝偐偺傏傞偲偄偆偙偲偩丅寍弍(帊)偺敪惗偼丄偙偺帪戙偲傢偐偪偑偨偔傓偡傃偮偄偰偄傞丅帺慠偺椡偵偨偄偡傞懢屆恖偺嵟弶偺懳棫偺堄幆偼丄偐傟傜偑帺慠偺堦晹偱偁傝丄偦偺傆偲偙傠偵偔傞傑傟偰偄傞偲偄偆埨揼偺堄幆偐傜嬫暿偝傟傞丅偙偺嬫暿偝偊傕偑丄傢偨偟偨偪偑尰嵼偐傫偑偊傞帺妎揑側傕偺偲偼偪偑偭偰偄傞丅偱傕偁傞堎榓偺堄幆偲偟偰偒偞偟傪傒偣傞丅懢屆恖偼偦偺偲偒壗傪偟偰偄偨偐?帺慠偺杺椡偵偨偄偟偰丄傋偮偺杺椡傪嬻憐偟丄峴堊偟丄杺椡傪傆傞偆帺慠偵庤傪偮偗偰怘傪妋曐偟丄惗妶傪偮偯偗偰偄偨?偙偺惗妶偺側偐偵偼<楯摥>偑偁傝<惈>偑偁傝<柊傝>偑偁傝丄傑偨<嬇>偑偁偭偨丅<柊傝>偺側偐偵擡傃偙傫偩巆憸偑偁偭偨丅偙偆偄偆扨弮側惗妶偺孞曉偟偺側偐偵丄尞偼偡傋偰偐偔偝傟偰偄傞丅丂(P23-P24)
嘋傢偨偟偨偪偑丄寍弍偺敪惗偱摉柺偡傞傕傫偩偄偼丄偦偆偄偆偙偲偱偼側偄丅嬶懱揑側惗妶偺側偐偐傜丄寍弍偑傂偒偩偝傟偰偔傞嫟捠偺梫場偲偼側偵偐丄偦傟偼偳偺傛偆側晛曊揑側朄懃偵傓偡傃偮偄偰偄傞偐丄偲偄偆偙偲偩丅丂(P25)
拹丂乽偨偩丄婲偙傝偆傞崿棎偼偨偟偐偵傂偲偮偩偗傂偒偯偭偰偄傞丅尵岅偦偺傕偺偺壙抣丄尵岅昞弌偺壙抣丄尵岅寍弍偺壙抣偼丄偘傫傒偮偵偼傋偮偱側偗傟偽側傜側偄偺偵丄椺偲偟偰偟傔偡暥復偑暥妛嶌昳偱偁傞偨傔丄崿摨偺偍偦傟偑偁傞傛偆偵偁偮偐偭偰偒偨偙偲偩丅偩偐傜丄偘傫傒偮偵偄偊偽丄傢偨偟偼丄偄傑傑偱暥妛嶌昳傪偣偄偤偄昞弌偺壙抣偲偟偰偁偮偐偆偲偙傠傑偱偟偐榑媦偟偰偄側偄偲偄偆傋偒偩丅乿
拹丂岅拹乽奜憓乿(P15)丒丒丒丒